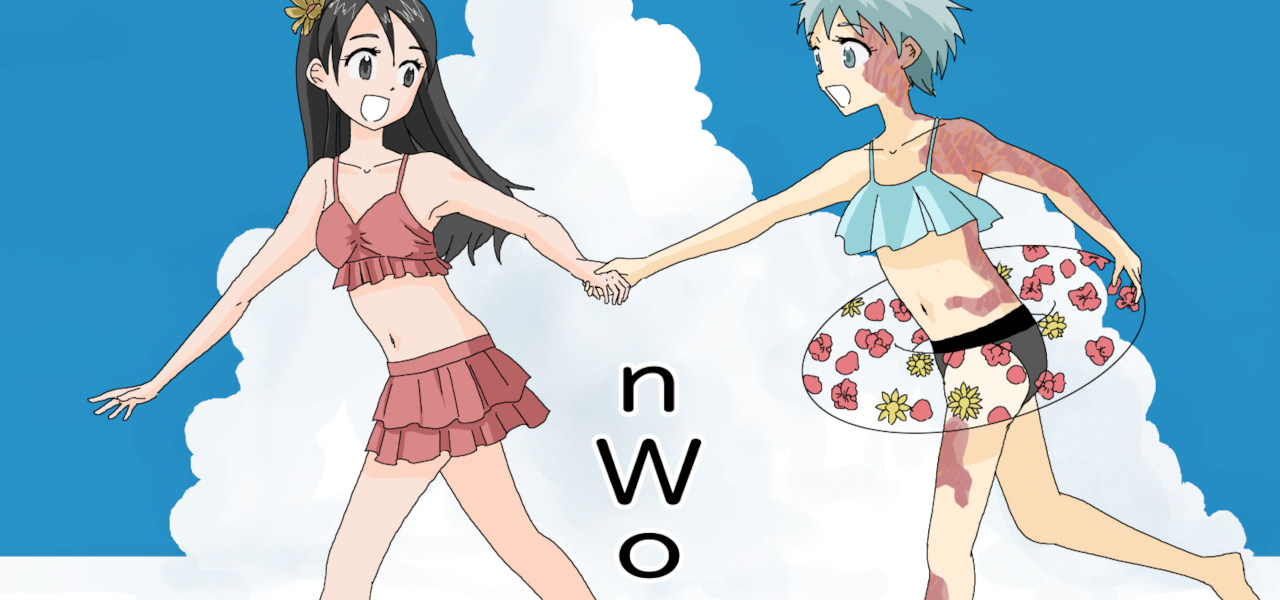無人のビルの谷間を蝶ネクタイ型のマイクでしゃべりながら遠くから一人の少年が歩いてくる。
「げに恐ろしきは殺人天国日本。一万人殺せば英雄で、一人殺せば商売になる。鉄道会社も喜びいさんで殺人商売にタイアップ。日本縦断殺人旅行。殺せ殺せ、みんな残らず殺してしまえ!」
バス停脇のベンチに座っていた男が横倒しに倒れる。その後頭部に深々と細長い針が突き刺さっている。
「役に立ったよ隠れ蓑。だって子供にゃ権利がない。経済大国日本じゃ、金の量が権利の量。金を持たない子供には、何の意見も認めません。さぁ、思う存分殴れ殴れ。おまえが子供だったときにやられたように、蹴って殴って脅迫しろ、『今夜のご飯はぬきです!』。なァに、心配はいらない。世間様には教育だと言っておけ!」
街灯から茶色のコート、帽子を身につけた小太りの男がロープで吊り下げられている。周囲にただよう異様な臭気。
「無能を養う余裕なんて、今の日本にゃありません。死ねば権威は糞まみれ。どんな権威も糞まみれ。民間人にだしぬかれ、次から次へとだしぬかれ。あるのは逮捕の権利だけ。そのくせ俺のような最悪の、殺人者をのうのうと泳がせて。おかしいねえ!」
禿頭のビール腹が白衣を血に染めて道端に転がっている。
「どんどん発明殺人マシーン。在野の科学者、本当かい? 人を見る目がなかったのが、致命的な失敗よ。あなたにもらったスニーカー、増強されたキック力。なんどもなんども蹴り上げられて、大人の威厳もどこへやら。中年は、血にまみれても中年です。やだねえ、しまらないねえ!」
少年、スクランブル交差点の中央で立ち止まる。昼間だというのに人ひとりいない。
「さて…」
少年の足下に一人の女性がうつぶせに倒れている。
「ここに一つ死体があります。彼女の背中からは包丁の柄が見えており、その刃は心臓にまで達していると思われます。まず彼女が自分で背中に手をまわして突き刺したとは考えにくい。女の力、物理的にもそれは不可能でしょう。これは明らかに他殺です。犯人はいまだ見つかっていません。いや、それ以前に警察が動いていない。これほど明確に人が死んでいるというのにです。警察が動かない以上、犯罪ではない。あなたたちの大好きな完全犯罪の成立です! しかしどうして? 平日の昼間、いちばん人目につくだろうこんな大都会のど真ん中という最も密室とはかけ離れた場所で、最も密室であるような状況が発生している。ふふ、悩んでいますね。私にはこの謎がすでに解けています。さァ、僕からの視聴者のみなさんへの挑戦です。犯人はいったい誰なのか。また、犯人はいかにしてこの完全犯罪を成し遂げたのか。答えはCMのあとです。(カメラ目線で指さしながら)君にこの謎が解けるか」
画面が砂嵐になり何分か続く。
「犯人は……私です。これは簡単ですね。なぜってこの物語のヒロインたる彼女の実存を抹消してしまうことのできるのは、作者をのぞけば、彼女よりも虚構内での位相が上位の私をおいて他ありえませんから。昨晩私は彼女の恋人をかたり、彼女をここへ呼びだした。彼女はまったく疑う様子もなくやってきた、その恋人にぞっこんまいってしまっていましたからね。そして交差点にひとり来るはずのない恋人を待つ彼女を、背後からあらかじめ用意しておいた出刃包丁でぶすり、とこういうわけです。ひどく苦しむものだからこいつの(蝶ネクタイを見せる)麻酔で眠らせてやりました。二度と醒めることのない眠りを眠らせてやったんです。ハハハハ。ああ、おかしい(目尻の涙をぬぐう)。しかしここまで聞いてみなさんは不思議に思うかもしれない。なぜそこまであからさまな殺人でありながら誰にも気づかれていないのか。じつは非常に簡単なのです。奇想天外なトリックを予想されていた方、申し訳ない。我々はこれまでの十億回になんなんとする連載の果てに、日本人口一億二千万人すべてを、あらゆるトリックでもって殺人しつくしてしまったのです! これが目撃者ゼロの真相です。警察も動きようがない。なぜってその構成員すべてが何らかの殺人事件の被害者になって、死んでしまっているんですからね。最後まで残った毎回物語に絡んでくるメインキャラクターたちは私が殺しました(カメラが引いて、交差点の信号の上に小学生三人の死体が乗っているのが画面に写る)。彼女と同じ理由から私が殺さねば死ななかったからです。なるほど、ここまではよくわかった、だが動機は何なのか。ええ、ええ、それを疑問に思うのはもっともです。動機は…あなたたちが一番よくおわかりのはずでしょうに。この日本においていったん語られはじめた虚構は、それが金を生む限りは語られ続けなければならないからです。あなたたちは一億二千万人殺しても飽き足りない。あなたたちは人死にが見たくて見たくてしようがない。(大声で)バカヤロウ! おまえたちのお望みどおりに死んでやろうじゃねえか! (ふところから拳銃を取り出しこめかみにあてる)見てろ、見てろよ…(少年の膝頭が次第にふるえだし、ついには失禁する)ヒヒィ、ヒヒヒヒィ、ヒィ…いやだ、いやだぁっ!」
少年、拳銃を捨てて駆け出す。
「(鼻水と涙で顔面をぐしゃぐしゃにしながら)やだ、やだよぅ、死にたくないよぅ…(後ろを振り返り目を見開く)ぎゃあっ、ぎゃああああっ」
少年の胴が突然まっぷたつになる。吹き出す大量の血。やがて完全に静かになる世界。
以上の内容の原稿が乗った作者の机が実写で大写しになる。
月: 1999年3月
廣井王子(2)
山に囲まれた一軒家。蝉の声。
「ご無沙汰しております、廣井さん」
「おやおや、これは珍しい顔を見ますな。この老人に何のご用ですかな。こんなところに来るまえにお仕事がありますでしょうに」
「いや、これは手厳しい(ハンカチで額の汗をふく)。私たちは今日、廣井さんにお願いがあって参ったのです」
「(聞こえないふうに)まぁまぁ、遠路はるばる暑い中をやってきて下さったことだ。とりあえずお上がりなさいな。日陰に入るだけでずいぶん違うもんですよ。お茶でも一服さしあげましょう」
「田舎の暮らしというのは存外ヒマなものでね。こんなことばかり上手くなってしまった(お茶をすすめる)」
「恐れいります」
「今をときめく一大ゲーム会社のお歴々が、私ごとき老いぼれに何を恐縮することがありましょうや」
「(自分の座っていた座布団を脇にやる)今日はそのことで、お話に参ったのです」
「(目を細めて)ほう」
「単刀直入に申します。廣井さん、あなたに戻っていただきたい」
「(立ち上がり縁側に腰掛ける。ニワトリに餌をやりながら)私は見てのとおり隠居の身ですよ」
「この三年というもの業界内の構図は激変しました。既存のソフトメーカーは軒並み潰れるか合併されるかし、パソコンでいわゆる18禁美少女ゲームを制作していた会社が台頭してきている。これまで築き上げてきた市場ノウハウがまったく通用しないんです。いまやギャルゲーである、ということが売れるための最低条件になってしまっている」
「ほほう、そうなんですか。ははは、世事にはすっかり疎くなってしまった」
「(後ろに控えていた若者が立ち上がる)廣井さん、あなたの魂はまだあきらめていないはずだ! それを証拠に、ご覧なさい(飯櫃のフタを開ける。中にはプレステ2が入っている)」
「(肩越しにちらりと見やって)孫が置いていったんですよ」
「(若者が何かいいつのろうとするのを手で制して)…最後の砦だった大手S社もついに軍門に下りました。見て下さい、先週発売されたS社の最新作『ファイナルファンタジー13』です。キリストの復活をモチーフにしたギャルゲーです。キリストが12歳の幼女で、その使徒たちも全員個性的な美少女だったという設定です。これが今爆発的にヒットしています。S社は時代に同化することで窮状を乗り切ったのです。しかし、我々には方策が見つからない。何本か見よう見まねで出したギャルゲーもすべて一万本と売れていません。社の総力をあげてあと一本作れるかどうか。もう、どうしたらいいかわからんのです。もう、どうしたらいいのか…(畳に涙をこぼす。その視界にすっと影がさす)」
「男がそう簡単に泣くもんじゃねえな」
「(見上げて)廣井さん…」
「(鶏糞で髪を後ろになでつけて、サングラスをかける)見せてみな、おまえたちの企画。おまえたちの必死の最後ッ屁をな!」
「廣井さんの復活だ!」
「(涙声で)は、はいッ! (鞄から紙束を取り出す)どうぞ、これです」
「(表紙を見て眉をしかめる)清少納言伝?」
「はい、大胆な歴史考証で女流作家清少納言の男性遍歴を浮き彫りにする平安恋愛ロマンです。社長自らの企画です。社長は大学時代国文科に所属してらっしゃって、卒論の題材は枕草子だったそうで…うわっ(企画書を顔面に叩きつけられる)」
「ボケ。売る気あんのか。こんなお大尽企画におまえら社運かけてんのか、アァ?」
「し、しかし」
「おまえら何もわかってねえのな。ま、いいや。とりあえずキャラクターの絵を見せてみな。絵だけで売れることってのはあるからよ」
「(鞄から紙束を取り出す)どうぞ、これです」
「(受け取り、見た瞬間に相手の顔面に叩きつける)ボケ。売る気あんのか。なんだ、この細目の白豚は、アァ?」
「げ、厳密な時代考証により平安美人を正確に再現…うわっ(肩を蹴られてひっくり返る)」
「話にならん。顔面の大きさは今の三分の一にしろ。目の大きさは今の五倍…いや、十倍だ」
「馬鹿な! それじゃまったく化け物じゃないですか!」
「リアリティは重要じゃねえんだよ。そのリアルから逃げ出して逃げ出して、その果てにゲームやらアニメやらの虚構へたどりついた連中を相手にすんだぜ? 現実の似姿でありながら、同時に現実の臭いを完全に消さなくちゃダメなんだよ! 小動物やらの目が身体のサイズに比して大きいのはなぜだかわかるか? あれは外敵に対して物理的な反撃手段を持ってねえから、無力なかわいらしさをアピールして、私はあなたに害を加えませんよということをアピールして、相手の敵愾心をそいで攻撃させないようにしてんだよ。これは理屈じゃねえんだ。美少女キャラの目を大きく書くのは、人間が動物だった頃のそういった本能に訴えてるんだ。加えて、相手が無力であるということの実感が、傷つけられることに極度に敏感なおたく連中の精神を安心させるんだよ。目の大きさは単純にその人間に内在する暴力の大きさと反比例してるといっていい。キャラの性格に基づいて目の大きさは変えろ。威圧感を生まない程度にだ。それから、この企画は全部破棄しろ」
「しかし、今から全部練り直していたのでは遅すぎます!」
「ヘッ、そんなせっぱ詰まってから俺ンとこ来やがって(立ち上がると箪笥の引き出しからファイルを取り出す)」
「そ、それは」
「俺が一年前から温めていた企画だ。題して『歌麻呂伝』」
「歌麻呂伝…」
「ふふ、舞台は江戸時代。一人の浮世絵絵師の日常生活を彫刻する…わかるか?」
「(後ろの若者が勢いこんで手をあげる)わかりました! その浮世絵絵師の持つチンポの見事さに毎夜訪れる白人女性たちが『オウ、ウタマーロ』と恍惚の声をあげるという内容ですねッ!」
「はい、アウト。やっぱおまえら負けて当然だわ。東大出て官庁入って権力機構のまっただなかにいるような人間なら白人のデカ女をチンポで蹂躙して征服欲を満たされることもあるかもしれんが、俺達が相手にするのはそんな上等な人間じゃないんだぜ。国の運行に関連する権力機構や企業なんかの経済機構から外れたおたく共を相手にするんだぜ。やつらが必要としているのは自分の優位を前提とした上から下への一方的な愛撫だ。あるいは相手のかわいいだけの女に過去の虐待された自分を投影した自己愛劇だ。設定はこうさ。主人公は浮世絵画家を目指すちょっと気弱で繊細な18歳。ひょんなことから普段は疎遠な祖父から町の長屋を遺産として相続することになる。管理人としてその長屋に訪れてびっくり。なんと住人が全員若い女なんだよ! こいつは売れるぜえ!(両手を広げてみせる)」
「馬鹿な! そんなの非現実的すぎる! 確率論的にありえない!」
「だがある日空から女が降ってきてもうモテモテという話よりはありそうだろう」
「それは比較にすぎませんよ」
「そう、しかし虚構の世界にどっぷりつかった連中にはそれがわからない。同じ車両に毎朝乗り合わせる二人が恋仲になるといったことも現実的にははっきりいって無いんだが、その虚構の持つ『ありそうだ』という部分がやつらのやつら自身を破滅させ続けてきた、やつらをすべての社会機構から外れさせてきた、不都合なことは見えない、盲目な楽観論で構成された頭脳をもしかしてと期待させるのさ」
「しかし、それでは、それでは、まるっきり白痴じゃないですか!」
「あれ、知らなかったの? 白痴なんだよ。ゲームやらアニメやらっていう商売は、システム的に最少人数でまわる、完成してしまった社会における大半の余剰の人員の中の、更に余った社会に不要な人間の不満のガス抜きをするための装置に過ぎないんだよ。精神的なせんずりの手助けとかわんねえんだよ。やつらは期待し続けるのさ。もしかしたらこんなことが次に俺にも起こるかもしれないってな。そして俺達の虚構が与えるわずかの希望にすがって、絶望的な現状に完全に絶望して死んでしまうこともなく無意味に生き続けて、俺達の上にカネを落とし続けるのさ。その無意味な命がつきるまでな。けけけけ」
「(膝の上で拳を握りしめ)私は、私にはそこまで割り切れません…」
「だからおまえらはいつまでたっても三流なんだよ。(黒目と白目が反転した気狂いの記号の目で)せいぜいいい夢見させてやろうぜぇ。やつらの精神とチンポが完全に充足しない程度に満足して、次の作品にもその次の作品にもやつらおたく共が生きている限り永遠に俺達にカネを貢ぎ続けるような、地獄のような夢をよ! ハハハ、アーッハッハッハッハ」
「高須さん」
「(憔悴した顔で振り返り)なんだ」
「我々は、最悪の悪魔と取引をしてしまったのではないでしょうか」
「他にどんな道があったっていうんだ。(自分に言い聞かせるように小声で)これしかなかったんだ。これしかなかった…」
「(遠くから大声で)おぉい、何してんだよ! 早く車まわせよ! 今日は前哨パーティだ! 赤坂で一番高い店を用意させろ! なぁに、すぐに俺が全部取り戻してやるさ! ほっといても可哀想なおたくたちが俺にカネをくれるようになってんだ! いひひひ、 これだからこの商売やめられないぜ!」
聖アヌス衆道院
ここは神の子羊たちが集う人里離れた衆道院。今日の彼らはどんな騒ぎを巻き起こしてくれるやら。
「おはようございます、ブラザー山本」
「おはようございます、ブラザー橋本。あら、今日のあなたの弁髪、とても素敵だわ」
「(頬を赤らめながら)おわかりになるのね。少し今までと結いかたを変えてみたの」
「うらやましいわ。あなたはお顔の形が良いから弁髪がとてもお似合いになる。私なんて、ほら、こんな馬ヅラでしょう? どんなに工夫してもおさまりが悪くって」
「ええ、本当ね」
「(低いドスのきいた声で)なんだと、この野郎」
「あっ、ごめんなさい。そんなつもりじゃ」
「おほほほほ。冗談よ、冗談。ブラザー橋本ったらすぐ本気にお取りになるんだから」
「まぁ! ブラザー山本ったらにくらしい! おほほほほ…あらっ。(食堂の入り口に目をやって)ご覧になって、ブラザー山本」
「ああ、あれはブラザー坂井じゃないの。かれがどうかして?」
「(声をひそめて)ここだけの話ですわよ。他言なさらないでね。かれ、ファーザーグレゴリウスとできてるらしいのよ」
「ええっ! それは初耳だわ。でも、それが本当だとしたら、私、嫉妬で狂ってしまいそう」
「(野太い声で)まったくだ。あんなひ弱なボウヤがファーザーグレゴリウスのチンポを独占してるかと思うとたまらねえぜ」
「ブラザー橋本」
「あら、あたしとしたことがはしたない。おほほほほ…こっちに来るわよ」
「(側を通り過ぎながら会釈して)ごきげんよう、ブラザー山本、ブラザー橋本」
「(つくり笑顔で)ごきげんよう、ブラザー坂井」
「(ブラザー坂井が後ろの席に着くのを確認して)ねえ、ご覧になった?」
「ええ、ええ。ブラザー坂井のあのお顔! おしろいの下から髭が突き出していたわ。きっと昨日の晩から今までファーザーグレゴリウスのお部屋で楽しんでいたに違いないわ。くやしい(ナプキンを噛む)」
「しっ。ファーザーグレゴリウスがいらっしゃったわよ」
「(背景に薔薇を背負って)みなさん、おはようございます。今日も私たちはこのように豊かな朝を迎えることができた。この幸福を私は神に感謝したい」
「(うっとりした顔で)ああ…越中ふんどしの白と赤銅色の上腕三頭筋のコントラスト…素敵…」
「(うっとりした顔で)ああ…私は今日もあなたに会えたことを感謝したいですわ…」
「ときにブラザー山本」
「(はじかれたように立ち上がり)はっ、はい。なんでしょう、ファーザーグレゴリウス」
「(穏やかに目を細めて)サオがスープにつかっていますよ」
「(顔を真っ赤にして)ま、まぁっ! 私としたことがはしたない。(サオをスープから取り出して水気をはらう)ぴっぴっ」
「うらやましいですわ。ファーザーグレゴリウスにお声を頂けるなんて」
「おからかいにならないで。私、恥ずかしくてもう死んでしまいたい(顔を両手で覆う)」
「ときにブラザー橋本」
「(はじかれたように立ち上がり)はっ、はい。なんでしょう、ファーザーグレゴリウス」
「(穏やかに目を細めて)タマがスープにつかっていますよ」
「(顔を真っ赤にして)ま、まぁっ! 私としたことがはしたない。(タマをスープから取り出して水気をはらう)ぴっぴっ」
「さて、それでは食事の前にみなでこの恵みを感謝して祈りましょう……」
「(赤毛の弁髪をふりまわしながら)遅刻遅刻遅刻~ッ!」
「(中庭から食堂棟を見て)まずいよ、ブラザー三島! もう朝のお祈りはじまっちゃってるよ!」
「大丈夫、お祈りが終わるまでに席についていればいいのよ! ついてらっしゃい!(弁髪をヘリコプターのように回転させて中庭を横断し、食堂へ飛び立つ)」
「あ~ん、待ってよぅ(弁髪をヘリコプターのように回転させて中庭を横断し、食堂へ飛び立つ)」
「……アーメン」
「がっしゃ~ん(両手両足を丸めるようにして窓ガラスを柵ごと破壊、空中で前転しながら自分の席につく)」
「がっしゃ~ん(両手両足を丸めるようにして窓ガラスを柵ごと破壊、空中で前転しながら自分の席につく)」
「それではみなさん、いただきましょう。神への感謝の気持ちを忘れずに」
「(さりげなく弁髪についたガラスの破片を指で払いながら)どうやら気づかれなかったみたいね」
「もう、ブラザー三島ったらめちゃくちゃするんだから。私ひやひやしたわよ」
「ときにブラザー三島」
「(はじかれたように立ち上がり)は、はいっ! なんでしょうか、ファーザーグレゴリウス」
「(頭を抱えて)やっぱり気づかれてたんだわ」
「(穏やかに目を細めて)アヌスがスープにつかってますよ」
「(顔を真っ赤にして)ま、まぁっ! 私としたことがはしたない! (アヌスをスープから取り出して水気をはらう)ぴっぴっ…でもこのことで、どうぞ私のことをはしたない男だなんて思わないで下さいましね、ファーザーグレゴリウス」
「(組んだ手の上にアゴをのせて)ええ、もちろんですよ、ブラザー三島。私はあなたのそんな元気なところがとても好きですね。ただ、今度からは遅れても窓からじゃなくちゃんと扉から入ってきて下さい(にっこり微笑む)」
「あちゃ~っ」
「気づいてらっしゃったんですね。失敗失敗(舌を出す)」
「今のお聞きになった、ブラザー山本」
「ええ、ええ。ブラザー三島のことをファーザーが好きとおっしゃったわ」
「(野太い声で)ちくしょう、あのガキ、新参者のくせしていい気になりやがって。今度廊下で会ったら顔面にチョウパン五発もぶちこんでやるぜ」
「ブラザー橋本」
「おほほほほ。失敬。でも、ブラザー坂井には今の発言心中穏やかならないところじゃないかしら(ブラザー坂井のほうに目をやる)」
「そうね。いずれにしても一波乱ありそうね…(ブラザー坂井のほうに目をやる。ブラザー坂井、表情を変えず弁髪を左手で押さえながら完璧な作法でスープを口に運んでいる)」
D.J. FOOD(6)
「 Jam, Jam! MX7! 今週もまたD.J. FOODの”KAWL 4 U”の時間がやってきたぜ! それではいつものように始めよう、 Uhhhhhhhhhhhh, Check it out!
まァ、今でこそ地方局の一D.J.に専属でおさまりいただくわずかのサラリーで細々と二人の娘を養う、地域振興券に非常な喜びを感じるような、お釣りの出ないことに憤りを感じるような、娘二人の現世の様々の欲からもっとも遠い清らかな寝顔に現世の様々の欲の中でもっとも浅ましい欲を抱いて自己嫌悪に陥るような、そんな小市民的な飼い慣らされた日常を堅実に歩んでいるわけだけれど、あの頃は血気盛んなものだったからMOO・念平などというペンネームで子供だましの薄っぺらい熱血学園ガキ大将漫画をしこしこと記述して小金を稼ぎ、安い焼酎などを購入して悪酔いし、抑圧の外れた意識でもって意味の通じない奇声を発しながら外へ駆け出し、電柱に激突して横転、二万人の足に被害を出すほどの荒くれ者っぷりでした。小学館漫画賞をいただいたこともあるんですよ。下から読んだらペンネーム。さて、いつもの犬のようなおしゃべりはこれくらいにして、まず最初のお便りは静岡にお住まいのバルダーズ・ゲート最高!さんからです。『こんばんは、FOODさん、いつも楽しく聞いています。楽しく聞いているんですけど、FOODさんって嘘つきだと思う。だってFOODさんの昔の話って毎回めちゃくちゃだし、全部本当なんてことありえないと思う。全然整合性がないもん。それだけです。あとはいいと思う』 うん、いい指摘だと思うな。現代ほど現実の虚構化が進んでいる時代は過去なかったと言っていい。人間の知恵がある現実を、例えば誰かに伝えるために、言葉でもって確定させようとすること、それ自体がすでに虚構をつくりだしているんだ。家を出て、見上げた空が君にとってとても気持ちのいい様子だったとする。それを、出会った友人なりに伝えるために『抜けるような青空』という言葉でもって説明したとしよう。そのとき、君の目の前の空は確かに青かったが、東のほうから黒い雲がやってきつつあったことや、飛行機が横切ったことや、月がうっすらと見えていたことなんかは省略されている。なぜならそれらは君が感じた『とても気持ちのいい』感情と反する、あるいは全く関係ない事項であるから、省略してしまったほうが相手に誤解なく君の感じが伝わるだろうと君は無意識に思ったからだ。たったこれだけの操作だけれど、それは現実を虚構化していると言える。会話だってそうだ。現代には間をきらい、声を張って、演劇的にしゃべる人間のなんて多いことだろう。そしてみんながみんな、一語の無駄もない”意味のある”やりとりをしようとしている。すべての言葉に意味性を与えようとしている。まるでそれぞれが推理小説の中の登場人物でもあるかのようじゃないか。ネット上なんかもうそれ以外は無いって感じだね。会話の即時的で無さに現実の言語化から更にキーボードやらの装置で打ち出すという段階が加わって、意味の無さは極限まで削られ、必然だけが場を支配する。ときおり見受けられる無意味性でさえ、意味性へコントラストを与えるための役割を受けている。つまり意味が与えられている。要するにね、君の感じている整合性の無さっていうのは、君の周囲をとりまいている、君が知らずならされ適応してしまった虚構内感覚での違和感なんだよ。現実にもともと整合性なんてありはしないんだ。だから君が僕の話に感じるような、もっともあり得なく思えることも、それは虚構内でのありえなさ、おさまりの悪さに過ぎないってことさ。それに、もしかしたら僕自身、虚構の中の人間かも知れないじゃないか。長くなってしまった。さて、次のお便りは栃木にお住まいの片山春美ちゃんからのお便り。『FOODさんひどい。こないだ栃木に来るって言ってたのに、来なかったじゃないですか。ずっと待ってたんですよ。藤野さんは私の友だちです。今度はぜったい来て下さい』 ごめんごめん。本当に行くつもりだったんだよ。死ぬ予定だった叔父が持ち直してね。それもこれも間違って小麦粉を送ってしまったスタッフの中川君のせいだよ。恨むなら彼を恨んでください。本当に今度行きたいと思います。ごめんね。最後のお便りは大阪府にお住まいの小鳥くんからです。『こんばんは、D.J. FOODさん。何度も迷ったんですけど、重大な告白をするためにペンを取りました。ぼくは最近ホームページを作ったんですが、なんだかダメなんです。最初のうちはいろいろみんな褒めてくれて嬉しかったんですけど、最近はもう全然なんです。どうしたらいいでしょう。気持ちに張りが無くなってしまって。このままじゃ僕はダメになってしまうような気がする』 小鳥くん、どんな劇的な革命も変革も、最後には日常に吸い込まれていくんだ。若い頃は、Life is a carnival、ただお祭りのように大騒ぎで毎日が過ぎて、こんなふうに死ぬまで過ごせたらとよく思ったものだ。いろいろと無茶なこともやったよ。でもこんな僕も、最近わかってきた。当たり前の毎日を積み重ねることの尊さを。人の親として大地に身を横たえ、次の世代の肥やしとして朽ちていく喜びを。カストロ議長っているだろう。あの人も自分を取り巻く現実を打破するために革命を求めたはずなのに、その熱狂は死体のように冷えてゆき、いつのまにか自分がかつて自分を取り巻いていた打破すべき現実とまったく重なっていることに気がついてしまったんだ。かれの演壇に立つ疲れた年老いた顔を見たとき、僕はそんなことを思った。だから君も失われていくものを嘆かずにゆっくりと前へ進んでくれ。そして時期が来たら、次に来る者たちのために身を横たえ、彼らに我が身を喰わせるといい。そうやって、人類は歩んできたんだ。今日はなんだか最後に少しセンチになってしまった。来週はまたいつものように大騒ぎでいきたい。Life is a carnival。
それじゃ、来週のこの時間まで、C U Next Week」
廣井王子(1)
「(両手を左右にひらひらさせながら、調子っぱずれな節まわしで)北へ~ゆこうランララン、新しい北へスキップ~…おぉい、みんな喜べよ。新しい企画通してきたぜ。その名もずばり『南へ。』だ。高校三年で受験ノイローゼになった主人公に父親が沖縄行きの往復航空券を手渡してくれるところから物語が始まるんだ。もちろん、米軍基地の兵士であるところの巨乳ホルスタイン娘やら、シーサーに憧れて来邦したベトナム娘やらヒロインたちのバリエーションもばっちりだ。台詞ももういくつか考えてあるんだ、例えばこうさ、『シーサーって、チンポみたいで暖かいですよね』。どうだい、胸がしめつけられるような甘い切なさだろう。あと新システムだが、『北へ。』のCBS(Conversation Break System)を更に進化させたチンポ・バクハツ・システム(Chinpo Bakuhatsu System)を搭載だ。会話の流れをXボタンで中断して『お、おねえさん、ボカァもう』とエロシーンに突入するって寸法さ。もう企画段階であらかじめ売れることが約束されてしまったようなゲームだろう、ええおい?」
「廣井さん」
「しかし全くよく思いついたもんよ。取材と接待と慰安が同時にできるんだもんなぁ。そうそう、こいつはシリーズ化することが本決まりになったよ。じつは第三弾ももう決めてきてあんだ。第三弾は大阪を題材にしたずばり、『キタへミナミへ。』だ。こっちのほうはまだ骨格しかできていないんだが、作品のイメージを象徴するシーンをひとつ考えてある。大阪弁の土着の娘が主人公に言うんだ、『通天閣って、チンポみたいやと思わへん?』。どうだい、胸がしめつけられるような甘い切なさだろう。ただ問題はまともな大阪弁をしゃべれる声優がいないってことだな。これは公募するか…いひ、また有名になりたい頭の弱い娘としっぽり仲良くできるチャンスだよ、いひひひひ」
「廣井さん」
「(口元のよだれをぬぐいながら)な、なんだよ、雁首そろえて集まっちゃって。やめろよ、そんな辛気くさいツラは。ほら、もっといつもみたく明るくいこうぜ、なぁ」
「廣井さん、そちらが空いています。席について下さい」
「なんだよ、今日のおまえたちなんだかおかしいぜ」
「(強く)席について」
「なんだよまったく、わけわかんねえよ…(しぶしぶ席につく)」
「(立ち上がり)さて、みなさまお待たせいたしました。これより本日の議題、総帥・廣井王子の罷免について討議したいと思います。進行は私がつとめさせていただきます」
「ヒーメン? ヒーメンだって? おまえらみんな正気かよ、勤務時間中だぜ(馬鹿笑いする)」
「(無視して)それでは第一の被害者である太谷郁江さんに証言をいただきます(会議室の扉が開き、一人の女性がハンカチで顔を押さえながら入ってくる)」
「(涙声で)あ、あの私、太谷って言います、太谷郁江。このたびこちらのゲームの声優と、主題歌をやらせてもらいました。最初ゲームに使われるっていう女の子の絵を見せてもらって、それがすごく繊細で可愛らしくて、二つ返事でオッケーして、アフレコもすごく熱の入ったいい演技ができたんです、それで、あの、えっと」
「廣井さんとのことを話してもらえますか?」
「あ、はい。廣井さんとお会いしたのは主題歌の収録のときのことでした。私、曲も歌詞も気に入ってて、いっしょに歌う子たちともがんばろうねって話してて、それでその日もいい感じで収録が進んでたんです。そしたら歌の途中に廣井さんが入ってきて、しばらく椅子に座って聞いてたんですけど、突然椅子を蹴って立ち上がって、こんな歌じゃダメだって。それで、私たちのところに来て、いやがる私たちから無理矢理歌詞カードを取り上げて、極太マッキーで修正を入れたんです。私、私だけじゃなくてみんなもすごく気に入ってたのに、録音スタジオの人たちもいいねいいねって言ってくれてたのに、それなのに、それなのに、廣井さんは、う(涙ぐむ)」
「大丈夫ですか。続けられますか?」
「(ハンカチで涙をふいて)はい、もう大丈夫です。廣井さんは、いえ、あの男は、修正した歌詞カードを返して、面白そうに、本当に悪魔のように愉快そうに私たちの顔をのぞきこんで、『ちゃんと歌えよ、本当におまえたちのホタテが蟹で充満しているようにな』って。馬鹿笑いして。私たち何のことだか最初わからなくて、顔をみあわせてきょとんとしてたんですけど、返された歌詞カードに書いてあったのは、か、『蟹がいっぱい、ホタテいっぱい』…う、うふ、うっく、うわぁぁぁぁ(泣き崩れる)」
「ざわざわ」「いやがるのに無理矢理」「ひどい」「妙齢の女性にホタテを強要するとは」
「(列席者を見渡して)今の証言をご記憶下さい。それでは第二の被害者である阪本真亜矢さんに証言をいただきます(会議室の扉が開き、一人の女性がハンカチで顔を押さえながら入ってくる)」
「(涙声で)あ、あの私、阪本って言います、阪本真亜矢。このたびこちらのゲームで声優をやらせてもらって、あ、ロシア人の役だったんです。彼女、ガラス工芸に憧れて日本に住んでるって設定で、私、台本読んで、すごく感情移入して、がんばろうって思ってて。アフレコが進むにつれてますます彼女のことが好きになって、それで、あの、えっと」
「廣井さんとのことを話してもらえますか?」
「あ、はい。あれは、あの、収録も中盤にさしかかったころで、アフレコ現場にいらっしゃったんです、廣井さん。私、この作品のプロデューサーの方だよって紹介されて、すごい緊張しちゃって、何回もリテイク出しちゃって、そしたら、あの、う(涙ぐむ)」
「廣井さんに言われたことをすべておっしゃって下さい。おつらいでしょうが」
「(ハンカチで涙をふいて)わ、わかりました。廣井さん、みるみる不機嫌になって、スタジオの壁を蹴りつけたりして、最後に大声でこう言ったんです、(ふるえる声で)お、『おい、そこのトウの立ったねえちゃん、何年この業界やってんだよ。ただでさえ下手くそなんだから余計な手間ぐらい取らせないでおこうとは思わねえのかよ』…う、うふ、うっく、うわぁぁぁぁ(泣き崩れる)」
「ざわざわ」「ひどい」「正直すぎる」「なにもそこまで言わなくても」
「…ありがとうございます。それだけでしょうか」
「(小さくしゃくりあげながら身を起こし)いえ、まだあります。まだあります」
「お願いします」
「それから廣井さん、しばらく現場を見てたんですけど、退屈になったらしくてうろうろしだして、私のほうに近づいてくるといやがる私から無理矢理台本を取り上げて、これじゃ臨場感が足りないな、みたいなことを言って、ポケットから取り出した極太マッキーで修正を入れたんです。私、その部分の台詞がすごく好きで、家でも何度も練習して、あの、こんな台詞です、『ガラスって、人肌みたいで暖かいよね』、すごくいいと思いませんか、彼女の優しさや心の豊かさがとてもよく表れていると思うんです、それなのに、それなのに、廣井さんは、う(涙ぐむ)」
「阪本さん、もう結構です」
「いえ、いえ、言わせて下さい。廣井さんは、いえ、あの男は、修正した台本を返して、面白そうに、本当に悪魔のように愉快そうに私の顔をのぞきこんで、『言ってみろよ、なぁに、いつもの調子でやりゃいいんだ』って。そこに書いてあったのは、そこに書いてあったのは(蒼白で倒れそうになる。支えようとする左右の人間を手で制して)…『ガラスって、チンポみたいで暖かいよね』…地獄に、地獄に落ちればいい! 私も、あの男も! ちくしょう、ちくしょう、ちくしょう…(付き人に支えられながら会議室を出ていく)」
「ざわざわ」「いやがるのを無理矢理」「ひどい」「妙齢の女性にチンポを強要するとは」
「以上が総帥・廣井王子の罪状に関する証言です。(向き直り)さて、廣井さん。何か反論はありますか?」
「バカヤロウ、反論も何も、こんな」
「(さえぎって)無いようですね。それでは総帥・廣井王子の罷免に賛成の方、挙手を願います(全員の手があがる)。賛成多数。数えるまでもありませんね。本日ただいまの時刻をもって、廣井王子の罷免を決定致します」
「おい、待てよ、冗談だろ? いったい誰がこの会社をここまでに育てあげたと思ってんだ? すべて俺のおかげだろうが!」
「廣井さん、貴方は少々やりすぎたんですよ。天外魔境2に携わっていたころの貴方は輝いていた…(目をつむる)」
「(低く)このインポ野郎め。俺は俺の間違いに気がついたんだよ。俺は本道に立ち返ったんだ」
「今どきエロばかりでゲーム会社が成り立つと本気で思っているんですか?」
「(噛みつくように)じゃあ、テメエはエロぬきでゲーム会社が成り立つと本気で思ってんだな?」
「(肩をすくめて)廣井さんにはそろそろご退場願いましょうか。(慇懃に)あなたの今後の人生がやすからんことを」
「(引きずり出されながら)三年だ! 三年後をみていろ! 俺が正しかったことが証明される三年後を! そのときこそおまえたちは俺の足下にひざまずき、戻ってきて下さいと哀願するんだ! はは、ははは、ははははははは」
裸の王様
上品なバーのさざめき。突然入り口の扉がくの字に折れ曲がり逆方向の壁にスッとんで叩きつけられる。
「(チンポ丸出しで)デストロォォォォイ! 裸の王様のお出ましだァ! おっと、精薄ども、動くんじゃねえよ! もしぴくりとでも動いてみやがれ、俺様のこいつが火をふくぜ!(ト、人差し指と親指を折り曲げて拳銃の形にした右手を構える)」
「ジョージ、なんなのあれ。私怖いわ」
「HAHAHA、春先にはこういうヤツが多いんだよ。すぐにつまみだしてやるから安心しな、ヨーコ……(錨のいれずみが入った上腕を誇示しながら)どうやら入る場所を間違えたみてえだな。俺が病院に送り返してやるよ。ヘッヘッ」
「(癇癪の青筋をこめかみに浮かせて)動くなっていったでしょおッ! (人差し指を男の頭部に向けて)ばぁん」
メリケンの頭部がはじけとぶ。飛び出した目玉がシャンパンのグラスに沈み、泡を立てる。
「きゃああああああっ」
「(人差し指の先を吹いて)いい? みんなこの男みたくなりたくなかったら動くんじゃないよ…ああ、暑い。何か冷たい飲み物が欲しいなぁ(カウンターに目をやる)」
バーテン、ひきつった笑いを浮かべながら飲み物を用意しようと後ろの棚に手をのばす。
「動くなっていったでしょおッ! ばぁんばぁん」
バーテンの頭部が四分の一吹き飛び、腹に向こう側が見通せる大穴があき、そうして糸の切れた人形のように横倒しに倒れる。開いた蛇口から吹き出す大量のビール。
「これが心理学で言うところのダブルバインドってヤツよ。試験に出すから覚えておいたほうが利口ですよォ…おい、そこの金髪」
「(半笑いで)な、なんスか」
「(バーテンの死体を指さし)なんて言うんだっけ、こういうの」
「あ…あの(薄ら笑いを浮かべる)」
「ばぁんばぁんばぁん」
金髪の身体にみっつ穴があく。金髪、その穴を何度も信じられないという泣きそうな顔で確認し前のめりに倒れる。金髪の死体にのしかかられた老婆が白目をむいて卒倒する。
「馬鹿。ほんと馬鹿だね。みため通りの馬鹿。オリジナリティのかけらも無いね。民族としてのアイデンティティを放棄してるくせに個人としてのアイデンティティすら確立できてないんだよ。ほんと馬鹿。最低だね…おい、そこの女」
「(半笑いで)な、なんでしょう」
「(バーテンの死体を指さし)なんて言うんだっけ、こういうの」
「ダ、ダブルバインド」
「せいか~い。かしこ~い。ご褒美たくさんあげなくちゃねえ? ばぁんばぁんばぁんばぁんばぁん」
一瞬のちに女の身体は肉の破片でしかなくなる。燃え残った灰が崩れるように、数秒おいて彼女だった残骸がその場に濡れた音をたてて崩れる。
「復習ですよ、復習。けけけっ。さぁて、つまらない遊びはこのへんにしとかないとな。話すことはたくさんあるんだ。まず掲示板のことだが、これは別におまえらとコミュニケーションをとるために設置してんじゃねえんだ。俺の存在が唯一絶対であり、おまえらの意見なんざ一切聞き入れる気はねえってことをおまえたちにも目に見える形でわからせるために置いてあるんだ。その深遠な逆接を読みとりもできずに、ヘラヘラなれなれしく話しかけてくんじゃねえ! おまえがコスプレしようが下痢しようが俺の知ったことか! くだらねえ批判もだ! それは自分のホームページに反映させてろ! 読む時間と書く時間が無駄だ! ただ賛美しろ! 俺を褒めたたえろ! ばぁんばぁん」
二人の男女が眉間を寸分たがわず打ち抜かれ、びっくりしたような表情のまま吹き出す血の勢いで後ろむきに倒れる。
「ああ、せいせいした。まったくよォ…ばぁん」
左脇下から見えない背後を撃つ。若い男性が胸に穴をあけられくるくるコマのように回転して倒れる。
「クズ、クズ! 批評家きどりめ! 『もう限界ですか?』だと? したり顔め! 死ね死ねっ! ばぁんばぁん」
もみ手でつくり笑いの男が両足を撃ち抜かれる。噴水のような出血。
「友だちからだと? 友だち募集だと? おまえが欲しがってるのは友だちなんかじゃなく自分の賛美者だろうが! 不完全で矮小な自らの自我を補償してくれる白痴的な追従者だろうが! 幼少期の濃密な愛情の欠如から自己存在を意味性によって形づくることができなかったので、そんな一時しのぎの、くだらない、間に合わせの品でなんとか応急手当しようと必死ですかァ? おまえがタチ悪いのは、その操作にある程度自覚的なことだ。無理だよ、おまえみたいなのは一生友だちなんてできないね…(向き直り)おまえたちみたいのは何年生きたって意味ないよ、進歩ないよ。死ね死ねっ! おまえたちみんな死んでしまえ! ばぁんばぁんばぁん、ばぁんばぁんばぁんばぁん」
裸の男が人々の密集した一角に飛び込み、たちまち店内は阿鼻叫喚のちまたとなる。
すべてが終わった後、立っているのは裸の男だけ。血煙にけぶる店内を大股に横切って最奥のソファに身を投げ出す。
「(半眼でけだるく)純粋な愛情を手に入れた肉だけが人間になることができるんだ。それ以外? それ以外の肉は人であることを喪失して神になるのさ。いや、もっと正確に言うなら神と全くズレなく重なる自我を手に入れさせられるんだ。その中で神の自我にふさわしい能力を持つものは、圧倒的な賛美者に囲まれ時代の真の神となり、それのかなわなかった肉は――つまり神たる能力を持たなかった肉は、だな――こんな安普請のつくりごとの中で(ト、手をのばし後ろの壁を軽く叩く。薄っぺらなベニヤの壁は倒れてその向こうに虚無をのぞかせる)賛美者をかき集めるために裸で舞い踊るのさ。けけけ。いずれにしても人間じゃない以上人間の幸せは手に入らねえがな。(目をつむる)最初にチンポを舐めさせていたのは俺のほうだったはずなのに、いつのまに俺がチンポを舐める側になっちまったんだろうな…」
セットの後ろに無数の顔が浮かびあがる。その顔には一様に目・鼻・口がついていない。
「(跳ね起きて)バカヤロウ! 降りてこい! いつまでそこで眺めてるつもりだ! 舞台に立てよ! こっちに来いよ! ばぁんばぁん(弾はすべて水面に投げた石のようにわずかの波紋を残して吸い込まれていく)。 くそ、くそっ! そっちがそのつもりなら、見てろ、見てやがれ!」
裸の男、ペニスを握りしめこすりはじめる。
「どうだ、畜生、こういうのが見たいんだろう、こういうのが見たかったんだろう!」
虚無に浮かぶのっぺらぼうの顔の筋肉がうごめき、笑いともとれるような感じをかたち作る。男のペニスが勃起しはじめる。
「(荒い息の下で)あ、やっぱり…喜んでくれてるんだ。あなたたちが喜んでくれると僕はとても嬉しいんだ…あなたたちが喜んでくれないと僕は自分がいないような気持ちになる…だって僕にはあなたたちを笑わせて喜ばせることしかできないから…それ以外の価値なんて僕にはないんだ…知ってるよ、知ってる…ああ…」
突然のっぺらぼうの笑みが消える。冷たいさげすんだ視線の感じが残る。顔が一つづつ消えはじめる。男のペニスが萎縮していく。
「あっ…待って、待ってよ! ひどい、ひどいじゃないか! 見ていってよ、最後まで見ていってよ! ひィ、ひィィィィィィ」
裸の男、誰もいない廃墟につっぷして泣き出す。が、突然身を起こし、
「なぁんてね。びっくりした? びっくりした? おい、みんな、いつまで寝てんだよ!」
撃ち抜かれた部位はそのままに、男の声に呼応して死んだ客たちがむくりと起き出す。
「いやぁ、もう小鳥くんたら迫真の演技なんだもん。私あせっちゃった(^^;」
「ほんとほんと(笑)。俺、マジでちょっとちびっちゃったよ(TT」
「メンゴメンゴ(笑)。でもネットって本当にいいよね! たくさん友だちできるし、それに…」
「それに?」
「千佳ちゃんにも会えたし…(*^^*)ポッ」
「きゃあ☆ それってもしかして…告白?(^^;」
その様をいつのまにかまた空中に現れた無数の顔が見つめている。口元に浮かぶ侮蔑の笑い。
「あはは、いいなぁ(^^) みんなほんと最高だよ。ネットワーク最高! ずっとここにいたいなぁ(泣)」
「いいんだよ、ずっとここにいて(^^; 現実はつらいからね(笑) 現実は容赦ないからね(爆笑)」
福本伸行的クライマックス麻雀劇画
えんじ色のブルマが宙を舞って卓上に落ちる。
「ツモ。5200だ」
積み上げられる現金を手で払いのけ、
「いらぬ世話だ。すべて幼女同人誌に変えてもらおう」
金庫から取り出される幼女同人誌20冊。規制のない昭和40年当時の幼女同人誌は、現在の価値に換算すると約200冊分…!
「少なくとも今までワシが殺してきた、ロリコンを装ってはいるが実は成熟した自我との折衝を恐れているただ自分が好きなだけの人間…そういう輩とは質が違うというわけか…!」
小鳥巣の口元に浮かぶ笑み。
「だが、それでも負けるが麻雀だ」
「悪いな。通らず、だ」
小鳥巣が白パンティを卓に置くのに反応して倒される手牌。
「8000」
テーブルを殴りつける小鳥巣。
「馬鹿な! もう100時間以上は打ち続けているはずだ! なぜ切れない? なぜ三人で交代して打つワシたちを圧倒できる? 狂ってる、狂ってる、この…最悪の童女愛趣味者め!」
引いてきた縦笛に間髪入れず左端の網タイツを切りとばす。ざわめく黒服たち。
「おい、今のでアガりじゃないのか?」
「まさか、まさかヤツは…!」
「それ以上の勝ちに何の意味がある!? 多すぎる勝ちは賭けを成立させる世界そのもののバランスを崩してしまう! やめろ、生きて帰りたかったらやめるんだ!」
流れ始めるブルージーな音楽。
「俺はただ」
ツモ山に青白い手がのびる。
「醒めない夢を見ていたいだけなのさ」
発光する、骨そのもののような指が牌に触れる。鳴り響く銃声。卓に肉のぶつかるにぶい音。
「(かすれた声で)和了、です」
力無く開かれた指の間からこぼれ落ちる黒ランドセル。男の目に白い膜がかかる。
「殺すことは、なかったのに」
勝負の終わった麻雀卓を取り囲む三人の黒服たち。冷えていく男の死体。
「奇跡は起こらなかったな。この男も小鳥巣様を倒すことはできなかったわけだ」
「いや、見ろ」
「ああ……!」
卓上に流れる血が黒ランドセルを赤ランドセルに染めていく。
「ロリータ大三元完成、か」
窓を開け、月を見上げる黒服。雲ひとつない夜空に完全な満月。黒服のサングラスから光るものが伝い落ちる。
the lyrics to fly
俺はきっとおまえのことだから / 逃げて逃げてたどりついた / この掃き溜めみたいな場所でも /
きっと長くもたないんだろうなって / ケツを割っちまうんだろうなって / ひそかに思ってたよ /
でもおまえは危なっかしい足取りで / 無気力の足かせをはめられ /
まともに動くこともままならないような / 倦怠の重石をのせられ / もうしょうがねえ /
とうにへばって座り込んで泣き出して / そうしてもおかしくないのに / 少なくとも俺は責めやしないのに /
何かを運ぶしか知らない牛のように / いらいらするような速度で / よたよたよたよた /
たどりついちまいやがった / 個人が得る最悪の制限を / その人格の上に受けて /
なのに同じような何事も無い顔で / いいわけをせず誰かのせいにもせず / とうとうたどりついちまいやがった /
俺はおまえのことがずっと嫌いだったけれど / ようやく重石を道端に放り投げ / 涙と鼻水で顔を汚し/
肩であえぐこの瞬間のおまえだけは / とても好きだと言うことができるよ / 愛していると言うことができるよ /
俺はきっとまた / すぐおまえのことが嫌いになるんだろうが / この愛を感じた一瞬のせいで /
よりいっそう嫌いになるんだろうが / たとえそうだとしても / 俺は今のおまえを愛しいと思うよ / 尊いと思うよ /
おめでとう / おめでとう /
風の歌を聴け
僕たちは店の奥にある薄暗いコーナーで脱衣麻雀を相手に時間を潰した。幾ばくかの小銭を代償に死んだ時間を提供してくれるただのガラクタだ。しかし鼠はどんなものに対しても真剣だった。ゲーム・オーヴァーの赤い文字がお嬢様の真っ白なパンティの上に表示されたとき、僕たちは二人の財布をあわせての全財産、ちょうど50枚の百円玉を投入し終わったところだった。
「お高くとまりやがって。この売女が!」
鼠があらあらしく筐体を蹴り上げる。チョッキ姿の店員が人混みをかきわけこちらに向かってくるのに、僕は鼠を後ろから抱えるようにしてゲームセンターの外へと連れ出した。
冬の夜気は、寄る辺無い人間にとってずいぶん身にこたえる。街灯に群がる蛾の羽音が響きわたる路地裏で、誰も追ってこないのを確認して僕は路上に座り込んだ。鼠はどうにも腹の虫がおさまらないといったふうでコーラの自販機を殴りつけた。ケースの灯りが明滅して、消える。
「おい。もうよせよ。」
「5000円だぜ。職も無いのに。何やってんだ、俺たちは?」
鼠が吐き捨てた唾は、道端に広がる反吐と混じり合って濡れた音をたてた。
「間延びした時間、ケチな遊び、こんなのはもうたくさんだ! なぁ、あんたはこのままでいいと思ってんのか?」
「しょうがないだろ。俺たちを受け入れてくれる場所なんて、この社会には無いんだよ。」
「だからって、」
「おまえはそうやっていつも、酒や何やの勢いを借りて、問題を声にした時点で満足しちまってるんだよ。俺は本当に、絶望的にどうしようもないのを知ってるのさ。だから俺は、いつも黙ることにしている。」
とびかかってくるかと思ったが、鼠は急に脱力したようになってその場に座り込んでしまった。
「わかってるんだよ。でも不安なんだ。俺はあんたみたく大人じゃないから、言わずにはいられないんだ。」
「俺だって、何かわかってるわけじゃないよ。ただ、自分がわかっていないことをわかっているだけなんだ。」
沈黙。僕の言ったことが聞こえたのかどうか、鼠は宙を睨んで言った。
「考えたことないか? このまま、アニメや漫画の二次元の異性だけが興味の対象のまま、二十年経ったらって。定職にもつかず、社会からのかろうじてのお目こぼしをさずかって、稼いだ日銭をLDやらグッズやらにつぎこんで、人づきあいはネットの上しか無くて、ネットでは馬鹿みたいに明るい演技して、外見は年をとるのに失敗して不気味に若々しくて、そんで二十年で技術はすげえ進歩してて、ほとんど人間と変わらないエロゲーキャラの等身大人形とセックスしてんだよ。直結したノートパソコンとマウスでヴァギナの位置や愛液の量を調整したりしながら、その人形を愛撫してんだよ、本当に心からの愛情から。やっぱ純愛ですね、鬼畜系はダメですよ、とか言ってんだよ。ネットで。顔文字つきで。萌え~とか言ってんだよ、本当は何よりも自分のことが一番好きなくせに。それは、正しいのか? もうそれは人間じゃないんじゃないのか? 人間とは呼べないんじゃないのか? …俺たちはどうなっちまうんだろう。俺たちは本当に、どうなっちまうんだろう。」
鼠は抱えた膝の間に顔をうずめると、すすり泣きはじめた。僕はジーンズの尻から煙草を取り出すと、火をつけた。
たちのぼる煙に、けばけばしい都会のネオンライトがゆらいだ。だが、それは煙のせいではなく知らず流れ出た涙のせいらしかった。
たとえそうなることをあらかじめ知っていたとして、僕たちにどうしようがあるというのだろう。僕は鼠の述懐を聞いていて、むしろ心地いいと感じている自分に気がついていた。
鼠は十分ほど泣き続けていたろうか、顔をあげると照れくさそうにセーターのすそで涙をぬぐった。
「その携帯ストラップ、いいな。」
「ああ、いいだろ。おじゃ魔女どれみだよ。見つけるのに苦労したんだぜ。」
僕たち二人は顔を見合わせると、声をたてて笑った。
小鳥猊下その愛
「『あら、それじゃあなたはとあるVIPと知り合いだと言っていたけれど、今の話だと女性の身体を触ってもちんちんが起立しない男が友達にいるってだけじゃないの』
『 いや、ぼくは確かにVIPと知り合いなのさ。なぜなら彼はVery Impotent Personだからね!』
『まぁ! もう、ボブったら本当に憎らしい!』
『アハハ。君があんまり真面目なんでちょっとからかってみたくなったのさ、メアリー!』」
「あっ。小鳥猊下が少しも笑えない覚えたてのアメリカンジョークを上に向けた掌をへその付近で小刻みに左右に揺らしながらヒクツな漫才師の笑顔で発話しつつ御出座なされたぞ」
「ああ、なんてださおなら面白くないのかしら。思わずあくびとともに大量の涙がまなじりから吹き出したわ。そしてそれは私の淫水を暗喩しており、その量と正比例しているわ」
「なんや、今日の客はノリが悪いで。舞台は客との共同作業や。よぉ覚えとき。ほなワシは失礼させてもらうで」
「もう。なんで僕がこんな売れない演歌歌手みたいなことしなきゃいけないわけ。客の質は最悪だしさぁ。だいたいチンポとかオマンコとかしゃべるだけですぐ自我の抑圧から解放された心の一番深い底からの笑いを白痴的に爆笑できるような人間はわざわざぼくの公演を見に来ることないんだよ。幼児期に感情を抑圧せねば今まで生きてこれなかったような人種が、履歴書に記載された情報と二時間ほどの面接で判断されてしまうような人格の表層のやりとりに疲れ果てた人種こそが、そのすさまじいまでの心のくびきを解き放つ時間を持つために、錯覚のような一瞬間だけでも楽になるためにやって来て欲しいんだよ。君もヘラヘラもみ手してないでもっとマシな仕事入れる努力したらどうなのよ。いい加減にしないと温厚なぼくでも怒るよ、ほんと。(ノックの音にいずまいを正しあわてて煙草をもみ消しながら)あ、は~い。どうぞ、開いてますから。あれっ。女の子じゃない。どうしたの。とりあえず中にお入りなさいな。ずぶ濡れじゃない。うん。ぼくに会いたくてわざわざ北海道から出てきたんだ。君もヘラヘラもみ手してないで着替え持ってきてあげなさいよ。こんな場末の盛り場を一人でうろついちゃ危ないよ。明日になったら送ってあげるから、今日のところは泊まっていきなさい。え、帰りたくないの。義理のお父さんが暴力をふるうんだ。泣かないで。お母さんには相談したの。知ってる。世間体のために見ないふりをしているのか。泣かないでよ。…ときに経済力のない子供であるという事実はそれだけで充分に屈辱的だよ。ぼくがここで放り出したらこの子はきっとどんどん身を落としていくんだろうなぁ。…よければ、ぼくといっしょに来ないかい。君に君を喰いものにしない、世間体や打算でない本当の愛情をくれる暖かい午後のようなお父さんとお母さんをあげるよ。保証してやれるわけじゃないけれど、君は今より幸せになれるかもしれない。うん、いい子だね。まだ名前を聞いていなかったね。名前は…」
「真奈美、どうしたんだ。電気もつけないで」
「お父さん。うん、ちょっと昔のことを思い出していたの」
「そうか。(穏やかな顔で手をさしのべながら)さぁ、もう夕御飯の時間だ。今日はステーキだってお母さん言ってたぞ」
「(目尻をぬぐって明るく)やったぁ。あたし、ステーキだぁい好き!」