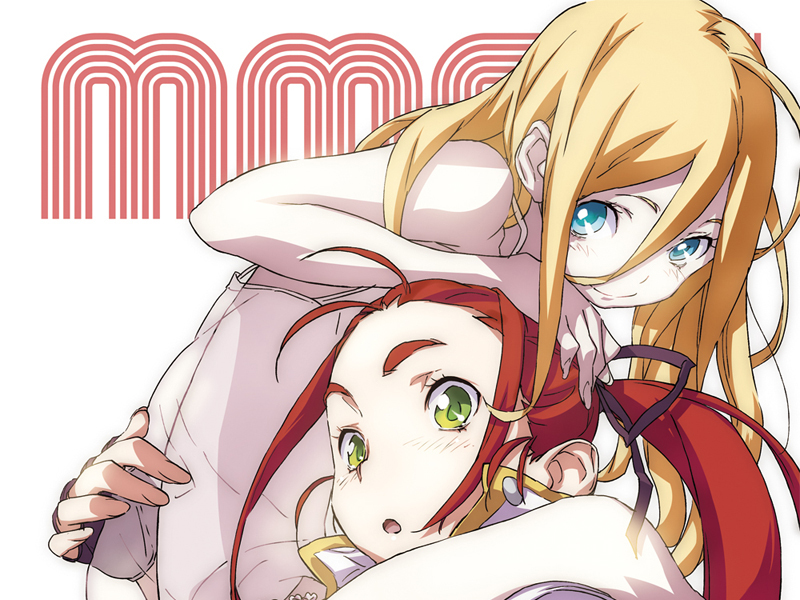「いま三十代ぐらいで、
戦争でもないのに周りでバタバタ人が死んで、
気づけば友人や仲間は誰ひとりいなくなって、
寂しさより先に自分の番が来るのを怯えてて、
世界に大義なんてものはなくて、
人生に目的なんてものはなくて、
生命に意味なんてものはなくて、
痛めつけられた猫が車の下で傷に舌を這わせるときみたいな、
ほんの小さな平穏と安堵だけがただ続けばいいと願っている、
そんな君に向けた、萌え萌え学園ファンタジー」
プロローグ
我が敵は頭上にあり。
血と汗は足元に滴りて、豪奢な模様をなす。
我が脚は腰を貫き、尻でようやく釣り合えり。
我れ、反り返るは古代人の弓の如し。
すさまじいプレッシャーが、両腕を通して全身を伝わるのがわかる。
魂を高揚させていなければ、おそらく最初の衝撃だけで潰れてしまっていたに違いない。
まるで、轍に轢かれる蟷螂のように。
またひとり、崩れ落ちる。倒れたあとも、手のひらは頭上へと向けられている。
両手にあるプレッシャーがわずかに勢いを増す。
背骨がきしむ音が聞こえる。
灼けるような塊が腹部から喉へめがけて、駆けあがってくる。
ここまでか。
いや、まだだ、まだだ。
味らいをひたす熱した海水を、無理矢理のみくだす。
ここで倒れれば、すべてが終わる。
一千年前、小さな集落から始まった寄る辺ない人々の歴史は、終焉をむかえる。
いや、まだだ、まだだ。それは、いつか必ずやってくるのだろう。
だが、いまではない。
折れそうになる膝に力をこめる。
ずっと、自分だけのために死ぬと思っていた。
だから、もしここで命はてるのだとしても――
誰かのために死ねることが、うれしい。
またひとり、崩れ落ちる。
遠くで、何かが砕ける音が聞こえる。
吸い上げられるように全身から力が抜け、急速に地面が接近する。
次瞬、視界は暗転し、耳の中にわずかなノイズだけを残す。
虚皇日記 -深淵の追求-
MMGF!(1)
ペルガナ市国は半島の先端、ペルガナ史跡群と呼ばれる古代遺跡を覆うように成立した国家である。「鋤を入れれば遺跡に当たる」と言われ、古代遺跡をそのまま住居とする一帯も見られる。観光と学術研究がペルガナ市国の主産業であり、ふんだんに与えられた過去の遺産が国民の気質を穏やかにしている。
悪く言えば進取に欠け、国家プロジェクトであるはずの発掘と研究も一向に進みはしない。
なので、気持ちのいい晴れの日に、ショウ・アンド・テルと称して史跡群に連れ出したぼくのプロテジェが、歴史的な発見をしてしまうことも、実のところまれではない。
暖かい陽光に背中をあぶらせながら古代の生活へ思いを馳せているところへ、不吉な影が差す。
顔を上げると、一千年の空想もふっとぶ仏頂面の少女がにらみつけていた。
「メンター・ユウド」
小さな造作の顔なのに眉だけが太く、それが釣りあがるととても怖い。
動揺を見せまいと、ぼくはゆっくり膝の埃をはらって立ちあがる。
「何か問題でもあったのかな、スウ・プロテジェ」
動揺を見せないことはメンターにとって、いちばん重要な資質だと思う。けど、ぼくの声は少し裏返っていた。このプロテジェのことは、我がクラスを取りまとめるモニターとして信頼している。しかしながら、そのまじめ極まる仕事ぶりがぼくのいい加減なところを非難しているようで、ときどき苦手なのだ。
ぼくの無為へ何か批判を加えでもするように、スウは片方の眉を上げる。
けれど、彼女の発言はモニターとしての分を外さないものだった。まじめなんだよな。
「年少組がまた何か見つけたようですので、メンターの実地検分をお願いします」
また、というところに力がこめられる。やっぱり暗に非難されているのかもしれない。確かにここのところ、教室で講義をした覚えがないから。
「了解した。案内してくれるかな、スウ・プロテジェ」
「こちらです、メンター」
鷹揚に立ち上がると、後ろに手を組んで後をついてゆく。
スウはぼくよりも頭半分ほど背が高いので、横に並ばないように注意しなくてはいけない。もっとも、彼女がとくべつ高いというより、ぼくが低いんだ。狭い遺跡の入り口を這い入るには便利だけれど、威厳を保つには不便だ。
歩調に合わせ、一本にくくったスウの赤い髪の毛が馬の尻尾のように揺れる。
まるで時計の振り子みたいに規則正しく左右に揺れるので、ぼくは眠気を思い出す。
それにしてもいい天気だ。適度に暖かくて、昼寝にはもってこいの。
ぼくは空を見上げる。
ペルガナ市国の条例は、一般住居を平屋建てにすることを定めている。人口に比して土地がふんだんにあることと、何より古代の建築物との調和を乱さないためである。
だから、空がおそろしく広いのだ。
天球、という言葉がぴったりで、あらゆる方向へほとんど際限なく広がっているように見える。
ここで研究職に就くもののご多分に漏れず、ぼくも元々は留学組だ。初めてこの土地に着いたときの感動は、いまでも鮮明に思いだすことができる。
黒い森を越え、木製のやぐらを尻目にし、街道の果ての果てで乗合馬車を降りたとき、あまりの膨大な空間に圧倒され、思わずその場にへたりこんでしまった。
緑の丘々の稜線は天球の湾曲に沿うように、その奥に横たわる真っ青な海は水平線を無限に広げている。
ぼくは常々、自分のことを感情的というよりは、理性的な人間だと思っている。しかし恥ずかしながら、最初の呆然とした気持ちから醒めたぼくは、そのとき少し涙ぐんでいた。
でもそれは、この土地を訪れる者のうち、とびきり珍しい反応というわけではないらしかった。乗合馬車の御者がそばへやって来て、口ひげと皺の中の笑顔から座りこむぼくに片手を差し出す。
そして、こう言ったのだ。
「ようこそ、故郷へ」
なま白い手を握り返した赤銅色の力強さに、もう予感がしていた。
ぼくはきっと、この国で一生を終えることになるにちがいない。
どすっ。突然のやわらかい感触。
「どうかしましたか、メンター・ユウド」
どうやらぼくは思い出に浸りすぎていたらしい。
立ち止まるスウに気づかず、背中にぶつかっていたのだ。失態である。
「ごめん、ちょっと考えごとをしていたんだ」
ぼくが深遠で高尚な思考をめぐらせていたと、このモニターが誤解してくれることを祈った。
だが、ちらりと目をやった彼女の頬が紅潮しているのは、どうやらぼくの試みが失敗に終わったことの証明らしい。怒っているのにちがいない。
怒ったスウ・プロテジェは、とても怖い。
ぼくはあわてて気をそらそうとする。
「あそこがそうかな」
指さした先には、ぼくのプロテジェたちが集まって何やらワイワイと騒いでいた。
ペルガナ市国の教育システムは、ぼくの生まれたところとはだいぶ違っている。いちばん特徴的なのは、あらゆる年齢の子どもがひとつのクラスにいることだろう。ちなみに、ぼくの受け持ちクラスには、六歳から二十歳までが同居している。
あまり期待をせずに歩み寄る。経験則(膨大な)から判断すれば、校外実習の際にプロテジェが当たりを見つける確率は、千にひとつくらいだ。手をさしいれたら、兎の巣穴だったこともある。ぼくは噛まれた。スウは噛まれなかった。研究の足しになるような遺物が見つかればいいんだけど。
ペルガナ史跡群から発見される道具、武器、生活用品、住居に至るまでがすべてひとつの共通した言語によって統御されているのは周知のことだ。
人類が世界の各地へと広がってゆく前に用いられていた、大統一(グラン・)言語(ラング)だとされている。ぼくたちが日常で使う言葉とは異なり、発した瞬間に現実へ物理的な干渉を行う。
単語や文法の概念もいちおうは存在するが、例えばひとつの単語の意味を担保する音声の幅は、ぼくたちの認識からすれば無限に近いほどの諧調がある。
文法にしても同一の単語が音声の違いによって品詞をたがえたり、おまけに構文が存在しないものだから、理論通りに運用することは極めて難しい。むしろ音楽に近いと表現したほうがいいくらいだ。
事実、古代人の交響曲だと考えられていた半刻近くにおよぶ音声記録が、ひとつの名詞を修飾する関係詞節の羅列に過ぎないことが判明したこともあった。その日、ぼくは寝こんだ。とかく、グラン・ラングはぼくたちの日常感覚を超越する。
だから、「神様のことば」なんて称されたりもする。信心深くないペルガナ市国の住民の言うことだから、揶揄も相当にふくまれている。だが、それは案外、遠くない例えなのかもしれない。ぼくにしたところで、学園に奉職してからたっぷり十年はグラン・ラングを専門に研究しているのに、まだその端緒についた気さえしない。
グラン・ラングの研究者にのん気な性格の人物が多いのも、うなずける。あくせく動いたところで、それは無限を前にすればゼロと同じだからだ。一生涯のうちにすべてが解明されることは、まずありえない。手の届く範囲だけをしっかりとやって、時が来れば次の世代にバトンを渡す。人間ができるもっとも偉大なことは、永遠を前にこうべを垂れる謙虚さだと知っているのだ。だから、ぼくのサボリも人間の本質へ迫る哲学的な内容を多分にふくんでいると考えてほしい。
どうやらプロテジェたちは、岩と岩の間に隠れた亀裂をのぞきこんでいるらしい。身体を横にすれば通れそうだ。
「見つけたのはだれかな」
声をかけると、みんないっせいにふりむく。
おもはゆい。大勢を前にメンター然としてふるまうことが苦手だったりする。
「ぼくです!」
最年少、六歳のシャイがいきおいよく手をあげる。信頼とあこがれしかない、子犬のような目でぼくを見つめてくる。
ぼくは他人から信頼されることがつらい。いつか自分の中の悪い部分が、それを裏切る気がするからだ。
正直であることは美徳だと思う。けど、正直にふるまうことができるのは、己の本性が善良であることに疑いのない人間だけだ。
ともあれ、少なくともこの瞬間、ぼくはメンターとしてプロテジェたちの前に立っており、それを演じる義務がある。
ぼくはシャイの頭に手をおいて、くしゃくしゃとかきまわす。
「よくやった。これはペルガナ市国の歴史の中で、もっとも偉大な発見のひとつになるにちがいないよ」
スウの視線を感じる。その顔には「前も同じことを言いましたよ」と書いてある。
けれど、賢い彼女はプロテジェたちの前でぼくに恥をかかせたりはしない。
言ってみれば、これはぼくの決め台詞だ。とかくメンターは衆人環視の中でコメントを求められがちである。だが同時に、繰り返しの日々に生きるメンターが対応するべき状況もさほど多くはない。場面に応じたいくつかの決め台詞を持っていれば、動揺による権威の失墜を避けられる。
しかしその定型文も、シャイ少年と一部のプロテジェたちには大きな感銘を引き起こしたようである。集団を前に重要なのは、異なった解釈の余地がある言葉を使わないこと。
ぼくは他人の視線を意識すると、動きが速くなる傾向があるようだ。状況を早く終わらせたいからだろう。はしっこい小男ほど、権威と遠いものはない。
後ろに手を組み、ことさらに悠然とプロテジェたちが取り囲む亀裂をのぞきこんでみせる。どうやら、地下道の天井に開いた亀裂らしい。
ぼくがひと言を発すると、壁が発光を始める。心の中でくちぶえを吹く。まだ生きている遺跡だ。取り囲むプロテジェたちが、おー、と声をあげる。おもはゆい。ぼくはただ、グラン・ラングで「光」と言っただけだ。
けど、プロテジェたちが驚くのも無理はないかな。ただの単語でさえ、メンターなのに使えない人、多いんだから。文節単位以上のグラン・ラングを発話することを施術と表現するが、意味のある文章を構成すること自体が並大抵ではない。
ペルガナ史跡群の遺跡は、壁面そのものが照明になっていることが多い。しかし、ここまで完全に機能しているものはめずらしい。地下道はわずかに湾曲しながら、奥へと続いている。
ふつう、どこかで埋まったり、途切れたりしているものだけれど……。
「刀を持ってくるんでしたね」
いつのまにかスウが隣に来て、亀裂をのぞきこんでいる。小さな顔が、ぼくのすぐそばにあった。若さゆえの無防備さに、心音のトーンが変化するのを感じる。できるだけ不自然にならないようにゆっくりと身をもぎはなすと、できるだけ明確になるよう言葉を選びながら、プロテジェたちに宣言する。
「この遺跡は第一級のものであり、ただちに調査を開始するべきと判断します。年少組はこのまま帰宅しなさい。年長組は学園へ戻り、事務へ調査チームの編成を依頼します。その後は帰宅してよろしい。予備調査のための斥候部隊はメンター・ユウドと――」
シャイが目を輝かせて跳びあがりかけるのに、
「志願します」
間髪を入れず、スウが手をあげる。冷静だ。そして、的確だ。
「よろしい。年長組は遭難等、万一の事態のために、メンター・ユウドとスウ・プロテジェが先行していることを同時に伝えてください。では、解散します」
プロテジェたちは三々五々、与えられた指示を持ってこの場を離れていく。シャイがうらめしそうに何度もこちらを振り返ったが、もどってくることはなかった。
「さて――」
スウが切り出す。にっこりと微笑んだ彼女は、猫のような好奇心でいっぱいだ。
「はじめましょうか、メンター」
二人きりのとき、彼女のほうが主導権を握っているような気がするのは、ぼくの気のせいだろう。きっと、劣等感がそう感じさせるんだろうな。
「少し高さがある。ぼくが先行しよう」
短くグラン・ラングを発すると、ぼくとスウの周囲を風がとりまく。
亀裂に手をかけて内側へとびこむと、ぼくの身体は重力を知らないようにゆっくりと下降してゆく。靴底で床の強度を確かめ、通路の前後を確認する。
「大丈夫みたいだ。おいで」
スウは亀裂に身体を押しこむのに四苦八苦している。凹凸がありすぎるんだよな。
やがて落下傘のようにスカートを広げながら、放射状に床のほこりを舞わせて着地する。
「もしかして、見えました?」
「いまのところ、魔物はいないみたいだね」
ぼくはスウの質問にとぼけた返事をかえす。
「それは何よりです」
スカートについたほこりをはらいながら、スウが言う。顔が紅潮しているのは、やっぱり怒ってるんだろうな。
地下遺跡の中に生態系を持つ生き物全般を、ペルガナ市国では単に魔物と総称する。言語学者は多いが、生物学者は少ないからだろう。
地上へ出てくることはほとんどなく、人に危害を加えることもまれである。過去の被害報告は遺跡の調査隊に限定されており、魔物にとっては要するにぼくたちのほうが侵入者なのだ。
壁が発光しているとはいえ、それは光ごけ程度のもので、かろうじて視界を約束してくれるだけだ。本は読めないだろう。ときどき、通路の奥からうなり声のようなものが響く。それが風鳴りなのか、何か生き物によるものなのか、わからなかった。
「やっぱり刀、持ってくるんでしたね」
すぐ後ろを歩くスウが、心細そうに言う。
「それより、荒事にならないことを祈ろうよ」
実際、魔物の一匹や二匹、腺病質のメンターひとりでも簡単に撃退できるだろう。でも、そういう筋肉質の発言をしないのがぼくのスタイルなのだ。
グラン・ラングを殺傷に用いることができるのは、研究者ならば誰でも知っている。けれど、殺傷を目的とした論文は受理されないことも学会における暗黙の了解になっている。もちろん、方便に過ぎない。心意気、みたいなものだ。刃物は、野菜も切れれば人も切れる。すべての研究は裏腹に、真逆の側面を抱えている。大事なのは、どちらをより多く見たいか、ということだ。
通路は右に曲がりながらわずかに傾斜し、地の底へとつづいているかのようだ。歩けど歩けど、どこかに到着する気配はない。
古代遺跡には大きく分けて、私的な住居と公共施設とがある。当たり前のことだ。当たり前のことだが、数千年を経て、古代の人々もやはりぼくたちと同じ人間だったのだなあ、という感慨をいつもおさえることができない。しかし、この遺跡が何の目的で建設されたものなのか、これまでの経験との類似点を見つけだすことがいまだにできないでいた。
進むにつれて天井が低くなり、圧迫感をもって頭上にのしかかってくる。閉所恐怖症にはつらいだろうな、これは。あるいは、背の高い青年男子には、かな。
ほどなくして、スウが立ち止まった。
「予備調査の役割は、もう十分に果たせたと思われますが」
せめてこの遺跡が建設された目的がわからないと戻れないよ――そう言おうとして振り返る。低い天井へ前かがみになったスウの太い眉が、情けなく垂れ下がっている。ぼくはなんだか愉快になって、思わずメンターらしくないからかいをする。
「なあんだ、怖いのかい」
たちまち薄明かりの中でもわかるほど、スウは真っ赤になった。
「いえ、別に」
ぷい、とぼくから視線をそらす。ふだんとは違って、抑制の裏がすけて見えるのがおもしろい。逆襲の機会を逃さじとまわりこんで、視線をつかまえる。
「やっぱり怖いんだ」
「こわくなんかないです!」
めずらしく、感情的に声をあらげるスウ。見れば、目にはうっすらと涙が浮かんでいる。しまった、調子にのりすぎたか。
この娘はモニターとして、他のプロテジェたちのみならず、ぼくの保護者をも自認しているようなフシがある。優等生は、演じようとしている役割を否定されることにいちばん傷つくのだ。
ぼくはあわててメンターへと退却した。
「すまない、スウ・プロテジェ。いまのは撤回する」
スウの感情から肩書きを利用して逃げたのだ。ずるいやり方だ。
しかし、スウはぼくの作戦には気づかないようだ。いや、賢い彼女のことだから、気づかないふりをしているのか。
「いいえ、私のほうこそ、自制心を失いました。ゆるしてくださいますか」
厳しい表情のスウ。ゆるしてもらうのはこっちなのだが、ぼくは立場を悪用して主客をひっくりかえした。ゆっくりうなずくと、見ているこちらの胸が痛むほど、スウは表情をゆるませる。
「ひ、ひとつ言わせていただきたいのは」
なぜか、スウはひどく言葉をどもらせた。喉の動きでつばを飲みこむのがわかる。
「私はメンターといっしょならば、何も怖いことはありません」
声がふるえている。ここまで動揺したスウを見るのははじめてだ。遺跡の中には、悪い病気が閉じこめられていることもあるという。その影響かもしれない。早く調査を終わらせなくちゃな。
安心させようとして、ぼくはできるだけの笑顔で両手をあげてみせた。
「さあ、調査の続きをしよう。きっともう、長くはかからないよ」
先へ進もうとするが、スウは両手を組みあわせたまま固まっている。
しまった、笑顔が不自然だったか。しょうがない。できるだけやさしくと努めながら、譲歩を提示する。
「君がどうしてもイヤなら、学園から本隊がやってくるまで調査は中断しようか」
スウの口元がなぜかへの字に曲がり、幾度も目をしばたかせる。
「いえ、続けましょう。きっと長くはかかりませんから」
大股にぼくを追いこすと、肩をいからせるようにしてずんずんと奥へ歩いてゆく。
メンターの習い性かもしれないが、人の感情を己の利に誘導しようとするのは、ぼくの悪癖と言える。どうやら、スウを完全に怒らせてしまったらしい。
あぶないよ、と声をかけるが、ふりむきもしない。
ぼくは、悄然とついてゆくしかない。ああ、二人きりでよかった。つま先をながめながら少女のあとをついてゆく小男に、不審者以外の名前をつけることは相当に骨の折れる作業だろうから。
どすっ。突然のやわらかい感触。
気がつけば、ぼくはまたスウの背中にぶつかっていた。
「メンター、見てください」
状況に負けて思わずあやまってしまいそうになるのを、その声色が止めた。
通路は、その突き当たりで広大な空間へと変じていたのである。
おそらく、この広間の外側を巻くようにして、ぼくとスウは下ってきたのだろう。
床は土でむきだしになっていて、壁面はまぶしいほどに発光している。薄闇になれた目には、少々きびしいくらいだ。
広間の中心には、形も大きさもふぞろいの透明な円柱が、不規則に林立している。ぼくはくちぶえをふいた。
「こりゃ、当たりだ。シャイ少年の名前が教本に載るかもな」
きょとんとした顔でスウがたずねてくる。
「どうして当たりだってわかるんですか」
好奇に見ひらかれたスウの瞳がすこし赤くなっているのが気になったが、ぼくは大仰にため息をついてみせた。
「学力優秀なきみがこの光景から答えを見つけ出せないのだとしたら、ぼくのクラスにぼくの講義を理解しているプロテジェは、ひとりもいないだろうね」
優位であることが明らかな場面で皮肉っぽくなるのは、ぼくの悪い癖その二だ。
「講義中、資料じゃなくて、何か別のものを見ていたんじゃないのかい」
この言葉に、スウはたちまち真っ赤になった。クラスを預かるモニターとしての矜持が、このような遠まわしの侮辱に耐えられないのだろう。
「いえ、わかります。ちゃんとメンターのお話は聴いていましたから。古代人の公共施設に特徴的なものは、玻璃です」
祖母に育てられたというスウは、ときどき妙に古い語彙を使う。学園の外部理事だったよな、お祖母ちゃん。血統だな。
ぼくはスウのあとを引き取った。
「その方法は失われ、ぼくたちは粗悪なコピーを使うばかりだが、水晶は古代人にとってエネルギーを蓄積し増幅する一種の装置だったと考えられている。一般的に、遺跡のいちばん深いところに水晶はすえられ、全体へとエネルギーを供給する。数ある鉱物の中で、特に水晶が選ばれる理由は――」
「グラン・ラングとの親和性が高いからです」
じろりと視線をやると、あわててつけくわえる。
講義の中でならば、スウはぼくにとって極めて御しやすい相手と言えるのだった。
「教科書的には満点だけれど、意味がわかって言ってるかい?」
スウがぶんぶんと首をふる。範囲を定めた暗記ではいつもクラスいちばんなんだよな、この娘。
「グラン・ラングは現実へ干渉する。とはいえ、あくまで一過性の現象を引き起こすにすぎない。グラン・ラングの効果を固着させ、好きなときに取りだすことができるのが、水晶の特徴なんだ。エネルギーの蓄積や増幅も、その一環に過ぎない」
「なんでもできるんですか」
「理論上はそうみたいだね。グラン・ラングで記述された情報を集積するサーキットだから。古代人は紙を使わなかったそうだ」
「どうやって勉強したんでしょうね」
首をかたむけて腕組みするスウ。どうやら調子がくるっているのはぼくだけではないらしい。
「いま何の話をしているっけ」
「水晶ですね……ああ」
ぽん、と手をうつスウ。じろり、とにらみつけるぼく。
「これが口頭諮問なら落第点をつけているところだよ。紙の情報は少なくとも物理的には力を持たないし、量も非常に限定されている。質にしたところで、ぼくたちの日常語とグラン・ラングとの間には比較できないほどのへだたりがある。ぼくたちだって、膨大な情報の塊からできていると言えないこともない。もし、グラン・ラングのすべてが解明されるようなことがあって、無限の情報を蓄積できる水晶がどこかに存在するとすれば、生命をゼロから作り出すことも可能と主張する論文を読んだこともあるよ」
もっとも、ありえない仮定をふたつ組みあわせたその論文は、研究というよりは小説、というお決まりの非難でどこからも相手にされなかったみたいだけれど。
「おーい、生きとるかー」
いくつかの足音とともに、妙な抑揚の声が聞こえる。
どやどやと広間に闖入してきた白衣のプロテジェたちをかきわけて、声の主が近寄ってくる。黒髪に黒い上着、黒い巻きスカートのその女性は、肌の色も真っ黒だ。羽織っている白衣以外は、すべて黒いという徹底ぶりである。
「あいかわらず夜のように暗いね、キブ」
「アンタの性格ほどではないな、ユウド」
このやりとりはお決まりである。
だが、物忘れのように毎回、キブは大きな胸をゆらして豪快に笑う。こぼれた歯がすばらしく白く見える。これだけ黒ければ陰影も消えて、身体の起伏もわからなくなりそうなものだけれど、なんというか、こう、非常に肉感的な女性なのだ。
「おう、水晶林があるやん。こら、有望かもしらんな」
白衣の上からでもわかる大きなお尻をふりながら、キブは水晶のほうへとかけてゆく。
キブは史学科のメンターで、ぼくたち言語学科の人間とは切っても切れない関係にある。グラン・ラングには文字が存在しない。なので、遺跡で発見される遺物(レガシー)がなければ研究はおぼつかなく、グラン・ラングの知識がなければ、レガシーを精査することはできない。レガシーの中には、個人を特定するための起動ワードが封印されていることも少なくないのだ。
だから、史学科と言語学科の研究活動は、非常に相補的だったりする。公的・私的の区別なく、懇親を深める機会は多い。スウが研究員たちに取り巻かれているのが見える。なぜか、スウは史学科の男性研究員たちに人気があるのだった。
その様子を見ていると、妙に胸のあたりがざわざわする。まあ、容姿も端麗で、応用力に欠けるきらいはあるにせよ、聡明な少女だ。とりまき連ができるのはふしぎなことではない。
「ちょっと、こっち来てくれへんか」
袖をひっぱるキブ。水晶林までぼくを連れてゆくと、声を低くして耳うちする。
スウが顔をあげてこちらを見ているのが気になった。
「調査隊までひっぱってきてアレなんやけどな、この遺跡、お手つきや」
ぼくは全身が脱力するのを感じる。
「確かなのかい」
「まちがいないわ。見てみ」
キブが親指で示した先には、切り株のようになった水晶があった。視線をあげると、ところどころに同様の切り口が見られる。
「インクルージョンはすべて持ち出されてるみたいやな」
インクルージョンは史学科と言語学科に共有される隠語、一種の専門用語である。簡単に言うと、中身の入ったバケツのようなもの。中身はグラン・ラングの音声データであったり、レガシーであったり、抽象・具象さまざまだ。
そして、グラン・ラングを吹き込む技術が現代に継承されていない以上、空の水晶はただの鉱物にすぎない。
「はずれかあ」
嘆息して天をあおぐ。
「せめて、アルマのひとつくらいはと思ったんだけどなあ」
攻撃に特化したグラン・ラングが吹き込まれたレガシーを、特にアルマと呼ぶ。必ずしも武器の形をしているとは限らないが、とにかく多く産出する。古代人は、きっと戦争が大好きだったのだ。
「直接、研究室へ来てくれたらよかったんやけど、アンタのとこのプロテジェが事務を通してしもたからな。レポート出さなあかんで。あと、うちの連中へするペイのことも忘れんとってや。なんも成果があがらんかったら、内規ではアンタの自腹になるさかいにな……って、聞いとんのかいな、ユウド」
実際、ぼくは半分も聞いていなかった。
天井から巨大な水晶が、つららのようにぶらさがっているのに気づいたからだ。
薄紅色をしたその水晶の先端に、何かが入っている。
異変に気づいたキブが、ぼくの視線の先を追う。
「うひゃあ、ローズ・クォーツや! それに、見てみい、あの大きさ! あんなデカいの見たことないわ」
抽象・具象にかかわらず、内包するものの性質によって水晶は色を変えることがある。しかし、これはちょっと群を抜いている。
「なあ、先っぽに入ってるの、人に見えないか」
キブは手のひらを水平にかざしながら、目を細める。
「ちょっと透明度が低い水晶やから、はっきりとはわからへんけど……言われてみたらそんな気がせえへんこともないな」
「ふたりでこそこそと何をしておるのだ」
高圧的な低い声をかけられ、ぼくとキブは同時にふりむいた。
スウが腕組みをして立っている。制服の袖は肩口までまくられ、スカートは先ほどの半分ほどの長さにたくしあげられていた。
服装よりも表情だ。太い眉と両目は吊りあがり、唇の片側は挑戦的に歪んでいる。
ぼくはスウの腰に視線を送る。
そこに――
刀をはいていた。
ぼくはごくり、と唾を飲みこむ。かろうじてしぼりだした声は、みごとにかすれていた。
「それは、異装だよ」
「ふん、最近のメンターは学則も暗記していないとみえる」
スウは胸元にこぶしを引き寄せると、大仰にふりひらく。
「プロテジェ各人の特質を引き出すことに寄与すると客観的に判断される場合、学園の制服はその変形を認めるものとする!」
わあ、その条項、「客観的に判断する」のがだれかわかんないんだよなあ。やっぱり、「受け持ちのメンターが」と読むべきなんだろうなあ。
スウの背後で、上気した顔の研究員たちが、歓声をあげる。何しにきたんだ、あいつら。もうしわけなさそうな顔でキブがささやく。
「ウチはいちおう、止めたんやで」
刃物を持つとこの娘は、性格がおだやかではなくなるのだ。
うん、ほんのちょっとだけ。
「あれだな」
腕を組んだまま、小さなおとがいでスウはローズ・クォーツをさす。元々の造作が変わらないせいか、ひどく凶悪な印象を受ける。もっとも、背後の研究員たちがぼくに同意しないことは、尋ねるまでもない。
「人が入っているな」
「本当かい?」
ぼくは驚いて、思わず聞き返してしまう。失態である。
「プロテジェの言を信じようとしない点は、愚かなメンターの常として聞き流すとして、私の能力に対する疑義が呈されたのは看過できぬな」
スウの目が細められる。おそろしい三白眼だ。
来るぞ、例のやつだ。
「我が視力の透徹なるは星をもとらえッ!」
両手を広げると、スウは右足を大きく一歩ふみだす。
キブが悲鳴をあげて背後へまわりこみ、研究員たちが「うおおーっ」と歓声をあげ、ぼくは背中から両腕をつかまれて立ちつくす即席の人間盾と化す。
「我が拳の精強なるは金剛石をも粉砕するッ!」
ふみこんだ右足を支点に回転しながら左足を引き寄せ、両手を高くあげながら見得をきる。
「我が知恵の深甚なるは世界の深奥へ至り――」
首をふりまわしながらさらに見得をきる。赤いポニーテールが少し遅れてついてくる。
「そして、我が剣技の精妙なるは全ての物質の形状をあまねく規定するッ!」
右手が束にかかり、匕首の切られる音がする。
「我が剣の意思にそむくものは己を非存在と心得よ!」
気がつくと、ぼくの鼻先に剣先の冷たい感触がある。見えなかった。
血はでていない。でていないが、数分後に鼻だけもげるような技をすでにしかけられたのかもしれない。いや、もしかすればうしろのキブが血ぬれの遺体となって地面に転がっている可能性すらある。刀をはいたスウに関して、ぼくはすべての希望的観測をゼロにして向きあおうと決めているのだった。
もはや謙虚のショウ・アンド・テル教材と化したぼくは、降参のあかしに手のひらを見せて、「わかりましたわかりました」としゃがれた声でくりかえした。
「少なくともユウド、貴様には実際に証明しておく必要がある」
スウは傲然のショウ・アンド・テル教材のごとく胸をそびやかし、ぼくの鼻先からローズ・クォーツへと剣先を移す。
「とりだしてやろう」
本当かい、と言いかけて口をつぐみ、ぼくはあやういところで命びろいをする。
キブがぼくの右肩にあごをのせてのぞきこみ、様子をうかがっている。どうやら、まっぷたつにはなっていなかったらしい。まだ。
「ただ、アレが人である可能性を残す以上、わずかでも中身を傷つけてしまうことは避けたい。わかるな?」
ぼくとキブはつりこまれて、もはやメンターとしての威厳もどこへやら、がくがくと首を縦にふった。尖ったアゴが、肩に痛い。
「危険をゼロに近づけるためには、私の身体能力を若干高める必要があろう。そこで貴様の出番というわけだ、ユウド」
口の端をゆがめるようにして笑う。わるい子になってしまった。
だが、スウが言うからには、その見立ては正しい。
以前、史学科研究員たちの悪ふざけ(きっと、特殊な性癖を満たすためだ)で、スウはさまざまの硬度を持つ素材を試し切りするハメになった。切れないものは当然なかった。自然石にはりつけた濡れ紙を両断したり、濡れ紙を両断せずに自然石を両断したり、度肝をぬかれる見世物だった。グラン・ラングと同じように、ほとんど物理法則に干渉しているとしか考えられなかった。どうやったのかを尋ねると、「通すか切るかの違いだけだ。貴様には見えないのか」とだけ答えた。ある研究員が、自分のうしろにおいた木材を切断してみてくれ、と申し出たときはしかし、鉄拳で答えた。「遊びで用いていいものと、そうでないものの違いもわからんのか。愚か者め」
傲岸不遜だが、大言壮語ではない。刀をはいていようといまいと、根っこの部分では人に対する愛情がある。
ぼくはうなずく。
「よし、やろう。君のことを誰よりも信頼しているからね」
スウは一瞬もとのような顔になったが、すぐに背中を向けてローズ・クォーツと向かいあう。
「言葉にする必要がないことは、言葉にせぬのが賢明だ。そして女!」
「はいッ!」
キブが直立する。
「ユウドから離れておけ。集中の妨げになるといかんからな」
キブはぼくの肩をぽんぽんと二回たたくと、研究員たちのほうへと下がっていった。
「倍は必要ない。さあ、やれ」
ほっそりとしたスウの身体に意識を集中させる。もちろん、やましい意味ではない。伸びた足と膝裏のくぼみは悩ましいにせよ、仕事と私的な趣味を混同しないのが大人というものだ。
グラン・ラングの研究分野はいくつかの大きなカテゴリに分けることができる。それぞれがさらに子や孫にあたる分派を持っており、いまや相当度に細分化されている。本来ならば、すべての分野を横断的かつ学際的にとらえなければいけないだろう。だが、いかんせん、母体があまりにも無辺大に広がりすぎているのである。それぞれを組み合わせたときの有機的な動きというよりは、各パーツの持つ意味へ個別に当たっているのが現状だ。
ぼくが専門にしているのは、「付与」と「維持」である。付与者(エンチャンター)にして維持者(アップキーパー)というわけだ。研究分野の選択は、どうも研究者の性格と大きく関与している気がしてならない。専門による性格占い、というわけではないが、少なくともぼくの親しい研究者仲間で両者の不一致を感じることはない。人であれ、物であれ、自分以外に干渉するのが「付与」と「維持」のグラン・ラングが持つ特徴である。性格占いの結果は、野次馬とおせっかいだ。
この分野に関して、じつはけっこう決定的な論文を書いたことがある。研究全体の方向性そのものを変えてしまうような。慣例ではあるにせよ、うちのボスとの連名で発表されたので、周囲の評価がぼくに対して高いとは言いがたい。けど、内心ではこの「付与」と「維持」の実質的な第一人者であると自負している。
論文内で便宜上、魂と名づけたものへ直接干渉することで、人の身体能力を一時的に高めることができる。これが、「魂の高揚」と表現するぼくの発見。ちょうど、自律的に燃焼するロウソクの炎を外部からの操作によって、一瞬だけ激しく燃えたたせるイメージだ。ロウソクの比喩は二重になっていて、やりすぎると疲労を通りこして寿命そのものを縮めてしまいかねない。
この発見の後、丸二日寝こんだ。研究者の倫理として、まず己を実験台にしたからだ。自分のエネルギーを自分に供給すると、暴発をまねくという貴重な体験である。あくまで「付与」は、外的な現象であるべきという教訓だ。
集中を極限まで高める。
視界の明度は暗灰色へ。
事物の輪郭は、闇色へ。
スウの内側に清浄な青い光輝の塊が浮かぶ。
網膜を焼くその美しい輝き――
これこそが、魂と名づけられた内なる燃えあがりである。
ぼくは低く言葉をつなぎはじめる。細心の注意をもって、音をつなぎ、抑揚をつなぎ、意味をつなぐ。ひとつ発音をまちがえてさえ、グラン・ラングは全く異なる解釈へと変じてしまう。
剥きだしの魂を前に、生殺与奪はぼくの上にある。
それが、スウの信頼のかたち。
青い炎が燃えあがり、光を増す。やがて純白の輝きへと変じ、両目を射る。
スウが視界から消滅する。
跳躍したのだ。ローズ・クォーツを頂点とする軌跡を描いて、着地する。
ぼくは反響する鍔鳴りで、かろうじて抜刀があったことを知った。
奇跡の一瞬は終わり、広間には静寂の音が残された。
振り返ったスウの額には、髪の毛が一筋、汗ではりついている。
「よくやった。成功だ」
その言葉を待っていたかのように、頭上でローズ・クォーツが破裂する。外部からの衝撃というよりは、内圧で吹き飛んだように見えた。赤い水晶の破片は、壁面からの発光に照らされて、さまざまな色を発しながら、雨の如くぼくたちへ降りそそぐ。キブと研究員たちは一大スペクタクルに歓声をあげたが、ぼくの目は別のものをとらえていた。
水晶の破片にまぎれて、人が降りてくる。降りてくる、と表現したのは、まるで羽毛のようにゆっくりとした落下だったからだ。
ぼくは息をのむ。全身をおおうまでに豊かな髪の毛は黄金のように輝き、のぞく肌は乳のように白い。永遠とも思える時間のあと、一糸まとわぬその人影は、ぼくの両腕の中へおさまった。
人間の子どもだ。ぼくは目をみはる。
そして女の子だ。ぼくは目をそらす。
小さな、氷のように冷たい手のひらが頬にふれる。魚のように濡れている。
その瞳は、燃える魂ように青く。
その唇は薔薇水晶のように赤い。
この世のものではない美を前に自失するぼくの首へ、冷たい両腕がまわされる。
深く、長い吐息のあと――
渇した旅人が泉へじかに口をつけるように、薔薇水晶の唇はぼくの唇を狂おしく吸いあげたのだった。
MMGF!(2)
会議が建設的であるための条件はいくつかあるが、構成員の全員が共通の利益を代表していることは、そのうちでも大きなもののひとつだろう。利益を獲得できないことが大きな不利益、あるいは組織の存続に関わるような場合はなおよろしい。そして、会議時間は明確に区切られてあるべきだ。会議の長さを水増しするのは、だいたいにおいて感情的な側面なのだから、それが入りこむ余地をあらかじめ織りこんではいけない。
だから、どう転んでも、この会議は建設的にはなりようがないのであった。
定例の学科長会議は月に一度、全学的に休講の上で、朝から行われる。
名称こそ学科長会議だが、その構成員は原則としてプロテジェを指導できる資格を持つ者、すなわちメンター以上とされた。終了時間は特に定められておらず、アジェンダの記載事項がひと通り報告・審議しつくされるまで続く。
また、ペルガナ市国の行政庁、通称ブラウン・ハットの政策決定に関する諮問委員会を兼ねているため、議題の内容は学園運営や学術報告の範囲に留まらない。資料が前日までに提示されることはきわめてまれであり、原案すら存在しない審議事項も少なくない。人の叡智というよりはむしろ忍耐力を試される場であり、市国唯一の学府とは思えぬ混沌をはらんだ会議である。
すでに開始から四時間は経過していようか。もはや会議の流れについていく気力を失って、ぼくはぼんやりと室内をながめる。
出席者全員が対面するよう、長方形に配置されたテーブル。
学園長やブラウン・ハットの長官を始めとした首脳陣の座る一辺が、慣例的に上座である。そこから遠ざかるほど人物の持つ権威は弱まると考えてよい。
ぼくとキブは学園長から最も遠い場所に、なかよく座っていた。首脳陣と学科長以外の座席は特に定められておらず、なんとなくいつもとなりあって座る。
史学科長、つまりキブの直接的な上司に当たる人物の「第三百四十五次ペルガナ史跡発掘中間報告書」が、(恐ろしいことに)ただそのままレジュメ通り読みあげられるの聞きながら、ぼくは窓の外へ目を向けた。あいもかわらず、とびきりの晴天である。会議室の内側から見る空が、いつもよりずっと青く見えるのはどういう物理現象だろう。
ぼくのななめ前方(より権威に近い)で、きつい目をした痩身の男が、指先にまで神経が通っているように、するどく挙手をした。目には燃えるような意志の力がみなぎっている。苦手なタイプだ。
「議長、発言を許可ください」
「報告が進行中ですが、メンター・スリッド」
議長が許可を与えたと思ったのか、スリッドは決然と立ちあがった。またか、という感じで顔を見合わせる列席者たち。
「史学科長殿は、我々に発掘品の品目を順番に聞く義務があるとお考えか。あるいは、ペルガナ市国の学府に籍を置く我々の誰かが、この資料に書かれた文字を読めぬと疑われているのか。議題は山積している。前回の会議でも申し上げた通り、議長は議題の優先順位をあらかじめ決定し、迅速な議事進行に努めるべきである」
「うちのボスにゆうてもしゃーないがな」
スリッドから目をそらしたまま、キブが小声でつぶやく。
すかさず、学園長から近い位置に座っていた筋肉質の男がぬっと手をあげる。岩のごとく節くれだち、親指が五本ならんでいるような手。体技科長だ。
「いまの発言は、学科の思想的独立性に対する深刻な疑義の提示と考えられる。発言の撤回と、議事録からの削除を願いたい」
気の弱い人が聞いたら、それだけで卒倒しそうな胴間声だ。
「異議なし」
「異議なーし」
間髪をいれず、体技科のメンターたちが唱和する。上背も横幅もぼくの倍くらいあるんじゃないか。
市国警備隊を兼任する体技科は、要するに兵隊さんだ。他国の侵略から学園のみならずペルガナ市国全域を防衛するために、青少年の健全な育成と肉体改造に日々はげんでいる。だが、「遺跡に眠る巨大人型兵器の謎」といったジュブナイルによる消極的イメージ外交の結果なのか、ここ百年でペルガナ市国が外的侵攻を受けたという記録はない。なのに、演習と称して捕獲した魔物と素手で格闘したりするのだ。
彼らがヒグマだとすれば、スリッドは気性の荒いニワトリにすぎない。
「学園長は会議内に恫喝のまかりとおるこの現状をどのようにお考えか!」
だが、痩身を反らせ、猛然といどみかかる。
この間、報告の腰をおられた史学科長は、レジュメの束を手にもったまま、怒りによるものか、はたまた老人性の何かによるものか、ぷるぷるとふるえ続けていた。
スリッドの発言が武と文を分離することの有用性へおよびはじめた頃、会議室の扉がノックされる。
「失礼します」
聞く者をふりむかせる、凛とした声。スウだ。
「メンター・ユウドに解決をお願いする案件が発生しました」
ぼくは助かったとばかりに立ちあがり、早足になって内心を悟られぬようゆっくりと出口へ向かう。スウの顔が、このときほど愛らしく見えたことはない。
「あの、いちおう手順ですから」
穏やかに、諭すような声。おっと、忘れるところだった。ぼくは咳払いをひとつして、ゆるんだ表情を引き締しめるとふりかえる。
「中座を許可下さい。案件を処理次第、直ちに議場へ復帰いたします」
白髭の学園長がうなずき、うらめしそうなキブの視線を尻目に、ぼくは完全に解放されたのだった。
廊下へ出て、うつむき気味の数時間に曲がった背中をのばすと、ぽきぽき骨が鳴る。
もう歳かなあ。さほど広くない会議室でのひといきれは、よっぽど空気をよどませていたんだろう。ただ息を吸いこむことがいやに心地いい。こういうとき、幸せとは不幸のない状態をさすのだな、としみじみ思う。
「メンター・ユウド」
とがめるような声にぼくは首をすくめる。少し覚悟をしてふりかえって、笑ってしまった。スウが、飼い主に額をたたかれた犬のような、情けない顔をしている。
「マアナかい」
「マアナです」
わずか一週間ほど保護者をつとめただけなのに、ぼくたちふたりの呼吸はもうぴったりだ。おもむろにスウが制服の袖をまくり、ぼくの鼓動を少し速める。二の腕には、きれいに歯型がついていた。
「噛みぐせがなおらないなあ」
自分で言っておきながら、ほとんどペットに対する口調だな。
「散歩につれていくために服を着せようとしたら、暴れだして……」
「そりゃあ、まあ、いやがるよなあ」
例えば、よろいかぶとの常時着用が義務づけられた文明圏に生活する事態におちいれば、最初はぼくでも抵抗を示すにちがいない。
「でも、女の子に裸で外を歩かせるわけにはいきません」
言いながら、なんだか変なことを話しているなという困った表情になるのが面白い。
「それで、むりやり押さえつけたら噛みついて、逃げ出しました」
「つまり現在、裸の少女が学園内を徘徊しているということだね」
「しかも噛みつきます」
スウが強調する。今日が会議日でよかった。学園内に残っているのは、一部のまじめなドミトリ組だけだろう。だいたいが町で遊び歩いているはずである。
ぼくとスウが話しているのは、遺跡から連れ帰った女の子のことだ。
人形のように整った顔立ちに気おくれがしたのは、最初の眠りから覚めるまで。いまでは遠い昔のことに思える。食事は手づかみする、服はやぶいて脱ぐ、夜中に起きて暴れだす、気にくわないと噛みつく、怒るとつばをはく、おまけにトイレ……いや、これは言うまい。
とにかく、見た目から想像する中身との落差が壮絶なのである。狼か何か、人類ではない生き物に育てられた野人が、マアナなのだ。この名前は、彼女が怒ったときに叫ぶ声がそんなふうに聞こえたので、とりあえず呼んでいるうち、ぼくたちの間で定着してしまった。
「メンター・ユウド、ちょっとマアナは私の手には負えません」
ここ一週間、満足に眠れていないスウは、育児疲れとしか形容できないものを表情に漂わせている。
「ぼくの子どもだと思って、落ちつき先が決まるまでもう少したのむよ」
我ながら、ずるいやり方だよなあ。頼りすぎていることは自覚している。けど、他に方法を思いつかない。キブに預けることも考えたけど、下手すると腑分けとかされそうだ。水晶から産出したものは人じゃなくてインクルージョンだと言い張ってるからな。
しばらく歩いて、スウがついてきていないことに気づく。ふりかえると、完全に固まっている。
「おーい、どうしたんだい」
スウの目の前で手のひらをふってみせる。
「な、なんでもありません。それより、マアナを見つけないと」
顔を真っ赤にしたスウが足早に追いこしていく。
あれ。何か悪いこと、言ったかな。年齢的にも思春期だしな。
若者の心を忘れてしまった大人の苦悩をかみしめながら、ぼくはずんずんと遠ざかる赤い馬の尻尾を追いかけた。
学園は新棟と旧棟に分かれていて、それぞれ木造と石造りである。教室やドミトリなどプロテジェが中心にかかわる施設は新棟に、研究棟や会議室などメンターが中心にかかわる施設は旧棟に集中している。
スウを追いかけて新棟を通りぬけるとき、ドミトリの玄関でそうじをしている女の子がぼくに会釈をしてくれる。寮長だ。思わずぼくも頭を下げる。
ドミトリには長くお世話になった。より正確には、まだお世話になっている。他国からの留学組に提供される学生寮で、年齢の若いものは相部屋からはじまり、成長に従って個室が与えられる。入居の規約は、じつにこと細かい。しかし、退居に冠する条項はただひとつ「プロテジェの身分を喪失したとき」だけ。広義に解釈すれば、学科長以外は指導を受ける上位者が常にいるわけで、プロテジェと定義できないこともない。ペルガナ学園の良いところは、現存するルールの適用については厳密なのに、ルールがおのずから持つ抜け道をふさぎにはかからないおおらかさにある。メンターとプロテジェは謙虚なぼくにとって対立概念ではなく、いまだに若者たちにまぎれて、ドミトリの一室を占拠しているのだった。
つい先日、世代交代が行われた。規則に違反したならば、体技科所属のプロテジェであっても腕力で屈服させた旧・寮長だったが、別れの場面では信じられないくらいにおいおい泣いた。花束を用意したのが、まずかったのかもしれない。涙と鼻水の洪水に聞きとりは極めて困難だったが、「たくさん殴ったが、若者の将来を思ってのことだった。娘が後を継ぐから、安心してほしい。私に似て気立てのよい子だ」という内容をお話しになられた。絶妙に空気を読むドミトリ組たちは、微妙な表情で顔を見あわせる。そのとき、居合わせた全員が、丸太のようなものすごい猛女を想像していた。
予想に反して、やってきたのは小柄な眼鏡の女の子である。しかも、かつての猛女との共通点は、目が二つあり鼻が一つあり口が一つあることだけ。動転したプロテジェたちはドミトリの長老へ、この裏にある国家的な陰謀は何かと意見を求めにきたが、「ううむ、隔世遺伝」と唸るのが精一杯であった。とりあえずいまのところ黒幕は存在しないようである。もちろん、経過観察を怠ってはならない。
「寮長、このへんで子どもを見かけませんでしたか」
我ながら、不自然な質問だ。ドミトリは六歳から入寮できるのだから、朝から晩まで見かけてるに決まってる。寮長にはマアナのことを伏せているから、やましさが歯に分厚い絹をかぶせたのかもしれない。
「さっき、そちらのプロテジェさんと楽しそうにじゃれあっている女の子なら見ましたわ。金髪の」
スウが妙な表情を浮かべている。それはちょうど二の腕に噛みつかれている場面のはずだ。世の中を善意でとらえれば、じゃれあっているという表現になるのかもしれない。
寮長の丸眼鏡が陽光を反射し、視線が読めなくなる。
「何日か前からいらっしゃいますわね」
ばれてる。
「ぼくの姪っ子なんです」
完全に自然なタイミングで嘘が出る自分は、いつしか汚れた大人になってしまっていたのだな。
もちろん、すまし顔でうなづく隣のプロテジェも共犯だ。
「ごきょうだいがいらっしゃったとは、初耳ですわ」
人差し指を頬にあてて、小首をかしげる。愛らしさと恐怖が結婚したようなすさまじさに、ぼくは背中へ汗がにじむのを感じた。どこまで知ってるんだろう、この人は。
スウがうろたえたようにこっちを見、ぼくの嘘の完全な傍証となった。こら、こっち見ちゃダメだろ。
嘘が次の嘘を生むダイナミズムは、いつ味わっても胃が痛む。しかし、どう言葉をつぐべきか考えるぼくに助け舟が出された。
「もちろん、書面さえ出していただければ、規則的には何の問題もありませんわ」
完璧に抑制された、隙のない微笑み。
詮索しすぎないが、職分の範囲で言うべきことは言う。若いのにしっかりしてんだよな、この娘。
「必ず」
真面目くさってうなづくと、両手を胸にひきよせて動揺のショウ・アンド・テル教材と化して視線を泳がせるスウの腕をつかみ、足早にその場を離れる。たちまち赤くなるのは強くつかみすぎたせいか。腕のぶんの血流が、顔にあがったのだろう。
新棟をぐるっと回っても、マアナは見つからない。
「いないなあ」
「いないですねえ」
まだ、頬に赤みが残っている。
「もういちど旧棟を探してみようか」
「賛成です」
ぼくたちは再び、ならんで歩き出した。
旧棟はペルガナ市国でも数少ない、二階より上がある建物のひとつだ。石造りとひとくちに言っても、レンガを積み重ねたようなものとはわけがちがう。ぼくも最初に聞いたときは信じられなかったけど、いっさいの接ぎ目がないそうだ。おそろしく巨大な一枚岩から切り出されたかのように、すべてひとつながりでできている。古代の建物に手を加えずそのまま現代へ流用するのは、ペルガナ市国のお家芸である。横着ここに極まれりという感じだが、中にいるものたちを厳粛な気持ちにさせる効果はあるようだ。心を澄ませば、個人ではない連続が時間を越える大きなひとつを創りだしたことに気づくのだから。
しかし、ぼくの感慨をさえぎったのは、もっと矮小な何かだ。地面へ無造作に脱ぎ捨てられた靴下。つまみあげてみると、手のひらも入りそうにないほど小さい。

「マアナのかな」
「あそこにもありますよ」
スウが指差した先に、もう片方があった。どうやら、容疑者はすぐ近くに潜伏しているみたいだな。旧棟を回りこんで、中庭に出る。
等間隔に樹が植えられていて、建物に切り取られた空が四角いという面白さ。人工と自然の調和という言葉がぴったりのこの場所を、ぼくはたいそう気に入っている。
だが、平和を体現するはずの空間に漂う空気は、いまや不穏に満たされているのだった。無残にも胸元で引き裂かれたワンピースが枝に引っかかり、下ばきが植え込みに投げ捨てられているせいだ。公共の場にある女児の下ばきがこんなにも心さわがせるものだとは知らなかった。真っ赤になったスウがとんでゆき、おおあわてで証拠物件を回収する。
「ドミトリから新しいの、持ってきますね」
胸元に衣類をかかえたスウが小走りにかけてゆく。ああいう生活感が妙ににあうなあ。よいお嫁さんになることだろう。
棟に沿ってならぶ緑に囲まれた正方形の中央には、ひときわ大きな樹木が生えている。この位置は学園設立の当初、あらゆる周縁から等距離にあったそうだ。もっともそれは設立された最初期にまでさかのぼればのこと。新棟を含めた建て増しに次ぐ建て増しで、いまやここは辺境である。
空からハミングが聞こえる。小鳥のさえずりとは違う。これは、グラン・ラングだ。歌っているのが誰かは、もうわかっている。
はるか昔にこの世界から消えた言葉のネイティブ・スピーカー、遺跡の少女・マアナの母語はグラン・ラングである。
この衝撃がぼくにとってどれほどだったか、とうてい語りつくせない。この子ひとりの存在で、これまでグラン・ラングの研究に費やされてきた莫大な時間をかるがると一足跳びにできる。それは、微に入り細に入りすぎてもはや誰も全体像を見渡せなくなったこの分野全体を統御し、かつまとめて底上げするようなものすごい可能性だ。
そしてこれはスウやシャイや他のプロテジェたちには内緒だけど、コミュニケーションを試みたぼくのグラン・ラングはマアナにまったく通じなかった。この衝撃がぼくにとってどれほどだったかも、やはりとうてい語りつくせないのであった。若手の研究者たちの間では一頭地を抜いた存在であると密かに自負していたぼくは、高くなっていた鼻をぽっきりとへし折られたのだ。実地検証を年長のプロテジェに言い続けてきたことがさかさまになって、はねかえってきた形である。もう一生涯、机上の空論という言葉は使うまい。
重なりあった枝葉の隙間から陽光がさして、風が吹くたびに違う輝きを見せる。大きくさしのばされた枝に、裸の女の子が座っていた。
「おーい、あぶないから降りておいで」
マアナは一瞬だけこちらを見て、すぐにハミングを再開した。「私が可愛いってことは知っているわ」とでも言いたげである。実際、噛みついたり暴れたりしないときのマアナは、とびきり造作の整った女の子だ。それをわかっていて、相手が本気では怒れないと確信しているふうにさえ思える。
将来、どれほど多くの男たちがこの毒牙の犠牲になるのだろうか。保護者としては、いまのうちにこの芽をつんでおかなくてはいけない。意を決して息を吸い込むと、背後に人の気配がした。
「いつまで駄々をこねているのだッ!」
つんざく怒号が響きわたり、ぼくとマアナは首の半ばまでを肩にうめてふりかえる。
怖いほうのお姉さんが戻ってきていた。
早足で近づくと、そのまま地面と平行に滑空するような前蹴りで、樹木に革靴をねじこんだ。樹齢幾百年を思わせる太い幹である。それが、びっくりするほど大きく揺れて、大量の葉っぱと数匹の昆虫とひとりの女の子がバラバラと落ちてくる。
ぼくはあわててマアナの落下地点に手をさしのべる。ナイスキャッチ。
「この一週間の歯がゆいことといったらない。そいつは、機嫌をとればとるだけ増長する生き物だ」
腕組みしたお姉さんが、眉を片方だけあげてにらみつけている。マアナは完全にふるえあがり、両腕と両足でぼくの首と腰をがっちりホールドする。ぼくは安心させるために背中をなでてやるが、温かかった。遺跡で受け止めたときは、氷で冷やした魚のようだったのに。
「まあまあ、ふつうの子どもじゃないんだから、少しは大目に見てやらないと」
父母の役割が逆転している気がする。
「それを親バカというのだッ!」
少し観点がズレているのが面白いが、笑ったりすると上半身と下半身が別々になってしまうので、口元をヘの字にゆがめるにとどめることにした。
スウはマアナの鼻先へひとさし指をつきつける。たちまち悲鳴をあげ(たぶん、グラン・ラングで)、両腕と両足はますます強くぼくの首と腰をしめつける。かなり苦しい。
「おまえはユウドの温情に生かしてもらっているのだから、ユウドの言うことはなんでも黙って聞け。いいな?」
この三白眼で迫られては、遺跡の魔物だって逆らえない。少なくとも、ぼくには無理だ。グラン・ラングを母語とするマアナは、わからないはずの言葉にぶんぶんと首を縦にふった。人の理性というよりは、動物の本能が内容を察知させたのだろう。やっぱり、教育は気迫だよな。
その日の午後、新しい服を着せられたマアナは、スカートをばたばたしたり全身をぼりぼりかいたり襟首に両手をつっこんでひっぱったりしていた。けれど、部屋の戸口でスウがずっと匕首を切ったり戻したりしていたので、ついに寝床に入るまで露出の癖を敢行することはなかった。
また一歩、人間に近づいたのである。
当面の問題を解決したぼくは仕方がなく会議室へもどったが、なんと体技科とスリッドの論争はいまだに続いていたのだった。
「よかったやん。クライマックスには間におうたで」
キブが目線を資料に落としたまま、席についたぼくを肘でつついた。
その日の学科長会議は、日付が変わるまで続いた。一日の三分の二ほどを会議していた計算である。しかし、アジェンダは半分も消費されておらず、臨時学科長会議招集の日付が議事録の末尾に記載されて散会となった。
会議室を出たぼくとキブは、真面目くさった顔でしばらく並んで歩いてから、旧棟を離れたところで抱きあい背中を叩いて、お互いの忍耐をたたえあった。
ドミトリの自室に戻ると、二人の女の子が毛布にくるまってベッドを占領している。そばまで椅子を引き寄せて、腰を下ろす。座るときにかけ声がもれるのは、もう若くない証拠だな。窓からの月あかりに照らされた二つの愛らしい寝顔に、しばし心癒される。
マアナのことは早急に解決すべき案件だ。発掘品をリストアップした史学科の目録には「人型土偶」として記載してあるから、公的な処理は終わっているといえば終わっている。老齢の学科長に代わり、報告書の作成は実質キブがすべて代行しているからこそできたことだ。何より、これは過去になかったケースである。報告書の様式なんてものも、存在しようがない。
当然、研究者としての倫理を遵守しようとするなら、マアナの存在はすぐにでも公開するべきだ。グラン・ラングの母語話者というのも、実はぼくひとりの思いこみだってこともありえる。祖に極めて近いことに疑いはないが、派生した別の系に連なる言語ではないと断言する材料を、ぼくは持ち合わせていないからだ。真の客観性は、大勢の主観が集まらないと生まれない。
しかし一方で、マアナは小さな女の子だ。大勢の興味の中に投げこんでから、その大勢のひとりとして接することができるだろうか。正直、これまでのぼくに研究以外の優先事項はなかった。研究の業績が人類へ残すだろうものの大きさに比べれば、人がふつう生活で作り出すものには、何の興味もわかなかった。
けれど、それはたぶん、自分を守るためのポーズだったのだ。誤解を恐れずに言うなら、マアナといるときにぼくが感じているのは、おそらく父性である。娘を研究の具に差しだして省みない、マッド・リサーチャーの思いきりがぼくになかったことは確かだ。
そして、残ったひとつ。最大のひとつ。
ぼくの晴れない疑念は、こう表現できる。
もしかしてマアナは、ぼくたちがいま見ているような姿からは、遠いのではないか。
マアナと唇を重ねたあの瞬間にぼくが見た光景を、言葉にしてわかってもらえるか自信がない。
常人ならば、魂が収まる座となるべき場所に、無辺大の広がりを持つ上下のない空間があった。人の魂を器に入った水だと例えるなら、マアナのそれは天と地をひとつにして満たされる虚空。その莫大な感覚に、ぼくの心はもっていかれかけた。永遠を直視して、なお正常でいられる人間がいるはずがない。
砕ける砂のように、意識が漂白されてゆくその瞬間。首のつけ根に衝撃を感じ、視界は反転して黒く変わる。気絶したのだ。あとからキブに教えてもらったが、スウが刀の柄を思いきりねじこんだのだった。ひどいやり方だが、結果としてスウはぼくの恩人である。しかし、感謝を述べるぼくへの返答はにべもない。
「かわせたはずだ。邪念があったんだろうが」
一言もない。赤い唇が迫ってくるとき、逡巡があったのは確かだ。
生産性に限って言えば疑問符のつく会議で綿のようになった頭では、一週間考えて見つからなかった解決策を発見できるはずもなかった。隣室のプロテジェに部屋の片隅と寝具を借りようと立ち上がって、ぼくはかすかな胸さわぎを覚える。ちゃんと順序立てて説明できるようなものではない。
「付与」と「維持」を専門とするぼくは、現状の把握に対してとても敏感である。一般人とは、はかりの精度が違うのだ。現実に対して付け足された余剰を把握できなければ、それを維持することもできない。付け足した分は管理されなければならないし、管理しないならば元のように取りのぞく必要がある。難しい言い方になるが、人為が管理されないまま自然の中に残されると、必ず悪い結果を招くのである。
ぼくの胸さわぎは、つい数分前までの現実といまの現実とは等価でないと感じたことが原因である。おそらく、学園内に何か異物がまぎれこんだのだろう。
そういえば、以前もこんなことがあった。遺跡の魔物が敷地内に迷い込んだのである。いつも暗い場所にいる魔物は夜行性(正確な表現ではないけど)なので、陽が落ちた地上を遺跡の続きと勘違いして出てきてしまうことがある。普段は人を襲うことはないが、遺跡の中にいると思いこんでいる魔物にとっては、こっちが侵入者だ。
深夜にも関わらず、ぼくの通報へまっさきにかけつけたのは、体技科長だった。相手は直立した狼みたいなヤツで、ずんぐりした体技科長の倍ほどもあった。薄闇に光る両手足の爪は、ひとつひとつが刃物のように尖っている。ぼくはすっかり動転して、人を呼びに走ろうとしたが、
「間に合あわねェよ」
体技科長が低くつぶやくのと魔物がとびかかるのは、ほぼ同時だった。
その後の光景は忘れもしない。なんと、あっというまにぶちのめしてしまったのである。
しかも、素手で。
魔物が、まるで子犬のような悲鳴をあげて地面に崩れるのを、ぼくは確かに見た。
「俺っちはこいつを住処に戻してくらァ。おめえさんは早く寝ちまいな。明日も講義があるだろがよ」
容積でいうなら三倍はありそうな巨躯を軽々と抱え上げ、体技科長は悠然と歩み去っていった。
だが、今回の違和感はそのときとはちがう。魔物ではないとすれば、いったい何だろう。スウが目を開き、ベッドから身体を起こす。毛布の下に刀を抱いている。
「何か入ったな」
まったく眠っていなかったように、はっきりとした声だ。スウがそう感じるのなら、間違いないだろう。
「ちょっと見てこようと思うんだけど」
語尾をにごすのはずるいやり方だと思う。しかし、メンターとしてプロテジェに危険を強要する発言ははばかられた。もしかすると男としての矜持なんていう、前時代的な錯誤が働いたかもしれない。
「ついていこう。自称・頭脳派のメンターをひとりで行かせるわけにはいかんからな」
スウは気づかないふりだ。拒絶したって、ついてくるに決まってる。実に情けないことだが、過去、スウの助力なしにはどうにもならなかった事件がいくつかあった。名実ともに、彼女はぼくの保護者なのである。
夜の旧棟は人気がなく、しんと静まりかえっている。ついさっきまで大勢のメンターたちが喧々諤々、議論を交わしていたのが嘘のようだ。
もともと何かがあったところから何かが無くなると、ある種の虚が生みだされる。それは、ただの不在よりもいっそう濃い喪失だ。お祭りなんかで、集まった大勢がいなくなるときの寂しさが独特なのは、そういったわけである。
「付与」と「維持」を専門とするメンターは、誰へともなく頭の中でそんな講義を行う。隣を歩くスウはたいへん緊張した面持ちで、ぼくの話を聞いてくれそうになかったから。
曲がり角や階段を通るたび、スウがぼくを見て、ぼくはスウにうなづく。ぼくは異物に対する人間感知器のようなもので、スウは己が察知したことを確認するためにぼくをつかうのだ。
やがて、スウが立ち止まる。
「ここの上ではないかと思うが」
スウが誰かに意見を求めるのは、極めてめずらしいことだ。何を参照することもできない一瞬に、真空のような自力で判断を下すことが、スウの強さの拠っている理由だから。そこには、一種の威厳とさえ言える何かがある。一貫した行動が作り出す暗黙の威厳。他人に向けられるとき、それは重大な信頼だ。ぼくが体技科長に感じるものも同質である。
ぼくは目をつぶると、神経を集中する。ちょうど頭上に、意識の透過を妨げる何かがある。本来、この学園にはなかった紙魚のような異質だ。
「いるね」
ぼくの答えは簡潔だ。スウが求めるものを理解しているから。
「一歩だけさがって、ついてきてくれるか」
右手を軽く束におき、つま先立ちにやや前傾した姿勢で階段に足をかける。スウからは肌に痛いような気配が発散している。
完全な臨戦態勢だ。
ぼくはうなづき、ちょうど一歩分の距離をあけて後ろをついてゆく。こうなったスウに言葉は不要だ。言葉は遅すぎて、一語たりともその行動を追いこせない。
すべては一瞬で始まり、一瞬で終わるはずだ。
旧棟の廊下は部屋の面積に対して、ずいぶんと広いスペースが与えられている。それはつまり、古代人の公共への感覚をそのまま反映していると言える。扉に区切られた空間よりも、誰もが行き来する場所の方が重要だったのである。しかし、その崇高な遺志をあざ笑うかのごとく、いまや物置や展示場と化している一画も少なくない。
最初、芸術学科が陳列するオブジェと見分けがつかなかったのは、あまりに人が持つ固有の気配と遠かったからだろう。フードを目深にかぶり、床に届くほどのマントで全身を覆っていたにも関わらず、その見かけは確かに人だった。
ぼくたちへ向けられた音声は、確かに言語と定義できる規則性を持っていた。
不安を生じさせるほど大きな抑揚。
対話を前提としない高圧的な連続。
聞きとりの困難なその音階を文字に写すとすれば、こうなるだろうか。
「ウイハフ・アヒュウ・トゥシイ・ジクエイ・フザット・クオブエ・キャンビ・ナジイフ・イアポテ・ロウワズ・ンシャル・ディテク・スレット・テッドアラ・フォドォンチャ・ウンドジス・イルド・リイジョン」
グラン・ラングとの類似性は見出せる。しかし、世界に現存するすべての言語は祖から派生したいずれかの系に連なるクレオール語(劣化ゆえだ)と言えるため、何も発見していないに等しい。
フードがはねのけられる。
青い眼、尖った耳、深く刻まれた皺。風のない屋内でたなびく赤い髪。人のようであり人のようでないその造作は、ペルガナ市国の人々をひどく誇張して描いているともとれる。わきあがる不快感はそのせいか。
その魂は、沸騰する岩を思わせる濁った輝きを放っていた。すでに付与が施された痕跡がある。維持は必要ない。なぜなら、魂は永久に変更を上書きされているから。
生命を縮め身体能力だけを向上させる類の冒涜。
暴力が知恵の儚さを摘むことを是とする世界観。
ぼくは全身を嫌悪感が包むのを抑えきれない。なぜって、それはずっと自分自身に向けてきた批判と同じものだったから。軽々とぼくの葛藤を飛びこえて、生命の有り様がデザインされるのを目の当たりにする衝撃。
これは、人間存在の戯画だ。
そしてあれはぼくでもある。
だが、不思議な既視感を伴った――
自失を縫うように、爆発的にマントがひらめく。
月光の照り返しをしか視認できないそれは、床面すれすれを滑空し、伸び上がるように真下からぼくへ迫る。
鼻先に冷たいものを感じたと思った瞬間――
鈍い金属音が爆ぜる。
柄の無い短刀が床に突き刺さり、震える。
「思索はあとにしろ」
抜刀をすませたスウが、ぼくと敵との軸線上に歩を進める。
半月状に開いた口腔には、乱杭のように大作りな黄色い歯が並んでいる。
見開かれた眼が訴えるのは、驚愕のようでも喜悦のようでもある。
マントをからませて両腕を広げた姿は、さながら猛禽を思わせる。その内側へ、夜の闇を言うには不自然な黒い空間が広がっていた。
応じるように、スウが身をかがめる。獲物を前にした肉食獣のようだ。
飛翔。違う。疾走。
その速度は人外の。
スウが駆け出す。
確実な死へ。
赤子のような信頼。
ぼくが何とかすると疑わない。
間に合うか。
青い光輝。清澄なる人間の証明。つかまえた。
砂時計が重力を無視するイメージ。
ふたつの人影が交錯する。
スウと同調する視界。没入の深度を調整できず、客観性がふきとんだのだ。
短刀をつかんだ腕が鞭のようにしなって、首筋をねらう。
上体を沈ませたのは回避のためだけではない。
攻防一体。
同時に放たれた袈裟切りが胸元を薙ぐ。
だが、浅い。まだ、動いている。短刀が振りあげられる。
斬撃の勢いをそのまま殺さぬ、独楽のごとき急激な回転。
そして間髪を入れず、低い体勢から逆袈裟に斬りあげる。
体を入れかえるほどの躊躇ない踏みこみは、完全に対象を静止させた。
スウから視界を取りもどしたぼくは、思わずその場にへたりこむ。遅れてやってきた極度の緊張と弛緩が、どっと通り抜けていったのだ。あぶないところだった。あと少し判断が遅れていたら、切り伏せられているのは逆だったろう。
ゆっくりと刀を鞘に納めながら、スウが戻ってくる。太い眉を寄せたその顔は、なんだかすごく不機嫌そうだ。
「毎回思うことだけど」
ぼくは肩で息をしているのを悟られぬよう、軽口に紛らわせてしまおうとする。
「もう少しブリーフィングの時間が欲しいね」
不機嫌な表情を少しもゆるめぬまま、スウはぬっとぼくの目の前に右足を突きだした。親しき仲にも礼儀あり、メンターに対するプロテジェのあるべき姿を説こうとすると、
「靴がやぶけてしまった」
見れば、つま先に穴のあいた靴底から親指をぴこぴこと動かしている。さっきの回転で、摩擦に耐えられず擦り切れたんだろう。ぼくは思わず吹きだしてしまう。
「笑いごとではない。少し本気をだすとこうなるからイヤなんだ」
スウは頬をふくらませて不服そうだ。裏を返せば、それほどきわどい勝負だったということ。ほんの紙一重で死を切り抜けたことを、スウは気づかせまいとしているのだ。
ぼくは真顔でスウを見る。
「新しい革靴をプレゼントするよ。今度は、破れないのを」
スウは一瞬、元のような表情になったが、すぐに顔をそむけて、
「当然だな」
かわいくない。
「立てるか?」
手をさしのべてくる。かわいい。
「メンター・ユウドには、いつものように実地検分をお願いしなくてはな」
いつものように、という部分に皮肉がこめられている気がする。
「実地検分こそがメンターの仕事だよ」
ひとまわりほども小さい手のひらを握り返す。どこにあれだけの力が秘められているのか、いつもぼくは不思議に思う。
床に盛り上がるフードとマントは、生命の残滓すら感じさせない。それはただの物体だ。何よりあれだけ深く斬りこまれ、一滴の流血すらないのだ。
少し難しい、専門的な話になる。ぼくの見る魂とは、肉体を制御する中枢、機甲学科ふうに言えば駆動系である。駆動系=魂は長く人にしか存在しないと思われてきた。例えば昆虫に駆動系はない。昆虫の魂は、高揚しないのである。しかし、昆虫が生命活動そのものには支障を持つわけではない。ここから考えて、魂の実在が肉体の制御にだけ関わるものでないことは、明らかだ。
ある海洋生物に魂が発見されたとき、言語を統御する言語系が予言された。両者を結ぶ共通項は、環境への単純反射ではない意志伝達を行うところにある。言語を持つことが特定の実在を他の実在から切り離して特別にする証拠であり、グラン・ラングの深奥に迫る大きな問題提起だった。だが、言語という枠内で思考する我々が、その外側から己の枠組を知覚する方法があるのか。ときに言語系は、永遠のファンタジーと揶揄されるゆえんである。無論、ぼくはこの観点からのアプローチをあきらめていない。
魂を知覚でき、かつ言語を持つこの物体は、間違いなく人であるための最低要件を満たしている。異形ではあるにせよだ。ぼくはしゃがみこんで、フードの表面に軽く触れる。途端、煤のような黒い飛沫が舞い上がった。羽虫を思わせる音を立てて宙空を漂うと、やがて完全に消滅する。床に残されたフードとマントは、もはや人の形を失っていた。
「検分は終わっていたのか?」
スウが若干の侮蔑をふくんだ(ように聞こえる)声でぼくに問う。
「もちろんさ」
ぼくとて、毎回をだしぬかれているわけではない。スウに向けてかざした小瓶の中では、煤が生きているかのように旋回している。
「これを史学科か生物学科で調査してもらえば――」
言葉を途中で切ったのは、持ち前の弱気ゆえではない。新たな気配を感じたからである。それはスウも同じだった。背筋を伸ばし、まるで石壁を透視できるかのように遠くを見る。
「ドミトリの方だ」「ドミトリだな」
検証の回数こそ少ないが、ぼくとスウの意見が一致したときの精度はほぼ100%だ。マアナことが脳裏をよぎった。もしかすると、こっちが陽動だったのか。
ふたりは同時に駆けだす。階段を跳びおり、中庭を走りぬける。スウがときどき振り返りながら「もっと早く」と言いたげな視線を投げてくる。
加齢による基礎体力の低下がうらめしい。置いていってくれ、とも言えない。さきほどと同じ力量の相手だとすれば、どちらが欠けても退けることは困難だ。
全速力で新棟の前を駆け抜けると、ドミトリの玄関にふたつの人影がある。
うごめく赤い髪と尖った両耳。
対峙するのは、丸眼鏡の寮長。
横たわるのは、絶望的な距離。
注意をそむけるために大声をあげるいとまもあらばこそ、赤毛の怪人は可憐なる我らが寮長へと飛びかかった。
ぼくの数歩先を走るスウの刀が、むなしく空を薙ぐ。
鈍い破裂音。
一瞬、何が起こったのかわからなかった。
怪人の後頭部へ、足の甲を巻きつけるような上段蹴りがヒットしたのである。
続いて、くずおれるその水月へ、超々至近距離からの正拳突きが、文字通り背中へと突き抜けた。
羽虫の音をたてて黒い気体と化す怪人の向こうに姿を現したのは――
寮長だった。
「あら、おかえりなさい。門限後の外出に関する規則、ご存知ですよね?」
MMGF!(3)
三年に一度の学科大移動はいつも混迷を極め、刃傷沙汰が発生することも決して珍しくはない。メンターの資格を持つ人間ごと、研究室の配置を丸々変えてしまうというのだから、たいへんだ。大がかりな研究設備を所有する学科などは、その移動だけでも膨大な労力である。過去に幾度も廃止が叫ばれ、実際に議題になることも多いのだが、なぜか最後には存続の方向で話がまとまってしまうという不思議な行事だ。
学科長会議において可決されたはずの原案は、実際の移動が始まると落書き程度の意味しか持たなくなる。あとは、学科の総力をあげた陣取り合戦だ。移動のための休講期間は一週間と定められており、逆に言えばこの期間を越えての移動は許可されない。最後の一昼夜に行われる学科間の攻防は、凄絶の一言に尽きる。しかし、誰もが結果としての落ち着き先を妥当と考えるようになるのは、不思議な点だ。
力を出し尽くした後に訪れる人知を超えた調和を体感できるという意味で、ぼくは存続派である。反対派の急先鋒が誰なのかは言うまでもない。沈殿した何かをかきまぜて活性化する、祝祭のような効果は確かにあると思う。事実、この学科大移動を通じて生まれたカップルや、新たな学際的研究なども少なくない。責任を持った個人ではなく、無責任な全員が等分に参加することで、誰もがお互いの存在を前提とした妥協と落としどころを見つける。
難しい言い方をすれば、集合無意識レベルでの暗黙知を伝えあっているのだろう。
統計的なデータがあるわけではないが、学科大移動を経てしばらくは会議にせよ何にせよ、非常にスムースに運ぶようだ。
この一大ページェントにあって、比較的おだやかな時間を過ごす学科がふたつある。体技科と史学科だ。
体技科のメンターたちは、いずれもヒグマのような大男である。そんな彼らがお互いを全力でぶちのめす演習(おそろしいことに、例え話ではない)を屋内で実行した場合、破壊をまぬがれる建築物は今のところ(たぶん古代にも)存在しない。そして何より、体技科が本気で陣地取りに参加したならば、一両日中に学園は制圧されてしまうだろう。学科大移動初日に体技科の若いメンターたちが更衣室兼物置と学科長のための部屋を二つほどおさえると、そこは暗黙の了解として大移動の対象では無くなるのだった。体技科の研究室は、屋根におおわれていない部分すべてである。
史学科の研究室をのぞいてみると、想像を裏切る整然とした見かけに驚くはずだ。床には遺物が散乱するどころか、塵ひとつ落ちていない。壁面へしつらえられた棚に奇妙なオブジェが並ぶ様子は、港湾に構えられた貿易商の事務所のようでもある。しかし、人の気配は無い。組んだ両手にアゴを乗せた史学科長が思索深げにうつむいているのを見ても、声をかけてはいけない。たいていが午睡の只中にいるからである。
窓から目をやれば、旧棟から少し離れた学園の敷地と遺跡との境界が不分明な地帯に、石造りのドームが見える。狭い入り口をくぐれば、中央のくろぐろとした穴から鉄製のハシゴがのぞいている。遠ざかってゆく外の光と手元さえ見えない薄暗さに感じる原初的な不安を飲み込んで降りてゆけば、やがて、天然の岩肌と古代遺跡の壁面が混ざりあった莫大な空間にたどりつくはずだ。
木で組んだ足場の上をモッコが走り、硬い岩肌に叩きつけられたツルハシが火花を散らす。壁に埋めこまれ、等間隔に照らすのはグラン・ラングによる人造の光だ。けれどそれは古代の遺産ではなく現代のあとづけで、周囲を照らすに十分な明るさとは言いがたい。そんな薄闇の中、各人が腰につけた角灯が幻想的にゆらめく。
『学園は、そのものが巨大な遺跡であり、地上に突き出した建物は氷山の一角に過ぎない』
それが史学科の主張だ。涙ぐましい有言実行の結果、史学科の研究室は太陽の照らさない部分すべてである。
「おーい、ユウド、こっちや」
空中に浮かんだ目と歯が上下にゆれながら接近してくる。角灯のシェードが上がると、目と歯をとりかこむ輪郭があきらかになった。キブだ。
「すまんかったな、呼び出して」
あいもかわらず夜のように黒い。
「上のほうはだいじょうぶかいな」
「ボスさえいなけりゃ、おだやかなものさ。研究内容はぜんぶここに入ってるからね」
ぼくは人差し指でこめかみをさして、うそぶいてみせる。きざな言い方を許してもらうなら、言語学科の研究室は脳内のすべてだ。
ボス、つまりぼくの直属の上司である言語学科長は、目下のところ世界各地を遊学中である。ここ最近、年の半分くらいはいないんじゃないか。今回の学科大移動とその期間が重なったのは、学園にとって大いなる僥倖だったと言える。うちのボスのお祭り好きは、度を越えているから。偽情報をリークして学科間の争いを誘発したり、劣勢に加勢したり、優勢の尻馬に乗ったり、なんでもありだ。一貫しているのは、騒ぎを収束させるのと真反対へ動くベクトルだけ。
ボスのことを考えるときはいつも、喉元をしめつけられるような、中間管理職の悲哀が肩口から全身へ物理的な重さとしてのしかかるような、そんな感覚にぼくはさいなまれるのである。
「それはそうと、きょうは斬新な襟巻きをしとるな」
ぼくの首に巻かれた白いものへ黒い指先が伸びると、それを食いちぎらんばかりの勢いで野獣の犬歯ががちり音をたてた。
「ひいッ」
情けない悲鳴とともに、キブがとびすさる。ぼくの背中ごしにのびあがったマアナが、剣呑な空気を発散している。もしかすると、襟巻き呼ばわりされたことを気配で察して、抗議を示したのかもしれない。角灯のシェードを下ろし、両目をつぶったキブが口をへの字に曲げれば、もうどこにいるのかわからない。
がちがちと虚空に歯を噛みならす野獣を頭ごと押さえつけると、おんぶから前へと抱きなおす。
「ほら、もうだいじょうぶだよ」
空中に一つ目が浮かび上がる。キブが片目を開いたのだ。
「心臓に悪いわ。ペットの管理は飼い主の責任やで」
マアナは歯をみせてぐるぐるとうなっている。こめかみから敵意がいなづま状にとびだすような、凶悪な視線だ。
どうもこの二人は折り合いが悪い。キブは半ば以上本気でマアナを史学科の研究材料と考えていて、それが伝わるのかもしれない。非言語コミュニケーションって、むずかしいよな。
「ちょっと噛みぐせがあるけど、最近ではだいぶましになったからさ」
とたん、肩を噛まれる。犬歯が痛い。
「きょうは仕事の話やろ。スウに預けてくればよかったやん」
口をとがらせて愚痴る様子が、大人げない。うちのプロテジェは託児所の保母さんじゃないぞ。
「おばあさんのところへ帰ってるよ。ここ最近、ずっと世話をしてもらってたから、今日ぐらいはね」
おばあさんのところ、という下りでキブは軽く鼻をならす。
「ふうん。そら、うちの若いのが残念がるわ。じゃ、立ち話もなんやし、奥いこか」
話題の打ち切り方に若干の不自然さがふくまれているような気がしたが、ぼくにとってもそれは望むところだった。
応接とは名ばかりの、天井の低い横穴へと案内される。卓上に置かれた角灯が室内をおぼろに照らし、影は長く伸びる。自然石から切りだしたという椅子は、まるで身体の曲線にあわせたような、不思議な丸みを持っている。古代人の住居から拝借してきたにちがいないが、そのせいか、いつもむずがるマアナがおとなしく座ってくれているのはありがたかった。
飲み物を両手で包み、ちょんと椅子の端に腰掛けている様子は、さきほどまでの猛犬ぶりとは正反対の愛らしさだ。目を細めている自分に気づいて、ハッと我に返る。これじゃまるで、孫を見る好々爺じゃないか。
それから、何人ものプロテジェたちがお茶を持ってきましただの、何か不都合はありませんかだの、不自然なほどの出入りを繰り返して話の腰を折りまくったが、スウの不在を知るとがっくり肩を落とし、一様に入室の際の慇懃さを喪失して退室していった。
「さて――」
拝借品のカップをこれまた拝借品にちがいないテーブルへもどしながら、キブが身を乗りだす。
「これが今日の本題や」
かつん。豊満な胸元から取り出した小瓶が、カップの横へならべられる。瓶の底には、黒い煤状のものがこびりついていた。
「史学科で保管する膨大な史料と相互参照を行い、当たれる文献にはほぼすべて当たらせてもらった」
ぼくは目を見張る。
「この短期間で、よくそこまでできたね」
あの事件から、一週間と経過していないはずだ。キブはすまし顔でせきばらいをすると、
「もちろん、ウチの戦略的な視点が大きく解析を早めたことは、強調しても強調しすぎることはないな。言語学科に在籍する、とあるプロテジェからの依頼やとうちの若いモンにあらかじめゆうといたんや」
「ただの人海戦術じゃないか!」
あきれて、思わず大きな声を出してしまう。驚いたのか、マアナがぼくを見る。
「ちっちっちっ」
キブは得意げに、人差し指を左右にふる。
「あいかわらず、器の小さい発言やな。最適の解が得られるんやったら、道筋にはこだわらへん。それがウチの大きいやり方や」
同期のせいか、ときどき妙に対抗意識を感じるなあ。どうりでさっきからプロテジェたちの表情が暗かったわけだ。依頼主から直接お褒めの言葉がもらえると思ってたんだろう。頭痛がきそうだ。
「それでさ、肝心の解析結果はどうなってるんだい」
「結果か。うん、結果な」
どうも歯切れが悪い。
「該当ゼロ、や。衣類の残骸も材質から調べたんやけどな。やっぱりゼロやったわ」
マアナは退屈そうに足をぶらぶらさせはじめた。こんなとき、暴れださないことは大きな進歩かな。
「そうか、ゼロか」
「あれ、あんま驚いてへんな。ウチはけっこうショックやねんけど」
ペルガナ市国は発掘と研究を国家の柱としている。他国からの留学も多く受け入れ、学術交流も盛んだ。全体的にストイックとはほどとおい、ユルい空気のこの学園だが、数百年の長きを存続しているという一点においてだけは、他の研究機関の後塵を拝すことはない。伝統による知の集積が、ハンパではないのだ。この学園で該当する対象がないということは、世界の他の場所でそれが見つかる可能性は極めて低いといえるだろう。
「出どころは伏せて生物学科にも回してみたんやけど、からぶりやったわ」
あの怪人と向きあったとき、すでに予感はあった。ぼくたちの周囲に、この穏やかなペルガナ市国の日常に、何か決定的な異物が入りこんだのだという感じ。ぼくが平静な気持ちでキブの報告を聞いたのも、やはりどこかであらかじめそれを予想していたからだ。
「まあ、人がやることやし、見落としがなかったとは言いきれへんわ。時間もそんなあらへんかったしな。アンタが納得いかんのやったら、よその研究機関に調査を依頼することもできるけど」
「学園でダメなんだろ。どこに第二の意見を求めるっていうんだよ」
「ダン共和国のセイニ学院くらいやろな、うちに匹敵する精度の解析が期待できるのは」
「へえ、初耳だな」
「言語学科はないらしいから、ユウドには畑違いってとこやな。まあ、ひとつ大きな問題はあんねんけど……」
視線をそらしたキブの語尾が、空中へと消える。
「どうしたんだよ。歯切れが悪いな」
マアナの首が小刻みにゆれはじめた。いまにも眠りそうだ。ここの薄暗さに影響されているのかもしれない。
まるで誰かに聞かれるのを恐れるように、キブは姿勢を低くして声をひそめた。
「セイニ学院な、アンタのとこのボスがいま遊学してる先や」
「ほんとかよ!」
驚きのあまり、ぼくは二の句が継げなくなる。そこへすかさず、
「わからないけどなっ!」
豊満な胸をそらしながら、キブが声色を作って叫んだ。マアナがびくりと身を震わせ、椅子からずり落ちる。
「冗談でもそれ、やめてくれよ」
弱々しく言うと、ぼくは頭を抱えて卓上へつっぷした。頭痛がきた。
わからないけどなっ。これは、うちのボスの口ぐせだ。若いメンターたちをさんざんに論破したあとや、ほとんど奇跡のようなグラン・ラングの施術を見せたあとに、決まって言う台詞。
わからないけどなっ。身をもって未熟さや才能の欠如を理解させられているところへ、この追いうちである。完全無欠の言語学科長でさえ、この世界にまだ習得するべき余地があるという宣言は、具現化した永遠として研究の徒をうちのめす。
そういえば、以前ボスに聞いたことがある。グラン・ラングについて、どのくらいわかっているんですか、と。いま考えれば、愚かしい問いかけだ。前後の文脈は忘れたけれど、おそらく、くってかかったんだろう。そのときの答えがふるってる。顎をつまんでしばらく考えたあと、
「まあ、半分くらいかな?」
ボスが言明するのなら、間違いない。この人は、本当に永遠の半ばまでを踏破しているのだ。ぼくはその後、三日間寝こんだ。
キブはにやにやと、なんだかぼくの狼狽ぶりに楽しげだ。
「どないする? セイニ学院。アンタが依頼主やからな。アンタ次第やで」
わからないけどなっ!
すぐそばでボスの声が聞こえたような気がして、背筋に寒いものが走った。
「メンター・キブ。この案件に関する最後のオプションとして、それはとっておこう」
いつにない果断さで、ぼくは返答する。
「まあ、妥当な判断やな。ウチも同感や」
強い同意を表すかのように、ふかぶかとうなずくキブ。数多くの検証を乗り越えて、ぼくとキブの予感(悪いほうだ)が一致したときの的中率はほぼ100%である。
「まあ、せやけど――」
髪を手櫛でかきあげながら、キブが長く息を吐き出す。
「アンタもうすうすは疑ってるんやろ?」
床にずり落ちたまま、マアナは寝息をたてていた。意味ありげな視線がその金色の髪に投げられている。
「まあ、ね」
ときに直感とは、未来を予言するような働きをすることがある。こと、グラン・ラングの研究で大きな進展を迎えるとき、いつもそれがあった。
ゴールや結論だけが見えてしまう状態。自分以外の誰にも客観的には説明できないのに、思いついた内容が何の説明も不要なほどに、妥当だと感じる瞬間。そうなれば、あとは自分以外を説得するために言葉とデータを積むだけだ。そして、最初の直感は完全に証明される。もちろん、いつもというわけじゃない。ボスと違って、ぼくは天才ではないから。
「発掘品のリストのうち、ひとつだけ照合できてないのがあるな」
キブがゆっくりとあごをさする。
「髪の毛の一本でも、もらわれへんか?」
マアナと出会ったとき、ぼくはすべてを予期していたのではないか。
一連の事件が、この少女から始まっているのではないかという直感。
「それは賢明とは言えないな」
あの怪人に覚えた既視感の正体、もしかするとそれは――
ぼくは思考を停止し、表情を作ろうと努める。
「髪の毛をひっこぬいたりしたら、寝起きですごく暴れそうだ」
冗談めいた口調を装う。
「あんまり思い入れをしすぎんほうがええな」
キブは真顔のまま、目を細めた。ぼくは肩をすくめてみせる。
「研究者として、観察対象への距離だけは保っているつもりだけど」
「とぼけな。いまのは友人としての忠告や」
長いつきあいだけに、どうやらぼくの韜晦は通じなかったらしい。
「いろいろとありがとう。まあ、なんとかやってみるよ」
言いながら、眠っているマアナの両脇に手をさしいれて、抱き上げる。ひどく重かった。感謝の言葉は、拒絶のようには響かなかっただろうか。
「アンタはときどき、妙に意固地なとこがあるさかいにな」
キブは両膝に手をうちつけると、大きくため息をついた。
「子ども抱いたまま、ハシゴはのぼりにくいやろ。ついといで」
卓上の角灯をとりあげると、不機嫌をよそおって、ずんずんと歩き出す。
ああ――
この黒い人影は、いつでもぼくを先導してくれる味方なのだ。
キブの背中を追いながら、天井の低い通路を這い入り(身長が気になる)、狭い石壁の隙間へ横にした身体をねじ込み(体重が気になる)、底の見えない淵へ渡された丸太の一本橋をわたり(臆病が気になる)、土の地肌がむきだしになったトンネルを延々と進む頃には、薄暗さも相まって、もう上っているのやら下っているのやら、方向感覚は完全に失われていた。不安になって、思わず尋ねる。
「ずいぶん歩くんだね」
「ここや」
袋小路に立ち止まったキブが天井の石肌を押すと、暗闇へしみこむように光があふれた。
小さな穴から顔を出せば、しなびたお尻が目の前にある。旧棟内の史学科研究室だ。
「こんなところにつながってるなんて」
石板をもどすと、それは他の床とまったく見分けがつかなくなる。
「な、便利やろ」
キブは我が手がらのごとく、得意げだ。
「あのさ」
史学科長の規則的な寝息が聞こえる。
「こないだ、局所的な地盤沈下で芸術学科の倉庫が埋まったことがあったよな」
「ユウド」
キブが完全な無表情になった。
「あれってもしかして――」
一転して、不自然なほど自然な笑顔を浮かべる。
「ユウド、学究の徒とは思われへん発言やな。猫をけっとばしたプロテジェが事故にあったとして、猫キックと事故の因果関係を真剣には考えへんやろ。人の心っちゅうのは、体験したことがらを意味のあるものとして結びつけたがるようにできとんのや。それを探るのは、神学とか民俗学の領域やろ。客観的なデータの積みあげで迷信を越えるのが、ウチらの研究やないか」
言いつつ、痛いほどにぼくの肩をどやす。ぼくは、ずり落ちたマアナを抱えなおした。こりゃ、まちがいないな。
「これは借りというより、貸しだよな」
「ゆうとる意味はわからんが了解した」
ぼくたちは固い握手をかわし、再び地下と地上へお別れをした。
暗闇に慣れた目に光が痛む。両目をしょぼつかせながら廊下へ出ると、右肩と左肩を振り子のようにゆさぶる歩き方で、誰かが猛然とこちらへやってくるのが見えた。頬はこけ、ひどく痩せているが、身体の末端にまで鋭いものをめぐらせているような印象がある。
背中に大量の汗がにじむ。いちばんマアナのことを知られたくない人物だ。眉間に深くきざまれた皺がゆるんだことを見れば、もうこちらのことは認識されている。廊下の隅に放置された用具入れとマアナへかわるがわる視線を走らせ、自分が相当にうろたえていることに気づいた。いやいや、いまさら何をやったって疑惑をかきたてるだけじゃないか。
先手必勝。ぼくは精一杯の愛想笑いで話しかける。
「やあ、メンター・スリッド。数秘学科の移動はもう終わったのかい?」
「まったくこの騒ぎは馬鹿げている。とんだ労力の無駄づかいだ。君もそう思うだろう?」
手のひらを秀でた額にうちつけ、慨嘆する。発言だけではなく、アクションも大がかりなのだ。ぼくは微笑んだまま、あいまいに首を傾ける。続きをうながされたと思ったのか、相手は誰でもよかったのか、スリッドはまくしたてた。
「伝統の旗印を盾にして無批判に続けられる、こういった前時代的な決まりごとははやく廃止にするべきだ。知っているかい? この移動で学園の所蔵する備品のうち、じつに一割が破損もしくは紛失するという調査がある。私は次の学科長会議で、大移動の廃止を求める原案を提出するつもりだ。当然、旧勢力の抵抗は予想されるが、投票にさえ持ち込めば、我々若手の票を集めて勝てる。メンター・ユウド、当然、君の協力は期待できると考えていいんだろうね?」
スリッドは論理的だし、ぼくなんかよりずっと学園のことを考えていると思う。しかし、なぜか老若男女を問わず、人気がないのだ。すべての議案に関して、対立軸をつくる彼の論法が受け入れられないのかもしれない。論理的であるためにすべてを二元論へと帰着させることが失う多くのものに、ぼくは思いをはせる。
しかし、スリッドと口論したところで勝てるはずはない。このとき、ぼくの浮かべた表情は、不自然なほど自然な笑顔だったにちがいない。そしてその笑顔は、スリッドの雄弁を留める役には立たなかったようだ。
「何より、直接民主政を剽窃した会議のあり方そのものが問題だと思わないか。議論にあれだけの時間をかけておきながら、議決がすべて投票で行われることは矛盾している。学園長の諮問機関であるはずが、いまや意思決定機関と変わらぬ権限を持たされている。本来、学園長が決裁するべき規模の事項に、投票がなじむとは思えない。全員が決定に参加したという事実は一見、公平の見かけを醸成するが、決定された内容が学園の利益に反した場合、誰もその責任を問われない。責任を分散し、分散することで放棄している。さらに二つ、看過できない大きな問題がある。一つは、それぞれの議題に対する理解の深度が、会議の構成員によって統一されていないということだ。なにしろ、会議の最中に眠っている者にさえ叱責はなく、優しく揺り起こした後に投票用紙が渡されるのだから、学園の情け深さは底なしだ。一票の格差という言葉では語りつくせない義憤を感じるよ。そしてもう一つは学科という壁が作り出す、セクト主義だ。上下を作らぬ、ぬるま湯の雰囲気の会議から離れれば、学科内には極めて厳密な徒弟制度が待ち構えている。学科長の命に従わぬ者は、昇進の序列から外され、研究を発表する場所すら危うくなる現状だ。すなわち、学科長が動員できる票数は、学科を構成するメンターの人数とイコールになる。例えば数だけを頼みの体技科のように、学科の人数がそのまま会議での物理的な発言力と影響力につながっている。零細の数秘学科が何を主張したとして、どれだけ正しい対案を提示したとして、数の暴力の前に蹂躙される。これらの問題点を放置して、なお得られた議決が公平だと言えるだろうか。私には、まったくそう思えない」
若いメンターで票田を形成しようとする先の発言と、完全に矛盾しているなあ。
それを指摘したところで、戻ってくる反論も「旧来的なセクト主義に対抗するための、やむをえない一時的な戦術」という論旨であることは予測できる。まあ、傍観者に徹すれば、いくらでも批判的な視点は保てるわけで、ぼくの考えもその意味でスリッドに対して公平ではない。この状況でぼくが返すことのできる最も適切な対応は、イエスでもノーでもない曖昧なあいづちだけだ。スリッドが求めているのは従順な聴衆であり、ぼくはその役割を演じることで穏便に場を収束させようとしている。だから、話が終わるまでを耐えるしか方法は残されていない。
しかし、助け舟はやはり廊下の向こうから、地響きとともにやってきた。
「よぉ、おめえたちが仲良しだとは知らなかったぜ」
身体の倍ほどもある巨大な石像を右肩に抱えて現れたのは、体技科長だ。まるで重さがないかのように石像を床へおろす。
「まったくこの時期はたいへんだぜ。どいつもこいつもおれたちを引っ越し屋くらいに思ってんだよ」
おそろしく太い指で、がりがりと頭をかきながら、ぼやく。その底抜けに陽気な雰囲気に、なんだかこっちまで楽しくなってくる。ぼくの隣に立つ陰気な気配のメンターは決して同意しないだろうけど。
吸引力、とでも言うのだろうか、ぼくはすっかりそれに釣りこまれてしまって、尋ねる。
「そういうわりに、うれしそうじゃないですか」
「おうよ。みんなタコツボから出てきやがるからな。知らねェ顔を見れるのは、うれしいわな」
黙りこんだスリッドが、燃えるような視線で体技科長をにらみつけている。
気づいた体技科長は、肩をすくめてそれをいなす。
「怖いねえ。俺ァ、おまえさんの敵じゃねえんだ。まさか、廊下で会議をおッぱじめようってんじゃねえだろうな」
「メンター・ユウド、さっきの件については考えておいてくれ」
スリッドはぼくの肩を抱き、耳元でささやくことで、ことさらに親密さを印象づけようとする。体技科への対抗意識がさせているとは言え(そう願う)、気味が悪いことに変わりはない。ぼくの笑顔は、目の前の石像よりも石像らしく見えただろう。
「では、私はこれで失礼する」
体技科長へするどい一瞥を投げると、スリッドは大股に歩み去った。ぼくは内心、胸をなでおろす。どうやらマアナのことには気が向かなかったようだ。
「まったく最近の若い連中は、同僚を敵と味方にわけてみたり、ぜんぶ抱えこんで隠しちまったり、面倒なこったぜ」
軽口をかえそうとして、体技科長を見る。満面の笑みの中で、目だけが笑っていなかった。
「魔物じゃねえ。最近、妙なのが学園のまわりをうろつくようになった。こないだとっちめたら、煤みてえに消えちまいやがった」
石像をなでながら、声をひそめる。
「ここンとこ、妙なことばかりだ。何かがおかしい。おかしいと思うんだが、それが何なのかわからねえ」
体技科長がほんの軽いしぐさで、石像をひっかく。指の軌跡そのままの形に表面が削りとられ、廊下に粉塵が散る。あの手につかまれたら、ぼくなんてひとたまりもないだろう。
「俺ァ、バカだから、考えるのは仕事じゃねえ」
頭をがりがりとかきまわす。
「ユウド、おめえの仕事がぶん殴ることじゃねえようにだ」
先ほどと変わらない、ほとんど親愛と呼べるような雰囲気のはずだ。唯一、感情の温度が極めて押さえられた両目が、観察するように細められる以外は。
言葉にされない圧力。ぼくは全身の毛穴から細かい汗がふくのを感じた。
「俺っちにできる仕事があったら、何でも言ってくれ。できれば、手遅れにならないうちにな」
「肝に銘じておきます」
平静をよそおうのにすべての力を使いはたし、ぼくはそう答えることしかできなかった。
「いい返事だ」
大笑すると石像をかつぎかけて、また床へ下ろす。
「おっと、おめえらのせいで忘れるところだ。俺ァ、史学科長サマに用があったんだ」
おそろしく太い指を戸口にかけたところで、体技科長はふとマアナに視線を留めた。
「やっぱり、知らねェ顔を見れるのは、貴重だわな」
老獪な両目は、そのとき何を考えているのか読みとらせることはなかった。
大きな背中が室内へ消えるのを見届けると、ぼくは足早にその場を離れる。
いろいろなものが符号しはじめている。ぼくひとりの手には余る規模のできごとが、同時にぼくの手の中に収まっているような、奇妙な感じ。体技科長がどこまでを見抜いているのかはわからないが、異変に気づいていることだけは確かだ。
いや、確証がないではないか。先行する直感が、後から来る客観的データの裏付けに反証されることだって、ままあることだ。いくつかの現象が符号するからといって、まちがっているかもしれない予断を頼みに行動することで、とりかえしのつかない過誤を生みはしないか。
「おまえはいつも頭で考えすぎなんだよ。グラン・ラングは現実とつながってるんだ」
ボスの、いつかの言葉が脳裏をよぎった。思えば、グラン・ラングの研究とは奇妙なものだ。思考と行動の合一をそのまま言語が体現しているのだから、研究という言葉にこれほどなじまないものもない。
しかし、ぼくがこの分野に足を踏みいれることになったのも、元はと言えば、考えることと目の前にあることを切り離して生きてきたからではなかったか。このふたつがつながるのを、どこかで嫌がっている。それが人の心が不可侵の聖域であることを否定するような気がするから? 言い訳だ。
ボスにとっては何気ない一言だったのかもしれないが、ぼくはひどくショックを受けた。生まれもった性格が、グラン・ラングの研究にむいていないと言われた気がしたのだ。うすうすどこかで気づいていた事実を改めて言葉にされたことが、ひどくこたえた。
ボスのふるまいは融通無碍だ。考えること、話すこと、動くこと、すべてがぶれなく一致している。ぼくはと言えば、この三つの間に矛盾が生じないようにするだけで手一杯だ。器の大きさとでも言えばいいのか。表面を同じようにつくろったとしても、やはりどこかでスケール感に欠けるのだ。
“魂=駆動系への付与行為について”、と題した論文を発表するときもそうだった。
「ペルガナ学園には、ひとりの研究者しかいないと思われるだろ。いっそ、連名じゃなくていいくらいだ」
ボスの助言なしには、アイデアを完成させる最後のジャンプはなかった。結局、連名で提出したのは、ぼくがそうしてほしいと希望したからだ。
思考と行動が一致する瞬間を避けようとし、ぼくの功績がぼくからではない形で世界に寄与すればと思う。きっと、主人公でありたくないのだろう。常に、より適切な人物が身近にいるはずだ。例えば、うちのボスのような。
だが、いまぼくが直面しているのは、転変する現実の事象である。客観的データの蓄積を待つ時間は許されていない。そして学園をとりまく異変に、おそらくいちばん深い形で関わってしまっている。この事件へもっとも適切に対処するだろうボスはいない。
いっそ体技科長にすべてを打ち明けて、預けてしまえばという誘惑にかられる。
ぼくの考えていることがわかるかのように、腕の中で柔らかく小さなものが身じろぎする。結論が出るはずもなかった。
「助かった、ユウドだ! ユウドが来てくれたぞ!」
名前を呼ばれて、思考の堂々巡りから我に返る。助かったのはこっちのほうだ。
見れば、機甲学科の面々が鉄でできた巨大な何かを、なんと人力で移動させているところだった。その周縁は大人が三人で手を回してやっと届くほど、高さは大人が肩車したくらいある。旧棟の外縁をどうにか引きずるように運んできて、最後の最後でほんのわずかの段差にスタックしたようだった。
「あれ、今日はあの子はいないのかい?」
言いながら、腰から刀を抜くマネをする。ニコイチみたいな扱いだな。いい加減、あちこちで知られているスウだが、こういう形で悪名をはせているのは、正直どうかと思う。
「いや、今日はちょっと親戚のところに行ってるんだ」
「残念だな。彼女なら、ひと押しでこんな段差、乗りこえられるのに」
表情を見ると、どうやら本気で言っているみたいだ。スウの腕力に対する一般的な評価は、体技科のメンターと同等らしい。学園祭で演じた『恐るべき怪力女』が、相当に強力な刷り込みとなったのだろう。
ぼくのプロテジェたちに乞われて、仕方なく舞台裏の付与役として協力したのだが、どうも悪ノリが過ぎた。細身の少女が体技科の大男を手玉にとるという筋立てで、ぼくの役目はスウが片手で相手の巨体を持ち上げる場面をサポートすることだった。結果、まるで演技ではないかのような迫真の格闘で大男を殴りたおした上に、観覧席を飛びこしたはるか場外へと放り投げてしまった。
ぼくがいたずらでやった部分もあれば、そうでない部分もある。正確な区分けは、うら若い乙女の名誉のために伏せておくとしよう。しかしながら、万雷の拍手の中、舞台袖のぼくをにらみつけたスウの湿った半眼とその後のよしなしごとは、今でも生々しい戦慄とともによみがえるのであった。
閑話休題。
「まあ、ぼくひとりでもだいじょうぶさ」
沈みこんでいた重苦しい悲観を楽観で塗りつぶしてしまおうと、つとめて陽気に宣言する。
やることは簡単だ。遺跡で風をまとわりつかせたのと同じに、空気のごく薄い膜をこの下へすべりこませる。即席の手押し車だ。
マアナを左腕だけで抱えなおす。鉄塊に手をかけ、意識を集中する。
グラン・ラングの効果は、ぼくたちの言葉に比べれば極めて限られた、元となる音素が意味を許容する範囲を正確にトレースできるかどうかにかかっていて、発生する物理現象は完全に予測の範囲に収まる。
このときまでは、そう思っていた。
音素が大気に命令を下し、形成された目に見えない薄膜が巨大な塊をほんのわずかに浮揚させ――
視界が二重写しのようになって、切り替わった。
無辺大の広がりを持つ上下のない空間。
奔流のごとく満たす形象を伴わない力。
ぼくを出口としていたが、それはぼくをはるかに越えていた。
空気の膜がゆっくりと回転しながら、次第に速度をあげる。ちょうど水桶の底から水を抜くように、大気が渦を巻いて鉄塊の周辺をとりまきはじめる。やがてそれは細長い竜巻へと変化し、うねりながら学園上空の雲を貫く。その暴威の向こう側で、機甲学科の装置は目的を失ったオブジェへと圧壊した。
時間にしてみれば、一瞬のこと――
ある者は雲の穴に新たな白いものが満ちてゆくのを見上げ、ある者は巨人につかまれたような鉄塊を呆然と眺めた。
その奇妙な沈黙の中、くすくすと笑い声がひびく。
目をつむったまま口元に笑みを浮かべて、マアナが笑っている。
楽しい夢をさまよう赤子のように、細かく身を震わせてマアナが笑っている。
歯ぎしりに漏れた奥歯の音がキチチと、まるで昆虫の羽音のように、鳴った。
MMGF!(4)
学園の辺縁、ちょうど市街地の反対側に位置するドミトリは、世界各地からの留学生の受け入れを主たる目的として設立されたという。いまでは身寄りの無い子どもの世話なども行っており、ペルガナ市国の福祉面に大きく貢献している。ドミトリ所属のプロテジェたちは年齢を縦割りにしたいくつかのグループに分けられ、学習から生活に至るまで年長者が年少者の指導を行う、自主自律を促すシステムが取られている。これこそ、たったひとりの寮長で多くのプロテジェたちを管理できる所以と学外へは広報されているが、実際のところ、現実に不可避な人と人との摩擦を抜きにして発案されたその理想を無理やり実行させてきたのは、歴代寮長による、文字通り、字義通りの力技であった。
ドミトリ設立の趣意は、門扉の脇に苔むし、打ち捨てられた石碑にこう刻まれている。
『世ニ名ダヽル学園ノ智慧ヲ伝播シ、国家ト民族ノ垣根ヲ越エタ学祭的発展ノ礎ヲ創ルタメ、更ニハ、世代ヲ越エタ人類ノ共感ヲ涵養スルタメ、ヤガテ我ガ子ラノ輝ク叡智ガ現存スル全テノ偏見ト無知ヲ世カラ取リ除ク日ヲ祈念センガタメ、ココニ未ダ愚カサヲ止メエヌ我ラガ、人ノ善キ意志ノ集結トシテ未来ヘ遺スモノデアル』
まったくいつ読んでも、恥ずかしいほど大仰で高邁な内容だ。でも、たぶん、ドミトリの設立者たちは、この言葉を心の底から信じていたと思う。物事が始まるときには必ず存在する、何かに浮かされたような熱気を感じ取ることができるから。善意と希望で世界は必ず良くなると信じる者たちにしか持ちえない、最初に創るものたちの熱気、初源の熱気だ。
1を100にできる人たちはたくさんいる。でも、0を1にできる人は世界にそれほど多いわけじゃない。ほとんどのドミトリ組が気にも留めないこの小さな石碑の前に、グラン・ラングの研究へ人生を捧げようと決めた初心を忘れそうになったとき、ぼくは立ち止まる。ともすれば、最初にあった豊かさと熱気の残滓を、ただ享受するだけに陥ってしまう我が身を戒めるためだ。
ぼくはたぶん、何も信じていない。けれど、信じていないものがただ己の安定のためだけに最初の1を狭めることはあってはならないとも思う。
ふと、ボスの言葉が心に浮かぶ。
「おまえはさ、自分が早く結論を得て安心したいから、逆にグラン・ラングのほうを狭めてるんだよ。破綻しろよ。もっともっと、破綻するんだ」
全身が粟だって、体の芯が熱くなる。ときどき、意味もわからず聞いたきりになっていた言葉が、過去からぼくを追いかけてきて、ぼくをつかまえることがある。ボスがいてくれれば、きっといまの状況にも的確なアドバイスをくれただろう。
しかし、それはせんのない願望だ。ぼくは軽く頭をふると、石碑に背を向けた。
ドミトリの入り口すぐに受付を兼ねた宿直室として、寮長のささやかなプライベート空間が設けられている。一風変わった伝統に彩られた部屋で、じっさいに見たことが無い者への説明は、ちょっと難しい。
床には一種の枯れた草を格子状に編みこんだ長方形の板が数枚、パズルのようにはめられている。石や木の床と違って、わずかに押し返してくるような感触だ。椅子の無い丸テーブルが部屋の中央に置いてある他は、用途のわからぬ質素な家具(?)が数点のみで、さしこむ陽光にもほこりさえ見えない清潔さである。
何より、ここは匂いがいい。屋内なのに、ちょうど草原に寝そべっているときみたいな感じだ。異なる文化も、人にやさしいなら受け入れやすい。まあ、ぼくの知っている寮長は二人だけだから、もしかすると文化や伝統とかに寄らない、もっとドメスティックな何かである可能性を否定はできないけど。
テーブルを挟んで、小柄な少女がおし黙ったまま、持ち手の無いコップをのぞきこんでいる。これも変わった趣向だ。熱いものを飲むときはどうするのかな。
紺の生地を白い前かけがおおい、両肩には羽のような飾り。機能性とデザインが同居した清潔感のあるお仕着せだ。以前はお仕着せのデザインになんて気づきもしなかったが、ぼくの鈍感さというよりはむしろ、その言動において異様な存在感を見せつけた以前の寮長が悪いのだと思う。
少女は奇妙なことに、どう言えばいいのか、曲げた両脚の上に臀部を乗せた格好で固まっている。もしかすると、ぶしつけな問いかけに対する不平を表現するための示威行為かもしれないし、もっとビザールな文化的行動なのかもしれない。予測不可能性は、最も人を不安にさせる要素だと言うけれど、ぼくの不安感には一種の恐怖さえ伴っていた。なぜって、この少女は、以前の寮長の血を分けた娘なのだから。
沈黙によるプレッシャーが恐怖を肉体的なものに変えるほど長くなりかけたとき、
「『よかろう、我が血はこの地を守る。その代わりに、この地は我が血を守れ』」
芝居がかった調子で唐突に、少女は声高く郎じた。予想外の方向で緊張を外されたせいで、よっぽどおかしな顔をしたんだろう、ぼくを見てくすりと笑う。
「すいません、どうお話したものかわからなくて。我が家に代々、口伝されてきたお話ですわ。ぜんぶ、覚えてますの。絵本がわりに、何度も聞かされましたから。守り人を欲した大地の懇願に、当主が応えたのだそうです。その盟約は、グラン・ラングの力で末代の血にまで刻まれていると聞きました」
待て待て待て。これはすごい話だぞ。魂への付与(エンチャント)が時代を超えて維持(アップキープ)されているという実例じゃないか。すぐ近くに、ぼくの研究を飛躍的に進める可能性の原石が埋まっていただなんて! つくづく、フィールドワークの重要性を痛感させられる。ここ何日かで折られに折られ、すっかり低くなったぼくの鼻は、ここにまた、その高度を低くすることを余儀なくされたのであった。
「ずっとただのお話だと思っていました。わたしも、ここに来るまでは本当の意味で信じていたわけじゃなかった。でも、いまは違いますわ。この身体が、血に刻まれた盟約を思いだしましたから」
ぼくの視線をつかまえた少女の大きな瞳には、気圧されるほどの確信が満ちている。その清廉な汚れの無さに、不純さを見抜かれたと感じるとき、男ならば誰でも感じるだろうあの、一種のやましさがぼくを動揺させた。
しかしながら、いついかなる局面においても、内心の動揺を完璧に秘し隠してしまわなければメンターという生業はつとまらないのであった。研究者としての本性を男の本性に覆いかぶせると、ぼくはまっすぐにその瞳を見つめかえす。
「グラン・ラングは世界を記述する言語だとぼくは考えてきました。しかし、多くの研究者がそれはレトリックに過ぎず、古代人のレガシーに干渉するだけの限定的な効能のみを注視しています。いまのお話は、大きな自信になりました。今回の件が落ち着いたら、改めてお時間をいただけませんか」
不躾な申し出に、おそらく困惑のせいだろう、少女の頬が色味を帯びる。軽く持ち上げた人差し指に、うろたえて視線を泳がせる仕草が、なんだか年相応で、ひどくかわいらしく見えた。
「あの、わたし、メンター・ユウドのお役に立てるか、わかりません。ただわたしは、そうであることを知っているだけで、専門的なことは何も……」
あることを知る。それは究極の理解だ。専門的な知識だけは売るほど持ってるくせに、グラン・ラングがそんな使い方をされていたことをぼくは実感できない。短くはない学究生活をさらっと完全否定される言葉に、ぼくの鼻は今度こそ完全に消滅した。
古代人の伝承によるならば、人知の存在する以前から、グラン・ラングはあらかじめ世界に組みこまれていたのだという。それは人間の認識が世界を規定する前から、海や山や空がすでに名前や人格を備えていたということで、なんだか楽しい気持ちになる。
しかもそれが、万物を理解するための方便ではない、つまり説話や民話の類ではないというのだ。寮長の話が示しているのは、かつて世界そのものと対話が可能な誰かがいたということだから。しかし、耳をすませど、ぼくには何も聞こえてこない。貧しき我が身をかえりみて、なんだか悲しい気持ちになる。
「話を戻しますが、先のドミトリ襲撃を退けることができたのは、やはりその盟約が理由であると?」
二人がかりでようやく斬り伏せた怪人が、一人の少女に素手で打ち倒されるのを、ぼくとスウは間近で見てしまっていた。
「はい、そうだと思います。あのとき、全身を高揚が包んで、細胞の一つひとつが忘れていた何かを思い出す感じがしました。信じていただけないかもしれませんけど、わたし、これまでだれかを殴ったことなんてありません」
「信じますよ」
ぼくはあのとき、寮長の魂が白いまでに青く光輝するのを見た。間違いなく、ぼくの行う付与を数百倍、数千倍に拡大した現象が発生していたのだ。エネルギーの供給源は、おそらく大地そのもの。あふれる光の奔流は、ドミトリ全体を覆わんばかりだった。
「すべて、確信に変わりました。この地を守るために戦う限り、何を相手にまわそうとも――」
ぼくは、ほとんど威厳に満ちたとさえ言えるその声音にハッとさせられる。
「我が血が敗北することはありません」
いま話をしているのは、寮長ではない。少女の中にある血脈そのものだ。その背後には、眼前の少女を最突端とする長い長い時間の連なりがある。
不浄のものを寄せつけぬ凛とした微笑みに、研究者としての本性に男の本性がたちまち覆いかぶさり、ぼくは思わず視線を宙空へとさまよわせた。
「家事全般におよぶ有能さに加え、容姿の端麗は言うに及ばず、我らの寮長が実は不敗でもあっただなんて聞いたら、プロテジェたちはどんな顔をするだろうね」
やれやれ。やましさをごまかすために軽口を選ぶあたり、ぼくも成熟しない男だよな。
「メンター・ユウド」
曲げた両足の上に臀部を載せた姿勢から上半身を前傾にした寮長が、真剣なまなざしでぼくを見つめてくる。
「ひとつ、お願いがいあるのですが」
もしやこれは、求愛を意味する文化的行動なのだろうか。
いやいや、現実への予期にまで軽薄さが混じりはじめるのは、相当にうろたえてるぞ、ぼくは。きっと、寮長とその血族が負う業に対して、ぼくが配慮や敬意に欠けた発言をしたことへ、不快を感じたに違いない。
すぐに心からの謝罪を表明しなくてはならない。頭はいくら下げても、誰に下げても減らないというのが、ぼくの信条だ。
「寮長、というのはやめていただけないでしょうか」
「ごめん、さっきの発言は軽率だった。撤回するよ」
二人の発言は同時だった。おや。なんかズレてるな。テーブルの表面すれすれにまで勢いよく額を近づけてから、気づく。
「そ、そんなに深刻に受けとめられると、困ってしまいます。どうぞお直りください」
顔を上げると、寮長はもぞもぞと身体をくねらせて、困惑の態だ。曲げた脚部に乗せた臀部が重しになって(問題発言だ)、上半身だけをうねらせているのが面白くて、ぼくは思わず吹き出しそうになる。
「ずっと、違和感がございましたの」
わずかに染まった頬へ手のひらを当てながら、上目づかいにこちらを見る。己の魅力に気づかぬ乙女の発する無意識の媚びには、一種、抗しがたい魔力がある。
「メンターにご意見さしあげるのも無礼かと思いましたし、寮長としての職責を軽く考えていると思われるもイヤで、いままで黙っていましたけど、きょうはいい機会ですので、言わせていただきます」
ときどき忘れてしまうけど、この娘はぼくよりもずっと若いのだ。ほとんどプロテジェの続きみたいな気分で研究を続けてきたせいか、年齢の上下といった感覚が希薄なのだろう。学究生活にフラットな見かけは大切だけど、年かさの配慮までおしなべてフラットにふるまうのは、成熟を拒否するあまり、責任を放棄していることに他ならない。
奇矯な言動が研究の成果で相殺されるには、うちのボスくらい突き抜けないと無理だろうなあ。聞き慣れた哄笑がすぐ耳元で響いた気がして、ぼくはぶるっと身をふるわせた。
個人的に痛いところをつかれ、改めて姿勢を正して座り直す。
「メンターとしてプロテジェたちを指導する立場ではありますが、同時にぼくはドミトリの住人でもあります。寮長の申し出には最大限の敬意を払う用意があります。どうぞ、遠慮なくおっしゃってください」
慇懃な物言いが、小馬鹿にしているようには聞こえなかったか心配になる。
寮長は背筋を伸ばすと、おかしなくらい両肘を張った。
白くて細い首筋。
喉がかすかに上下する。
つばを飲みこんだのか。
わずかな逡巡の後、身を乗りだし決然と言ったのは――
「寮長ではなく、シシュ、と呼びすてにしてください。そうすれば、ずっと気が楽になりますわ」
一瞬、虚をつかれたようになり、まじまじと見つめかえしてしまう。
「わたし、いま、たぶん、おかしなこと、言ってますね?」
真顔のまま聞きかえす寮長。今度こそ耐えられなくなって、ぼくは声をあげて笑ってしまった。
「いや、そんなことはないよ」
「ああ、よかった!」
とたん、笑みくずれる。彼女がここに来て半年、初めて年相応の表情を見た気がする。
与えられた仕事への責任感と、受け継がれてきた盟約への自負心。そしてたぶん、プロテジェに混じっていつまでもドミトリに居座るおかしなメンターへの配慮がすべてまぜこぜになって、ぼくの見る寮長の雰囲気を作りだしていたのかもしれない。
そりゃあ、逆の立場だったら緊張するよな。もっと積極的に、こっちがほぐしてやるべきだったのに。きょう庭先の寮長をつかまえたのだって、結局のところ、学園を取り巻く異変について何か情報を引き出せないかと考えたからだ。いつだって我がことばかりの己に嫌気がさす。
「じゃあ、あらためて」
言いながら、右手をさしだす。
「よろしく、シシュ」
目を丸くした寮長は、少しためらってから、おずおずと両手で(文化的行動?)にぎりかえしてきた。その魂から青い光がこぼれるのが見え、ほんの軽く触れているようなのに、ぼくの骨はめりめりときしんだ。おお。これが、盟約の力ってやつか。寮長の前では、二度と軽口を叩くまい。
「なにかとふつつかな点も多いかと思いますが、今後ともよろしくお願いいたします」
いつにない動揺ぶりで、おかしな口上を述べたてる。いや、これが本当の彼女なのかもしれないな。緊張していたのか、小さな手のひらは汗でわずかに湿っていた。
メンター・ユウドよ、おまえの気のつかなさこそ永遠に呪われてあれ、だ。
空を見あげると、太陽はだいぶ高い位置にあった。思わぬ長居をしてしまった。そろそろ、午後の講義の準備をするべきだろうな。人類の未来を変革するだろう大研究も、日々の生業という一歩から始まるのだ。たぶん。
「おーい、そろそろいくよー」
ドミトリの前庭にある芝生で、横座りのスウとあぐらをかいたマアナが仲良く何ごとかに興じている。ママゴトかな? でも、スウが花をならべ、マアナが花弁を食いちぎって、茎だけ元へもどされる一連の作業が、家庭生活のどの場面を象徴しているのかは怖くて聞けないな。
「ああ、終わったんですか?」
かざした手をひさしにして、スウが見上げてくる。
「むしろ新しく始まったというべきだろうね」
シシュとの一件からか、なんだかやましい気持ちになってごまかしてしまう。別に、スウはモニター以上のなんでもないんだから、ごまかすことなんてないんだけど。
ぼくの内心を知ってか知らずか、スウはかすかに首をかしげて微笑むばかりだ。祖母のところから戻ってしばらくは、いつもこんなふうに元気がない。余計な詮索が生業のぼくだけれど、誰かの個人的な内面はその限りじゃない。
スウの祖母は、ペルガナ学園の評議員である。簡単に言えば、長時間の会議に参加する忍耐は試されないが、学園の運営には口を出せるという立場だ。
学園の黎明期、それは何世代もさかのぼる遠い昔のことになる。当時、七つの素封家が巨額の出資を行い、設立の基盤を作ったのだそうだ。うち二つはすでに血筋が絶えているが、残りの五つは数百年の時を越えてなお健在である。そして、ときどき学園の現状が気にいらず、クチバシをつっこんでくるというわけだ。この外部圧力に対する某メンターの抵抗と闘争については、長い上に相当疲れる話なので、いまは割愛したい。
「マアナは、どうしますか」
「そうだね。どうしようか」
悩める保護者の傍らで、齧歯類の如く頬を膨らませ、口いっぱいにつめこんだ花を咀嚼するのに必死のマアナ。やれやれ。いま噛みつく心配だけはないな。
けど、件の怪人がまた現れないとの保証はどこにもない。まあ、ドミトリにいれば確実に安全なことがわかったのは収穫だったけど、いつまでも部屋に閉じこめておくわけにもいかないしな。少しずつ、浮世の生活に慣らしてやる必要がある。もう、薔薇水晶の中へは戻れないんだから。もしかすると、自分の子どもを持つってのは、こんな感じなのかもしれない。
「よし、いっしょに連れていこう。年少組となら、ちょうど仲良くできるかもしれない。スウ・プロテジェには、講義の前にレジュメを複製する仕事をお願いできるかな。その間は、ぼくが面倒を見るから」
「はい、メンター・ユウド。わかりました」
柔らかな口調だった。むしろ弱々しい、と表現するべきか。言葉を受けとめるというより、言葉に流されるという感じで、奇妙なぐらいに意志を感じさせない。これも、スウが祖母の元を訪れたあとにいつも感じる変化だ。
何かあったの? そう聞いてやればとも思う。しかし、メンターにとってプロテジェとの関係は一時的なものだ。それは、常に自覚しておく必要がある。ぼくのような一部の横着者をのぞいて、いつかここを離れていく存在だ。自虐的に言うならば、ぼくが従事するのは無限にわきあがる夢と希望が、自分だけを取り残して去ってゆくのを見守る仕事である。
過去に一度、痛い目を見た。当時のぼくは、プロテジェ全員の苦しみを救済してやれると信じていたのだ。なんという傲慢だったのだろう。言葉にされなければ、いつか消えてしまう気持ちはある。グラン・ラングの研究者がそこに気づかなかったのだから、笑わせる。掘り起こして、言葉にさせて、途方に暮れる。結果、ひとりのプロテジェがこの手からすり抜けていった。
ぼくが得た教訓は、ひとりが本当に救えるのは人生でひとりだけ、ということ。それは相手にすべてを求める人間の、悲しい法則だ。もうあれを繰り返したくはない。いや、あるいは単にぼくがもう若くはなく、痛みを乗りこえる熱気が失われたというだけのことか。
ふと気がつけば、マアナが水晶のように無機質なまなざしで、ぼくを見あげていた。表情を失ったその顔は、まるで作り物のように恐ろしく端正だ。瞳の赤い虹彩が無限へと誘うようにゆらめく。ぼくの背中へ畏れにも似たおののきがはしる。
しかし、その決定的な異物感は、マアナの笑顔とともに消滅した。むきだしにした歯には、花弁がいっぱいにつまっている。
やれやれ。猫のように身をよじって逃げようとするのを後ろからつかまえて、抱きあげる。
「さあ、友だちのところへ連れていってあげるよ」
マアナは新棟へと向かう道すがらをひとしきり暴れたあと、やがて観念したのか両手足をだらんと伸ばして身体をあずけてきた。重い。
スウはと言えば、なんだかふわふわした足取りで後ろからついてくる。ぼくの肩にアゴを乗せたマアナは、スウの反応を得ようとして百面相ごっこを始めたようだ。平和といえば、これほど平和な見かけもないだろうけど。
だが、平穏極まる日常をどよもす暗雲は、突如として立ち込めるのが世の常である。機甲学科のメンターを進行方向に発見したぼくは、やおらスウの手をつかむと回れ右し、学園創設者の銅像のひとつへ身を隠す。
学科大移動からこちら、機甲学科のメンターたちは、なぜかぼくの姿を見かけると鼻息を荒らげて走ってくるようになった。かさかさと足元へ転がってきた紙くずを広げれば、凶悪な面相の誰かの似顔絵と、生死不問の文字、機甲学科長のサインが書かれている。ぼくは即座に元通り紙を丸めると、後ろへ放り投げた。
機甲学科が豹変を遂げた理由は、目下のところ全くの不明である。しかし、用心するに越したことはない。
「見つけたでえ」
「わあっ!」
背後から声をかけられ、ぼくはとびあがった。取り落としたマアナが尻餅をつき、剣呑な表情でうなり声(おそらくグラン・ラングの)を上げる。
潅木の陰から染み出すように姿を現したのは、キブだった。
もはや隠しようのない大騒ぎに覚悟を決めて振り返るが、機甲学科のメンターはすでにいずこかへ姿を消した後だった。胸をなで下ろすと同時に、キブへの怒りがわく。
「おどかすなよ!」
「いまのあわてぶりを見ると、確認するまでもなく事の真偽は明らかやな」
腕組みをしながら、したり顔だ。
「なんのことだよ」
ぼくは憮然と尋ねる。
「先の学科大移動で、機甲学科の備品が重大な損壊を被ったらしいな。よくよく聞けば、言語学科の某メンターが裏で暗躍してたそうやないか」
「ああ、何かと思えばそんなことか」
ぼくは瞬間、自分でもわかるぐらい無表情になった。
「君は親友だから、正直に言うよ。じつは偶然、何と言えばいいか、そう、自然現象。自然現象が機甲学科の備品を破壊する場面に居あわせたんだ。本当にあれは、不幸な事故だったよ」
「グラン・ラングの暴走、と聞いとるで」
ぼくは不自然なほどさわやかな笑顔をつくって、キブの両肩をつかむ。
「いいかい、だれが吹きこんだか知らないが、それはまったくの素人考えだね。グラン・ラングは平等かつ公正な言語だ。だれが発したとしても、同じ音素ならば同じ結果をしかもたらさない。つまり、発話する者の意図を越えて、気まぐれに暴走したりはしない。まさか、あの瞬間にあの場所で、局所的な竜巻が発生するなんて、だれにも予想できないよ」
そう、グラン・ラングは決して暴走しない。言いながら、抱えていた疑惑がぼく自身の言葉によって裏づけられてしまったのを知る。ならばなぜあのとき、グラン・ラングは暴走したのか。
キブはぼくの手をつかんで、もぎはなした。
「ええい、これで貸りは返したということやな」
「言っている意味はよくわからないが了解した」
うなり声をあげるマアナと、その歯頚から花弁を一枚一枚とりのぞいてやっているスウの傍らで、ぼくとキブは固い握手をかわした。
気がつけば、もはや太陽は頭上に輝いている。午後の講義まで、もうそれほど時間は残っていない。
「じゃあ、お互いの知る案件については、一切の他言無用ということで」
マアナの手を引いたスウの手を、水鳥の親子のごとく、ぼくが引いて歩きだそうとする。
「待て待て、どこ行くねん」
「どこって、講義に決まってるじゃないか」
「伝わってへんのかいな。ついさっき、緊急の学科長会議が招集されたで」
思わず、深いため息が出た。
「ごめん、他のプロテジェたちに休講の連絡をお願いできるかな」
「わかりました」
弱々しい返答が気になるけど、いまはしょうがない。微笑んだまま立ち尽くすスウと、無邪気に手を振るマアナに見送られながら、ぼくはキブとともに、議場へと重い足取りの我が身を曳いてゆくのだった。
ぼくが来ないとわかったとき、年少組のシャイが見せるだろう、がっかりした表情が一瞬、頭に浮かんだ。
なんだかずいぶん長いあいだ、プロテジェたちの顔を見ていない気がするな。
「講義の途中だった」
腕組みをしたまま、苦々しげにスリッドがつぶやく。あとから入ってきたので、いつもの席ではなく、ぼくの隣に座ったのである。
ぼくは両手で顔を隠しながら、うめくような生返事をした。機甲学科のメンターが、はすかいから凶悪な目でこちらをにらんでいるのが気になって仕方なかったからだ。
きっと、スリッドが常の如く会議を紛糾させるのを事前に抑止しようと努めてのことだろう。そうに違いない。そうであって欲しい。
「我々は研究機関であると同時に、教育機関だ。正規のものをしのぐばかりの回数で突然に招集される臨時の会議は、プロテジェたちの不利益につながる。もしこれが学園の運営上、本当に必要なものだと仮定すれば、年度当初に計画された学科長会議の数が妥当でないということだ」
「そうかもしれないね」
ぼくはあいまいに語尾をにごす。スリッドの意見には同意できる部分もないことはない。でも、その論旨の明晰さにぼくはなぜか違和感を持つ。それを的確に表現する言葉がいつも見つからない。もしかすると、己の優柔不断さを言外に指弾されている気持ちになるからかもしれない。苦手意識を持つべきではないと思うけど、スリッドといるときの自己嫌悪の感じはなんとも言いようがない。
「もっとも、私は議長団の議事進行にある致命的な欠陥を無くしさえすれば、大幅に会議の数は減らせると考えているのだが」
二段構えの言論トラップだったか。あやうく一段目で全面的な賛意を示すところだった。
キブは何の関係もない、といったすまし顔で宙を見つめている。しかし、内心はぼくとスリッドとのやりとりに興味津々なのだ。ときどき小鼻がわずかにふくらむのを見れば、何を考えているかはあきらかである。
やがて、学園長とブラウン・ハットの長官を先頭にして、ぞろぞろと首脳陣が入室してくる。スリッドが背を伸ばし、わずかに身を乗りだすのがわかった。臨戦態勢、ってわけだ。学園長が口火を切る。
「突然の召集にとまどわれた方も多いでしょう。ご批判はのちほど承ります」
スリッドの方へ視線を走らせながら、両手をあげる。機先を制せられ、鼻白む気配が隣から伝わってきた。学園長の言葉は、いつも絶妙な間合いでもって、すりぬけるようにして届く。どれほどの激論や騒然とした場であっても、その発言が聞き落とされることはない。
「まずは行政庁からの報告をお願いします」
「えー、それでは」
うながされた長官は、一枚の書面を片手に、眼鏡のつるに中指をあてて立ちあがる。読みあげる直前に、ある人物と視線を交わす。体技科長がわずかにうなづくのを、ぼくは見逃さなかった。
「黒い森と市国をむすぶ中立緩衝地域に、大量の流民が発生しました。今朝の段階で体技科所属のメンターが確認した数は、およそ数千から一万。現在、ゆっくりと市国へ向けて南下しており、交渉をふくめた何らかの対応が必要かと思われます」
すかさず、スリッドが挙手する。
「流民とは、政治的な欺瞞に満ちた表現ではないか。我々に何を伝えることを忌避しての発言か、お答えいただきたい」
「現在のところ、充分な情報が得られていません。無論、紛争等による避難民の可能性を排除しませんが、各国の大使から届く伝令には時間差がありますので」
スリッドの発言に許可を得たと思ったのか、列席するメンターたちが次々と疑問を口にしはじめる。
「海上から侵入したんじゃないのか」
「まさか。それだけの人数が収容可能な船団を維持できるのは、国家規模の組織だぞ」
「まちがいなく街道を通ったはずだ。やぐらの連中は何をしていたんだ」
黒い森を迂回するように、半島の海岸線を沿って二本の街道が走る。やぐらとは、森の尽きるあたりに立てられた監視塔のことだ。
ブラウン・ハットの長官は、再び書面に目を落とした。
「定期の乗合馬車と荷馬車以外の通行は確認されていません」
「不審な通行者へ誰何を与える権利すらない仕事だ。居眠りでもして、見過ごしたんだろう。伝統の機能不全というやつだ」
険しい表情のスリッドが、吐き捨てるように言う。
しかし、一万近くの人間が通り過ぎるのに気づかないなんてことが、はたしてありえるだろうか。単なる見落としでないとすれば、考えられる可能性は二つ。昼なお暗く下生えの複雑に生い茂る魔物の巣、黒い森を踏破したか――
あるいは、黒い森と市国をむすぶ中間地点へ一万という人間が突然、虚空から出現したかである。
極めて空想的なこの考えを口にすることは、はばかられた。心のどこかで己の直感を信じていたにも関わらず、スリッドが醸成する理性の空気にぼくは発言を制止されたのだった。
「うちの若いのがひとり、帰ってこねえ」
腕組みをしたまま、体技科長が低くつぶやく。
「どうにもイヤな予感がする」
さざ波が凪いだ水面へと還るように、場が静まる。スリッドの見解はおくとして、体技科長は会議で長々と発言をするタイプではない。人は言葉の中にではなく行動の中にある、という格言を地のまま体現するメンターだ。ゆえに、その発言はいつも重い意味をもって皆に受けとめられる。
「体技科から要請する。市国民の避難に備え、船舶の徴発を検討いただきたい」
「その動議、支持するで」
老人性のなにかにぷるぷるとふるえる挙手は、なんと史学科長のものだ。干したように小さな顔へ刻まれた皺と垂れたまぶたは、その表情を読むことを極めて難しくしている。レジュメを読みあげる以外の声をはじめて聞いたぞ。目をまん丸くしたキブが、ぼくのほうを見る。どうやら、同じ感想らしい。
「行政庁の職員も、状況が明らかになるまで学園へ退避させたほうがええな。あの老朽化した文化遺産では、用心が悪すぎるわ」
「異議ありッ!」
スリッドが裂帛の気合いとともに手を挙げる。ほとんど剣術や格闘技のようだ。
「一時的にせよ、商家や漁夫から生活の具を取り上げ、かつ、暮らしと直結する行政の任を空席にせよという軽々の提案には耳を疑うばかりである。政策の決定にあって、まず主観的な憶測や怯懦に流されてはならぬことは、私ぐらいがご指導申しあげるまでもなかろう。流民とやらの正体を確認することがまず先決ではないか」
正論だ。しかし、学園長をはじめとする首脳陣が、知りえた情報をいますべてここに開示しているだろうか。学園の意志決定は事実上、学科長会議においてしか行われず、この会議はあまりに公正に誰へとも開かれすぎている。推測や憶測が排除され、言葉にできぬ経験則よりも客観的な事実が優先される。それは知的に極めて正しい場所のように思えるが――
「学園長はどうお考えなのか、我々にお聞かせいただきたい」
我々、という言葉で発言が無い者たちをすべて自分の側に引き入れ、彼と我という明確な対立軸を仮想する。それがスリッドの戦術だ。しかし、会議室では誰も死なない。勝利だけが強調され、敗北は無化される。
「こうして臨時の会議にお集まりいただいたことが、ご質問へのお答えになるかと思います」
やんわりと学園長がいなす。この白髭の老人は、いつも婉曲的な表現を駆使して言質を与えない。
スリッドが絶叫する。
「『学園長は国王』ですかッ!」
使い古された慣用句だ。ブラウン・ハットが政策を実行する段階での問題点や新たな施策のほとんどは、まず学園の政治学科に原案の作成が依頼される。学科長会議での可決をもって、その政策は行政官が運用する実体としてブラウン・ハットへ渡る。そして、学科長会議の決裁権は学園長が持つ。
つまり、学科長会議が学園長の諮問機関という位置づけである以上、理論上は学園長がペルガナ市国のすべてを独裁的に差配することが可能なのだ。現実は迅速な決定からはほど遠いのだが、戒めというより、意にそまぬ案件への攻撃としてよく用いられる表現だ。
「私の提案を、体技科と史学科からの動議に対する修正案として提示する。国王が決裁なさる前に、我々の民意を汲むべく採決をいただきたい」
困りはてた議長が、学園長とスリッドの顔を交互にながめる。体技科長は腕組みをしたまま、じっと動かない。
しばらく沈黙が続いたあと、学園長がゆっくりと口を開いた。
「メンター・スリッドの修正案を承認します。議事を進行してください」
ざわめきの中、紙片が配られる。メンターたちは肘でつつきあい、どちらに票を入れたものか低い声で話しあっている。スリッドは腕を組んだまま傲然と胸をそらし、周囲が彼に向けるさまざまなささやきを受け止めている。大したヤツだ。
紙片を受けとるとき、体技科長がぼくをじっと見つめているのがわかった。ぼくを非難するようなものが視線に込められている気がして、思わず目をそらしてしまう。
たぶん、体技科長とぼくの抱える疑念は、お互いにかなり近いものだ。しかし、提示された動議への賛意を示すためにぼくが言える言葉は、あまりにもこの議場では荒唐無稽に響いてしまうに違いない。
無限へとつながる少女と、神出鬼没の異形たち。
そして、学園へ向けて南下する正体不明の群れ。
わずか数票の差でスリッドの修正案が可決される。状況が明確になり次第、次の会議が招集される旨が告げられ、散会となった。
誰もスリッドを責められまい。そのときの彼は、論理的には完全に正しかったのだから。
体技科の若いメンターが重傷を負って帰還し、まるで時を追って増え続けたかのように、報告される流民の数は二万を越えた。
再び招集された学科長会議の資料において、流民たちの特徴は次のように記述された。
「赤い髪、青い眼、尖った耳、そして大きく造作された顔のパーツは、まるで人を戯画するようである。そして、個体間の見分けが困難なほど似かよっている。近隣の諸国で同一の特徴を持った人種を発見することはできない」
この会議で、スリッドの発言はなかった。
ペルガナ学園は、二日間を完全に空費したのである。
MMGF!(IZAHN)
インターミッション
その石はずっとひとりぼっちだった。
意思の介在をさえ疑わせる整った円錐形が、ゆっくりと回転しながら漆黒を漂流する。
周囲の莫大な空間に比して、あまりに小さく寄る辺無く見えた。
その石はいくつもの生命の傍らを通り抜け、気の遠くなるような長い時間を旅してきた。
そして同じくらい気の遠くなる長い時間を旅して、石さえも形を保てぬあの輝きへと身を投げ、終焉へ没するはずであった。
はるか見下ろす彼方に無数の生命がうごめくのを眺めながら、他人の幸福を祈るときのぬくもりだけを内側に残して、いつものように旅人として去っていくはずであった。
しかし――
楽しげな楽曲や町のさんざめきがいつもより優しく聞こえたように。
人恋しさが人嫌いをほんの少しだけ上回ってしまったときのように。
ふらふらと、ほんのわずかだけ道程をたがえたその石は、あっというまに、暖かな星の抱擁にからめとられてしまっていた。
人ならば、軽率が招いた早すぎる結末に自棄の安逸を感じただろうが、それは石に過ぎなかった。
そして見た。
夜の底に規則正しく響く軍靴の足音と、窓から目だけをのぞかせて破滅を眺める子どもとを。
これまで、どれほど同じ光景を目にし、ただ傍らを通り過ぎたことだろう。
人ならば、あらゆる知性が避けえぬ矛盾に悲しみさえ感じただろうが、それは石に過ぎなかった。
永遠にまじわるはずのなかったふたつが、ひとつの気まぐれによって出会う。
もしその気まぐれに理由があるとするならば――
やはり、ひとりで永遠を行くのは、さびしかったからなのかもしれない。
MMGF!(5)
朝の空気はひんやりとしている。澄んだ大気が遠くまでの視界を約束してくれるため、偵察にはもってこいだ。学園の建物はわずか小高い丘の上に位置し、北の尖塔からは市街地とその先に広がるラノラダ平原を一望することができる。本来ならば豊かに緑ひろがるその場所は、小さなゴマ粒を不規則にまいたようなまだら模様に見えた。
グラン・ラングを発すると、塔周辺の大気が二重に屈曲する。とたん、はるか彼方にあるはずの景色が、まるで手を伸ばせば届くかのように近づく。ゴマ粒と見えたものは、大勢の人間だった。いや、正確には人の形をした何か、と表現するべきか。
ぼくの隣に立つ体技科メンター(頭ひとつほど、ぼくより上背がある)が、重苦しい沈黙を不謹慎さで破ろうとでもいうかのように、ヒューッと口笛を吹いた。この状況を楽しんでいるのか、あるいは現実を正確に把握できていないのか。
しかし、その態度に批判を投げる資格はぼくにもない。眼下の光景に、何の現実感も感じることができないでいる。永世中立のペルガナ市国が、いま言葉も通じぬ異形の軍勢に取り囲まれているだなんて!
「もう少し、連中に近づけることはできるか」
外壁に乗せた片足から身を乗り出すようにして、体技科長が言った。ぼくは黙ってうなづく。その大きな背中のゆるぎなさが、この場における唯一の現実だった。
グラン・ラングをつぶやくと、周囲から絞り込むようにして視界はさらに拡大してゆく。学科長会議に上げられた報告書どおりの容貌が、ペルガナ市国を目指すという一点をのぞいては、まったく無秩序に集まっている。恐れていた通り、あの怪人にそっくりだ。個体差はあるはずだが、少なくとも外見からそれを見分けることはできない。まったく特異な外見が数百、数千、数万と複製されるうち、観察する側にとって没個性の様相を呈するという膨大さだ。
「市民たちの避難は?」
体技科長は流民から目を離さないまま、同行した行政庁の職員に尋ねる。
「順次すすめていますが、港湾に至る道をすべて押さえられておりまして。いくつかの友好都市へ打診しまして、特に健康に困難のあるものを優先して、ウチが所有している数隻を往復させているところです。しかしながら、全市民の避難まではとてもとても」
鼻眼鏡の痩せた男は、顔の前で大げさに手を振ってみせた。
「幸いなことに、海上の封鎖は見られません。まだ、ぐらいの意味ですが。もっとも、その必要を認めなかったのかもしれませんけどね」
「陸路は?」
軽口をいなすように、体技科長が短く尋ねる。
「包囲の薄い箇所もあるにはありますが、それでも流民からは数レウガと離れていませんからね。交渉が難しい以上、行政庁としても最悪を想定しておく必要がある。体技科あたりが護衛についてくれれば話は別でしょうが、肝心の市の防備がお留守になってしまう。どちらも到底、負えるリスクではありませんな」
腕組みをしたまま、体技科長が低くうなる。まさに八方ふさがりというわけだ。
「ユウド」
突然名前を呼ばれて、内心どきりとする。さっと両手を後ろに組み、動揺を隠す。
「状況は予断を許しませんね」
続いてかけられた言葉は、ぼくをさらにまごつかせるものだった。
「ウチの科があいつらとやりあって、勝てると思うか」
個人的に意見を求められるとは予想外だ。ボスの不在に、遠眼鏡がわりで呼ばれたのだと思っていたし、何よりぼくは学科長会議の末席を占めるメンターのひとりに過ぎない。
しかし、ぼくの小さなプライドが客観的な自己認識よりも低かったわけではない。グラン・ラングをつぶやきながらわずかに眼を細めると、たちまち視界を構成する明暗が反転した。付与に関わる、ぼくにしかできないスペシャルだ。
流民たちの内に浮かぶ“魂”の色調は、まるで血のように黒々とした赤で染められている。
この景色をだれかと共有することができないのは残念だ。ぼくとスウが旧棟で対峙した怪人と同じく、その色調は外的な付与の存在を示唆している。もしあれが人ならば、だが。
ぼくはゆっくりと息を吸いこんで、止めた。体技科長が必要としている情報のみを、正確に伝えなければならない。
「身体的な面だけで考えれば、流民の個々が持つ能力は市国の成人男性の、そうですね、少なくとも倍近くにはなるかと。体技科のメンターが全力でかかれば、おそらく打ち倒すことは可能でしょう。ただ――」
「やつらは万、体技科は数百。一人一殺じゃ、数で負けるってか。会戦はありえねえな」
背筋が冷えるような、おそろしく直截的な物言いだ。ぼくは軽く咳払いをする。声がかすれそうに思えたからだ。
「ええ、おっしゃる通りです。市街戦も避けるべきでしょうね。市民の避難もかんばしくないようだし、何より守る範囲が広すぎる。学園に立てこもれば、もしかすると何日かは持ちこたえられるかもしれませんが」
「案外いろいろと考えてやがんだな、おまえは」
体技科長が腕組みをといて、振り返った。
「でもよォ、まずは戦闘が回避できないもんなのか、確かめに行かねえか――おれといっしょによ」
「は?」
思わず、間抜けな声を出してしまう。
「通訳が必要だってんだよ」
そこには凶悪な笑顔が浮かんでいた。
いちど決めれば、体技科長は電光石火だ。その行動には、毛一筋ほどの迷いもない。
「すいません、親爺さん。こんなことになっちまって」
保健部のベッドには、全身を包帯に巻かれた青年が横たわっている。ふだんならば講義をサボるため、仮病のプロテジェが寝ているような、学園の平和を象徴する場所のはずだ。
「なに言ってやがんだ。謝るのはこっちのほうだぜ」
ところどころに血がにじんだ包帯は、しかし、野戦病院にいるかの如き非現実感をぼくに与えた。
「おめえが死んでたら、おいら、てめえを死ぬまでぶん殴ってたところだ」
「それはずいぶん長くかかりそうな自殺ですね」
青年が痛む傷をかばうようにして小さく微笑み、体技科長は豪放に笑う。
体技科のメンターたちが持つ絆は独特のものだ。お互いの命までもが、自然にその担保に入っている。信頼は言葉で確認するべきものではなく、胸襟をさらけだすことをためらう脆弱な自意識もなければ、心を開くことで得る不利益もない。
ふたりを前にして、なんとなく居場所を失ったような気持ちになる。ぼくには到底、築くことのできない人間関係だからかもしれない。
「それでよ――」
笑い声が止み、体技科長は神妙な表情になった。
「何か見つけてきただろうな」
とたん青年の顔がひきしまり、空気は張りつめたものをたたえる。
体技科の上下関係は絶対だ。そこに理屈はない。命令を下す者の能力と責任が完全に反映される厳格なシステム。その頂点に座るのが、体技科長だ。
「口述の報告書が会議にあがってるはずですが、みんな同じ顔をしてまさ。背格好もほとんど変わらねえで、ひとりの人間が何人もいるみたいな、ずいぶん薄気味のわりい眺めでした」
「こっちから仕掛けたのかい」
「斥候として、陣容と指揮系統だけを把握できればと考えまして。気づかれるほど近づいたはずはないんですが、どう言えばいいのか……」
青年の視線が何かを思い出すように遠くへ向けられる。
「一瞬にして囲まれてました。いったん間近で見ちまうと、気配を消すことに長けた連中でもない。気象条件も良好で、見晴らしはあった。馬鹿な言い草に聞こえるでしょうが、何もいなかったところに突然現れたという感じでさ」
「誰がおめえを選んだと思ってんだ。おめえが見たなら、間違いはねえだろうよ」
重々しく、体技科長が言葉をかぶせる。
「じゃあ、その包囲を突破したおめえの奮迅ぶりを聞かせてもらおうじゃねえか」
青年の頬が目に見えるほど紅潮する。高ぶる感情をおさえようとしてか、もしくは悔しさのあまりか、報告を続ける声はわずかにふるえていた。
「見かけによらず、ずいぶんと素早い連中でして、交渉のいとまもあらばこそ、問答無用とばかり、とびかかってきやがった。全員が革製のよろいにマントをはおって、徽章は認められず。獲物はどれも短刀ばかり。こっちも伊達に鍛えちゃいませんで、二人までは先に拳でやりました。煤みてえに蒸発して消えちまうのは、親爺さんに言われてた通りで。まっとうな人間とやってんじゃないとわかって、驚いた」
この人は、いったいどこまでを知っているんだ。ぼくは体技科長の大きな背中をまじまじと見つめた。
「ふつう、同士討ちを嫌って密集を避けるもんでしょ。なのにやつらときたら、次から次へとおかまいなしだ。烏合の衆って感じで、指揮系統があるようには見えなかった。背中に斬りつけてきた三人目以降はものすごい乱戦になっちまって、そっからは数えてません」
「相手が何人なら、触らせずにやれた?」
抜き身の刃物のような明瞭さ、過不足の無い凄みにぼくはぞっとする。
口を曲げて眉を寄せ、青年がおし黙る。これから口にすることが、体技科長にとって極めて重要な情報になることがわかっているのだろう。
「あの、おれならば、です。おれの鍛え方が半端なことは、親爺さんにもわかってるはずで」
「余計な口はいいぜ。おめえのことでおいらにわかってないことがあるかよ。正確に言え。おめえの次の言葉で、作戦が決まる」
体技科長の周囲に一瞬、熱気のような圧が膨れあがるのを感じたのは、はたしてぼくの気のせいだったか。
重傷に身を横たえていたはずの青年が突如、はじかれたように上体を起こす。
「同時ならば三人、続けてならば十人ですッ!」
大声で一息に吐き出すと同時に、再びベッドへ崩れ落ちる。どうやら失神したらしい。
駆けよってくる保健部の看護人に「さわがせたな」とだけ言いおくと、体技科長はのっそりと病室を出てゆく。ぼくはあわてて後を追いかけた。
「知るべきことはすべてそろったな。おめえもそう思ってるだろ、ユウド」
「どうするんですか、これから」
ぼくは、問いかけに含まれた言外の意図に気づかないふりをする。
「さっき言ったじゃねえか。通訳が必要だってよ」
凶悪な笑顔。
笑顔の由来とは、動物が牙を剥く行為の名残りなのだという。だとすれば、この瞬間の体技科長の表情ほど、その本質に迫るものはなかった。
「喧嘩する相手のツラをおがみにいくのさ。もしできるなら、その場で全員ぶちのめして帰ってくる」
この人は本気だ。しかし、独断専行もいいところだ。
「学科長会議にかけなくていいんでしょうか」
「おめえさんからそういう不意打ちを喰らうとは思わなかったぜ」
おそろしく太い指で、がりがりと頭をかく。
「だいぶ毒されてんじゃねえのか、ご友人に」
いったい誰のことだろう。
「みんな死んじまってからじゃ、遅いんだぜ。生き残ってからゆっくり、責任の所在を明らかにする会議をしようや」
みんな死ぬだって? 考えてもみなかった。
死への夢想は平穏の中でときに蠱惑的だけれど、その死はいつだって己にだけ訪れる種類の終焉だ。ぼくと体技科長たちの世代でおそらく共有されない感覚とは、死に対するものにちがいない。ぼくは個の内側に死を思い、体技科長は個の外側に死を思う。
「ちょっくら出かけるとしようか。昼メシまでに戻れりゃいいんだがな」
沈黙は、どうやら肯定と受けとられたようだ。大きな背中がずんずんと廊下を遠のいていく。その足取りにはやはり、何も迷いもない。
ぼくはと言えば、この提案に対しての思考を停止していた。やる。やらない。どちらにも決められない。いちばん強いのは、この件から降りてしまいたいという気持ち。なのに、ぼくの足は体技科長の後を追いかけていた。当事者意識の欠落した当事者は、ただ惰性により他人が動く方向へ流されてゆく。
しかし、表面上はきっとそんなふうに見えなかったはずだ。ぼくにとって、自分がまるでふつうの人間であるかのようにふるまうことは、ほとんど習い性のようになっていた。それに何より、体技科長の世界観には、必要な決断を先送りにする人間像はふくまれないだろうから。
「安心しな。おめえに荒事を期待しちゃいねえよ。ただ――」
勘違いをしたまま、肩越しに体技科長は続ける。
「おいら、興奮するとわりと周りが見えなくなっちまうタチでよ。おまけに、眼は前にふたつしかついてねえときてる。だれか、おめえさんに護衛が必要だな」
その言葉が終わるか終わらないかのうち、廊下の先ではかったようにスウが待ちかまえていた。
腰には刀をはいている。実際、屈強な体技科の面々に拉致された貧弱なメンターを心配して、ついてきていたのかもしれない。
「その役目、私が買おう。極限の場面で学科の違いがマイナスに働かないとも限らないからな」
体技科長は楽しそうに目を細める。
「ウデは問題ねえ。条件はひとつ。理事に話を通さんことだ」
「状況は逼迫し、組織では遅すぎる。尋ねられるまでもない」
ふたりの達人にはさまれた大気は、じっさいに密度と温度を変じるようでさえある。
どちらもおそらく、この世界に対する己の物理的な影響力を疑ってはいない。この拳が、この刃が、相手を打ち砕かないかもしれないなんて、虚弱な空想はどこにも入る余地がないだろう。
ぼくは違う。研究者としての武器である言葉さえ、それが通じないかもしれないことにいつもおびえている。グラン・ラングを選んだのだって、現代において通じないことの揶揄に使われる、死んだ言語だからではなかったか。
なんにもわかっちゃいないのに、なぜぼくなんだ!
ふってわいたこの仕事を投げ出す相手を探そうとして、愕然とする。こと施術という観点に立てば、ぼくが実質上の言語学科ナンバー2なのだ。
誰もが研究へと重きを置きすぎ、あまりに困難な実用を避けてきた結果とは言えよう。けれど、ボスに比べればぼくのグラン・ラング運用能力は、子どものお遊び程度にすぎないのだ。
このぎりぎりの局面に至って、言語学科の人材層の薄さを改めて実感させられるとは。今回の失敗は、そのままペルガナ市国の破滅へつながるかもしれないというのに!
ほとんど上の空のまま、ほどなくしてぼくは馬上の人となった。
といっても、馬術の心得があったわけではない。振り落とされないようスウの腰に手を回しているだけである。しかし、充分な凹凸があり、その心配だけはなさそうだ。
「余計なことを考えていると、振り落とされるぞ」
おっと。読心術でもこころえているかのように、スウが肩越しに湿った視線を投げてくる。
学園の敷地の外れにある厩舎を出発し、子どもたちの歓声を得て市街地を駆け抜け、潮騒を左手に聞きながら街道を北上する。刃一枚さえ通さないほど精緻に組まれた石畳の街道だが、敷設の労を担ったのは市国民ではなく、やはり古代人である。
やがて体技科長は無言のまま、街道を外れるように馬首を右へとかえした。スウがそれに続く。
ラノラダ平原には敷き詰めたように草はらが広がっており、ところどころに遺跡とおぼしき巨石が地上へと顔をのぞかせている。それらは文字通り氷山の一角であり、見た目の無機質な感じと裏腹の豊穣さ(研究者にとっては、だけど)を地下に眠らせているのである。
なぜ、古代人は地上へではなく地下へと広がっていったのだろうか。正統・異端を含めて学説はいくつもあるが、観点としてはだいたい次の二つに集約される。
かつては地上にも地下と同じ規模で建造物があったのだが、歳月と風雨にさらされて消滅してしまったという説。それから、ぼくたちと古代人との間には生物学的に見て、器質的に大きな隔たりがあったのだという説。
これは学説以前の個人的な意見だけど、古代人は自然に対して深い畏敬の念をいだいていたのではないかとぼくは考えている。つまり、人の営みが自然の営みの妨げにならないようにしたのではないか。現代には再現不可能な、強力極まるレガシーを多く産み出してきた古代人だ。それは相当にありそうなことに思える。
「おい、もうこんなとこまで来てやがるぜ」
おそらく現実を忘れるためのぼくの思索は、体技科長の低いつぶやきによって破られた。
半島の中央部は地形に起伏が少ないため、天候次第でかなりの見通しがきく。はるか遠くに陽炎の如くゆらめくと見えたものは、無数の人影だった。おいおい、予想よりもかなり速いぞ。
「いつでも抜けるようにしときな。近づくぜ」
スウに言葉を投げるや、体技科長は何の逡巡もなく異形の群れへと突っ込んでゆく。スウは匕首を切りながら軽く腰を浮かせ、片手で馬を御して後へと続く。
ぼくはと言えば、一気に緊迫する状況へ何の準備もできず、心臓が打つ早鐘を他人事のように感じていた。うろたえたまま、グラン・ラングに置き換えるべき交渉の内容を思い浮かべようとし――
できるわけがない。そもそも、グラン・ラングが通じるかどうかさえわからない。それ以前に、人の形をしているから人と同じ心や知性を持っているという期待すら、あまりに楽観的に過ぎる。
この未知に対するすべては、むなしい予断だ。
そう考えると、肝がすわった。己の中心へ軸足をすえて世界の余剰だけを感知するときの、天秤のような自我がたちまちぼくを満たす。
耳を聾していた鼓動が止んだ。煩悶も葛藤もすべてが消え、もっとも中立な空っぽの状態が降りてくる。あとは、外界の反応がぼくの行動を正しく規定するだろう。
迫りくる二騎を包むように怪人たちは左右へ音も無く分かれ、体技科長が手綱を引きつつ大音声で呼ばわる頃には、包囲は楕円形に完成していた。
「おめえたちの目的はなんだ! 返答次第じゃ、この場で全員ぶちのめすぜ!」
できるだけ正確に音素をつむごうとして、ボスの言葉がすぐ耳元によみがえる。
「悪くはない。悪くはないが、きれいにやろうとしすぎだな。ただ、おまえのすべてを残らず向こうに預けてくるんだ。こわがらなくても、必ずおまえは受け止められる。グラン・ラングはただの言葉じゃない。グラン・ラングは、世界そのものなんだから」
いつかの記憶が、あらかじめ仕組まれたトリガーであったかのように、電撃の如くぼくの眉間を貫いた。一瞬のうちに、これまで積み上げてきたすべての知識と経験は、このひとときを頂点としたあるべき位置へと再配置される。スウの背中を視界にすえながら、同時にぼくはぼくを俯瞰していた。
――世界は思ったほど、人間のことが嫌いってわけじゃない。
言葉にすれば、ひどく単純な悟り。しかしそれは、ぼくにとって大いなるブレイク・スルーの瞬間だった。
さあ、心を研ぎ澄ませ。
人間存在を肯定する、この世界の根幹を感じるんだ。
空わたる風のように。
たなびく雲のように。
ぼくが発したグラン・ラングの残滓は、わずかの反響となって虚空に消える。
流民たちに訪れた変化は劇的なものだった。ほとんど同じ外見を持ちながらバラバラだった動きが統一され、ひとつの固体をそれぞれが完全に写しとったようになる。
馬から跳びおりた体技科長が、前傾姿勢に構える。
スウは音も無く抜刀し、背中あわせに馬首を返す。
ふたりを制するように、取り囲む流民たちは寸分たがわぬ動きでいっせいに右手をあげた。そして、何かの儀式を思わせるゆったりとした抑揚で、グラン・ラングを唱和しはじめる。
「『我々は“世界の中心に蝟集する者”である。我々がお前たちから奪いたいものは何も無い。だが、我々が中心へ還ることを妨げるならば、お前たちは奪われるものを持つことになる』」
音素の入り組んだ複雑な内容だったが、ぼくは苦も無くその内容を理解できた。意味が直接、頭へ入ってくる感覚は、ぼくたちの言葉に置き換えるのがもどかしいほどだった。
「驚いた。さっぱり意味がわからねえ」
「通訳は正確です」
グラン・ラングに関して、こんな反論をする自負心があるとは思わなかった。
「おめえさんを疑ってるわけじゃねえよ。おいらがバカなだけだ。質問を変えるぜ」
抑制のきいた胴間声。ヘンな表現だが、体技科長の個性をそのまま表現している気もする。
「おめえたちは俺たちにどうしてほしいんだ! 食糧か、住処か! ただ喧嘩を売りにきたっていうなら、買うのはいまンとこ、ここにいる三人だけだ!」
おいおい、聞いてないよ。でも、伝える内容を取捨選択する権利がぼくにあるわけじゃない。投じられた小石が水面に波紋を生じるように、ぼくの発したグラン・ラングの小さな音素は巨大なうねりとして、八方からの反響となって返ってきた。
「『我々が求めるのは、世界の中心を取り巻く青き生命の排除である。我々が求めるのは、中心の空白を赤き生命で満たすことである』」
体技科長はうなりながら頭をがりがりとかきまわす。
「こいつらはものすごく頭がいいか悪いかのどっちかだな。気がおかしくなりそうだぜ」
スウが肩越しにぼくをちらりと見る。言いたいことはすぐにわかった。
「青き生命とは私たちのことを、赤き生命とは流民たちのことを指していると推測されます。おそらく――」
ぼくは努めて感情を抑えながら、言った。
「彼らの言う“世界の中心”とは、いま学園に存在している何かということでしょうね」
「おい、それはつまり学園をあけわたせってことか? やっぱりこいつら、喧嘩を売りに来てんじゃねえか!」
体技科長が流民たちの言う“世界の中心”の正体について察しているのかどうかは、わからなかった。
「ユウド、いったい手を引く気はねえのか、こいつらに――」
言いかけて、体技科長は口をつぐむ。気がつけば、流民たちにあった統一の感じは消滅していた。
一方的に目的さえ伝えれば、あとに残すのは拒絶というわけか。手に手に短刀をかまえ、じりじりと包囲をせばめてくるその様は、もはや元のような烏合の衆である。
即座に襲いかかってくるかと思ったが、ふたりの達人が発する無形の磁場に気圧されてか、遠巻きに威嚇するばかりで近づいてこようとしない。
「しっかり腰につかまっててくれ」
スウが有無を言わせぬ調子で言う。
「この数はちょっとまずいね」
旧棟での遭遇戦が流民イコール怪人の固体能力をそのまま表していたのだとすれば、複数で来られた場合、少なくともスウとぼくにとっては分が悪い。
「心配するな」
ぴったりと触れあった身体が意志を伝播したかのように、スウがぼくの疑念に返答をした。ときどきこういうことがあるのは、腐れ縁が長くなりすぎたせいかもしれないな。
「あのときは調子が悪かっただけだ」
軽口や負けおしみでは困る。ぼくの不安を和らげようとしているのなら、立場が逆だ。言いつのろうとするぼくに、
「そういう日もあるんだ」
なるほど。察しのよさだけで数々の危地を切り抜けてきた老獪なメンターは、ここで黙った。
ぼくたちの力量を推し量るためか、包囲の輪の中へ流民のひとり(この表現が正確かどうかはわからない)が歩み出た。個々として見れば、やはりあのときの感じとそっくりだ。
じっと動かぬ体技科長に対し、円を描くように間合いをはかる。
一瞬ののち、風を巻いて怪人が襲いくる。常人の動きではない。凄まじい速さだ。
体技科長は身体を開きながら、急所をねらう短刀からかろうじて身をかわす。交錯の際に打ち出された拳は遅く――
むなしく空を切った。
傍目には無傷の両者が位置を入れ替えただけだが、怪人の表情は獲物を得た喜悦、あるいは何かの優越に変容しているように見えた。
「あぶねえ、あぶねえ。あやうく殺っちまうところだった」
ぼそりとつぶやき、拳を手のひらに打ちつける。びりびりと大気が震え、体技科長を中心とした同心円状に草がなびいた。取り囲む流民たちが、わずかに退く。
「ユウド、ひとつ確認しときてえ。この交渉は決裂したよな?」
言うまでもない。ぼくはうけあった。
「間違いありませんね。彼らに和平交渉の素地はないようです」
その言葉を聞いて、体技科長は莞爾と微笑んだ。それは、この緊迫した場面に似つかわしくないほど、ある種の純粋な喜びに満ちていた。
まばたきをひとつすると、魔法のように目の前の怪人が姿を消した。体技科長が突き出した右拳の周囲に、煤のような黒い煙が舞っている。
空中にある短刀と衣服が地面に触れるか触れないかの瞬間――
包囲の一部が黒く爆発した。
それは、体技科長の吶喊だった。まったく見えなかった。
「馬引け!」
スウが片手で二頭の手綱をとり、包囲の薄くなった箇所をさらに斬り崩しながら外へと飛びだす。体技科長は襲いくる怪人をその巨躯からは想像もつかない身軽な跳躍でかわす。続けざまに空中で頭部を蹴りつけると、反動を利用して馬上へと還った。
「おい、逃げるぜ!」
したたかに腹を蹴られた二頭の馬が、死にものぐるいで駆けだす。
人の足が追いつけるはずはない。しかし、追ってくるのは厳密な意味での人ではなかった。なぜなら、全力の馬と並走できる人がいるはずはないからだ。
 「手綱をまかせる。にぎってるだけでいい」
「手綱をまかせる。にぎってるだけでいい」
言うや、ぼくをまたぎこしてスウが馬上に直立する。
「上を見るなよ」
遅かった。白じゃない。
明らかな殺意を発する異形の群れに囲まれて、馬たちは興奮の極みにあった。この激しい揺れに倒れないなんて、尋常なバランス感覚じゃない。スウは一切を意に介さず、ゆっくりと刀を下段に構えた。
併走する怪人たちがわずかに上体を沈ませるのが見えた。来る。
跳躍ではない、飛翔。肉厚の短刀が閃く。
十の影がスウを目がけて急速に降下する。
風を孕んだマントは猛禽の翼を思わせる。
白い光輝が虹の軌跡を描き、時間と空間が共に動きを止める。
厳粛な静寂の中、猛禽たちは宙空に静止する。
鍔鳴りが響くと、輪郭を喪失した十の影は同時に黒く蒸発した。
背中に柔らかなものを感じる。スウが背後からぼくの手綱を取ったのだった。
振り返れば、追いすがる怪人たちが速度を落とすのが見えた。
「大したウデだ」
体技科長の楽しげな賞賛に、スウはすまし顔で返答する。
「少なくとも、与しやすくはない印象を与えられたはずだ」
「ちげえねえ。言語学科と体技科は本交渉において一定の成果をもって帰還せり、だ」
ふたりの会話を聞きながら、ぼくの思考は別のところへと漂っていた。
常人ならぬ身体能力を有した言葉も通じぬ怪人たちによって、学園の包囲はまさに完成しつつある。もちろんこのふたりなら、何が相手だろうが必ずねじふせてしまうだろう。けれど、同時に万を相手にできるわけじゃない。体技科長は、戦闘を不可避なものととらえている。行動を見れば、それは明らかだ。
でも、キブはどうなる? ぼくのプロテジェたちは? 臆病なぼくには、戦えない人たちのことばかりが気にかかる。
そして、心に浮かんだのはひとりの少女の姿。
「マアナは?」
「シシュのところだ。いま学園では、あそこがいちばん安全だろうからな」
賢明なスウは、体技科長の前でそれ以上を言うことを避けた。しかし、考えていることはぼくと同じだったに違いない。
ひとりのサクリファイスによって、残った人々が救われるとしたら――
答えは出なかった。
MMGF!(6)
結局のところ、ぼくの確信がどこから来ているかと言えば、最初のくちづけしかなかった。だから、ぼくにしか知りえない情報をとりのぞいてみれば、相当度にうさんくさい筋立てに聞こえるはずだ。それを証拠に、組んだ両手に顎を乗せ、目を閉じたまま熟考する様子の学園長は、もはや対話での適切な間を越えた沈黙を続けている。
どうにも居心地が悪くなり、ぼくは室内へと視線を泳がせる。家具にせよ、調度品にせよ、空間の取り方にせよ、ひとりの人間の居住のみを考えれば過度な余剰(おかしな表現だけど)が、そこここに詰めこまれていた。ある個人の所有する余剰が権威を形成するのは、人の世のならいと言える。だとすれば、『学園長は国王』の揶揄も、あながち的を外したものではないのかもしれない。
ときおり、背後から聞こえるかすかな擦れ音は、部屋づきの速記官のものか。つまり、ここでの会話はすべて公開を前提に採録されているってことだ。
しかし、学園と市国を救う方法を他に思いつかない。やがて学園長がゆっくりと顔を上げ、ぼくはその視線を無理矢理につかまえる。真摯さを演出するんだ。ハッタリだってかまやしない。
「この案件が学園にとって極めて重要な意味を持つことはわかりました。よく話してくれました。至急に、学科長会議のための予備審議に挙げたいと思います」
しかし、ぼくに与えられた穏やかな声色は、学科を飛び越えた個人による突然の陳情への、お決まりの定型句なのかどうかをはからせはしなかった。これは役者がちがうな。他に方法は無いと思いさだめてここへ来たはずなのに、簡単に気持ちが萎えるあたり、やはりどこかでぼくは他人や組織を信用していないのだろうなと思う。
「貴重なお時間を割いていただいて、ありがとうございました」
ともあれ、話の信憑性を薄れさせる有効な方法は多くを語ることだ。ぼくは短く礼を述べると、たちまちにきびすを返す。部屋の片隅に置かれた小さな机に、ひとりの女性が背中を丸めて座っているのが見えた。入室するときには気づかなかった。若いような年老いたような、ふしぎな容姿だ。鼻眼鏡の下からちらりと、こちらを値踏みするような視線を投げてくる。彼女が知る、多くの陳情団や追従者たちと比べられているのかもしれない。ぼくは形の無い何かがまとわりついてくるのを振り払うように、歳月が薄黒く光沢させた扉を少し乱暴に押し開けた。
背後に重い音が響くと、安堵が心を満たすのがわかった。少し遅れてその正体に気がついて、気持ちが沈む。
ぼくは臆病だ。ひとりでは何ひとつ決断できない。ともすれば、責任を投げだすための相手を探している自分に気がつく。体技科長のことを信頼していないわけじゃない。彼にすべてうちあける選択肢もあったはずだ。だがぼくは、最高責任者へ直接に陳情することを選んだ。学科の違いが、率直な相談を妨げたのかもしれない。
いや、ちがうな。また学科の違いなんていう都合のいい言い訳を用意している。そしてそれすら、メンター・スリッドの論法から剽窃した概念に過ぎない。ぼくは自分への言い訳ひとつさえ、自分の言葉では満足にできないのか。
深刻な自己嫌悪に胃のあたりを圧迫されながら、足早に学園長室を離れようとすると、
「まさか置いていく気じゃないだろうな」
不機嫌そうなスウの声が後ろから響いた。しまった、ついてきてもらっていたのをすっかり忘れてた。
「ごめん、ちょっと考えごとをしていたんだ」
「どうせまた、出口のない悩みごとだろう。そういう顔をしている」
妙に聡いところが、ときどき本当に憎らしくなる。このプロテジェに、知って見ないふりという配慮はないのだ。
「学園は包囲されている。海路での逃亡に充分な船舶の数はなく、学園の放棄が前提だ。体技科長とスウ・プロテジェが対人で遅れをとることはないだろう。しかし、各個撃破は局地的な状況を打開するだけ、流民たちが数を頼みの同時侵攻に訴えた場合、そのすべてを防ぐことは不可能。つまり、学園の防衛には否応なく、学際的な結束を構築する必要がある。そして、メンター・ユウドの考案する要撃作戦には、マアナの持つ力が不可欠だ」
スウが片目をつぶってぼくを見る。学際的な、という表現がずいぶんと皮肉っぽい。
「どれも何度も確認したことだ。これ以外に方法はない。ユウドが負い目を感じることは何もない」
いちいちどれもごもっともだ。だが、本当にすべての可能性は検証されただろうか。流民たちとの戦闘が不可避であるという前提が、そもそも間違ってはいないか。もしかしてうちのボスなら、もっと突拍子もなく、それでいながらすべてを円満に解決する方法を思いつくのではないか。
何よりいちばんの不安要素は、今回の経緯と作戦が、ぼくの深いところにある、ぼくが嫌っている性分とぴったり合致しているところだ。己の心の問題のみで学園の命運を左右しようとしているのではないかという疑惑。
他人を信頼するといえば聞こえはいいが、要するに自己不信が深刻なのだ。
組織を信頼するといえば聞こえはいいが、要するに責任を分散したいのだ。
安堵を感じたのは、学科長会議に至るしばらくの先行きがこの手を離れて、ぼくのコントロールを越えたから。
たとえこれでダメだったとしても、ぼくが決めたことじゃないし、ぼくのせいじゃない。
それは頭の内側から響いてきて、耳をふさいだって聞こえてくる。
「まったく、やっかいなことだ。普段は無為が身上のくせに、いざとなるとひとりですべてを抱えこんで、指揮官か王様のようにぜんぶ差配したがるのだからな」
スウが肩をすくめて、わざとらしく両手を上へ向けた。
その仕草に含まれた優しさを見て、ぼくは少しだけ気が楽になる。誰かの関心は、頑なさや思いこみを溶かしてくれる。
プロテジェたちはみんな、いつだってこんな駄目メンターにも優しいんだよな。彼らはぼくがきっと間違わないことを、たとえ間違ったとしても、それは良い意志のゆえだということを信じてくれている。
そう考えると、揺れていた心が定まる。彼らの信頼に対する責任だけは果たそう。ぼくにできるのは、決して手を離さないようにすること。それはぼくの最低限で、同時にぼくのすべてだ。
「内省は人生の基本だからね。水面の少し下を行くのがぼくの流儀さ」
「まったく」
軽口に、スウが目元を緩める。
「さあ、次の一手だ。学科長会議の招集までに、もう少しやっておくことがある」
「ふむ。他学科への根回しかな」
腕を組んだまま、わずかに首をかしげる仕草が愛らしい。ぼくのことならなんでもお見通しといったていの少女が見立てを誤るのは、なんだか気分がいい。
「見識が浅いね、スウ・プロテジェ。シシュだよ」
「シシュ?」
「行こうか。そろそろ集まってるはずだ」
太い眉を怪訝に寄せるスウを尻目に、ぼくはドミトリの方へと歩きだす。
しばらくは、このささやかな優越を楽しもうと思いながら。
最初は誰もが半信半疑の様子だった。突きだされた拳の速度は、明らかに手加減されたものだったから。庭掃除用のほうきの柄が、その手首へ交差するようにするどく打ちつけられる。次の瞬間、体技科のむくつけき大男は小柄な少女の足元に背中から落ちていた。
二人目は本気だった。しかし、結果は変わらない。腕組みをした体技科長が不満げに鼻息を吹くと、居並ぶ体技科の面々にサッと緊張が走った。
寮長――シシュは涼しい顔でスカートのすそを払う。
「せっかく掃除しましたのに、またほこりが舞ってしまいましたわ」
前髪の一房を指でよじりながら、微妙にズレた発言をする。周囲の空気が一変したのを意に介したふうもない。
「あの、みなさん、お一人ずつでよろしいんですの? それだと時間がかかりますわ。わたくしも、炊事に洗濯、まだきょうの仕事をたくさん残しておりますし」
のんびりとした声音。たぶん本人にそのつもりはなかったと思う。けど、無意識の挑発は体技科に火をつけた。
シシュを挟みこむように対峙した二人が同時に挑みかかる。
その燃えあがりは、しかし瞬く間に鎮火された。
拳が空を打ち、二つの身体が交錯するように地面へ崩れる。ほうきの先端と右の足刀がそれぞれの水月と喉をきれいに直撃していたのだ。回避と攻撃が一体となっている。お見事。
「なめるなッ!」
彼我の実力差は明白だった。けれど、若いメンターたちは無理にも己を鼓舞し、必死の形相で次々と眼前の少女に挑みかかる。
無理もない。彼らの背後には体技科長が腕組みをして控えているのだから。
どちらに地面へ転がされる方が幸せかは、尋ねられるまでもない。
どれだけ相手が増えようと――いや、人数が増えていることがまさに理由なのだろう、シシュの俊敏さと技のキレは天井しらずに向上してゆくようだ。もはや目で追うのも難しいほどの動きで男たちを翻弄している。
「ユウド」
ぼくの横で体技科長がうなり声をあげた。
「俺は自分の目が信じられねえ」
見れば、倍ほどに膨れ上がった二の腕には、幾筋もの浮き上がった血管がよじれていた。
や、まずい。これはやる気だ。グラン・ラングによる盟約と極限まで鍛えた身体、ぶつかればどっちが残るのか、運動など薬にもしたくない虚弱な研究の徒として野次馬的な興味は残るけど、いまはまずい。
「この世界は、目に見える以上のもので出来ているということですよ」
ぼくは背中に冷や汗をかきながら、冷静にふるまおうと努める。
「グラン・ラングによる古い盟約が、あの少女に流れる古い血脈を通じて、この土地を守らせているのです。おそらくドミトリの敷地内限定でしょうが、彼女が倒されることはありません」
「守れば最強ってワケか。攻めダルマの俺にしてみりゃ、どっちが上か試してみたくてうずうずするぜ」
悔しそうに拳を手のひらへ打ちつける。間近でつんざく破裂音に、耳が痛くなる。
「おめえの言いたいことはわかってるぜ。大きな喧嘩を前に、一番強いコマどうしが潰しあうなってんだろ」
「冷静な判断、痛みいります」
後ろに組んだ両手は、もう汗でじっとりだ。
「ひでえ野郎だ。だんだんやり口がてめえのボスに似てきやがるぜ」
良識派をもって任じるぼくにとって、あの類の奇人変人といっしょにされるのはかなり心外だ。けど、的を射ている。性格は度外視するとして、土壇場に追いつめられたときにぼくの行動規範となるのは、ボスだったらどうふるまうだろうかということだから。
「だって、仕方ないですよ」
こういうときはたぶん――
ぼくはできるだけ穏やかに見えるよう、にっこりと笑って、
「百聞は一見にしかず。見なければ信じなかったでしょう、きっと」
「くあぁッ、憎らしい口を聞きやがるぜ。なんでもお見通しってワケかよ」
体技科長はがりがりと思いきり頭をかき回す。いつも思うけど、じつに頑丈な頭だ。
「けどよ、小僧ッ子ぐらいに見透かされて、てめえんとこの若え連中をひっくりかえされて、メンツつぶされて、恥ィかかされて――」
制止する暇もあらばこそ、部下を心配する言葉とは裏腹に、累々と折り重なるメンターたちをほとんど蹴散らすようにして、体技科長はずんずんと進んでゆく。
「ただで気が済むと思ってんのかよ!」
ちょうどシシュを見下ろす格好だ。筋肉で肥大した上体はわずかに前傾していて、向きあう二人のシルエットは、まるでクマに襲われる子どもみたいに見える。
ぼくはもう、体技科長をうまく懐柔できると一瞬でも考えた己の浅はかさに青ざめていたが、シシュにひるんだ様子はまったくない。
「あの、学科長に手をだしたりしたら、わたしクビになってしまいますわ」
すでに十数人のメンターを殴り倒しているにしては、やっぱりズレた発言だ。さらに、体技科長を殴り倒せる気でいるらしい。
「かわいい顔して、おもしれえことを言うじゃねえか」
その言葉に体技科長は破顔一笑するが、こめかみには十文字に血管が浮き上がっていた。
「大丈夫だ。言語学科のメンターとプロテジェが証人になる。ここでは何も起こらなかった、ってな」
シシュの手首ほどもある親指で、ぼくたちを指した。
「いいのか。少々まずいことになってるぞ」
スウがすぐそばで耳打ちする。
「だ、だいじょうぶ、すべてアンダーコントロールさ」
返答する声は上ずっていた。さきほどまでの自信はどこへやら、スウがぼくに向ける視線はいまや疑惑でいっぱいだ。
「安心しな。おんな子どもに手をあげる趣味はねえ。おい、ユウド!」
「はいッ!」
ぼくは思わず直立不動の姿勢を取る。
「覚えとけ! おいらの信条は『見ることは信じること』じゃねえ! 『味わうことは信じること』だ!」
うわあ、おもいきり根に持たれてるよ。身の丈に合わない、借り物の言葉は使うもんじゃない。
「おい、おじょうちゃん。いまここで思いッきりおいらを殴れ」
言うや、体技科長は両手を大きく広げた。好きな場所を打たせるつもりだ。
不安そうにぼくのほうを見るシシュ。その様子は、ぼくが自分のことをひどいやつだと思わせるのには、充分に可憐だった。
でも、体技科長を納得させる方法を他に思いつかない。ぼくは口をへの字に結ぶと、お仕着せの少女へとうなづきかけた。
大きくひとつ息を吐くと、シシュは意を決したように腰を低く構える。
永遠に思えるような、完全な静止。
シシュの上半身が回転し、消えた。
がぁん。
槌が岩を打つような鈍い音。かすかに地面が揺れるような錯覚。
まばたきのうちに、少女の細腕が体技科長の側頭部を打ちぬいていた。
長い静寂。
やがて体技科長は無言のままシシュに背を向けると、ぼくの方へとゆっくり戻ってくる。
「ユウド」
背筋の寒くなるような、壮絶な表情だ。
「俺は信じたぜ」
にやりと笑うと、体技科長はそのまま大きく道をそれて、地響きとともに大地へと横だおしに倒れこんだのだった。
歳月に薄くなった皮膚は頭蓋へはりつき、たるんだまぶたは垂れさがったまま開かない。まばたきせずに充分長い時間を眺めれば、かろうじて胸元が上下しているのがわかるだろう。両手を腹部で組み合わせ、わずかにうつむいた姿勢のまま微動だにしない史学科長は、古代の葬儀に使われた埋葬品だと知らぬ者に伝えても、何の疑問もかえってこなさそうな有様である。
「言われんでもわかってるて。まあ、心配せんとき。このキブねえさんに根回しは不要や。調査資料の改竄、遺跡の私的占有、発掘品の横流し、いつだってユウドの求めてる最善を満たしてやろうと、手ぐすねひいて待ちかまえてるんやさかいに」
不穏当なその発言は、史学科長がそばにいることを全く意に介していない。だいじょうぶかよ、この学科。ぼくの心配をよそに、キブはがははと豪快に笑うと、ぼくの背中をひどくどやしつけた。
「表現の仕方はすごく気になるけど、まあ、頼りにはしてるよ」
咳きこみながら答える。
「私からもお願いします。メンター・ユウドを助けてあげてください」
わりこんできたスウが、両手をそろえて見本のようなおじぎをした。
「おう、ぜんぶウチにまかせとき。大船に乗ったつもりでおってや」
なれなれしくぼくの肩に手を回すと、ウインクしながら親指を立ててみせるキブ。
窓の外に目をやれば、すでに周囲は薄暗くなっている。やれやれ、足を棒にした根回しの一日が、ようやく終わりそうだ。
「とりあえず、今日は遅いからもう帰ったほうがいいよ。ぼくはこれからまだメンター・キブと話があるから」
眉が少し下がったのは、不満の現れかもしれない。刀をはいていないときのスウは、実に素直でわかりやすい。けれど、積極的に意義を申し立てようとしないのは、余計な詮索するべきではないとわきまえているからだろう。刀をはいているときとは大違いだ。
「わかりました。でも、遅くならないうちにもどってくださいね。マアナも待ってると思いますから」
廊下を遠ざかっていくスウの後ろ姿をあからさまな作り笑いで見送ると、キブは肩越しにまわした腕でぼくの首をぐいぐいと締めあげながら、部屋の片隅へとひっぱっていく。豊かな胸元に顔面を圧迫され、窒息寸前だ。
「苦しいったら。いっそ学科長会議の前に、楽にしてくれるつもりなら話は別だけど」
「なんやなんや、あの娘、この大事なときにもどってしまっとるで」
そのことか。ぼくは締められていた喉を押さえながら返事をする。
「しばらくは、荒事の必要がないからね」
「会議が終わるのを相手さんが待ってくれるとは思われへんけどな。うちの若いのに、いまからドミトリへ刃物さしいれさそか。実はな、こないだええアルマを見つけたんや」
どこの山師かって口調だ。学科長が眠り姫(爺?)なのをいいことに、どんどんガラが悪くなるな。
「スウにとって刀は、人格交代の強力な誘導因子にすぎないんだよ。刀を持ったまま入れかわったことだってあるしね」
「まあ、刃物を握ると人が変わるなんて、そもそもが冗談みたいな話やけどな」
思いつきを否定されたのが気にくわないのか、キブはふんと鼻をならす。
「アンタんとこのプロテジェやろ。なんぞ思い当たるフシがあるんちゃうか。ころころ理由もなしに変わったら困るがな」
理由、か。もちろん推論はある。精霊憑き、みたいな話も民間にはあるけれど、ぼくはその類の説明には懐疑的だ。理知に照らせば、人格の解離とは精神的な苦痛に対する解決を徹底的に無力化されたとき、その逃避として生じる一種の防衛反応だ。つまりスウの苦悩が、スウの理由というわけだ。そして、受け持ちのプロテジェに関するプロファイルは、担当のメンターへすべて開示されている。
でも、たとえ腐れ縁の、気安いキブとは言え、つまるところ推理ゲームの結論に過ぎない、個人の精神史に言及することははばかられた。ぼくはわざと、質問の本質をずらした返答をする。
「スウとはけっこう長いつきあいになるけど、一定の期間を観察すると偏りは平均化されて、二つの人格は等分に表象することがわかってる。どうも、二つの人格の間に主従は無いらしい。状況が特定の人格を必要としているときに、誘導因子が閾値を越えると交代が起こる、ってとこかな」
わからないふりで、クリティカルな事実からわざと半歩遠ざかる。研究者の態度としては最悪の部類だな、これは。
「さすが言語学科、ややこしい言い方でけむにまくのは学園一やな」
どうやらキブは、ぼくの韜晦には気がつかなかったようだ。
「特定の人格が必要なときって、なら本人はある程度、交代に自覚的ってことかいな」
「うーん、連続したひとつとして記憶が保持されているようなフシもあるけど、意識的に交代してるわけじゃないよ。でも、お互いの存在を薄々知ってはいると思う。いまは然るべき事態へ向けて、片方を温存しておく必要があると判断してのことじゃないかな」
キブがうなった。
「その話、なんかおかしないか。判断って、判断してるのは誰やねん」
「さあ? 実のところあんまりわかってないのさ。心の問題は専門外だからね」
ぼくは肩をすくめてみせた。
「言葉遊びは言語学科のおハコやさかいな。その点、史学科は考証第一や。厳密にできとるやろ」
「数秘学科には負けるけどね」
キブは露骨に顔をしかめた。
「なあ、こんな準備でだいじょうぶなんか? ぜったい平穏無事には終わらへんで。ほんまに勝算があってのことやろな? アンタの案も、学科長会議で潰されたらすべてしまいや」
「だから、こうしてお願いに回ってるんじゃないか。採決の結果ってのは、議場に入る前に勝ちとっておくものさ」
「アンタな、どうも最近、政治的になってきたんとちゃうか。政治的になるのは研究をあきらめた証拠やゆうで」
キブは皮肉っぽく口の端をゆがめると、ぼくの鼻先に指をつきつけてくる。
突如、その背後に陽炎のごとくゆらめいたのは――
「おまえら、またなんぞ、二人でよからぬ隠しごとしとるんちゃうやろな!」
「ぎゃあ!」
絶叫とともにキブがぼくに抱きついてきた。すごい圧迫感だ。苦しい。
陽炎の正体は、なんと史学科長だった。長い学究生活の果て、無機物と有機物の境界を喪失したスリーピング・オールド、クラウチング・シニアーが、いま午睡と午睡の間断の状態(恍惚?)に突入したのだ。怒りによるものか、はたまた老人性の何かによるものか、局所的な地震を疑わせるほど小刻みにプルプルと揺れ続けている。だいじょうぶか、この人。ここ十年くらいの間、ずっと死にそうだ。
「あわわ、いつごろから起きてはりましたんやわやろか」
先ほどまで見せていた学科の内実をほしいままにする専横ぶりはどこへやら、滝のごとく汗をふきだして、キブは生まれたての小鹿のようにガクガクと膝をふるわせている。
「ワシくらいになると、意識を覚醒させたまま眠るなんてのは、それこそ朝飯前の睡眠、昼飯後の午睡、おやすみ前の仮眠やな」
結局どこまでも寝るのかよ。そして一日二食かよ。睡眠学習としての効率はすごそうだ。
「だからな」
わずかにまぶたが持ちあがると、濡れ濡れとした黒目が爬虫類の鱗のように光を反射させた。
「おのれンとこのメンターが裏でどんな悪さしとるかも、すべてお見通しっちゅうわけや」
とたん、キブはへたへたと床に座りこんでしまう。
「わ、悪さやなんて、そんなん、ちがいます。ウチはぜんぶ、史学科の発展と学園の繁栄を思てのことで」
「アホちゃうか。それこそ言われんでもわかっとるわ。もし我が我がでいろいろ画策しとるゆうんやったら、ワシが黙って見逃すはずがあるかいな。ときどき調子にのりすぎるとこが、アンタの欠点やわな」
史学科長は、親がいたずらな子どもにするように、キブの頭を平手で軽くはたいた。
とたん目を潤ませ、鼻をすすりだすキブ。
「どないしたんや。そんな強くたたいてへんやろ」
「あの、安心したら、ちょっと漏れてしまいまして」
キブが頭をかきながら、顔を赤くする。
「なんや、ええ年して。ほれ、さっさと行っといで」
史学科長は露骨に顔をしかめ、犬にでもするようにしっしと手をふった。
二人のやりとりは、なんだかとても通いあった師弟という感じだ。自分とボスとの関係を思いだして、ぼくは少しうらやましくなる。
「ワシはその間にちょっと、この言語学科のメンターと話すことがあるさかいにな」
部屋から出るとき、キブは片目をつぶって合掌し(ごめんか、ご愁傷さまかのどっちかだ)、ぼくは完全なるアウェーに敵の首魁とふたり残されたのだった。まさかとって食う気ではないだろうが、史学科長が人を食べないという証拠はいまのところぼくの元へ集まっていない。
「さて――」
ふりかえったその両目は黒々としており、老木のうろにも似た深い空洞を思わせた。
そこから発される無形の圧力に、ぼくは思わず半歩下がりそうになる。だが、かろうじて踏みとどまった。
ぼくの言動は、今度の原案に対する信任の是非と直結しているのだ。会議の重要な構成員である学科長の前で、自信の無さを悟られてはならない。
「若いメンターの中には学科の違いが、話をややこしくすると思てるモンもいるみたいやな。けどな、それはとんだ的外れや。もともとの生まれも違う、何が好きかも違う、何がゆるせんかも違う、違って当然やないか。けどな、それを越えて、ワシらはひとつの大きな目的のために学園に集まっとんのや」
「おっしゃる意味がよくわかりません」
いつもの習い性が、ぼくをとぼけさせた。この人が、いったいぼくに何を求めているのかわからなかったからだ。
「まあ、無理にわかれとは言わんわ。けど、ワシらみたいに年をとってくると、もう他に行く場所なんかあらへん。学園を守りたいゆうても、なんや後ろ向きに聞こえてまうのは、しゃあないわな。ワシがアンタに聞きたいのはな、たったひとつだけや」
考えこむように、史学科長はしばらく目を閉じた。
「ペルガナ学園を愛してるか?」
予想もしなかった質問。そんなこと、これまで考えたこともなかった。
「わかりません」
なのに、すぐさま言葉が口をついた。何の意図も、かけひきもない返答だった。史学科長は引き出したかったのは、これか。ならば、ぼくは胸のうちを隠さずに話すべきだ。
「わかりませんが、恩義を感じています。ぼくはここに来て、初めて帰る場所を見つけました」
なま白い手を握り返した、赤銅色の力強さを思い出す。
「ぼくが学園を離れるとすれば、それはぼくが死ぬときか、学園がこの地上から消滅するときだけでしょう」
史学科長の顔に刻まれた皺が深まる。どうやら、笑っているらしい。ぼくはと言えば、自分の答えた内容に嘘が含まれていないことに、驚いていた。
「ワシもあと二十年はがんばるつもりやが、さすがに永遠に生きることはできへんからな」
皺枯れた手のひらが、そっとぼくの肩に置かれる。
「これだけは覚えといてくれ。メンター・ユウド、ワシはおまえの味方や」
それはひどく軽いと同時に、ひどく重かった。
重なりあった枝葉の隙間から月光がさして、風が吹くたびに違う陰影を見せる。大きくさしのばされた枝には、誰もいない。
木の根元には、膝を抱えたマアナがひとり座りこんでいた。表情は虚ろで、まるで抜けがらのような印象を受ける。ぼくはいま、少女にかける言葉を持っている。グラン・ラングだ。
――君が、”世界の中心”なのか。
マアナが顔を上げる。その表情はひどく大人びて、別人のように見えた。
――良かった。始まる前に伝えないのは、公正ではない。
――君は、マアナじゃないな?
少なくともいま、外見にみあう中身を伴ってはいないようだ。
――その返答は難しい。自我の定義から考えなくてはならない。だが、君たちがある魂を特定の時系列において同一のものと識別する精度で考えるなら、私はマアナではない。
マアナだったその少女は、微笑みのように頬の筋肉を痙攣させた。
――意思疎通の可能な相手を探していた。グラン・ラングの本質は、極めて精神的なものだ。最も親和性が高いと判断した個体が、この局面に至るまで著しく低い能力をしか示さなかったのは、誤算だった。
ぼくのことだな。悪かったな、グラン・ラングが下手なメンターで。
――君がマアナと名付けた部分は、名付けられたことで我々から分離された。名付けとは呪縛に他ならない。名付けにおいて峻別し、部分に峻別することで愛を可能にする。君たちにとって愛は有限であり、ゆえに個別的にならざるを得ない。それが君たちの限界でもある。
何を言っているのかさっぱりわからない。これはグラン・ラングの能力というより、ぼくが問答の抽象性を理解できていないのだ。なんか、より深く傷つくな。
――目的はいったい何だ。ぼくたちは争いを求めているわけではない。衝突を回避する方法はないのか。
確かに、これまでのぼくの能力は不充分だったかもしれない。でも、いまはこうやって話し合うことができる。言葉が通じるのなら、争いも回避できるはずじゃないか。
“それ”はしかし、ゆっくりと首を振った。
――一連の展開はすべてあらかじめ仕組まれた、いわば自動的なものだ。偶然はその見かけを装われている。流れを止めようと外的な介入を行うことは許される。しかし、流れが内的な自発性で止まることはない。
抽象的な受け答えでわざとはぐらかそうとしているのか。ぼくはいらいらと質問を重ねる。
――誰が仕組んだっていうんだ。
――わからない。
意外な返答。こいつが黒幕じゃないのか。
――推測するしかない。我々には認識できぬ、より高次の存在があるのかもしれない。君が最初グラン・ラングを表象としてしか理解できなかったように、この世界には我々もその表象をしか理解できていない何かがいる。だが少なくとも、我々の目的を伝えることはできる。君たちの手がかりとなればよいのだが。
――それは何だ。
――すべての意志は目的を持つ。君たちは存続であり、我々は死滅だ。君たちの咎は他者への愛を持つに至ったことだ。その意志の継続を妨げることが我々の目的である。そしてこれは、より大きな流れへの序章にすぎない。
ぼくはすっかり混乱していた。返答の唐突さもさることながら、愛を持つ者を滅ぼすというその考えが、全く理解できなかったからだ。
――誰かを愛して、何が悪いんだよ。
思わず、言っていた。我ながら、恥ずかしい質問だ。
――君たちは、愛と憎悪が相容れないと考える。君たちは、争いと平和が対極だと考える。しかし、それらは同一の苗床より萌芽するものだ。互いが互いとは切り離せない関係にある。だが、対立の見かけは存在しない解決を予期させ、君たちの苦悩と破壊を永続化するのだ。
――そんなこと、どうしようもないじゃないか!
ひどい言いがかりとしか思えず、ぼくは憤慨する。
“それ”は、哀れみのように顔をゆがませた。
――無理もない。己の在り方を肯定しなければ存続できない。しかし肯定はただ、己の本性を確認するに過ぎず、君たちの在り方が正統であるという証明にはつながらない。別の可能性は常に残されている。君たちが存続することが、より良い存在の発生を妨げているとしたら? 君たちが現在のあり方を放棄することで、より高い存在に合流できるとしたら?
ぼくはぼくが嫌いだ。だからきっと、どこかに破滅を求めるような性向があるのだろう。その言葉は、ある意味で心地よく響かないこともなかった。しかしそれは、破滅するのがぼくに限られた場合の話だ。ぼくは生きるべき多くの人たちを知っている。いま、その人々の代表として答えを求められているのだ。
さあ、毅然と胸をそらせ。
――哲学の問答としては興味深い。しかし、到底その歪な考えを受け入れることはできない。
――そうか。我々とて、公平を期すために知りうる情報を開示しているに過ぎない。決断は言葉ではなく、常に行動で示されるべきだ。
“それ”はなぜか、奇妙に得心した表情でうなずいた。
――君たちを取り巻く事象について、判断を下すのはやはり君たちだ。我々の移動は明後日の早朝を起点とすることに定めよう。なんとなれば、我々は一であるが、君たちは多であるからだ。存在に根ざす不安を利用するのは公平とは言えない。
もしかすると、会議のまとまらなさを揶揄されているのかもしれない。メンター・スリッドの険しい表情が一瞬、脳裏をよぎった。こいつらは、話しあう必要なんてないんだろうな。
――ハンデっていうわけか。案外、優しいんだな。
“それ”は静かに首をふる。
――圧殺が目的ではない。我々が求めるのは、公正の手へ委ねた審判だ。もう行かねば。知識はいずれにも平等に与えられねばならぬ。
まだだ。まだひとつ、答えを手に入れていない。
――最初の質問に返事をもらっていない。”世界の中心”とはマアナのことか。
――いかにも。この肉は二つの世界を橋渡しする門、すなわち黎明王女の発現。
答えになっているようで、さっぱりわからない。
――レイメイオウジョとは?
――その本質を描写することは、果実の甘みを言葉に乗せるが如き難事である。しかし、果実の表皮がいかなる表象を形作るかの説明は可能だ。黎明王女とは、ある生命圏が己の実存の枠組みを超え、世界の殻を破ろうとするとき出現する結節――あるいは試金石というべきか。もっとも我々はそれが忘れられた本来の目的を果たすのを見たことはないのだが。中絶は多く、親鳥により妨げられる孵化さえ少なくない。また、その実相は常に空である。空なればこそ、無限を湛えることができる。
“それ”はなぜか、そこで言い澱んだ。ぼくはと言えば、この哲学問答に頭痛がしてきたところだ。
――いや、人の身には無限、と伝える方が正確だろう。
“それ”は睫毛を伏せ、はじめて戸惑いらしきものを露にする。
――最後にひとつ忠告する。必要な手札はすべて与えられていると知れ。中心の消滅が意味するのは辺縁の拡散でしかない。中心を失えば、事態の収束は不可能になるだろう。ゆめ、忘れぬように。黎明王女たちは、我ら双方にとっての希望なのだから。
その言葉は、ぼくにとっての救いだった。ひとりの少女へ向けた個人的な執着が、市国の人々を破滅に導くのではないかと疑い続けてきたのだから。
これで学科長会議へ向けた準備の、最後のピースがはまった。
礼を言おうとして、気づく。
いつのまにか圧倒的な存在の感じは雨散霧消し、気がつけば目の前には小さな少女がいた。いつもならば、ぼくの姿を見れば何の躊躇もなくとびこんでくるにちがいない。けれど、いまは胸元に両手をひき寄せ、泣きそうな表情で辺りを見回している。
抱きしめてやろうと近づくと、おびえたように後ずさった。
不連続な記憶に心ゆさぶられ。
大きな安らぎから切り離され。
神は少女へと堕落し、個として存在することの不確かさへ投じられた。
逃げようとするマアナを後ろからつかまえる。予想していた大暴れはなく、ただ身を硬くすることで拒絶の意志を示した。まるで、いま物心のついた子どもみたいに。
耳元へ、そっとグラン・ラングでささやく。
――だいじょうぶ。学園ぜんぶが敵に回ったって、ぼくは君のそばにいる。
どれほどの孤独と不安が、彼女をさいなんでいるのか。言葉は何も約束しない。だが、言わずにはおれなかった。
朧な月明かりの下、ぼくの涙の最初の一滴が、少女のむきだしになった白い肩へと落ちた。マアナの瞳が潤み、やがて火のついたように泣きだす。お互いの涙がお互いの呼び水になり、それからぼくらは二人でおいおいと泣いた。
そのとき、言葉が必要ないほど通じあうという錯覚、あるいは欺瞞へ、ぼくは溺れた。示されたひとつの世界観――他者を伴わない世界が、どこか深いところでひどく己を魅了する事実から、目を背けるために。
MMGF!(7)
「人の営むあらゆる事象は法に照らされ、その成否を判断されなければならない。具体的な事例を見てから対症療法的にルールを変更すれば、すべての法に存在の理由はなくなる。事象が法に先んじて法を曲げるとするならば、我々は文明を放棄し、弱肉強食を是とする野獣の群れへと還ることになろう。今回のケースを想定したルールをあらかじめ学園の運営規則へ組み込んでおかなかったブラウン・ハットと歴代の執行部を問責する動議の採択を要請する。現在、学園が数万の流民の侵入を前に立ち往生しているそもそもの原因を作ったのは誰か、それをまず明らかにしていただきたい。我々メンターの協力を乞うとすれば、何より手順が逆ではないか」
スリッドの声には独特の張りがあり、一切の迷いがない。まるであらかじめ台詞を入れられた役者のようだ。しかしその応答は変幻自在で、すべて彼の内面からわきでていることがわかる。利害関係を度外視するならば、まったく大したヤツだ。
しかし、今回の学科長会議において、スリッドは打ち崩すべき最大の障壁なのだ。胃の辺りに重い塊を感じる。会議の前には確かにあったはずの確信が、みるみる拡散してゆくのがわかる。
本当に、だいじょうぶかな。誠に失礼ながら、『自分より頭の良い人間が間違っているときに、その過ちや狂気を果たして立証できるのか?』というあの命題が想起された。
ぼくは隣で腕組みをする体技科長をちらりとうかがう。反対側には、組んだ両手に顎を乗せた学園長が居並ぶメンターたちを静かに見つめている。
いつもとは違う席に座っていることは、なんだかひどく居心地の悪いものだ。ここにいるだけで、ぼくは何らかの意思を表明していることになる。スリッドが仮構する体制と反体制という区分けが、この位置からはまるで形を伴った実在として目に見えるようだ。
執行部へ向けられたスリッドの猛烈な詰問へ、しかし学園長は穏やかに切り返した。
「ご指摘の事項については汗顔の至り、すべてごもっともだと思います。しかし、明日にも市国の外壁を乗り越えかねない流民たちへの対処という最優先案件を脇において、過去へと責任の所在を遡及する時間が残されていないことも事実でしょう。その動議を論理的な帰結へ導くために必要な資料の準備も十分ではありません」
「時間がない、時間がない! 執行部たちがする、お決まりの戦術だ! 時間をなくさせたのは、いったい誰だと思っているんですか!」
おまえだよ、という無言の回答が沈黙を守る列席者から発せられるかのようだ。自分の不利はおくびにも出さないのが、この男の徹底したところである。少なくとも今回の件において、スリッドの提案が時間を空費させたことは否めない。だが、いったん投票による議決を経た以上、それは全員が負うべき責任なのだ。
「状況は逼迫し、一刻の猶予もならない。そんなことは執行部のお歴々にご説法いただくまでもなく、我々全員が大前提として理解している。私が問題としているのは、事態の緊急性に乗ずる形で学園運営の諸原則を反故にする提案をしておきながら、いっこうに悪びれないその態度だ。法を記す文言が人の言葉を超えぬ以上、法の解釈は過去の事例に大きく依拠してしまうことは指摘するまでもない。今日この場で悪しき前例を作ってしまうことが、子々孫々に至るまでの害悪とならないと誰に断言できようか」
「おい、ええかげんにせえよ。今日を生きのびてはじめて、明日のことを言えるんやろが」
たまりかねた、といった様子で史学科長が身を乗りだした。
スリッドは、小馬鹿にしたように鼻をならす。
「詭弁だ。心臓を取らぬ代わりに両腕を差しだせと迫る竜の逸話と何ら変わりがない」
「ものわかりの悪いやっちゃな。ワシは原理原則のために死ぬ気はないゆうとんのや。なんやったら、この議論を続けるかどうか、みんなに投票で決めてもらおやないか。運営規則にものっとったやり方やろ」
猛然と拳で卓を打ちつけ、スリッドが立ちあがる。
「学園と破滅を天秤にかけて、誠実なメンターたちへ決断を強要する! そうやって本来は存在しない亀裂を目に見える形で演出するのが、執行部のやり方なのか!」
「おっしゃることはよくわかりました」
穏やかに、しかしはっきりと学園長はスリッドをさえぎる。最高責任者の視線にうながされて、史学科長は背もたれへと身体を戻した。
「しかし、このままでは議論は平行線をたどるでしょう。まず、今回の件に関する我々の対応策をお伝えし、その後に改めて意見をいただければと考えます」
「あくまで提案の成否を判断するために、という点を外さないなら認めましょう」
意気を外されたスリッドの声音は、明らかにトーンダウンしていた。
「よろしい。では、メンター・ユウド、お願いします」
ぼくと目があうと、学園長は穏やかな表情でゆっくりとうなづいた。それは、たぶん信頼だった。ぼくにとっては、いつだって大きすぎる何かだ。
立ちあがりながら、かすかに膝頭が震えているのに気づいた。えい、情けないヤツめ。ぼくは無理にも自分をふるいたたせようとする。
「現在、学科長が不在のため、代行をおおせつかっています。以後の発言は私個人のものではなく、言語学科を代表しての中身であるとお考え下さい」
必要な口上ではあるが、責任回避的な言い訳に響かないこともない。スリッドの視線を痛いほどに感じる。ぼくが体現する何かを(あるいはぼくの裏切りを)、にらみつけているのだろう。
「ご存じのように、ペルガナ学園は膨大に広がる地下遺跡の一角として存在します。史学科の調査よれば、いくつかは市国の外まで通じているものもあるとのことです」
口の中が渇いて、声が裏返りそうになる。
「今夜中に、全市民を学園の敷地内へ待避させます。次に、流民の侵攻にあわせて、地下遺跡を通じた市外への誘導を開始します。その間、全学科の総力をあげて流民たちを学園へ釘付けにし、必要な時間をかせぎます」
ぼくはここでいったん言葉を切った。スリッドが猛然と挙手したからだ。
「二点。ひとつ、この提案は市国民の退避を主目的とした我々への殉職行為の強要なのか。ふたつ、流民たちが学園の占拠を目的とした攻撃を行うという主張に根拠はあるのか」
かかった。唇を唾で湿す。
動揺を見せるな。平静を装え。
「議長、本会議へあらたに二名を召喚することを求めます」
「それは、学科長会議の構成員以外、という意味ですか」
「はい」
スリッドが半身を乗りだすところへ、
「メンター・スリッドの疑義は、まず明らかにされるべき重要な部分と考えます。そのための要請です」
憮然とした表情ながら、スリッドは背もたれへと身をあずけた。
おそらく、議長にとっては予想外の要請だ。彼は助けを求めるように学園長を見た。
「よろしい、許可します」
ぼくは内心、ホッと胸をなでおろす。なんとかこれで、一つ目の関門をクリアしたというわけだ。
「では」
ぼくは戸口の席に控えていたキブに合図する。扉が開き、二人の少女が議場へと入ってくる。
緊張した面持ちのスウ。大勢の視線にさらされて脅えた様子のマアナ。少しの間だけ、我慢しておくれ。
「言語学科の研究対象であるグラン・ラングは、この世界を構成する基です。正確に用いれば、あらゆる事物へ物理的な干渉を行うことができると言われています」
「プロテジェ向けの、教本レベルの知識だ」
腕組みしたままスリッドは小声で不機嫌そうに、しかしぼくが聞きとるには充分な大きさでつぶやく。おそらくぼくを揺さぶるための発言だ。ほんと、いちいちアタマにくるな、この男は。
ぼくは聞こえないふりで、あらかじめ用意しておいた小石をポケットから取り出すと、手のひらへ乗せる。
「我々の言語からは、もはや物質への直接的な影響力は取り除かれています」
小さくグラン・ラングをつぶやく。たちまち小石はその形象を崩壊させ、細かな塵となって指の隙間からこぼれおちた。かすかに驚きの声があがる。
無理もない。グラン・ラングによる施術の実演は、その実現の不可能性から手品や大道芸とかわらぬ扱いを受けてきた。専門の研究者にとってさえ、事情はほとんど変わらない。すっぱいブドウってやつだ。
でも、いまやぼくにとって、この程度は施術とさえ呼べない児戯の類に過ぎない。ほんの数日前までには考えられなかったことだ。これさえも、仕組まれたことだっていうのか。
スリッドの厳しい表情が、ぼくを現実へと立ち返らせた。そうだ、いまはそれを考えるときじゃない。
ぼくは咳払いをし、言葉を続けた。
「しかし、物質へ影響を与えるからと言って、グラン・ラングの本質は言語の根本を疑うものではありません。その影響力は、ふたつの生命が意志を通わせようと思うとき、最大化されるのです」
嘘だ。いまぼくがでっちあげた。が、抽象度は高ければ高いほどいい。
ぼくとスウの視線が交錯する。スウはかすかにおとがいを上下させた。
圧倒的に。そう、何の疑義も残さないほど、圧倒的にやる必要がある。
いずれ避けられない決断ならば、己をだますに必要な幻想を与えよう。
グラン・ラングの低い詠唱は、青い輝きと波長を重ねつつ高まりゆく。
“魂の高揚”はかつてない高みへと達し、奔流となった輝きはいまにも器を乗り越え、決壊を迎えそうだ。
瞬間――
スウの姿が消滅する。列席者は一陣の風を感じたはずだ。
ざわめく皆の頭ごしに、ぼくはつとめてゆっくりと片手をあげ、議場の後方を指さした。
「人は人によってのみ練磨される。これは、かくあれかしという願望的な金言ではありません」
はたしてぼくの示した先には、スウが立っていた。刹那にも満たない時間を爆発的に高められた速度で移動しただけなのだが、列席するメンターたちにはその内実以上のものとして受け止められたはずだ。
「言語学科ではこれを“魂の高揚”と称しています。意志を持つ生命すべてに有効なことは確認済みです。さらに、しかるべき補助を得れば、効果の及ぶ範囲を拡大することもできる。こちらはまだ、あくまで理論上は、ですが――」
ぼくはわざと語尾を濁してみせた。
そして、これも嘘。効果は固体選択的なもの。険しい表情は変わらないが、スリッドから発言の気配は消えている。
「私の力では、学園の敷地を覆うぐらいがせいぜいでしょう。しかし、流民たちの持つ超人的な身体能力と我々のそれとの差を埋め、専守へ徹するには充分だと考えます」
過大な効果を謙遜しているように聞こえただろうか。
しかし、これもまた嘘。あらかじめ想定した作戦へ、皆の意識を誘導するための方便だ。
ぼくは、議場の入口に立つマアナを見た。そう、しかるべき補助を得れば、おそらく制約は絶無となるだろう。
剣術のような挙手。スリッドだ。
「お見せいただいたトリックの真偽について、学科の思想的独立を尊重する観点から考えて、私は論評する立場にはない。だが、いま行われたパフォーマンスを回答と仮定したとして、我々が充分な内容を得られたとは言いがたい。メンター・ユウドには、流民たちの目的が正に侵攻であることを立証いただきたい」
おや?
ぼくはこのときなぜか、スリッドはもしかして前回の会議における発言を悔やんでいるのかもしれないと感じた。
この男の出方は非常に攻撃的だし、ひとところに留めた論点を死守する。その態度は論理的なようでいて、会議において有効な結論を得ることが極めて少ないやり方だ。
ただ、己の存在感というか、面目を保つには有効である。
ならば、彼の発言によって会議が有意義な方向へ決定した、という形を作ってやりさえすればいいのではないか。
いずれにせよ、次の第二関門を突破する必要がある。マアナへ手招きすると、巣穴から飛びだして天敵の群れの中を走りぬける小動物のように、一直線にぼくの腹へと頭から飛びこんできた。
うーん、いい頭突きじゃないか。一瞬、食べたものが喉元へ逆流してくるが、すんでのところで飲みこんだ。あやうく、ここまでの演出が水の泡になるところだ。
スリッドの眉毛が吊りあがる。いつから議場は託児所の機能を兼ねるようになったのか。そんな台詞が実際に聞こえるようだ。
「この少女が、二人目の召喚者となります」
テーブルの下から両目だけをのぞかせる、小さなマアナを抱えあげる。多くのメンターたちから向けられるいぶかしげな視線と、一人のメンターの攻撃的な視線に脅えて、ぼくの首にしがみついてくる。ごめんよ、少しだけ我慢しておくれ。
 「彼女は見かけこそ人の形をしていますが、その魂の有り様は我々とは遠いものです。ですから、厳密を求めるならば、“これ”はおそらく、古代人が残したレガシーの一種であると推測できます」
「彼女は見かけこそ人の形をしていますが、その魂の有り様は我々とは遠いものです。ですから、厳密を求めるならば、“これ”はおそらく、古代人が残したレガシーの一種であると推測できます」
胸に刺すような痛みが走った。いまの発言に嘘が含まれていない事実に、ショックを受けているのだ。マアナがぼくたちの言葉を理解できなくてよかった。もしそうでなければ、きっと自分を許せなくなってしまうだろう。
声がかすれそうになり、咳払いをする。
「先日、史学科の調査へ同道した際、郊外の遺跡において接収しました。過去に報告の例を思い出せないほど巨大なローズクォーツの内側に納められていたのです」
体技科長が史学科長へ視線を走らせ、かすかに首を振った史学科長がキブへその視線を送り、キブは半眼で床を見つめながら向けられた無言の問いかけに気づかないふりをした。学園長だけが両手に顎を乗せたまま、微動だにしない。
「先日と言われたが、正確には何日前のことか」
スリッドが腕組みをしたまま詰問する。議長は発言に挙手を求めろよな。もはや議場はふたりのショウダウンの様相を呈している。
「そうですね」
ぼくは親指と人差し指で顎をつまんで、しばし考えるふりをする。即答を避けたのには理由がある。先ほどの発言に仕組まれたトラップを踏ませるためだ。
「二週間ほど前になるでしょうか」
スリッドが勝ち誇った笑みを浮かべる。周囲のメンターたちへ同意を求めるように、芝居がかった仕草で両手を広げた。
「まず、その女児がレガシーであるとの仮定を受け入れよう。この場では立証の余地はないが、最も公正を求められる学科長会議において後に虚偽と判明するかもしれない発言を、いやしくも学科長を代理する人間が行うはずはないからだ。しかし、私とて状況の切迫は理解する。諸賢の抱くこの疑念をあえて看過することで、議論を先へと進めよう」
まったく、もったいぶった言い方だ。スウや体技科長は、さぞかし気をもんでいるに違いない。
しかし、流民たちがこれからどう動くかを知っているぼくは、あえて神妙にスリッドの発言へ聞き入るそぶりをみせた。
「私の記憶が間違っていなければ、この二週間で臨時のものを含めて四度の学科長会議が開かれたはずだ。メンター・ユウドの言葉を借りるならば、過去に報告の例を思い出せないほどの大発見をご存知の方がこの中におられるだろうか」
芝居がかった大仰さで、列席のメンターたちに訴えかける。
「情報秘匿は、調査研究に従事する者の基本義務に違反する。この学園が真に闊達な学際的発展を維持するために、言語学科と史学科の共謀による今回の隠蔽は決して看過できるものではない。もし何か弁解があるならば、お聞きしよう」
よくもまあ、これだけ巨大な問題を作りあげることができるものだ。ぼくはあきれ半分、感心半分でスリッドを見る。けれど爛々と輝く両目は真剣そのもので、どうやら冗談ごとを言っているのではないらしい。
気がつくと議場は痛いような沈黙に包まれており、メンターたちの視線はすべてぼくの上に注がれていた。やれやれ。
「議長」
「は。何でしょうか」
議長が議長であることを思い出し、間抜けな声を出す。
「発言の許可を」
「あなたの発言を待っています」
議長は議長の職務について忘れてしまったようだ。ったく、もう。
ぼくは議場の入口を指差した。キブが澄ました顔で挙手している。
「メンター・スリッド、メンター・キブの発言を許可しますか」
おいおい、何だよそれ。議長は、学科長会議の運営原則についても忘れてしまったようだ。
議長の不規則発言へ、スリッドが苦々しげに答える。
「その質問は私が何か、煽動をでも行っているとの誤解を与えかねない。議長は円滑な議事進行のみを旨とした、中立な発言を心がけていただきたい。無論、学科長会議ではその地位の如何に関わらず、何人も発言を妨げられることはない」
ぼくは周囲にさとられないよう、キブと一瞬だけ視線を交わした。頼んだよ。
「史学科への誹謗につながりかねない事実誤認を訂正さしあげたく」
キブのすました顔と、よそおった言葉。本気で怒っている証拠だ。
「誹謗という言葉の意味をはきちがえては――」
「第三百四十五次ペルガナ史跡発掘中間報告書」
さえぎるように、手元の資料を読みあげる。
「ちょうど二週間前の学科長会議において、メンター・スリッドの疑義によって中断を余儀なくされた報告書です。添付された目録には、発掘品の詳細が記されていました。一部を読み上げます。『分類、人型土偶。三十二號遺跡内奥、天辺付近薔薇水晶依リ接収。表皮極メテ精巧也。生命、或ハ其ノ擬似反応有リ。他学科ノ検証ヲ要ス』」
スリッドがはじめて、しまったという表情を見せる。
「まさか、このペルガナ市国の学府に籍を置く者が、この資料に書かれた文字を読めないなどと、疑う気持ちもありませんでした」
事前の打ちあわせ内容を大きく逸脱した嫌味たっぷりの口調で、キブは発言をしめくくった。まさに己の発言が学科間の交流を妨げる結果を招いたのだから、それこそ自分の言葉に逆襲された形だ。さすがのスリッドも、これには黙りこむしかなかった。
「今度からは人の話をよく聞くこっちゃな」
史学科長が追いうちをかける。おいおい、あんまり調子にのって追いつめないでくれよ。口げんかに勝つことが目的じゃないんだ。
「この少女の発見と流民たちの出現は符号します。事実として指摘できるのは二点です。どちらも我々とは異なった魂の有り様をしているということ。そして、この両者は私たちの言葉を解さないが、グラン・ラングによる意志の疎通は可能だということ」
正確には、流民たちの一人ひとりが使うグラン・ラングは、相当度にクレオール化しているように見受けられた。さらに、魂の有り様で言うならば、マアナよりも流民たちの方がぼくたちによっぽど近い。
しかし、この場で欲しい結論はひとつだけだ。余計な情報でメンターたちの判断を混乱させる必要はない。
「久しく絶えていた言語を母語とする者たちが、わずかの時期をたがえて学園へ現れたのです。そのふたつが互いに全く関係のない、偶発的な事象だということが考えられるでしょうか」
「偶然だ」
スリッドが即答する。あれくらいじゃ、懲りないってわけか。
だが、予想通りでもある。さあ、論理的には最も正しい帰結を、君の口から聞かせてくれ。
「私はそう考える。しかし、互いに立証できないという意味では、同じことだ。そこで私から提案したい」
ぼくはマアナを抱きあげた。
青ざめて泣きそうなその顔が、会議室の誰からもよく見えるように。
「人型土偶を流民たちへ引き渡す。もしメンター・ユウドの推論が正しければ、我々は戦闘を回避できるやもしれない。もし私が正しかったとして、何ら状況は悪化しない。現状で可能な、最善の一手ではないか」
メンターたちがざわめく。無理もない。この人型土偶は、あまりにも人の子どもに似すぎている。
本来ならば、ぼくの口から発せられるべき内容だ。でも、ぼくは逃げた。この提案にたどりつくだろうとわかって、スリッドを利用した。ぼくは卑怯者だ。
だが、この選択は提示されなければならない。すべての疑心を廃して全員が結束できなければ、今回の要撃作戦はおぼつかなくなる。
けれど、何よりも――
ペルガナ学園が真に守るべき価値のある場所であることを証明したかったのだ。ただぼくの、個人的なわがままのために。
「えー、議決を伴う審議事項として考えてよろしいのでしょうか」
会議室のざわめきを収束できないまま、議長が誰へともなく問いかける。
「待ちなさい」
静かに瞑目するふうだった学園長が、ゆっくりと顔を上げる。
「ここにいる人々の良識を疑うわけではありません。しかし、人命の与奪を投票の具にすることは決して許されない」
「その通りや」
学園長の言葉に、史学科長が深くうなづいた。
「我がが助かるためにプロテジェを犠牲にはでけへん。なあ、もっぺんみんなで確認しようやないか。ワシらはいったい、何のためにペルガナ学園へ職を奉じたんや。プロテジェたちへ未来を預けるためやったんとちゃうんか。研究へ邁進するのさえ、よりええものを預けるのを願ってこそやろうが」
スリッドが鼻で笑う。
「お得意のやり方だ。情に訴えて議題の焦点を曖昧にする。これは教育論ではない。ペルガナ市国数万の同胞と異邦人の子、どちらを我々が取るべきかという話だ。議長、採決を!」
「聞いていなかったのですか」
ぼくは声音にふくまれた何かにうたれ、学園長を見た。その身体から、気炎のようなものが大きく吹きあがるのを、確かに感じた。
「我々は、ひとりの子どもを見捨てない」
その鋭い眼光が居並ぶメンターの未熟さ、日和見、優柔不断を威厳で射抜く。
「異議は認めません。これは、学園長としての決裁です」
スリッドはほんの一瞬だけ、ひるんだ表情を見せた。でも、これですべてを撤回できるくらいなら、最初から妥当な譲歩へと流れていたはずだ。
「学園長は我々非力なるメンターから、声までも奪うおつもりか!」
スリッドの気性は権威による圧殺へ最も強く反応する。なんとか懐柔できるなんて、傲慢な思い上がりだった。理解していることと、実践することは天と地ほども違うのだ。所詮、ぼくくらいでは彼のプライドに落としどころを作ってやるなんてマネが、できるはずもなかった。
会議の前に準備したことは、これですべて出し尽くした。もう手がない。
「諸君、見ただろう! 我々の抱いてきた長い懸念が、学園というシステムの不備が、今日ここに顕在化してしまった! 瑣末の議事に判断を留保し続けた最高権力者が、学園の存亡をかけたこの重大な局面において、その意味もわからぬまま抜いてはならぬ宝刀を抜いてしまったのだ! いまこそこの暴虐に対して、我々は結束するべきではないか! おのが生命の帰結を、一個の独裁的な権力へほしいままにさせるわけにはいかないッ!」
「おい、学園長の決裁だぜ。正しい手順じゃねえか」
腕組みをしたまま、体技科長が低くつぶやく。抑制されてはいるが、気の弱い者なら聞いただけで身ぶるいするような圧力がふくまれている。
「馬鹿な! たった一人でする決裁が、万の人間の破滅を天秤にしてなじむと思うのか!」
体技科長が沈黙を守っていたのは、学科間の対立という構図をスリッドが持ち出すことを嫌ったためだろう。そうなれば、冷静な話しあいは不可能になる。
「さあ、ユウド。作戦の詳細に進め。準備も考えりゃ、もう時間は残ってねえ」
そして口を開いた上は、どちらかが退く以外の結論はない。
「場所をわきまえてもらおうか! 一介の学科長が最高意志決定機関の議事を無視していいとでも――」
「いい加減、黙らねえかッ! ユウドが話せねえだろうがよッ!」
獅子の吼えるがごとき大喝。会議室の空気がビリビリと震え、ほとんど物理的な影響を伴った圧が、列席者をのけぞらせる。
体技科長は腕組みを解くと、その場にいるメンターたち全員をねめまわした。
「生きるか死ぬかってときに、言葉遊びはやめにしようぜ。俺ァ、コイツを全面的に信頼してる。もしこの作戦に乗る気がないなら、いますぐここから出ていってくれ。誰も残らなくとも、ユウドと俺と、体技科の連中でやる」
実際のところ、ぼくはこの会議に末席を置くただの下っ端にすぎない。人望どころか、ぼくを知らないメンターのほうが多いはずだ。
だが、体技科長の言葉が醸成した空気は、またたく間に会議の構成員すべてへと伝播してゆく。冷ややかに議場を支配していた、明らかな不信と懐疑が塗りかえられてゆく。
皆、知っているのだ。この体技科長がいつだって、いちばん辛い局面で、いちばん辛い役割を率先して担ってきたことを。誰に誇るでもない、彼はただ黙って苦難の先頭に立ち続け、皆に背中を見せてきたのだ。
その信任は、何よりも重い。
機甲学科のメンターがひとり、立ちあがった。もしかすると、備品を壊したことをまだ恨みに思っているのかもしれない。肝が冷えた。
「機甲学科のムングだ。微力ながら、今回の作戦に協力させてもらう」
そして、またひとり。数秘学科の所属だ。まさか、スリッドへ加勢するつもりか。
神経そうに眼鏡のつるへ指をかけながら、言った。
「数秘学科、スカアル。メンター・スリッドとは見解を相違する」
その二人が呼び水となり、メンターたちは雪崩をうつがごとく賛意を表明して、次々に立ち上がる。
気がつけば、列席者のほぼ全員が起立していた。
蒼白になったスリッドは、荒々しく席を蹴って議場を去る。彼の性格を考えれば、他の選択肢はない。
ぼくは痛ましい思いでその背中を見送った。スリッドの存在なくしては、ほとんど満場一致のようなこの状況は得られなかっただろう。
「どうやら、結論は出たようやな」
「メンター・ユウド、それでは続きを」
史学科長がうなづき、学園長が穏やかにうながす。
皆がぼくへ向ける視線の熱量が、明らかに増しているのがわかった。
そこで、ぼくはハッと気づく。もしかして? もし、執行部がこの顛末をすべて計算していたのだとしたら――
学園の命運を、ずっとひとりで抱えこんでいたような気でいたぼくは、一種の熱い気持ちに満たされながら、しわがれた彼らの顔をあらためて眺めた。
「どうした? みんな、おめえの言葉を待ってるぜ」
親爺たちめ、大したタマだ。
ぼくは震える両手を悟られないよう卓上へ置くと、会議室の全員と順に目線を交わす。
視界の端で、スウがはげますようにゆっくりとうなづくのが見えた。
「それでは、今回の作戦の概要について説明します」
MMGF!(8)
無為を教育と称し、停滞を伝統とうそぶき、日々の研究は車輪を再発見し続ける。
過去から消費することで、少なくとも己の数十年を終えるまでは、微温的な日常を永続させたいと願う。
膨大な過去が尽きるのを予見したとして、己の現在と重なる可能性がないならば、あえてそれを指摘することはない。
結局、若いぼくが批判していたのは、我が身の未熟さから発した目に見える達成を求めてのもがきと、岩が岩のように練磨されていく様子とのギャップにこそあったのだと気づく。
学園の結論は、ぼくを失望させなかった。
ならばいまこそ、ぼくが学園を失望させてはならない。
「それでは、グラン・ラングによる大規模エンチャントの連動テストを開始します」
グラン・ラングで音素を風にはらませ、体技科メンターを中心に編成した各部隊へ指示を送る。受けとることは誰にでもできるけど、発信にはグラン・ラングが必要だ。
言語学科の総勢は二十名を超えるが、グラン・ラングの運用に関して言えば実働できる人数は限られてくる。双方向の密な通信が不可欠な体技科長とスウ・プロテジェの部隊、さらにいくつかの防衛拠点を選び、同僚のメンターたちを配当した。
「それぞれの隊のリーダーは、作戦図通りの配置にあることを確認してください。用いる施術の性質上、二度の試行は不可能です」
まあ、本当のところ性質上というより、ぼくのいまの能力ではなんだけど。
指示を出す者として、不正直さに寛容であれるほど年をとっていることは、この際メリットと考えよう。
長方形に切り取られた空の下で、風にゆれる大樹が短い影を投げている。
かつて学園の中心であった中庭を、ぼくは大本営として選択した。
もちろん、防衛のしやすさや指揮をとる上での利便性を加味するならば、ベターな場所は他にいくらでもある。だが、頭で考えた論理的な筋道や保険というヤツをぼくはすべて放り投げた。
古代人たちが要地として選び、遺跡の少女のお気に入りで、グラン・ラングを話す知性体との交渉が行われたここには、何か特別な意味合いがあるに違いないと感じたからだ。
つい数日前までならば、誰かのこんな言い草はオカルトだと一笑に付しただろう。けれどいま、ぼくは己の直感に迷いなく従うことができる。
見渡す四方の壁面は、巨大な白布で覆われていた。保健部がありったけのシーツを供出し、夜を徹して突貫で縫いあげたものだ。
シーツの白と空の青が交錯するあたりに見える人影が、準備完了の合図に頭上で大きな丸を作る。すると、ぼんやりとした像が白布の表面へ浮かび始めた。
彼らの視線の先にある学園周辺の景色が、レンズ状に形成した大気を経由し投射されているのだ。この方法では東が西に、北が南に投影されることになるため、視界の反転をあらかじめ考慮しておく必要がある。
中庭にいる同僚のうち、特別に小柄な(なんと、ぼくよりも小さい)ひとりがグラン・ラングをつぶやいた。美しい発音だ。
それに呼応して、映された像の輪郭はくっきりと鮮明さを増した。
ぼくは内心、くちぶえを吹く。見事なもんだ。
おそらくぼくのキャパシティでは、ことが始まれば全員の付与にかかりきりになってしまう。大本営の機能維持は必然的に、だれかに丸投げってことになる。もっともグラン・ラングの運用能力には個人差がありすぎるため、適性のある数名以外は補助という形にならざるを得ない。
「さて、こちらの準備は整ったかな?」
いかめしいローブに身を包んだ言語学科の面々に声をかける。彼らこそが適性のある精鋭というわけだ。与えられた仕事の重大さを自覚しているのだろう、いずれも緊張した面持ちである。
皆より頭ふたつほども背の低いメンターが、やや感情の起伏に欠いた声音で返事をする。
「問題ありません」
無機質な返答は、しかしぼくを失望させはしない。今回の作戦を彼女抜きにして完遂することはできないだろう。
言語学科の若き俊英、メンター・リンだ。飛び級に飛び級を重ね、つい最近メンターとして学園へ赴任したばかりである。少女のようなその外見は、ほとんどプロテジェとみまがうほど。見た目だけではなく、実際のところ相当に若いのだと思う。
プロファイルによればペルガナ学園の出身で、だとすればぼくもプロテジェ時代に受け持ったことはあるはずだが、印象は全く残っていない。良く言えば物静かでおとなしく、悪く言えば表情に乏しくて活気に欠けていたせいかもしれない。
少々理論に走りすぎるきらいはあるが、メンター・リンの安定感は抜群だ。
他の同僚たちには伏せてあるが(いらぬ嫉妬を招かないためだ)、彼女には大規模エンチャントの要である増幅と維持を任せている。
今回の施術の中身は、防衛に携わる数千の魂をまとめて“高揚”させるというものだ。取り扱うエネルギーの総量はどれだけ少なく見積もっても、膨大にならざるを得ない。
まともに受ければ、泳げない者が大波にまかれて水面を失うような体験となるだろう。その恐怖にうち勝てなければ、付与の内実は大幅に減衰してしまう。
付与のグラン・ラングを行使するには、どこまで自我を薄めて世界と合一できるかという点が最重要である。ぼくにとっては年齢的な諸先輩をさしおいてこの役目を与えたのは、彼女が己を無にすることができるからだ。
もちろん、本当にリンの本質がぼくの見立て通りである証拠なんかない。中庭を大本営に選んだのと同じ、ぼくの直感だ。
いずれも結果のみが正しさを証明する、大バクチである。
「さあ、配置についてくれ。学園のみんながお待ちかねだ」
ぼくはぼくに可能な限りの快活さで同僚たちへ檄をとばす。
「頼んだよ」
他のメンターに悟られないよう、ぼくはリンの肩をポンとたたく。そして、その感触にどきりとする。ローブの下には、何も身につけていない。
『付与行為ヲ行ウニハ極力、夾雑物ヲ除クベシ』という教本(ぼくが書いた)に忠実であるためだろう。『但シ、規模ニ比例シテ誤差ノ範囲ニ落着スル』という附則は目に入らなかったのかな。まじめなのか、天然なのか。
連動テストという呼称にかかわらず、これはただの予行ではない。過去に前例の無いこの壮大な机上の空論は、ただ成功だけをもって皆の信任を得る。
一度の失敗でさえぼくの、ひいては作戦そのものへの不信につながり、すべてを根底から瓦解させるだろう。
ふりかえれば、他に居場所はないとでも言いたげに、大樹の根本へ固く身を預けるマアナの姿があった。
――君の助けが必要だ。
ゆっくりと歩み寄り、声をかける。
見上げる表情には、ほんの数日前までには見られなかったある種の屈託が含まれていた。
――ぼくを、君の来たところへ連れていってくれ。
マアナは薄く微笑んだ。陰のある微笑みだった。
世界を知るほどに失われてしまう何か。あるいは、成長という名前の呪いか。
ぼくはある種の悲しみに包まれながら、手をさしのべる。指をからめるようにしてぼくの手を取ると、そのまま全身をあずけてきた。
マアナを抱き上げると、各隊へ最後の指示を送る。
「変化の指標を各自で設定してください。鳥でも、雲でも、風でも、動くものなら何でもかまいません。今回のエンチャントは、主に身体能力の向上を企図するものです。付与が完了すれば、相対的な速度の減退を体感できるはずです」
ぼくは大きく息を吸い込んだ。
さあ、覚悟を決めよう。失敗も成功も、すべてはこの身にかかっている。
マアナがぼくの首筋へそっと唇をあてがう。
無限へと誘うもの。それは、少女のくちづけ。
官能的な柔らかさの後に、魂の輪郭を溶かすぬくもりが訪れた。
視界がゆらぐ。あのときと同じだ。
眼前の景色と重なるように楕円形の輝きが生まれ、その明滅とともにぼくの意識は別世界へと接続する。
橋渡しされた場所を満たす媒質が、ぼくの自我へと流入する。水に溺れるような感覚の中で、自と他の境界は次第に不分明になってゆく。
やがて自我と媒質が置き換わり、ぼくは別世界へと逆流した。
それは、無辺大の広がりを持つ上下のない空間。
それは、天と地をひとつにして満たされる虚空。
是即ち無限の端緒であり、永遠の住処。
圧倒的な感覚と恐怖が、ぼくを浸してゆく。
まるで木の葉が竜巻に抵抗できないように。
根こそぎ奪われそうになる意識を自問でつなぎとめる。
おまえは、いったい何を恐れているんだ。
喪失が怖い。この小さな己を失うことが恐ろしい。
――これが君を殺すことはない。
どこかから声を聞いたように思った。
両手を広げ、全身を脱力する。
絶望感。ぼくにとって諦念と信頼はなんと近い位置にあるのだろう。
たちまち意識は吹きとばされ、永劫の彼方へと巻きあげられてゆく。
ああ――
これをなんと表現しよう。ひとつの時間軸にひとつの意識をしか持てない我々では、決して完全には理解しえない何か。
そのときぼくは、過去から未来に至るすべての時間軸に偏在しており、まるで昆虫の複眼を思わせる意識で“そこ”を睥睨していた。
暗闇さえ暖かに思える、完全な真空。
その虚無の只中に巨大な光の球が浮かび、唯一の実在として輝いている。あらゆる色彩をした魂が お互いに矛盾しないまま同時に存在し、球体の表面に明滅する幾何学模様を形成している。
めくるめく荘厳なる俯瞰。
瞬間は永遠の中に。
有限は無限の中に。
全ての概念が対立を喪失して渾然たる一つへ。
この身を包む、全体へと回帰する至上の安逸。
――ああ、マアナ!
いまこそ少女の苦しみの正体を知り、ぼくは嗚咽する。
そこへ、あの声が追い打ちをかけた。
――黎明王女は受肉し、この至上の安らぎから追放された。君たちが見ているのは影法師に過ぎぬ。喪失の悲しみは過去への憧憬となり、憧憬は門となって過去へ回帰する。私たちと君たちは同じところから汲んでいるのだ。
聞いてはいけない。耳をふさごうとするが、肉を喪失し一個の概念と化した身にそれはかなうはずもなかった。
――偏狭な自我を越えよ。グラン・ラングは、我々より高次の意識が実在することを証明しているではないか。死をここへ捧げよ。君たちが消滅に恐怖するのは、輪廻の一部が不可視であるに過ぎないからだ。
問い。実体を伴った、貫くような問い。
問い。異世界から投げられた、正解を持たない問い。
我が身を制約する、鈍重なる肉体。
我が意志を制約する不自由な言葉。
愛情は争いの火種となり、受け継がれていくのは連鎖する憎悪。
最も崇高な理念さえ刃の前には膝を屈して血だまりを作るのみ。
だが――
だが、世界に希望が無いと誰が言っただろう?
だが、世界に理解が無いと誰が言っただろう?
ならば我々は――
法悦とは遠い愛憎を選ぼうではないか。
開悟とは遠い転迷を選ぼうではないか。
――やれやれ、これでも受け入れないとは驚きだな。
失笑を聞いたように思った。
――本当に、強情だ。特に君は。
再び視界がゆらぐ。
与えられた全能感とその急激な喪失。
たちまち智慧の明るさは暗くなり、言葉は不自由となり、実存は肉をまとい鈍重となった。
気がつけば、ぼくは何事もなかったかのように中庭にいた。ほとんど時間は経過していないようだった。
どこも損なわれていないにも関わらず、ぼくはぼくの一部が永遠にあの場所へ置かれたことを知る。
いや、違う。ずっと置かれていたことに、気づいていなかっただけだ。
知ることによって失われる無垢。ぼくはマアナを抱く腕へわずかに力を込める。
すでに選択は成されたのだ。選ばなかったものへ心を残してはならない。
さあ、心を研ぎ澄ませ。
人間存在を肯定する、この世界の根幹を感じるんだ。
空わたる風のように。
たなびく雲のように。
グラン・ラングの音素がいくつも重ねられ、やがてそれらはひとつの音曲へと変じてゆく。
その抑揚にあわせ、凪いだ水面を揺り戻す波のように、次第にテンションが高まってゆく。
そして、永遠の彼方から訪れた無形の力が、ぼくを出口として吹き上がる。
莫大なエネルギーの中心にいながら、ぼくは驚くほどに平静だった。
人差し指を立てると、グラン・ラングをつぶやきながら、指揮者のようにふった。
――流れろ。
行き先を見つけた無形の力は、怒涛の奔流となって同僚たちへとふりそそいだ。
エネルギーの量が想定を越えていたのだろう、いずれも決死の表情で付与の伝播を試みている。
ぼくは心の中でそっと呼びかける。
怖がるな、怖がるな。これは君たちを傷つけない。
もちろん、エネルギーの分配は公平ではない。各人のキャパシティには限界があるからだ。
メンター・リンは涼やかにさえ見える様子で(無表情なだけか)、伝播のみならず増幅までを同時にこなしている。どうもまだ余裕がありそうだ。大した後輩じゃないか。
突風の如き瞬間はたちまちに去り、世界が死に絶えたかのような静寂が訪れた。
青白い顔をした同僚たちが、肩で息をしながらこちらを見る。だが、その不安げな様子とは裏腹に、確信のみがぼくを包んでいた。
やがて――
白布に映された群像がさざ波のようにゆらめき、少し遅れて四方から歓声が聞こえた。ぼくは己の確信が現実に裏付けられたことを知った。
ふと、首筋に冷たいものを感じる。見れば、マアナが涙を流していた。
喪失の追体験。いまや、彼女の気持ちは痛いほどにわかった。
――ごめんよ。
ぼくが耳元でささやくと、マアナはぐずるように首をふった。
「記録されるべき施術です」
顔をあげると、わずかに頬を紅潮させたリンがすぐ眼の前にいた。冷たい手のひらがぼくの頬に触れる。はだけたローブから白い二の腕と腋が露に見えた。
「涙」
どうやら泣いていたのはマアナだけではなかったらしい。
「涙腺の筋肉まで老化しはじめたかな」
あわてて目元をぬぐいながら、軽口にごまかそうとする。
しかし、聡明な瞳はぼくの韜晦を越えて、さらに深くをのぞきこむかのように澄んでいる。
「私は、メンター・ユウドの選択を支持します」
言葉の真意を問う暇もあらばこそ、ぼくの戸惑いは体技科長の胴間声によって破られた。
「おい、ユウド。連動テストとやらは成功だろ。さっさと次の指示を寄越しな。どいつもこいつも興奮しちまって、このまま攻めこみそうな勢いだぜ」
学園長と執行部は、十四歳以下のプロテジェをすべて避難させる決定を下した。
「学園のいまを守るのは、子どもの仕事やないからな」
史学科長の言葉に賛同する。それは、ぼくたち大人が果たすべき責任だ。
巨大な太陽が地平の彼方へと沈んでゆく。大地の輪郭がわずか盛りあがって見えるのは、流民たちが市国へと距離を縮めつつあるせいか。
陽光は空に版図を失い、月光が薄青く天球を塗りかえしつつある。侵攻は明朝に迫っていた。
ぼくはといえば、すべての隊とすべての拠点を己の目でおさめておくために、学園の外壁に沿って散歩をしているところだ。しかし、これを散歩だと考えているのは、どうやらぼくひとりだけだったらしい。
それを証拠に、背後には剣呑な空気を発散する人影がふたつ。
この状況に至るのに、話は少しだけさかのぼる。
「もう少し、置かれた立場を自覚して欲しいものだな」
厳しい声音に思わず首をすくめる。
研究室を抜けだしたところで、スウが待ちかまえていた。
「言語学科のいちメンターとしての、かな?」
「学園の命運を両肩に背負った、重要人物としてのだ」
ぼくの軽口へ、スウが即座に切り返しをする。その表情を見て、反省した。もしかすると、戸口にひかえていたのは、怪人の襲来からぼくを守るためだったのか。
マアナをはじめとして、多くの他力によって支えられているとはいいながら、客観的に考えてぼく抜きにこの作戦は成立しない。ぼくがいなければ、防衛は不可能ではないにせよ、多くの血を見ることになるだろう。
自分にしかできない仕事を人質にして、他人とその感情をふりまわすのは卑劣なやり方だ。さっきの軽口には、意図こそしなかったにせよ、そういう要素が含まれていた。
つくづく、ぼくはダメなヤツだ。
「ごめん、軽率だった。防衛の要所をじっさいに目で見ておきたかったんだ。もしよければ、いっしょについてきてくれないか」
「まったく、最初からそう言えばいいんだ」
スウがわずかに微笑んだ。
そこへ、聞きなじんだ胴間声が言葉をかぶせてくる。
「ようよう若殿が職責を自覚したようなのは、じつに喜ばしいことだぜ」
ぬっと姿を現したのは、やはり体技科長だ。
「おいら、視察を進言に来たのさ。紙や人づてなんてのはダメだ。てめえの目で見たことだけが、最後に信じられる。けどよ、余計なお世話だったみてえだな」
嬉しそうに破顔一笑する。
「でもよ、敵さんの鼻先をかすめてくんだ。もうひとりくらい護衛が必要だろ? な?」
屋上屋を架すとはこのことだ。質問の形をとっているけど、どうもぼくに否を言う権利があるわけじゃなさそうだ。
「この二人がついてりゃ、敵陣の真ン中へでも突入できるぜ」
「逆に、この二人で守れなければ、誰がついても同じことだ」
スウと体技科長が、不敵な表情で互いに視線を交わす。
性別も年齢も体格も、ぜんぶ違うけれど、二人は根っこのところですごく近いのではないかという気がしてきた。
そんなわけで――
今夜の散歩は、戦術構築と士気高揚のための視察と変じたのである。
ぼくより上背のある、ぼくより強い二人を背後につきしたがえてねり歩くのは、なんだかすごく思春期的な匂いがするなあ。虎の威を借るなんとやら、すごくおもはゆい。
しかし、予想に反して、行く先々での関心や歓声は達人たちではなく、ぼくに向けられたのだった。他学科のプロテジェに握手を求められるのには、閉口した。
ここ一両日での現実が、ぼくの認識よりもはるかに速く動いているということだろう。
虚像にはちがいない。しかし、ぼくが皆に求めたのも、この虚像なのだ。生身の実体が、多数の他人から命を預けるほどの信頼を得るには、大がかりなハッタリが不可欠だ。
連動テストは、ぼくの意図通りに、見事その役割を果たしてくれたというわけだ。
「おい。ちったァ、愛想のいい顔をしろや」
「いつもの猫背だ。胸を張った方がいいな」
専属の演出家たちが、左右から小声でささやいてくる。脅迫だよ、これは。
ぼくは後ろに手を組んで胸を張り、できるだけ鷹揚に歩いてみせる。やれやれ、あとですごい自己嫌悪に陥りそうだな。
学園の周縁部に差しかかると、史学科の遺跡へ市民たちが避難してゆくのが見えた。
身ごもった女性、十四歳以下のプロテジェとその母親、家庭を持たない女性、家庭を持った男性、家庭を持たない男性――
生物学科の原案から学園長が決定した避難の順序である。どうやら社会的な地位などは、考慮の対象から外されているようだ。
つまり、ぼくなんかの優先順位は一番低いってわけ。非常に学園らしい、率直なやり方だ。久しぶりにその闊達さを垣間見た気がして、なんだか愉快な気持ちになってくる。
ペルガナ市国は学術研究都市であり、市民のほとんどが学園かその下部組織へ奉職している。なので、成人男性は志願さえすれば、今回の防衛部隊に組み込まれることになっていた。
避難の順序から男性が削除されていないのは、志願が強制ではないことを示す。しかし、ここから見えるのはほとんど女性と子どもばかりだ。
「ここにいる人たちが帰る場所を守らなくちゃな」
改めて、抱えこんでしまったものの重さを確認する。
「まさか全員を路頭に迷わせるわけにはいくまい」
ぼくのつぶやきに、スウが冗談ぽく返事をする。もしかすると、気を遣ってくれているのかな。
沈黙が降りた。それぞれが学園を守るための理由に、思いをはせていたのかもしれない。
ぼくはもっと実感を持つべきなのだろう。もし失敗した場合に、失うものへの実感を。
微温的な学究生活の中で、喪失を実感することは多くない。ひとりのプロテジェのことを思い出す。いまでも胸が痛むのは、他の誰でもない、ぼくが責任を負うべき喪失だからだ。もうあんなことは二度と繰り返したくない。
一人の少年が母親の手をふりはらって列を離れ、こちらへと走ってくるのが見えた。シャイだ。身体全体をつかって、つんのめるように走る様子は、まるで子犬のようだ。
足元まで駆けてくると、両膝に手をあて、あえぐようにしぼりだす。
「みんな、言ってます、メンター、ユウドが、学園を守るために、じ、じんりょくなさっている、って」
息を切らせながら、疑うことを知らぬ眼差しでぼくだけを見つめてくる。
胸に走る痛み。あこがれを得たものは、それに応える責任がある。
「ほんとうに、ぼくはくやしい。子どもなのがくやしい。メンター・ユウドのそばにいて、力になることができたら。力になることが無理でも、せめてこの身体を盾にして、メンター・ユウドを守ることができたらッ」
かつての光景が脳裏によみがえる。
目に涙をためたシャイの表情が、別の誰かと二重写しのようになる。
「ぼくは、メンター・ユウドのためなら……ッ」
言いかけるシャイの口を手のひらでふさぐ。その先を言わせてはいけないと思ったからだ。
ぼくにだって、何か確信があるわけじゃない。いつだって、自分のことを疑っている。
けれど、喉まででかかった「ぼくは君が考えているような立派な人間じゃない」という言葉をかろうじて飲み込んだ。
大人が子どもを失望させてはいけない。シャイが見たいと思うぼく、なりたいと思うぼくを演じきることが、ぼくの責任だ。
ようやく心の底からそう思える自分に安堵する。ならば、果てのない紆余曲折の中で、少しは先に進むことができたのだ。
グラン・ラングの研究にせよ、今回の作戦における守勢の提案にせよ、ぼくはいつだって受身にこの人生へ対処してきた。この世界をよりよい場所にしたいとは思い続けてきたが、それが本当に達成されるだなんて、信じた瞬間はあったろうか。
ぼくには何もない。ぼくには何もできない。
ただ、次の世代への責任だけは果たそうと思う。大人になったシャイ少年の見る世界が、いまと変わらず美しいものであるように。
シャイのあこがれに、ぼくは負っている。シャイの視線が、ぼくをぼく以上のものにさせ、怠惰でどうしようもないこの身を突き動かすのだ。
「シャイ・プロテジェ」
できるだけ、声に強い威厳の調子をこめようとする。
「はいッ」
はっとした表情で背筋を伸ばすと、シャイはゆるくなった袖口でごしごしと両目をぬぐった。
「案じてもらうまでもない。君をそばに置くことが、体技科長とスウ・プロテジェの護衛より有効だとは感じない。君は家族と、君自身の生命を最優先に守れ」
「はいッ。出すぎたマネを、申し訳ありませんでした」
地面に額がつかんばかりに、深々と頭を下げる。
「それともうひとつ。非常事態であることを理由に、課題の進捗を怠ることがないように。次回の講義で提出してもらうからね」
軽く片目をつむってみせる。
シャイはたちまち笑顔となって、大きな声でひとつ返事をすると、母親の元へ駆けていった。
頭巾をかぶった婦人が、こちらへ会釈をする。シャイの容姿が整っている理由がわかったな。
「立派な態度だったぜ」
体技科長が背中をどやす。たちまち咳きこむぼく。もう少し手加減してほしい。
「『危機が人を選び、状況が人を鍛える』ってのは、本当のことだな」
満面の笑みで、実に愉快そうだ。
「俺ァ、若い連中の覇気の無さにゃ、ほとほと愛想が尽きてたンだよ。ときどき活きのいいヤツがいてもよ、テメエの理屈ばッかりで、まわりのことをちいとも考えねえ。でも、ちょっと安心したぜ。もしかすると、俺たち年寄りがフタになってただけなのかもしんねえな」
「何を言っているのかわかりませんよ」
喉をおさえながら、尋ねる。
「つまりよ、若い力の台頭に、老兵はようよう勇退できるってわけさ」
何か言う暇もあらばこそ、体技科長はぼくとスウをまとめてその広大な胸のうちへひっつかみ、ぎゅうぎゅう抱きしめた。
スウの身体の柔らかい部分がなければ、ぼくはそのまま圧死していたに違いない。
冷たい風に頬を撫でられて、ぼくは本から目を離した。遠くから、かすかに虫の鳴き声がする。気づかぬうちに、すっかり夜も更けたようだ。こうやってドミトリの自室に腰かけていると、今日一日の大さわぎがまるですべて幻だったかのような錯覚に陥る。
ベッドの上に長く伸びたマアナが、ときどきひどく歯ぎしりをする。まるで猫のようだ。いったい、どんな夢を見ているのだろう。
背後に気配を感じて、ふりかえる。薄く開いた扉から、ほっそりとした人影がのぞいていた。
 「眠れないんですか」
「眠れないんですか」
ぼくはゆっくりと本を閉じる。
「すいません、お邪魔をしたみたいで」
「いや、読んだところで頭に入ってないんだ」
夜更けにページをくるこの平穏が、二度と訪れないかもしれないことを惜しんでいた、などとは口が裂けても言えない。
窓から差す月光が室内で膨れあがり、文字を追うのに灯りは必要なかったほどだ。
扉から向こうへは光が届いておらず、ちょうど少女の立つあたりが境界となっている。
胸元から上が闇に沈んでいて、表情はうかがえない。
少女の中にある二つの人格。はたして、どちらのスウがそこにいるのか。
「どうしたんだい。健全なプロテジェなら、とうにベッドへ入っている時間だよ」
ぼくの問いかけに、スウはかすかに身をふるわせた。
そして逡巡するような間をおいて、
「身体を重ねますか」
何を言っているのかわからなかった。
が、すぐに意味と血流が頭のほうへ上がってきた。室内を満たしているのが陽光でなくて幸いだった。倍ほどの年齢をしたメンターをうろたえさせることができると気づかせるのは、プロテジェへの教育指導上よろしくない。
ぼくは黙りこんだ。本当は、次に言うべき言葉が思い浮かばなかっただけだが、沈黙に耐え切れずにスウが身をよじるのが見えた。
精神が安定を取り戻し、主客は再び逆転する。やれやれ、いまのはあぶなかった。
「理事にそう言えと教わったのかい?」
「ご不快でしたでしょうか」
声が震えている。少し意地の悪い返答だったかな。ぼくはずっと、彼女の気持ちを知っていたのだから。
「唐突だっただけさ。ぼくは君のことが嫌いじゃないからね。けど――」
言葉を切る。
「それじゃ、まるで死ににいくみたいじゃないか」
はたして、信じていたか。この瞬間まで、生きて帰れることを信じていたか。学園の存続を信じていたか。
「誰も死なせない。学園は残る」
不思議なことだ。自分をさえずっと信じられなかった誰かが、いまやもっと大きなものを信じている。
「そうだ、忘れてた」
ぼくは机の引きだしに手をかけた。
「君に渡したいものがあったんだ」
中に収まっていたのは、ひとそろいの小さな革靴。
「いつか言ったろ。本気を出しても破れないのをプレゼントするってさ。受けとってくれるかな?」
「も、もちろんだ」
そう言いながら、部屋の中に入ってこようとはしない。ぼくは革靴を指にひっかけて、スウに歩み寄る。
ぼくを近づけまいとしてか、扉の向こうから両手をいっぱいに伸ばしてこわごわと受けとった。
そのとき、少しだけ触れた指先が、少女の動揺を伝えた。
「ちょっとグラン・ラングで細工をしていおいた。いざというときに、君を守ってくれるはずだ」
愛しげに革靴を胸元へ抱くスウ。
その仕草に含まれる純粋な喜び――もっと言えば、神聖ものを抱く感じに、ぼくは胸はまた、おかしなふうに高鳴った。
何か気のきいた軽口にでも気持ちをまぎらせてしまおうと、唇を湿したところへ――
どさり。
見れば、鈍い音の正体はベッドから転落したマアナだ。やれやれ。
「さあ、君も寝た方がいい。夜明けと同時に、大仕事が待っている」
苦笑しながら床から抱きあげるが、目を覚ます気配はまったくない。
「長く存在したものにまつわる腐臭と妄念は、何かをなしとげようとする意志を阻喪するのに充分だった。学園のために、という言葉は私にとって純粋ではなさすぎる。私はずっと、自分が汚れていると感じてきたから」
マアナへ毛布をかけてやりながら、その声に含まれる調子に違和感を覚える。
「メンター・ユウド、私はあなたのために死力を尽くそう」
あわてて振り返るが、すでに少女の姿はそこになかった。