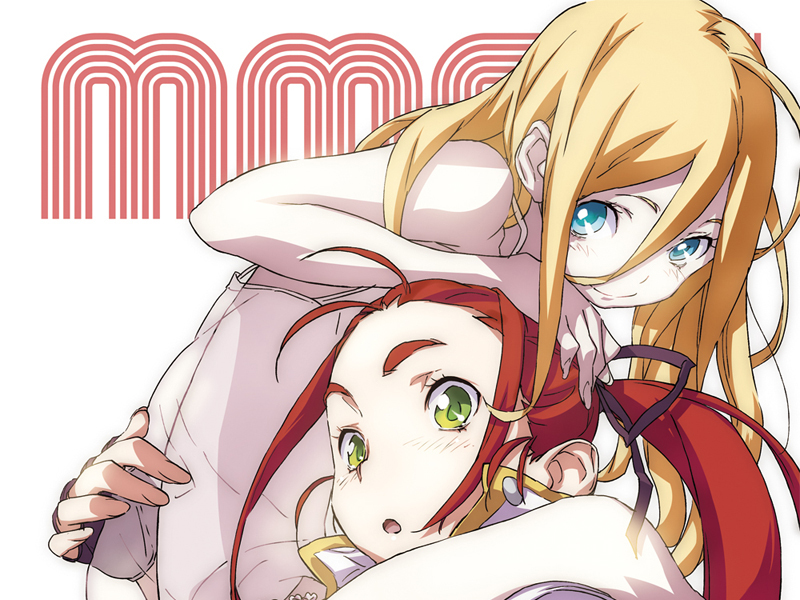無為を教育と称し、停滞を伝統とうそぶき、日々の研究は車輪を再発見し続ける。
過去から消費することで、少なくとも己の数十年を終えるまでは、微温的な日常を永続させたいと願う。
膨大な過去が尽きるのを予見したとして、己の現在と重なる可能性がないならば、あえてそれを指摘することはない。
結局、若いぼくが批判していたのは、我が身の未熟さから発した目に見える達成を求めてのもがきと、岩が岩のように練磨されていく様子とのギャップにこそあったのだと気づく。
学園の結論は、ぼくを失望させなかった。
ならばいまこそ、ぼくが学園を失望させてはならない。
「それでは、グラン・ラングによる大規模エンチャントの連動テストを開始します」
グラン・ラングで音素を風にはらませ、体技科メンターを中心に編成した各部隊へ指示を送る。受けとることは誰にでもできるけど、発信にはグラン・ラングが必要だ。
言語学科の総勢は二十名を超えるが、グラン・ラングの運用に関して言えば実働できる人数は限られてくる。双方向の密な通信が不可欠な体技科長とスウ・プロテジェの部隊、さらにいくつかの防衛拠点を選び、同僚のメンターたちを配当した。
「それぞれの隊のリーダーは、作戦図通りの配置にあることを確認してください。用いる施術の性質上、二度の試行は不可能です」
まあ、本当のところ性質上というより、ぼくのいまの能力ではなんだけど。
指示を出す者として、不正直さに寛容であれるほど年をとっていることは、この際メリットと考えよう。
長方形に切り取られた空の下で、風にゆれる大樹が短い影を投げている。
かつて学園の中心であった中庭を、ぼくは大本営として選択した。
もちろん、防衛のしやすさや指揮をとる上での利便性を加味するならば、ベターな場所は他にいくらでもある。だが、頭で考えた論理的な筋道や保険というヤツをぼくはすべて放り投げた。
古代人たちが要地として選び、遺跡の少女のお気に入りで、グラン・ラングを話す知性体との交渉が行われたここには、何か特別な意味合いがあるに違いないと感じたからだ。
つい数日前までならば、誰かのこんな言い草はオカルトだと一笑に付しただろう。けれどいま、ぼくは己の直感に迷いなく従うことができる。
見渡す四方の壁面は、巨大な白布で覆われていた。保健部がありったけのシーツを供出し、夜を徹して突貫で縫いあげたものだ。
シーツの白と空の青が交錯するあたりに見える人影が、準備完了の合図に頭上で大きな丸を作る。すると、ぼんやりとした像が白布の表面へ浮かび始めた。
彼らの視線の先にある学園周辺の景色が、レンズ状に形成した大気を経由し投射されているのだ。この方法では東が西に、北が南に投影されることになるため、視界の反転をあらかじめ考慮しておく必要がある。
中庭にいる同僚のうち、特別に小柄な(なんと、ぼくよりも小さい)ひとりがグラン・ラングをつぶやいた。美しい発音だ。
それに呼応して、映された像の輪郭はくっきりと鮮明さを増した。
ぼくは内心、くちぶえを吹く。見事なもんだ。
おそらくぼくのキャパシティでは、ことが始まれば全員の付与にかかりきりになってしまう。大本営の機能維持は必然的に、だれかに丸投げってことになる。もっともグラン・ラングの運用能力には個人差がありすぎるため、適性のある数名以外は補助という形にならざるを得ない。
「さて、こちらの準備は整ったかな?」
いかめしいローブに身を包んだ言語学科の面々に声をかける。彼らこそが適性のある精鋭というわけだ。与えられた仕事の重大さを自覚しているのだろう、いずれも緊張した面持ちである。
皆より頭ふたつほども背の低いメンターが、やや感情の起伏に欠いた声音で返事をする。
「問題ありません」
無機質な返答は、しかしぼくを失望させはしない。今回の作戦を彼女抜きにして完遂することはできないだろう。
言語学科の若き俊英、メンター・リンだ。飛び級に飛び級を重ね、つい最近メンターとして学園へ赴任したばかりである。少女のようなその外見は、ほとんどプロテジェとみまがうほど。見た目だけではなく、実際のところ相当に若いのだと思う。
プロファイルによればペルガナ学園の出身で、だとすればぼくもプロテジェ時代に受け持ったことはあるはずだが、印象は全く残っていない。良く言えば物静かでおとなしく、悪く言えば表情に乏しくて活気に欠けていたせいかもしれない。
少々理論に走りすぎるきらいはあるが、メンター・リンの安定感は抜群だ。
他の同僚たちには伏せてあるが(いらぬ嫉妬を招かないためだ)、彼女には大規模エンチャントの要である増幅と維持を任せている。
今回の施術の中身は、防衛に携わる数千の魂をまとめて“高揚”させるというものだ。取り扱うエネルギーの総量はどれだけ少なく見積もっても、膨大にならざるを得ない。
まともに受ければ、泳げない者が大波にまかれて水面を失うような体験となるだろう。その恐怖にうち勝てなければ、付与の内実は大幅に減衰してしまう。
付与のグラン・ラングを行使するには、どこまで自我を薄めて世界と合一できるかという点が最重要である。ぼくにとっては年齢的な諸先輩をさしおいてこの役目を与えたのは、彼女が己を無にすることができるからだ。
もちろん、本当にリンの本質がぼくの見立て通りである証拠なんかない。中庭を大本営に選んだのと同じ、ぼくの直感だ。
いずれも結果のみが正しさを証明する、大バクチである。
「さあ、配置についてくれ。学園のみんながお待ちかねだ」
ぼくはぼくに可能な限りの快活さで同僚たちへ檄をとばす。
「頼んだよ」
他のメンターに悟られないよう、ぼくはリンの肩をポンとたたく。そして、その感触にどきりとする。ローブの下には、何も身につけていない。
『付与行為ヲ行ウニハ極力、夾雑物ヲ除クベシ』という教本(ぼくが書いた)に忠実であるためだろう。『但シ、規模ニ比例シテ誤差ノ範囲ニ落着スル』という附則は目に入らなかったのかな。まじめなのか、天然なのか。
連動テストという呼称にかかわらず、これはただの予行ではない。過去に前例の無いこの壮大な机上の空論は、ただ成功だけをもって皆の信任を得る。
一度の失敗でさえぼくの、ひいては作戦そのものへの不信につながり、すべてを根底から瓦解させるだろう。
ふりかえれば、他に居場所はないとでも言いたげに、大樹の根本へ固く身を預けるマアナの姿があった。
――君の助けが必要だ。
ゆっくりと歩み寄り、声をかける。
見上げる表情には、ほんの数日前までには見られなかったある種の屈託が含まれていた。
――ぼくを、君の来たところへ連れていってくれ。
マアナは薄く微笑んだ。陰のある微笑みだった。
世界を知るほどに失われてしまう何か。あるいは、成長という名前の呪いか。
ぼくはある種の悲しみに包まれながら、手をさしのべる。指をからめるようにしてぼくの手を取ると、そのまま全身をあずけてきた。
マアナを抱き上げると、各隊へ最後の指示を送る。
「変化の指標を各自で設定してください。鳥でも、雲でも、風でも、動くものなら何でもかまいません。今回のエンチャントは、主に身体能力の向上を企図するものです。付与が完了すれば、相対的な速度の減退を体感できるはずです」
ぼくは大きく息を吸い込んだ。
さあ、覚悟を決めよう。失敗も成功も、すべてはこの身にかかっている。
マアナがぼくの首筋へそっと唇をあてがう。
無限へと誘うもの。それは、少女のくちづけ。
官能的な柔らかさの後に、魂の輪郭を溶かすぬくもりが訪れた。
視界がゆらぐ。あのときと同じだ。
眼前の景色と重なるように楕円形の輝きが生まれ、その明滅とともにぼくの意識は別世界へと接続する。
橋渡しされた場所を満たす媒質が、ぼくの自我へと流入する。水に溺れるような感覚の中で、自と他の境界は次第に不分明になってゆく。
やがて自我と媒質が置き換わり、ぼくは別世界へと逆流した。
それは、無辺大の広がりを持つ上下のない空間。
それは、天と地をひとつにして満たされる虚空。
是即ち無限の端緒であり、永遠の住処。
圧倒的な感覚と恐怖が、ぼくを浸してゆく。
まるで木の葉が竜巻に抵抗できないように。
根こそぎ奪われそうになる意識を自問でつなぎとめる。
おまえは、いったい何を恐れているんだ。
喪失が怖い。この小さな己を失うことが恐ろしい。
――これが君を殺すことはない。
どこかから声を聞いたように思った。
両手を広げ、全身を脱力する。
絶望感。ぼくにとって諦念と信頼はなんと近い位置にあるのだろう。
たちまち意識は吹きとばされ、永劫の彼方へと巻きあげられてゆく。
ああ――
これをなんと表現しよう。ひとつの時間軸にひとつの意識をしか持てない我々では、決して完全には理解しえない何か。
そのときぼくは、過去から未来に至るすべての時間軸に偏在しており、まるで昆虫の複眼を思わせる意識で“そこ”を睥睨していた。
暗闇さえ暖かに思える、完全な真空。
その虚無の只中に巨大な光の球が浮かび、唯一の実在として輝いている。あらゆる色彩をした魂が お互いに矛盾しないまま同時に存在し、球体の表面に明滅する幾何学模様を形成している。
めくるめく荘厳なる俯瞰。
瞬間は永遠の中に。
有限は無限の中に。
全ての概念が対立を喪失して渾然たる一つへ。
この身を包む、全体へと回帰する至上の安逸。
――ああ、マアナ!
いまこそ少女の苦しみの正体を知り、ぼくは嗚咽する。
そこへ、あの声が追い打ちをかけた。
――黎明王女は受肉し、この至上の安らぎから追放された。君たちが見ているのは影法師に過ぎぬ。喪失の悲しみは過去への憧憬となり、憧憬は門となって過去へ回帰する。私たちと君たちは同じところから汲んでいるのだ。
聞いてはいけない。耳をふさごうとするが、肉を喪失し一個の概念と化した身にそれはかなうはずもなかった。
――偏狭な自我を越えよ。グラン・ラングは、我々より高次の意識が実在することを証明しているではないか。死をここへ捧げよ。君たちが消滅に恐怖するのは、輪廻の一部が不可視であるに過ぎないからだ。
問い。実体を伴った、貫くような問い。
問い。異世界から投げられた、正解を持たない問い。
我が身を制約する、鈍重なる肉体。
我が意志を制約する不自由な言葉。
愛情は争いの火種となり、受け継がれていくのは連鎖する憎悪。
最も崇高な理念さえ刃の前には膝を屈して血だまりを作るのみ。
だが――
だが、世界に希望が無いと誰が言っただろう?
だが、世界に理解が無いと誰が言っただろう?
ならば我々は――
法悦とは遠い愛憎を選ぼうではないか。
開悟とは遠い転迷を選ぼうではないか。
――やれやれ、これでも受け入れないとは驚きだな。
失笑を聞いたように思った。
――本当に、強情だ。特に君は。
再び視界がゆらぐ。
与えられた全能感とその急激な喪失。
たちまち智慧の明るさは暗くなり、言葉は不自由となり、実存は肉をまとい鈍重となった。
気がつけば、ぼくは何事もなかったかのように中庭にいた。ほとんど時間は経過していないようだった。
どこも損なわれていないにも関わらず、ぼくはぼくの一部が永遠にあの場所へ置かれたことを知る。
いや、違う。ずっと置かれていたことに、気づいていなかっただけだ。
知ることによって失われる無垢。ぼくはマアナを抱く腕へわずかに力を込める。
すでに選択は成されたのだ。選ばなかったものへ心を残してはならない。
さあ、心を研ぎ澄ませ。
人間存在を肯定する、この世界の根幹を感じるんだ。
空わたる風のように。
たなびく雲のように。
グラン・ラングの音素がいくつも重ねられ、やがてそれらはひとつの音曲へと変じてゆく。
その抑揚にあわせ、凪いだ水面を揺り戻す波のように、次第にテンションが高まってゆく。
そして、永遠の彼方から訪れた無形の力が、ぼくを出口として吹き上がる。
莫大なエネルギーの中心にいながら、ぼくは驚くほどに平静だった。
人差し指を立てると、グラン・ラングをつぶやきながら、指揮者のようにふった。
――流れろ。
行き先を見つけた無形の力は、怒涛の奔流となって同僚たちへとふりそそいだ。
エネルギーの量が想定を越えていたのだろう、いずれも決死の表情で付与の伝播を試みている。
ぼくは心の中でそっと呼びかける。
怖がるな、怖がるな。これは君たちを傷つけない。
もちろん、エネルギーの分配は公平ではない。各人のキャパシティには限界があるからだ。
メンター・リンは涼やかにさえ見える様子で(無表情なだけか)、伝播のみならず増幅までを同時にこなしている。どうもまだ余裕がありそうだ。大した後輩じゃないか。
突風の如き瞬間はたちまちに去り、世界が死に絶えたかのような静寂が訪れた。
青白い顔をした同僚たちが、肩で息をしながらこちらを見る。だが、その不安げな様子とは裏腹に、確信のみがぼくを包んでいた。
やがて――
白布に映された群像がさざ波のようにゆらめき、少し遅れて四方から歓声が聞こえた。ぼくは己の確信が現実に裏付けられたことを知った。
ふと、首筋に冷たいものを感じる。見れば、マアナが涙を流していた。
喪失の追体験。いまや、彼女の気持ちは痛いほどにわかった。
――ごめんよ。
ぼくが耳元でささやくと、マアナはぐずるように首をふった。
「記録されるべき施術です」
顔をあげると、わずかに頬を紅潮させたリンがすぐ眼の前にいた。冷たい手のひらがぼくの頬に触れる。はだけたローブから白い二の腕と腋が露に見えた。
「涙」
どうやら泣いていたのはマアナだけではなかったらしい。
「涙腺の筋肉まで老化しはじめたかな」
あわてて目元をぬぐいながら、軽口にごまかそうとする。
しかし、聡明な瞳はぼくの韜晦を越えて、さらに深くをのぞきこむかのように澄んでいる。
「私は、メンター・ユウドの選択を支持します」
言葉の真意を問う暇もあらばこそ、ぼくの戸惑いは体技科長の胴間声によって破られた。
「おい、ユウド。連動テストとやらは成功だろ。さっさと次の指示を寄越しな。どいつもこいつも興奮しちまって、このまま攻めこみそうな勢いだぜ」
学園長と執行部は、十四歳以下のプロテジェをすべて避難させる決定を下した。
「学園のいまを守るのは、子どもの仕事やないからな」
史学科長の言葉に賛同する。それは、ぼくたち大人が果たすべき責任だ。
巨大な太陽が地平の彼方へと沈んでゆく。大地の輪郭がわずか盛りあがって見えるのは、流民たちが市国へと距離を縮めつつあるせいか。
陽光は空に版図を失い、月光が薄青く天球を塗りかえしつつある。侵攻は明朝に迫っていた。
ぼくはといえば、すべての隊とすべての拠点を己の目でおさめておくために、学園の外壁に沿って散歩をしているところだ。しかし、これを散歩だと考えているのは、どうやらぼくひとりだけだったらしい。
それを証拠に、背後には剣呑な空気を発散する人影がふたつ。
この状況に至るのに、話は少しだけさかのぼる。
「もう少し、置かれた立場を自覚して欲しいものだな」
厳しい声音に思わず首をすくめる。
研究室を抜けだしたところで、スウが待ちかまえていた。
「言語学科のいちメンターとしての、かな?」
「学園の命運を両肩に背負った、重要人物としてのだ」
ぼくの軽口へ、スウが即座に切り返しをする。その表情を見て、反省した。もしかすると、戸口にひかえていたのは、怪人の襲来からぼくを守るためだったのか。
マアナをはじめとして、多くの他力によって支えられているとはいいながら、客観的に考えてぼく抜きにこの作戦は成立しない。ぼくがいなければ、防衛は不可能ではないにせよ、多くの血を見ることになるだろう。
自分にしかできない仕事を人質にして、他人とその感情をふりまわすのは卑劣なやり方だ。さっきの軽口には、意図こそしなかったにせよ、そういう要素が含まれていた。
つくづく、ぼくはダメなヤツだ。
「ごめん、軽率だった。防衛の要所をじっさいに目で見ておきたかったんだ。もしよければ、いっしょについてきてくれないか」
「まったく、最初からそう言えばいいんだ」
スウがわずかに微笑んだ。
そこへ、聞きなじんだ胴間声が言葉をかぶせてくる。
「ようよう若殿が職責を自覚したようなのは、じつに喜ばしいことだぜ」
ぬっと姿を現したのは、やはり体技科長だ。
「おいら、視察を進言に来たのさ。紙や人づてなんてのはダメだ。てめえの目で見たことだけが、最後に信じられる。けどよ、余計なお世話だったみてえだな」
嬉しそうに破顔一笑する。
「でもよ、敵さんの鼻先をかすめてくんだ。もうひとりくらい護衛が必要だろ? な?」
屋上屋を架すとはこのことだ。質問の形をとっているけど、どうもぼくに否を言う権利があるわけじゃなさそうだ。
「この二人がついてりゃ、敵陣の真ン中へでも突入できるぜ」
「逆に、この二人で守れなければ、誰がついても同じことだ」
スウと体技科長が、不敵な表情で互いに視線を交わす。
性別も年齢も体格も、ぜんぶ違うけれど、二人は根っこのところですごく近いのではないかという気がしてきた。
そんなわけで――
今夜の散歩は、戦術構築と士気高揚のための視察と変じたのである。
ぼくより上背のある、ぼくより強い二人を背後につきしたがえてねり歩くのは、なんだかすごく思春期的な匂いがするなあ。虎の威を借るなんとやら、すごくおもはゆい。
しかし、予想に反して、行く先々での関心や歓声は達人たちではなく、ぼくに向けられたのだった。他学科のプロテジェに握手を求められるのには、閉口した。
ここ一両日での現実が、ぼくの認識よりもはるかに速く動いているということだろう。
虚像にはちがいない。しかし、ぼくが皆に求めたのも、この虚像なのだ。生身の実体が、多数の他人から命を預けるほどの信頼を得るには、大がかりなハッタリが不可欠だ。
連動テストは、ぼくの意図通りに、見事その役割を果たしてくれたというわけだ。
「おい。ちったァ、愛想のいい顔をしろや」
「いつもの猫背だ。胸を張った方がいいな」
専属の演出家たちが、左右から小声でささやいてくる。脅迫だよ、これは。
ぼくは後ろに手を組んで胸を張り、できるだけ鷹揚に歩いてみせる。やれやれ、あとですごい自己嫌悪に陥りそうだな。
学園の周縁部に差しかかると、史学科の遺跡へ市民たちが避難してゆくのが見えた。
身ごもった女性、十四歳以下のプロテジェとその母親、家庭を持たない女性、家庭を持った男性、家庭を持たない男性――
生物学科の原案から学園長が決定した避難の順序である。どうやら社会的な地位などは、考慮の対象から外されているようだ。
つまり、ぼくなんかの優先順位は一番低いってわけ。非常に学園らしい、率直なやり方だ。久しぶりにその闊達さを垣間見た気がして、なんだか愉快な気持ちになってくる。
ペルガナ市国は学術研究都市であり、市民のほとんどが学園かその下部組織へ奉職している。なので、成人男性は志願さえすれば、今回の防衛部隊に組み込まれることになっていた。
避難の順序から男性が削除されていないのは、志願が強制ではないことを示す。しかし、ここから見えるのはほとんど女性と子どもばかりだ。
「ここにいる人たちが帰る場所を守らなくちゃな」
改めて、抱えこんでしまったものの重さを確認する。
「まさか全員を路頭に迷わせるわけにはいくまい」
ぼくのつぶやきに、スウが冗談ぽく返事をする。もしかすると、気を遣ってくれているのかな。
沈黙が降りた。それぞれが学園を守るための理由に、思いをはせていたのかもしれない。
ぼくはもっと実感を持つべきなのだろう。もし失敗した場合に、失うものへの実感を。
微温的な学究生活の中で、喪失を実感することは多くない。ひとりのプロテジェのことを思い出す。いまでも胸が痛むのは、他の誰でもない、ぼくが責任を負うべき喪失だからだ。もうあんなことは二度と繰り返したくない。
一人の少年が母親の手をふりはらって列を離れ、こちらへと走ってくるのが見えた。シャイだ。身体全体をつかって、つんのめるように走る様子は、まるで子犬のようだ。
足元まで駆けてくると、両膝に手をあて、あえぐようにしぼりだす。
「みんな、言ってます、メンター、ユウドが、学園を守るために、じ、じんりょくなさっている、って」
息を切らせながら、疑うことを知らぬ眼差しでぼくだけを見つめてくる。
胸に走る痛み。あこがれを得たものは、それに応える責任がある。
「ほんとうに、ぼくはくやしい。子どもなのがくやしい。メンター・ユウドのそばにいて、力になることができたら。力になることが無理でも、せめてこの身体を盾にして、メンター・ユウドを守ることができたらッ」
かつての光景が脳裏によみがえる。
目に涙をためたシャイの表情が、別の誰かと二重写しのようになる。
「ぼくは、メンター・ユウドのためなら……ッ」
言いかけるシャイの口を手のひらでふさぐ。その先を言わせてはいけないと思ったからだ。
ぼくにだって、何か確信があるわけじゃない。いつだって、自分のことを疑っている。
けれど、喉まででかかった「ぼくは君が考えているような立派な人間じゃない」という言葉をかろうじて飲み込んだ。
大人が子どもを失望させてはいけない。シャイが見たいと思うぼく、なりたいと思うぼくを演じきることが、ぼくの責任だ。
ようやく心の底からそう思える自分に安堵する。ならば、果てのない紆余曲折の中で、少しは先に進むことができたのだ。
グラン・ラングの研究にせよ、今回の作戦における守勢の提案にせよ、ぼくはいつだって受身にこの人生へ対処してきた。この世界をよりよい場所にしたいとは思い続けてきたが、それが本当に達成されるだなんて、信じた瞬間はあったろうか。
ぼくには何もない。ぼくには何もできない。
ただ、次の世代への責任だけは果たそうと思う。大人になったシャイ少年の見る世界が、いまと変わらず美しいものであるように。
シャイのあこがれに、ぼくは負っている。シャイの視線が、ぼくをぼく以上のものにさせ、怠惰でどうしようもないこの身を突き動かすのだ。
「シャイ・プロテジェ」
できるだけ、声に強い威厳の調子をこめようとする。
「はいッ」
はっとした表情で背筋を伸ばすと、シャイはゆるくなった袖口でごしごしと両目をぬぐった。
「案じてもらうまでもない。君をそばに置くことが、体技科長とスウ・プロテジェの護衛より有効だとは感じない。君は家族と、君自身の生命を最優先に守れ」
「はいッ。出すぎたマネを、申し訳ありませんでした」
地面に額がつかんばかりに、深々と頭を下げる。
「それともうひとつ。非常事態であることを理由に、課題の進捗を怠ることがないように。次回の講義で提出してもらうからね」
軽く片目をつむってみせる。
シャイはたちまち笑顔となって、大きな声でひとつ返事をすると、母親の元へ駆けていった。
頭巾をかぶった婦人が、こちらへ会釈をする。シャイの容姿が整っている理由がわかったな。
「立派な態度だったぜ」
体技科長が背中をどやす。たちまち咳きこむぼく。もう少し手加減してほしい。
「『危機が人を選び、状況が人を鍛える』ってのは、本当のことだな」
満面の笑みで、実に愉快そうだ。
「俺ァ、若い連中の覇気の無さにゃ、ほとほと愛想が尽きてたンだよ。ときどき活きのいいヤツがいてもよ、テメエの理屈ばッかりで、まわりのことをちいとも考えねえ。でも、ちょっと安心したぜ。もしかすると、俺たち年寄りがフタになってただけなのかもしんねえな」
「何を言っているのかわかりませんよ」
喉をおさえながら、尋ねる。
「つまりよ、若い力の台頭に、老兵はようよう勇退できるってわけさ」
何か言う暇もあらばこそ、体技科長はぼくとスウをまとめてその広大な胸のうちへひっつかみ、ぎゅうぎゅう抱きしめた。
スウの身体の柔らかい部分がなければ、ぼくはそのまま圧死していたに違いない。
冷たい風に頬を撫でられて、ぼくは本から目を離した。遠くから、かすかに虫の鳴き声がする。気づかぬうちに、すっかり夜も更けたようだ。こうやってドミトリの自室に腰かけていると、今日一日の大さわぎがまるですべて幻だったかのような錯覚に陥る。
ベッドの上に長く伸びたマアナが、ときどきひどく歯ぎしりをする。まるで猫のようだ。いったい、どんな夢を見ているのだろう。
背後に気配を感じて、ふりかえる。薄く開いた扉から、ほっそりとした人影がのぞいていた。
 「眠れないんですか」
「眠れないんですか」
ぼくはゆっくりと本を閉じる。
「すいません、お邪魔をしたみたいで」
「いや、読んだところで頭に入ってないんだ」
夜更けにページをくるこの平穏が、二度と訪れないかもしれないことを惜しんでいた、などとは口が裂けても言えない。
窓から差す月光が室内で膨れあがり、文字を追うのに灯りは必要なかったほどだ。
扉から向こうへは光が届いておらず、ちょうど少女の立つあたりが境界となっている。
胸元から上が闇に沈んでいて、表情はうかがえない。
少女の中にある二つの人格。はたして、どちらのスウがそこにいるのか。
「どうしたんだい。健全なプロテジェなら、とうにベッドへ入っている時間だよ」
ぼくの問いかけに、スウはかすかに身をふるわせた。
そして逡巡するような間をおいて、
「身体を重ねますか」
何を言っているのかわからなかった。
が、すぐに意味と血流が頭のほうへ上がってきた。室内を満たしているのが陽光でなくて幸いだった。倍ほどの年齢をしたメンターをうろたえさせることができると気づかせるのは、プロテジェへの教育指導上よろしくない。
ぼくは黙りこんだ。本当は、次に言うべき言葉が思い浮かばなかっただけだが、沈黙に耐え切れずにスウが身をよじるのが見えた。
精神が安定を取り戻し、主客は再び逆転する。やれやれ、いまのはあぶなかった。
「理事にそう言えと教わったのかい?」
「ご不快でしたでしょうか」
声が震えている。少し意地の悪い返答だったかな。ぼくはずっと、彼女の気持ちを知っていたのだから。
「唐突だっただけさ。ぼくは君のことが嫌いじゃないからね。けど――」
言葉を切る。
「それじゃ、まるで死ににいくみたいじゃないか」
はたして、信じていたか。この瞬間まで、生きて帰れることを信じていたか。学園の存続を信じていたか。
「誰も死なせない。学園は残る」
不思議なことだ。自分をさえずっと信じられなかった誰かが、いまやもっと大きなものを信じている。
「そうだ、忘れてた」
ぼくは机の引きだしに手をかけた。
「君に渡したいものがあったんだ」
中に収まっていたのは、ひとそろいの小さな革靴。
「いつか言ったろ。本気を出しても破れないのをプレゼントするってさ。受けとってくれるかな?」
「も、もちろんだ」
そう言いながら、部屋の中に入ってこようとはしない。ぼくは革靴を指にひっかけて、スウに歩み寄る。
ぼくを近づけまいとしてか、扉の向こうから両手をいっぱいに伸ばしてこわごわと受けとった。
そのとき、少しだけ触れた指先が、少女の動揺を伝えた。
「ちょっとグラン・ラングで細工をしていおいた。いざというときに、君を守ってくれるはずだ」
愛しげに革靴を胸元へ抱くスウ。
その仕草に含まれる純粋な喜び――もっと言えば、神聖ものを抱く感じに、ぼくは胸はまた、おかしなふうに高鳴った。
何か気のきいた軽口にでも気持ちをまぎらせてしまおうと、唇を湿したところへ――
どさり。
見れば、鈍い音の正体はベッドから転落したマアナだ。やれやれ。
「さあ、君も寝た方がいい。夜明けと同時に、大仕事が待っている」
苦笑しながら床から抱きあげるが、目を覚ます気配はまったくない。
「長く存在したものにまつわる腐臭と妄念は、何かをなしとげようとする意志を阻喪するのに充分だった。学園のために、という言葉は私にとって純粋ではなさすぎる。私はずっと、自分が汚れていると感じてきたから」
マアナへ毛布をかけてやりながら、その声に含まれる調子に違和感を覚える。
「メンター・ユウド、私はあなたのために死力を尽くそう」
あわてて振り返るが、すでに少女の姿はそこになかった。
猫を起こさないように