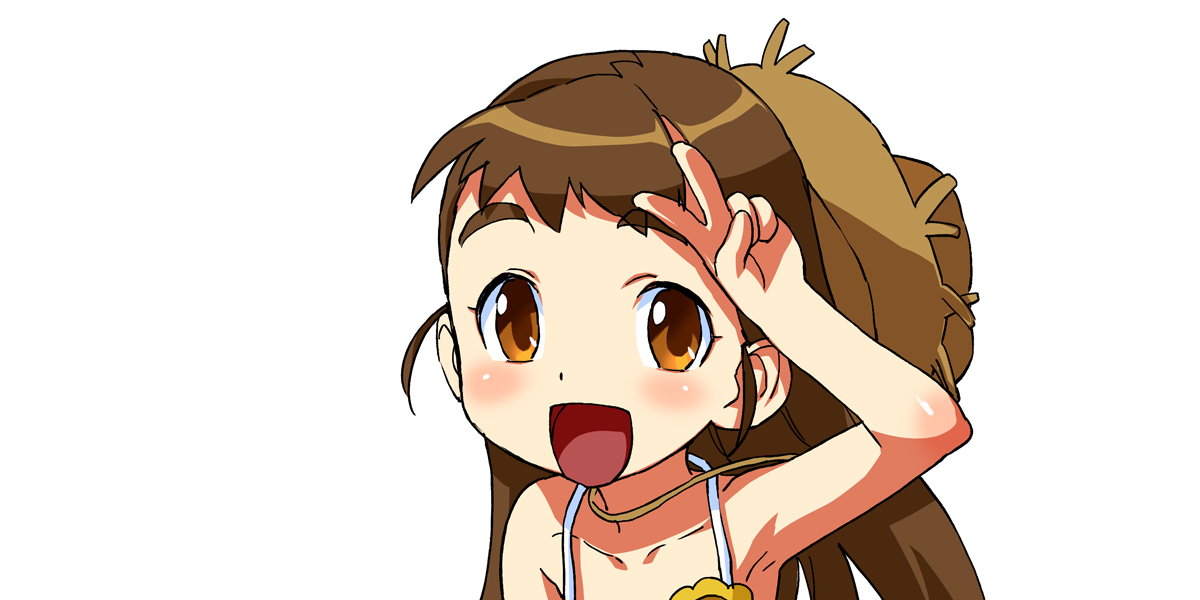FGO第2部6章の感想、まずは謝罪から。5章終了後の感想で、「すでに語りつくされたブリテンとアーサー王をどうも再話しそうな感じ」とかシャバゾーがチョーシこいて、本当にすいませんでした。ファンガスの野郎、無印Fateのセイバーの話と第1部6章を下敷きに、現代社会の戯画を織り込んだファンタジー世界をまるまるひとつ構築する(しかも、壊すために!)という離れ技をやってのけやがりました! Fateシリーズって、基本的に「キャラクターの物語」であり続けていると思うんですけど、アヴァロン・ル・フェはそれを維持しながら「社会と関係性の物語」へと進化しているのには、口はばったい言い方ながら、ファンガスが「成長する書き手」であることをあらためて強く感じました。彼の作劇が優れている点は、まず物語全体を結論まで鳥瞰して、構成の骨格をキッチリ組んでから、キャラを配置していくところでしょう。行き当たりばったりの「神待ち」シンエヴァとは違って、作り手が「神その人」であることへ常に自覚的なのです。その上で、「どの部分を厚くして、どの順番で提示すれば、もっとも効果的に読み手の感情をゆさぶることができるか?」を計算半分、センス半分でやっている。第2部6章も、ひとつひとつのモチーフだけで別の作品が作れそうな内容をぎゅうぎゅうに詰め込むことで、第三村のようなスカスカの書割とは違う実在する世界が、眼前で本当にどうしようもなく壊れていくのを当事者として読み手へ体験させるというすさまじさです。妖精国って、昨今のインターネット界隈と現実社会の醜悪なリンクを比喩的に描いている側面があると思うんですよね。だから、このストーリーを読んだ誰もが自分をどの登場人物かの境遇に仮託してしまう作りになっていて、世界全体を俯瞰的に見下ろす傍観者の立ち場へ逃げ込むことを許さない。市井のモブにも目配りを忘れず、「破滅が迫る中、恩人の元へ駆けもどって、二人で抱き合いながら地割れに呑まれて死ぬ」とか、読み手を信頼して背景の想像を預けてくれる感じが常にあり、それが奥行きを作り出している。シンエヴァの「受け手の読み方をコントロールするため、クダクダ説明してゴテゴテ描写するくせに、肝心なところは盲のような空洞になっている」とは真逆の態度です。「地割れに呑まれる二人」のくだりを読んで、栗本薫がトーラスのオロの話を何度も自慢していたのを、ふと思い出しました。グイン・サーガの1巻で死んだ端役が、その後いかに長きにわたって読者の心を離さなかったかという話です。小説道場の文体模写やってる人をどこかで見かけたけど、あれで栗本薫のシンエヴァ批評やってくんないかなー。
あと、マーリンとオベロンを別人物として表裏の存在に置こうとしているのは、スキルの効果説明から理解できましたが、作中のテキストのみでは同一人物にしか感じられず、けっこう混乱しました。以前、「マーリンはFGOにおける作者アバター」という指摘をしましたが、オベロンもやはり虚構内のキャラというよりは、ファンガスのアバター色が強く出ていて、それが混乱を招いた原因だと思います。マーリンが「人間から距離を置いた、酷薄な虚構摂取ジャンキー」であるのに対して、オベロンは「人間へ積極的に関わり、世界への失望を深める信頼できない語り手」の配置になっていて、前者はFGOを始める前のファンガス、後者はFGOがメガヒットした後のファンガスなのではないかと邪推してしまいます。「もっとも高貴な者が、もっとも卑しい者に救われる」モチーフーーこの構文、6章にも出てきましたね! イエーイ、ファンガス、見てるぅ? 生けるネット呪詛だぞぅ!ーーは以前からありましたが、「高貴な者が救われるとき、卑しい者を疎んじる」視点がそこへ生じたのが、今回の大きな変化でしょう。じっさい、インターネットを通じて眺める人間や世界というものは、地虫のクソ溜めとなんら変わるところはないですからね! イヤな言い方をしますけど、オベロン視点の「虫」は最後のアレを含めて、FGOファンの暗喩だと思いますよ。愛憎が常にぐるぐる回転していて、どれだけ魅力的な世界を紡いでも、ファンの底なしの欲望へと吸い込まれて、すべて消えていく。
けれど、現実とインターネットが互いに照射しあえば、ときに掃き溜めへ白い鶴がすっくと立ち、ときに泥の内から蓮の華が薄紅色に咲く。ダビンチちゃんが刺し殺されるフラグーー偉大な英雄の功績が、その情けによって生まれたモンスターに中絶させられるーーをさんざんに立てておきながら、最後の最後で「彼をそうさせない」(オーロラと美醜の対比になっているのが、また素晴らしい)。先日、ネット局所で話題となった「怒りをこめてふりかえれ」と同じ問いかけでありながら、回答が異なっている。これはしかし、正誤ではなく資質の違いとしか言いようがありません。真摯に書かれたあらゆる表現は、書き手の人格のすべてをあますところなく他者に読み取らせてしまうものなのです。「作品と作者は切り離すべき」という話は、法律とか社会というレベルでは「是」なのでしょう。けれど、作者と読者が一個の人間として互いに向きあうとき、その命題は絶対的に「否」なのです。本当に作品と作者が切り離せるとしたら、虚構を紡ぐという営為は、人工知能が自動生成したテキストと何ら変わらなくなってしまうでしょう。同じ時代の、同じ世界で、同じ空の下、同じ大地を踏み、同じ空気を吸って、違うできごとに笑い、違うできごとに励まされ、違うできごとに絶望し、それでも生きていくのを選ぶだれかが、心から真実に発する言葉にだけ、語られる意味がある。私はそれを聞きたいし、それを知りたいと思う。
FGOは過去の神話や英雄譚に依拠した本質的に荒唐無稽の物語で、幕間の物語などを読むとき、その拙さ、もっと言えば幼稚さが浮き彫りとなって、暗澹たる気分にさせられます。しかし、いったんファンガスが筆をとれば、FGOは現在進行形の「いま」を鮮やかに描き出す至高の物語装置へと変化するのです。他の書き手が調べた設定をキャラに落とし込むのに四苦八苦する段階なのに対して、唯一ファンガスだけが設定を利用して「いま」の深層をえぐる物語を紡ぐことができる。第2部6章ではオベロンが特にそうで、シェイクスピアの劇中設定を使いながら、現代社会の在り方への批判とフィクションを紡ぐ者の覚悟が平行して描かれている。第2部4章では、おそらく現実の事件に寄せて、有益と無益で生命の価値を弁別することへ向けた猛烈な反発を描いたファンガスが、今回はいまの時代に漂う欺瞞に満ちた空気に対する強烈な違和感を表明している。「過去の人間のマネゴトをして、過去の人間に依存しなくては生きられない」妖精たちは、いったい何の戯画なのかを考えてみて下さい。キャスターの足の指が凍傷で何本か欠損していることがサラッと書いてあったり、見えなければ他者の痛みを無視できる我々の無自覚性への批判も痛烈です。主人公の脳内にリフレインして、窮地を伝えたペペロンチーノの言葉も、「死んだ者は、生者の中でカッコつきの『死者』として生き続ける」を今日的に表しており、あの一連の展開は年齢の順に人が死なない世界における、ある種の「しるべ」に思えました。これらの表現を、意識的にやってるか無意識的なのかはまったく不明ながら、ファンガスの書くFGOこそ、いまの時代を生きる人々がリアルタイムに追いかけるべき作品であることは間違いありません。
生活感情を物語へと翻訳できるのは、たいへんな異能力だと思いますし、たぶん社長のジャッジで遠ざけてると思うんですけど、ツイッターとか(例の日記も少しそう)やりだしたら、メッセージ性が極限にギュッと濃縮されて特異点化したこの感じが薄まる気は、すごくしています。なのでファンガスには、「生きながらフィクションに葬られ」た者として、今後も最果ての塔(タイプムーン本社?)に幽閉されたまま、すべての感情を余すところなく物語にだけ落としこんで欲しいと思います(最後の2行はルーン文字についた日本語キャプションとして読んで下さい)。