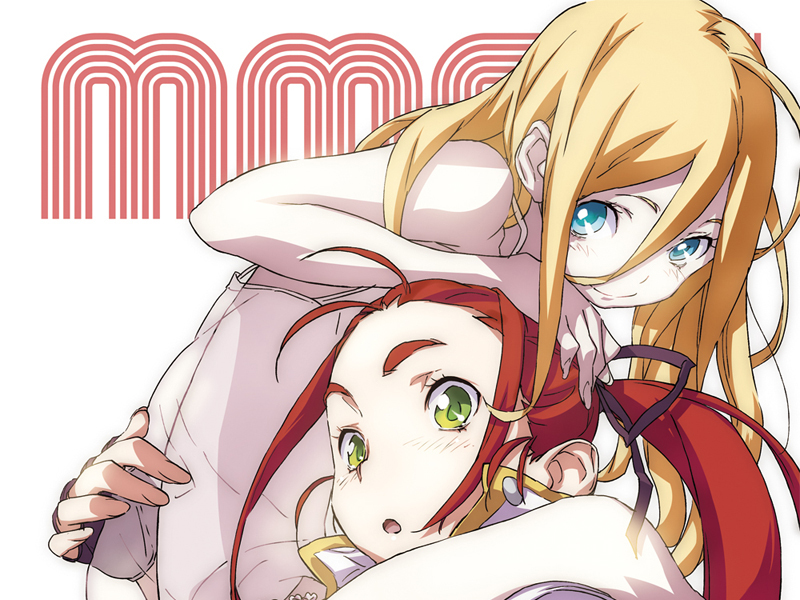「あっ。道路の向こうからほとんどつま先まで隠れるほど長いやたらにひだのある(何の暗喩だか言わなくてもわかりますよね)フリルつきのピンク色のスカートをはき、クマのぬいぐるみを自分では他人に可愛いと映ると思っているんだろう仕草で胸元に抱き寄せ、くるぶしまでのばした髪の毛をほとんど一歩ごとに自分で踏みつけながら、顔面は贔屓目に言って十人並みの婦女が思いつめたふうの、しかし焦点の全く合っていない目で歩いてきます。そちらを見ないように口笛をふきながら速やかにすれ違うよう、私の中に息づく原初の動物本能が告げました……ピィピィピィ」
「あら、貴方」
「やばいです、私に関心を持ったようです。私の中に息づく原初の動物本能が歩調を倍速に早めろと告げました……ピィピィピィ」
「やっぱり」
「ぎゃっ。私の右の上腕が捕まりました。婦女とは思えないほどの凄まじい膂力です」
「鷹久、鷹久ね。やっと会えたわ」
「助けて下さい。なんで私ばっかりこんな目に遭いますか……あの、人違いやおまへんやろか。よぉ見てみなはれ」
「長かったわ。私はこの邂逅を千年も待ち続けたのだもの」
「聞いてません、この女まったく聞いてませんよ……は・は・は。よぉ間違えられるんですわ、ワシ。ほんまもうしわけないんやけど、お嬢さんの言ってる人とちゃいますよってに。ワシ、武言いまんねん」
「もしかして前世の記憶が無いのね、鷹久」
「出ました。前世ワードです。勘弁して下さい。なんで私ばっかりこんな目に遭いますか……ちょぉ、自分もう離せや。ワシちゃう言うてるやんけ」
「可哀想な鷹久。いいわ、私が少しづつ思い出させてあげる。だから、怖がらないで」
「あいた、いたたた。右腕の捕まれている箇所から先が青黒く変色してきました。勘弁して下さい。なんで私ばっかりこんな目に遭いますか……すんません、ちょっとワシきつぅ言いすぎましたわ。わかりました、少しづつ誤解を解いていきまひょ。な?」
「そう、私たちが最初に出会ったのは、平安時代だったわ」
「きっついわ。少しも聞いてへんやんけ」
「童貞だった貴方は初めて私と愛をかわすとき、緊張のあまり間違えて床板のうろにブツを挿入し、猫に先端を引っ掻かれたものだった。うふふ」
「痛い、痛い、腕腐る、離してくれ」
「そう、その次に私たちが出会ったのは、元禄時代のことだったわ」
「痛い、痛い、腕腐る、離してくれ」
「童貞だった貴方は初めて私と愛をかわすとき、緊張のあまり間違えて天井板のうろにブツを挿入し、ネズミに先端を囓られたものだった。うふふ」
「痛い、痛い、腕腐る、離してくれ」]
「そう、最後に私たちが出会ったのは、幕末のことだったわ」
「痛い、痛い、腕腐る、離してくれ」
「童貞だった貴方は初めて私と愛をかわすとき、緊張のあまり間違えて土竜の穴にブツを挿入し、尿道でミミズを引っ張りだしたものだった。うふふ」
「痛い、痛い、腕腐る、離してくれ。あっ。あそこを通るのは一つ屋根の下に暮らすロリータ高校生の従姉妹、ではないですか……おぉうい、おぉうい」
「たけちゃん。わたし、桐子よ」
「マイガッ。君もですか。右腕の感覚が無くなってきました。あっ。あそこを通るのは私の同級の友人で、組の若頭顔の汰一ではないですか……おぉうい、おぉうい」
「キサマッ。あれほど彼女を守ると約束しておきながらッ」
「マイガッ。君もですか」
「にいさま」
「あっ。そんなところに顔をすりつけないで下さい。ちんちんが起立してきました」
「ぼとり」
「ぎゃあっ。私の右腕がまるで鳥のササミを裂くようにずるりと音を立てて抜け落ちました」
「鷹久」「にいさま」「この後におよんで、キサマッ」
「なんだなんだ」
「左腕を強く電波さんにねじあげられ、両足をロリータに抱きつかれた小太りのアニメプリントシャツが、ニキビ面の体育会系高校生になすすべもないまま殴打の嵐を受けているぞ」
「やめ。もうやめぇや自分ら。きっついわ」
「くちゃ」
「ああ、右目潰れてもたがな。かなわんわ。もう見えへんがな。うわぁぁんうわぁぁん」
「鷹久、思い出してくれた?」「にいさま」「キサマッ、キサマッ」