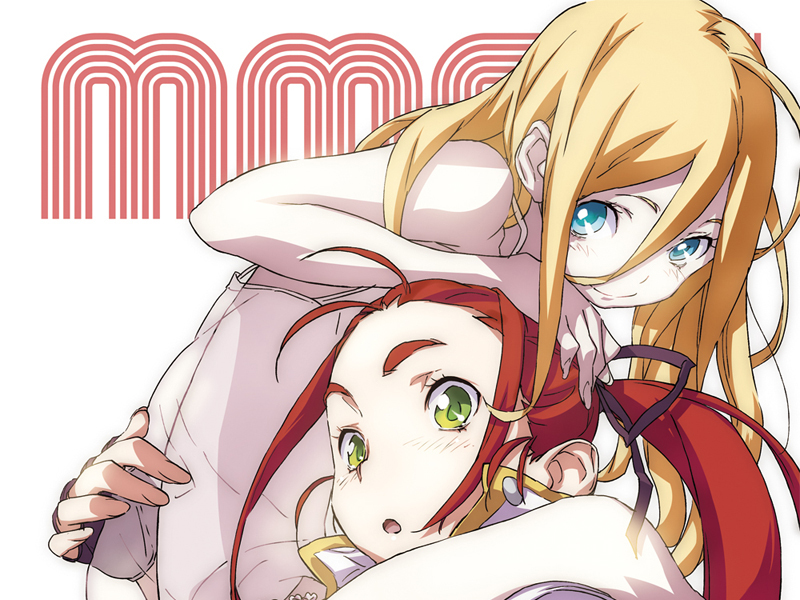シャッターの閉じる音がビルの谷間へかすかに響く。”漫画喫茶YOMYOM”と書かれた電飾の明かりが消える。のび放題にのびたあご髭に優しい顔の輪郭をまぎらせ、大きなサングラスに繊細すぎる少年の瞳を隠したその人は、数メートル毎に振り返り、人柄をしのばせる丁寧なおじぎを何度も何度もくりかえしながら、ついにはけぶる朝靄の中に遠く見えなくなった。
「終わったな」
「ああ、本当に」
早朝のオフィス街はおどろくほどに閑散としており、人の気配をまったく感じさせない。
「――有島と太田は?」
かれらが最後によこしたハガキにあった、初めて知るその名前に、ぼくは他人のようなよそよそしさを感じたものだった。
「ふたりとも昨日発ったよ。有島は田舎に帰って農家を継ぐんだそうだ。いま有機野菜が大当たりしてて、人手足りないんだって言ってた」
かれはいつものくせでポケットに手をつっこんだまま続ける。
「太田は両親の口ききで地元の市役所に就職が決まったんだってさ。幼なじみと来春結婚するんだそうだよ。『ついにつかまっちまった。墓場行きだ。俺の人生はもう終わったも同然だ』って、すごく嬉しそうに話してた」
「へえ、二人ともそんな、全然知らなかったな。全然知らなかった――」
ぼくはなんとなくうつむいて黙りこむ。かれはおりた沈黙にうながされるように煙草を取り出すと、火をつけた。
「そうだ、CHINPOだ。CHINPOはまだいるんだろ、こっちに」
変わっていく現実に逆らうように、すがるように、ぼくは云った。
けれど現実はいつもぼくを先回りして裏切る。
「CHINPO…いや、上田はどこか東北のほうの山奥にある療養所に移送されちまった。あいつの家に電話して名乗ったらさ、『保椿さんにそのような友人はおりません』だとさ。おれはあいつの友人じゃなかったんだそうだ。ずっと、いっしょにいたのにな。――知ってたか、あいつの両親、そろって大学教授なんだぜ! ちょっと笑えるよな。笑えるじゃないか――」
ビルの谷間を吹く風が小さな渦を巻いて、歩道の上にゴミを舞わせている。
「『友だちは…友だちと呼べる人はみんないなくなってしまった…誰も』」
「――シェイクスピアかい」
「いや」
向かいの歩道を何におびえるのか、一匹の野良猫が猛然と駆け抜けていく。
「エヴァさ」
かれは皮肉に口元をゆがめた。
「さてと」
ほとんど口をつけないままに短くなった煙草を放り投げると、かれはもたれかかっていたガードレールから身を離した。
「もう、行くわ」
そう云って、かれはYOMYOMのマスターが去っていったのとは逆の方向にゆっくりと歩き出した。ぼくはたまらなくなってその背中に声をかける。
「どうするんだい、これから。いったいどうするつもりなんだい」
かれは立ち止まると、ポケットから手を出した。
そしてかれは口を開いた。
「おれはずっとおたくだった。傍観者だった。世界がかくあることの痛みを最終的に我が身に引き受けることをせずに、何ひとつ実感のない空理空論をふりまわしていた。自分の正体さえわからないまま、世界の美しさだけは知りたくて、現実の似姿、うつろな鏡、虚構の中に溺れつづけた。それはひとえにおれが生まれながら喪失させられていたものを取り戻したかったからだ。だが、それでいながら当の現実を引き受けるだけの強さは、おれにはなかった」
かれはこれまでの演技をやめて、驚くほど素直な表情で、威圧するようでも、おびえるようでもなく、ただ静かにとつとつと話す。
「――おれが『世界、世界』と声高に、問題ありげに、さも重大そうに呼ばわるとき、それはけれど観念にすぎなかった。経済や政治や時代の病を負って苦悩する同朋たちのことでは全くなく、ただ自分だけを取り巻く違和感と不快感を意味していた。本当に、あきれるほど個人的なことだったんだよ! おれは、間違っていた」
かれはいま、初めて誰かに伝えようとしていた。届こうとしていた。
「おれは今日このまま部屋へ戻って、LDやビデオやCDや、ためこんだ様々のグッズをすべて破棄するつもりだ。それで何かが変わるなんて期待しちゃいないさ。結局また同じことを繰り返すだけのかもしれない。これはおれの中での、そう、儀式なんだ」
ぼくは微笑んだ。この数瞬に、これまでの長い長い時間より多くかれを理解したからだ。
そしてぼくは口を開いた。
「君の言うとおり、ぼくたちにとっての世界とはまったく個人的で脆弱な感覚に過ぎないと思う。――他人の物語というフィルターを通じて垣間見た世界の感じは、分厚い布ごしに物を触るようなもどかしさだった。渇いた者が海水を与えられるように、ぼくはますます渇いた。ぼくはもうあがくことはやめて、ぼくにとってリアルでない世界に他人を通じて連絡を持とうとする努力はやめて、ただ自分のことだけを物語ろうと思う。物語るという個人的な営為が、世界に対して普遍性を持つ瞬間がきっとあるとぼくは思うんだ。個人的な意味が世界的な意味を超克する瞬間がきっとあるとぼくは信じる。だから、ぼくはもう傷ついた人のようにふるまうことをしない。ぼくは物語ることで明け渡してしまった自分を取り返す。『たとえ他人の言葉に取り込まれても』、ね」
かれは大きく目を開いて、いまはじめて出会ったかのようにぼくを見た。
「――ゲーテかい」
「いや」
ぼくは答える。
「エヴァだよ」
ぼくたちは声をあげて、心の底から笑った。
やがてかれはしゃべりすぎたことを恥じるように顔をひきしめ、ポケットに両手をつっこむと、再び歩き出した。
ぼくはその背中に別れを言おうとして、ふと気がつく。
「待ってくれ! ぼくは、君の本当の名前をまだ知らない」
「おれの名前かい」
かれは最後に一度だけふりかえり、歌うように云った。
「おれの名前は――」
ビルのつくりだす峰から遅い都会の朝日がのぼる。誰もいなくなった店のシャッターに揺れる貼り紙。
“長らくご愛顧いただきました当店ですが、誠に勝手ながら本日(7/25)をもちまして閉店いたします。今まで本当にありがとうございました。”
Never seen a bluer sky.
猫を起こさないように