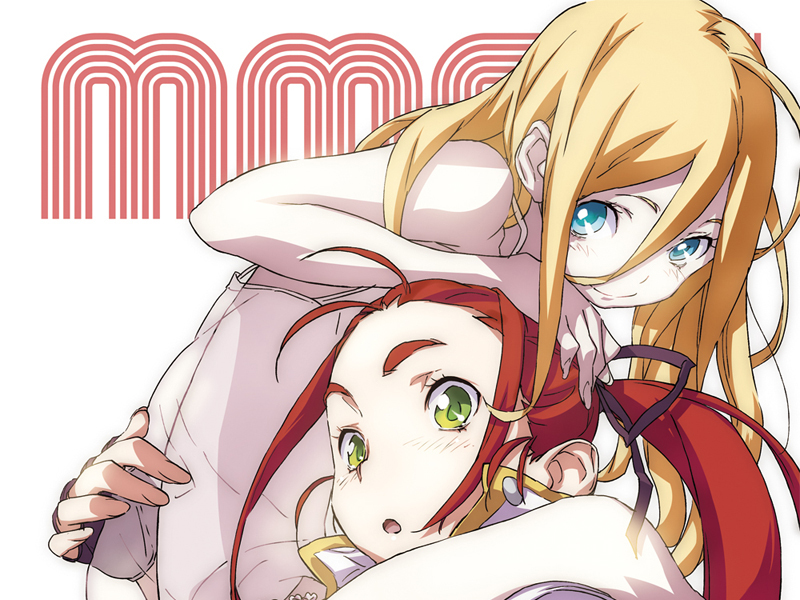学園の辺縁、ちょうど市街地の反対側に位置するドミトリは、世界各地からの留学生の受け入れを主たる目的として設立されたという。いまでは身寄りの無い子どもの世話なども行っており、ペルガナ市国の福祉面に大きく貢献している。ドミトリ所属のプロテジェたちは年齢を縦割りにしたいくつかのグループに分けられ、学習から生活に至るまで年長者が年少者の指導を行う、自主自律を促すシステムが取られている。これこそ、たったひとりの寮長で多くのプロテジェたちを管理できる所以と学外へは広報されているが、実際のところ、現実に不可避な人と人との摩擦を抜きにして発案されたその理想を無理やり実行させてきたのは、歴代寮長による、文字通り、字義通りの力技であった。
ドミトリ設立の趣意は、門扉の脇に苔むし、打ち捨てられた石碑にこう刻まれている。
『世ニ名ダヽル学園ノ智慧ヲ伝播シ、国家ト民族ノ垣根ヲ越エタ学祭的発展ノ礎ヲ創ルタメ、更ニハ、世代ヲ越エタ人類ノ共感ヲ涵養スルタメ、ヤガテ我ガ子ラノ輝ク叡智ガ現存スル全テノ偏見ト無知ヲ世カラ取リ除ク日ヲ祈念センガタメ、ココニ未ダ愚カサヲ止メエヌ我ラガ、人ノ善キ意志ノ集結トシテ未来ヘ遺スモノデアル』
まったくいつ読んでも、恥ずかしいほど大仰で高邁な内容だ。でも、たぶん、ドミトリの設立者たちは、この言葉を心の底から信じていたと思う。物事が始まるときには必ず存在する、何かに浮かされたような熱気を感じ取ることができるから。善意と希望で世界は必ず良くなると信じる者たちにしか持ちえない、最初に創るものたちの熱気、初源の熱気だ。
1を100にできる人たちはたくさんいる。でも、0を1にできる人は世界にそれほど多いわけじゃない。ほとんどのドミトリ組が気にも留めないこの小さな石碑の前に、グラン・ラングの研究へ人生を捧げようと決めた初心を忘れそうになったとき、ぼくは立ち止まる。ともすれば、最初にあった豊かさと熱気の残滓を、ただ享受するだけに陥ってしまう我が身を戒めるためだ。
ぼくはたぶん、何も信じていない。けれど、信じていないものがただ己の安定のためだけに最初の1を狭めることはあってはならないとも思う。
ふと、ボスの言葉が心に浮かぶ。
「おまえはさ、自分が早く結論を得て安心したいから、逆にグラン・ラングのほうを狭めてるんだよ。破綻しろよ。もっともっと、破綻するんだ」
全身が粟だって、体の芯が熱くなる。ときどき、意味もわからず聞いたきりになっていた言葉が、過去からぼくを追いかけてきて、ぼくをつかまえることがある。ボスがいてくれれば、きっといまの状況にも的確なアドバイスをくれただろう。
しかし、それはせんのない願望だ。ぼくは軽く頭をふると、石碑に背を向けた。
ドミトリの入り口すぐに受付を兼ねた宿直室として、寮長のささやかなプライベート空間が設けられている。一風変わった伝統に彩られた部屋で、じっさいに見たことが無い者への説明は、ちょっと難しい。
床には一種の枯れた草を格子状に編みこんだ長方形の板が数枚、パズルのようにはめられている。石や木の床と違って、わずかに押し返してくるような感触だ。椅子の無い丸テーブルが部屋の中央に置いてある他は、用途のわからぬ質素な家具(?)が数点のみで、さしこむ陽光にもほこりさえ見えない清潔さである。
何より、ここは匂いがいい。屋内なのに、ちょうど草原に寝そべっているときみたいな感じだ。異なる文化も、人にやさしいなら受け入れやすい。まあ、ぼくの知っている寮長は二人だけだから、もしかすると文化や伝統とかに寄らない、もっとドメスティックな何かである可能性を否定はできないけど。
テーブルを挟んで、小柄な少女がおし黙ったまま、持ち手の無いコップをのぞきこんでいる。これも変わった趣向だ。熱いものを飲むときはどうするのかな。
紺の生地を白い前かけがおおい、両肩には羽のような飾り。機能性とデザインが同居した清潔感のあるお仕着せだ。以前はお仕着せのデザインになんて気づきもしなかったが、ぼくの鈍感さというよりはむしろ、その言動において異様な存在感を見せつけた以前の寮長が悪いのだと思う。
少女は奇妙なことに、どう言えばいいのか、曲げた両脚の上に臀部を乗せた格好で固まっている。もしかすると、ぶしつけな問いかけに対する不平を表現するための示威行為かもしれないし、もっとビザールな文化的行動なのかもしれない。予測不可能性は、最も人を不安にさせる要素だと言うけれど、ぼくの不安感には一種の恐怖さえ伴っていた。なぜって、この少女は、以前の寮長の血を分けた娘なのだから。
沈黙によるプレッシャーが恐怖を肉体的なものに変えるほど長くなりかけたとき、
「『よかろう、我が血はこの地を守る。その代わりに、この地は我が血を守れ』」
芝居がかった調子で唐突に、少女は声高く郎じた。予想外の方向で緊張を外されたせいで、よっぽどおかしな顔をしたんだろう、ぼくを見てくすりと笑う。
「すいません、どうお話したものかわからなくて。我が家に代々、口伝されてきたお話ですわ。ぜんぶ、覚えてますの。絵本がわりに、何度も聞かされましたから。守り人を欲した大地の懇願に、当主が応えたのだそうです。その盟約は、グラン・ラングの力で末代の血にまで刻まれていると聞きました」
待て待て待て。これはすごい話だぞ。魂への付与(エンチャント)が時代を超えて維持(アップキープ)されているという実例じゃないか。すぐ近くに、ぼくの研究を飛躍的に進める可能性の原石が埋まっていただなんて! つくづく、フィールドワークの重要性を痛感させられる。ここ何日かで折られに折られ、すっかり低くなったぼくの鼻は、ここにまた、その高度を低くすることを余儀なくされたのであった。
「ずっとただのお話だと思っていました。わたしも、ここに来るまでは本当の意味で信じていたわけじゃなかった。でも、いまは違いますわ。この身体が、血に刻まれた盟約を思いだしましたから」
ぼくの視線をつかまえた少女の大きな瞳には、気圧されるほどの確信が満ちている。その清廉な汚れの無さに、不純さを見抜かれたと感じるとき、男ならば誰でも感じるだろうあの、一種のやましさがぼくを動揺させた。
しかしながら、いついかなる局面においても、内心の動揺を完璧に秘し隠してしまわなければメンターという生業はつとまらないのであった。研究者としての本性を男の本性に覆いかぶせると、ぼくはまっすぐにその瞳を見つめかえす。
「グラン・ラングは世界を記述する言語だとぼくは考えてきました。しかし、多くの研究者がそれはレトリックに過ぎず、古代人のレガシーに干渉するだけの限定的な効能のみを注視しています。いまのお話は、大きな自信になりました。今回の件が落ち着いたら、改めてお時間をいただけませんか」
不躾な申し出に、おそらく困惑のせいだろう、少女の頬が色味を帯びる。軽く持ち上げた人差し指に、うろたえて視線を泳がせる仕草が、なんだか年相応で、ひどくかわいらしく見えた。
「あの、わたし、メンター・ユウドのお役に立てるか、わかりません。ただわたしは、そうであることを知っているだけで、専門的なことは何も……」
あることを知る。それは究極の理解だ。専門的な知識だけは売るほど持ってるくせに、グラン・ラングがそんな使い方をされていたことをぼくは実感できない。短くはない学究生活をさらっと完全否定される言葉に、ぼくの鼻は今度こそ完全に消滅した。
古代人の伝承によるならば、人知の存在する以前から、グラン・ラングはあらかじめ世界に組みこまれていたのだという。それは人間の認識が世界を規定する前から、海や山や空がすでに名前や人格を備えていたということで、なんだか楽しい気持ちになる。
しかもそれが、万物を理解するための方便ではない、つまり説話や民話の類ではないというのだ。寮長の話が示しているのは、かつて世界そのものと対話が可能な誰かがいたということだから。しかし、耳をすませど、ぼくには何も聞こえてこない。貧しき我が身をかえりみて、なんだか悲しい気持ちになる。
「話を戻しますが、先のドミトリ襲撃を退けることができたのは、やはりその盟約が理由であると?」
二人がかりでようやく斬り伏せた怪人が、一人の少女に素手で打ち倒されるのを、ぼくとスウは間近で見てしまっていた。
「はい、そうだと思います。あのとき、全身を高揚が包んで、細胞の一つひとつが忘れていた何かを思い出す感じがしました。信じていただけないかもしれませんけど、わたし、これまでだれかを殴ったことなんてありません」
「信じますよ」
ぼくはあのとき、寮長の魂が白いまでに青く光輝するのを見た。間違いなく、ぼくの行う付与を数百倍、数千倍に拡大した現象が発生していたのだ。エネルギーの供給源は、おそらく大地そのもの。あふれる光の奔流は、ドミトリ全体を覆わんばかりだった。
「すべて、確信に変わりました。この地を守るために戦う限り、何を相手にまわそうとも――」
ぼくは、ほとんど威厳に満ちたとさえ言えるその声音にハッとさせられる。
「我が血が敗北することはありません」
いま話をしているのは、寮長ではない。少女の中にある血脈そのものだ。その背後には、眼前の少女を最突端とする長い長い時間の連なりがある。
不浄のものを寄せつけぬ凛とした微笑みに、研究者としての本性に男の本性がたちまち覆いかぶさり、ぼくは思わず視線を宙空へとさまよわせた。
「家事全般におよぶ有能さに加え、容姿の端麗は言うに及ばず、我らの寮長が実は不敗でもあっただなんて聞いたら、プロテジェたちはどんな顔をするだろうね」
やれやれ。やましさをごまかすために軽口を選ぶあたり、ぼくも成熟しない男だよな。
「メンター・ユウド」
曲げた両足の上に臀部を載せた姿勢から上半身を前傾にした寮長が、真剣なまなざしでぼくを見つめてくる。
「ひとつ、お願いがいあるのですが」
もしやこれは、求愛を意味する文化的行動なのだろうか。
いやいや、現実への予期にまで軽薄さが混じりはじめるのは、相当にうろたえてるぞ、ぼくは。きっと、寮長とその血族が負う業に対して、ぼくが配慮や敬意に欠けた発言をしたことへ、不快を感じたに違いない。
すぐに心からの謝罪を表明しなくてはならない。頭はいくら下げても、誰に下げても減らないというのが、ぼくの信条だ。
「寮長、というのはやめていただけないでしょうか」
「ごめん、さっきの発言は軽率だった。撤回するよ」
二人の発言は同時だった。おや。なんかズレてるな。テーブルの表面すれすれにまで勢いよく額を近づけてから、気づく。
「そ、そんなに深刻に受けとめられると、困ってしまいます。どうぞお直りください」
顔を上げると、寮長はもぞもぞと身体をくねらせて、困惑の態だ。曲げた脚部に乗せた臀部が重しになって(問題発言だ)、上半身だけをうねらせているのが面白くて、ぼくは思わず吹き出しそうになる。
「ずっと、違和感がございましたの」
わずかに染まった頬へ手のひらを当てながら、上目づかいにこちらを見る。己の魅力に気づかぬ乙女の発する無意識の媚びには、一種、抗しがたい魔力がある。
「メンターにご意見さしあげるのも無礼かと思いましたし、寮長としての職責を軽く考えていると思われるもイヤで、いままで黙っていましたけど、きょうはいい機会ですので、言わせていただきます」
ときどき忘れてしまうけど、この娘はぼくよりもずっと若いのだ。ほとんどプロテジェの続きみたいな気分で研究を続けてきたせいか、年齢の上下といった感覚が希薄なのだろう。学究生活にフラットな見かけは大切だけど、年かさの配慮までおしなべてフラットにふるまうのは、成熟を拒否するあまり、責任を放棄していることに他ならない。
奇矯な言動が研究の成果で相殺されるには、うちのボスくらい突き抜けないと無理だろうなあ。聞き慣れた哄笑がすぐ耳元で響いた気がして、ぼくはぶるっと身をふるわせた。
個人的に痛いところをつかれ、改めて姿勢を正して座り直す。
「メンターとしてプロテジェたちを指導する立場ではありますが、同時にぼくはドミトリの住人でもあります。寮長の申し出には最大限の敬意を払う用意があります。どうぞ、遠慮なくおっしゃってください」
慇懃な物言いが、小馬鹿にしているようには聞こえなかったか心配になる。
寮長は背筋を伸ばすと、おかしなくらい両肘を張った。
白くて細い首筋。
喉がかすかに上下する。
つばを飲みこんだのか。
わずかな逡巡の後、身を乗りだし決然と言ったのは――
「寮長ではなく、シシュ、と呼びすてにしてください。そうすれば、ずっと気が楽になりますわ」
一瞬、虚をつかれたようになり、まじまじと見つめかえしてしまう。
「わたし、いま、たぶん、おかしなこと、言ってますね?」
真顔のまま聞きかえす寮長。今度こそ耐えられなくなって、ぼくは声をあげて笑ってしまった。
「いや、そんなことはないよ」
「ああ、よかった!」
とたん、笑みくずれる。彼女がここに来て半年、初めて年相応の表情を見た気がする。
与えられた仕事への責任感と、受け継がれてきた盟約への自負心。そしてたぶん、プロテジェに混じっていつまでもドミトリに居座るおかしなメンターへの配慮がすべてまぜこぜになって、ぼくの見る寮長の雰囲気を作りだしていたのかもしれない。
そりゃあ、逆の立場だったら緊張するよな。もっと積極的に、こっちがほぐしてやるべきだったのに。きょう庭先の寮長をつかまえたのだって、結局のところ、学園を取り巻く異変について何か情報を引き出せないかと考えたからだ。いつだって我がことばかりの己に嫌気がさす。
「じゃあ、あらためて」
言いながら、右手をさしだす。
「よろしく、シシュ」
目を丸くした寮長は、少しためらってから、おずおずと両手で(文化的行動?)にぎりかえしてきた。その魂から青い光がこぼれるのが見え、ほんの軽く触れているようなのに、ぼくの骨はめりめりときしんだ。おお。これが、盟約の力ってやつか。寮長の前では、二度と軽口を叩くまい。
「なにかとふつつかな点も多いかと思いますが、今後ともよろしくお願いいたします」
いつにない動揺ぶりで、おかしな口上を述べたてる。いや、これが本当の彼女なのかもしれないな。緊張していたのか、小さな手のひらは汗でわずかに湿っていた。
メンター・ユウドよ、おまえの気のつかなさこそ永遠に呪われてあれ、だ。
空を見あげると、太陽はだいぶ高い位置にあった。思わぬ長居をしてしまった。そろそろ、午後の講義の準備をするべきだろうな。人類の未来を変革するだろう大研究も、日々の生業という一歩から始まるのだ。たぶん。
「おーい、そろそろいくよー」
ドミトリの前庭にある芝生で、横座りのスウとあぐらをかいたマアナが仲良く何ごとかに興じている。ママゴトかな? でも、スウが花をならべ、マアナが花弁を食いちぎって、茎だけ元へもどされる一連の作業が、家庭生活のどの場面を象徴しているのかは怖くて聞けないな。
「ああ、終わったんですか?」
かざした手をひさしにして、スウが見上げてくる。
「むしろ新しく始まったというべきだろうね」
シシュとの一件からか、なんだかやましい気持ちになってごまかしてしまう。別に、スウはモニター以上のなんでもないんだから、ごまかすことなんてないんだけど。
ぼくの内心を知ってか知らずか、スウはかすかに首をかしげて微笑むばかりだ。祖母のところから戻ってしばらくは、いつもこんなふうに元気がない。余計な詮索が生業のぼくだけれど、誰かの個人的な内面はその限りじゃない。
スウの祖母は、ペルガナ学園の評議員である。簡単に言えば、長時間の会議に参加する忍耐は試されないが、学園の運営には口を出せるという立場だ。
学園の黎明期、それは何世代もさかのぼる遠い昔のことになる。当時、七つの素封家が巨額の出資を行い、設立の基盤を作ったのだそうだ。うち二つはすでに血筋が絶えているが、残りの五つは数百年の時を越えてなお健在である。そして、ときどき学園の現状が気にいらず、クチバシをつっこんでくるというわけだ。この外部圧力に対する某メンターの抵抗と闘争については、長い上に相当疲れる話なので、いまは割愛したい。
「マアナは、どうしますか」
「そうだね。どうしようか」
悩める保護者の傍らで、齧歯類の如く頬を膨らませ、口いっぱいにつめこんだ花を咀嚼するのに必死のマアナ。やれやれ。いま噛みつく心配だけはないな。
けど、件の怪人がまた現れないとの保証はどこにもない。まあ、ドミトリにいれば確実に安全なことがわかったのは収穫だったけど、いつまでも部屋に閉じこめておくわけにもいかないしな。少しずつ、浮世の生活に慣らしてやる必要がある。もう、薔薇水晶の中へは戻れないんだから。もしかすると、自分の子どもを持つってのは、こんな感じなのかもしれない。
「よし、いっしょに連れていこう。年少組となら、ちょうど仲良くできるかもしれない。スウ・プロテジェには、講義の前にレジュメを複製する仕事をお願いできるかな。その間は、ぼくが面倒を見るから」
「はい、メンター・ユウド。わかりました」
柔らかな口調だった。むしろ弱々しい、と表現するべきか。言葉を受けとめるというより、言葉に流されるという感じで、奇妙なぐらいに意志を感じさせない。これも、スウが祖母の元を訪れたあとにいつも感じる変化だ。
何かあったの? そう聞いてやればとも思う。しかし、メンターにとってプロテジェとの関係は一時的なものだ。それは、常に自覚しておく必要がある。ぼくのような一部の横着者をのぞいて、いつかここを離れていく存在だ。自虐的に言うならば、ぼくが従事するのは無限にわきあがる夢と希望が、自分だけを取り残して去ってゆくのを見守る仕事である。
過去に一度、痛い目を見た。当時のぼくは、プロテジェ全員の苦しみを救済してやれると信じていたのだ。なんという傲慢だったのだろう。言葉にされなければ、いつか消えてしまう気持ちはある。グラン・ラングの研究者がそこに気づかなかったのだから、笑わせる。掘り起こして、言葉にさせて、途方に暮れる。結果、ひとりのプロテジェがこの手からすり抜けていった。
ぼくが得た教訓は、ひとりが本当に救えるのは人生でひとりだけ、ということ。それは相手にすべてを求める人間の、悲しい法則だ。もうあれを繰り返したくはない。いや、あるいは単にぼくがもう若くはなく、痛みを乗りこえる熱気が失われたというだけのことか。
ふと気がつけば、マアナが水晶のように無機質なまなざしで、ぼくを見あげていた。表情を失ったその顔は、まるで作り物のように恐ろしく端正だ。瞳の赤い虹彩が無限へと誘うようにゆらめく。ぼくの背中へ畏れにも似たおののきがはしる。
しかし、その決定的な異物感は、マアナの笑顔とともに消滅した。むきだしにした歯には、花弁がいっぱいにつまっている。
やれやれ。猫のように身をよじって逃げようとするのを後ろからつかまえて、抱きあげる。
「さあ、友だちのところへ連れていってあげるよ」
マアナは新棟へと向かう道すがらをひとしきり暴れたあと、やがて観念したのか両手足をだらんと伸ばして身体をあずけてきた。重い。
スウはと言えば、なんだかふわふわした足取りで後ろからついてくる。ぼくの肩にアゴを乗せたマアナは、スウの反応を得ようとして百面相ごっこを始めたようだ。平和といえば、これほど平和な見かけもないだろうけど。
だが、平穏極まる日常をどよもす暗雲は、突如として立ち込めるのが世の常である。機甲学科のメンターを進行方向に発見したぼくは、やおらスウの手をつかむと回れ右し、学園創設者の銅像のひとつへ身を隠す。
学科大移動からこちら、機甲学科のメンターたちは、なぜかぼくの姿を見かけると鼻息を荒らげて走ってくるようになった。かさかさと足元へ転がってきた紙くずを広げれば、凶悪な面相の誰かの似顔絵と、生死不問の文字、機甲学科長のサインが書かれている。ぼくは即座に元通り紙を丸めると、後ろへ放り投げた。
機甲学科が豹変を遂げた理由は、目下のところ全くの不明である。しかし、用心するに越したことはない。
「見つけたでえ」
「わあっ!」
背後から声をかけられ、ぼくはとびあがった。取り落としたマアナが尻餅をつき、剣呑な表情でうなり声(おそらくグラン・ラングの)を上げる。
潅木の陰から染み出すように姿を現したのは、キブだった。
もはや隠しようのない大騒ぎに覚悟を決めて振り返るが、機甲学科のメンターはすでにいずこかへ姿を消した後だった。胸をなで下ろすと同時に、キブへの怒りがわく。
「おどかすなよ!」
「いまのあわてぶりを見ると、確認するまでもなく事の真偽は明らかやな」
腕組みをしながら、したり顔だ。
「なんのことだよ」
ぼくは憮然と尋ねる。
「先の学科大移動で、機甲学科の備品が重大な損壊を被ったらしいな。よくよく聞けば、言語学科の某メンターが裏で暗躍してたそうやないか」
「ああ、何かと思えばそんなことか」
ぼくは瞬間、自分でもわかるぐらい無表情になった。
「君は親友だから、正直に言うよ。じつは偶然、何と言えばいいか、そう、自然現象。自然現象が機甲学科の備品を破壊する場面に居あわせたんだ。本当にあれは、不幸な事故だったよ」
「グラン・ラングの暴走、と聞いとるで」
ぼくは不自然なほどさわやかな笑顔をつくって、キブの両肩をつかむ。
「いいかい、だれが吹きこんだか知らないが、それはまったくの素人考えだね。グラン・ラングは平等かつ公正な言語だ。だれが発したとしても、同じ音素ならば同じ結果をしかもたらさない。つまり、発話する者の意図を越えて、気まぐれに暴走したりはしない。まさか、あの瞬間にあの場所で、局所的な竜巻が発生するなんて、だれにも予想できないよ」
そう、グラン・ラングは決して暴走しない。言いながら、抱えていた疑惑がぼく自身の言葉によって裏づけられてしまったのを知る。ならばなぜあのとき、グラン・ラングは暴走したのか。
キブはぼくの手をつかんで、もぎはなした。
「ええい、これで貸りは返したということやな」
「言っている意味はよくわからないが了解した」
うなり声をあげるマアナと、その歯頚から花弁を一枚一枚とりのぞいてやっているスウの傍らで、ぼくとキブは固い握手をかわした。
気がつけば、もはや太陽は頭上に輝いている。午後の講義まで、もうそれほど時間は残っていない。
「じゃあ、お互いの知る案件については、一切の他言無用ということで」
マアナの手を引いたスウの手を、水鳥の親子のごとく、ぼくが引いて歩きだそうとする。
「待て待て、どこ行くねん」
「どこって、講義に決まってるじゃないか」
「伝わってへんのかいな。ついさっき、緊急の学科長会議が招集されたで」
思わず、深いため息が出た。
「ごめん、他のプロテジェたちに休講の連絡をお願いできるかな」
「わかりました」
弱々しい返答が気になるけど、いまはしょうがない。微笑んだまま立ち尽くすスウと、無邪気に手を振るマアナに見送られながら、ぼくはキブとともに、議場へと重い足取りの我が身を曳いてゆくのだった。
ぼくが来ないとわかったとき、年少組のシャイが見せるだろう、がっかりした表情が一瞬、頭に浮かんだ。
なんだかずいぶん長いあいだ、プロテジェたちの顔を見ていない気がするな。
「講義の途中だった」
腕組みをしたまま、苦々しげにスリッドがつぶやく。あとから入ってきたので、いつもの席ではなく、ぼくの隣に座ったのである。
ぼくは両手で顔を隠しながら、うめくような生返事をした。機甲学科のメンターが、はすかいから凶悪な目でこちらをにらんでいるのが気になって仕方なかったからだ。
きっと、スリッドが常の如く会議を紛糾させるのを事前に抑止しようと努めてのことだろう。そうに違いない。そうであって欲しい。
「我々は研究機関であると同時に、教育機関だ。正規のものをしのぐばかりの回数で突然に招集される臨時の会議は、プロテジェたちの不利益につながる。もしこれが学園の運営上、本当に必要なものだと仮定すれば、年度当初に計画された学科長会議の数が妥当でないということだ」
「そうかもしれないね」
ぼくはあいまいに語尾をにごす。スリッドの意見には同意できる部分もないことはない。でも、その論旨の明晰さにぼくはなぜか違和感を持つ。それを的確に表現する言葉がいつも見つからない。もしかすると、己の優柔不断さを言外に指弾されている気持ちになるからかもしれない。苦手意識を持つべきではないと思うけど、スリッドといるときの自己嫌悪の感じはなんとも言いようがない。
「もっとも、私は議長団の議事進行にある致命的な欠陥を無くしさえすれば、大幅に会議の数は減らせると考えているのだが」
二段構えの言論トラップだったか。あやうく一段目で全面的な賛意を示すところだった。
キブは何の関係もない、といったすまし顔で宙を見つめている。しかし、内心はぼくとスリッドとのやりとりに興味津々なのだ。ときどき小鼻がわずかにふくらむのを見れば、何を考えているかはあきらかである。
やがて、学園長とブラウン・ハットの長官を先頭にして、ぞろぞろと首脳陣が入室してくる。スリッドが背を伸ばし、わずかに身を乗りだすのがわかった。臨戦態勢、ってわけだ。学園長が口火を切る。
「突然の召集にとまどわれた方も多いでしょう。ご批判はのちほど承ります」
スリッドの方へ視線を走らせながら、両手をあげる。機先を制せられ、鼻白む気配が隣から伝わってきた。学園長の言葉は、いつも絶妙な間合いでもって、すりぬけるようにして届く。どれほどの激論や騒然とした場であっても、その発言が聞き落とされることはない。
「まずは行政庁からの報告をお願いします」
「えー、それでは」
うながされた長官は、一枚の書面を片手に、眼鏡のつるに中指をあてて立ちあがる。読みあげる直前に、ある人物と視線を交わす。体技科長がわずかにうなづくのを、ぼくは見逃さなかった。
「黒い森と市国をむすぶ中立緩衝地域に、大量の流民が発生しました。今朝の段階で体技科所属のメンターが確認した数は、およそ数千から一万。現在、ゆっくりと市国へ向けて南下しており、交渉をふくめた何らかの対応が必要かと思われます」
すかさず、スリッドが挙手する。
「流民とは、政治的な欺瞞に満ちた表現ではないか。我々に何を伝えることを忌避しての発言か、お答えいただきたい」
「現在のところ、充分な情報が得られていません。無論、紛争等による避難民の可能性を排除しませんが、各国の大使から届く伝令には時間差がありますので」
スリッドの発言に許可を得たと思ったのか、列席するメンターたちが次々と疑問を口にしはじめる。
「海上から侵入したんじゃないのか」
「まさか。それだけの人数が収容可能な船団を維持できるのは、国家規模の組織だぞ」
「まちがいなく街道を通ったはずだ。やぐらの連中は何をしていたんだ」
黒い森を迂回するように、半島の海岸線を沿って二本の街道が走る。やぐらとは、森の尽きるあたりに立てられた監視塔のことだ。
ブラウン・ハットの長官は、再び書面に目を落とした。
「定期の乗合馬車と荷馬車以外の通行は確認されていません」
「不審な通行者へ誰何を与える権利すらない仕事だ。居眠りでもして、見過ごしたんだろう。伝統の機能不全というやつだ」
険しい表情のスリッドが、吐き捨てるように言う。
しかし、一万近くの人間が通り過ぎるのに気づかないなんてことが、はたしてありえるだろうか。単なる見落としでないとすれば、考えられる可能性は二つ。昼なお暗く下生えの複雑に生い茂る魔物の巣、黒い森を踏破したか――
あるいは、黒い森と市国をむすぶ中間地点へ一万という人間が突然、虚空から出現したかである。
極めて空想的なこの考えを口にすることは、はばかられた。心のどこかで己の直感を信じていたにも関わらず、スリッドが醸成する理性の空気にぼくは発言を制止されたのだった。
「うちの若いのがひとり、帰ってこねえ」
腕組みをしたまま、体技科長が低くつぶやく。
「どうにもイヤな予感がする」
さざ波が凪いだ水面へと還るように、場が静まる。スリッドの見解はおくとして、体技科長は会議で長々と発言をするタイプではない。人は言葉の中にではなく行動の中にある、という格言を地のまま体現するメンターだ。ゆえに、その発言はいつも重い意味をもって皆に受けとめられる。
「体技科から要請する。市国民の避難に備え、船舶の徴発を検討いただきたい」
「その動議、支持するで」
老人性のなにかにぷるぷるとふるえる挙手は、なんと史学科長のものだ。干したように小さな顔へ刻まれた皺と垂れたまぶたは、その表情を読むことを極めて難しくしている。レジュメを読みあげる以外の声をはじめて聞いたぞ。目をまん丸くしたキブが、ぼくのほうを見る。どうやら、同じ感想らしい。
「行政庁の職員も、状況が明らかになるまで学園へ退避させたほうがええな。あの老朽化した文化遺産では、用心が悪すぎるわ」
「異議ありッ!」
スリッドが裂帛の気合いとともに手を挙げる。ほとんど剣術や格闘技のようだ。
「一時的にせよ、商家や漁夫から生活の具を取り上げ、かつ、暮らしと直結する行政の任を空席にせよという軽々の提案には耳を疑うばかりである。政策の決定にあって、まず主観的な憶測や怯懦に流されてはならぬことは、私ぐらいがご指導申しあげるまでもなかろう。流民とやらの正体を確認することがまず先決ではないか」
正論だ。しかし、学園長をはじめとする首脳陣が、知りえた情報をいますべてここに開示しているだろうか。学園の意志決定は事実上、学科長会議においてしか行われず、この会議はあまりに公正に誰へとも開かれすぎている。推測や憶測が排除され、言葉にできぬ経験則よりも客観的な事実が優先される。それは知的に極めて正しい場所のように思えるが――
「学園長はどうお考えなのか、我々にお聞かせいただきたい」
我々、という言葉で発言が無い者たちをすべて自分の側に引き入れ、彼と我という明確な対立軸を仮想する。それがスリッドの戦術だ。しかし、会議室では誰も死なない。勝利だけが強調され、敗北は無化される。
「こうして臨時の会議にお集まりいただいたことが、ご質問へのお答えになるかと思います」
やんわりと学園長がいなす。この白髭の老人は、いつも婉曲的な表現を駆使して言質を与えない。
スリッドが絶叫する。
「『学園長は国王』ですかッ!」
使い古された慣用句だ。ブラウン・ハットが政策を実行する段階での問題点や新たな施策のほとんどは、まず学園の政治学科に原案の作成が依頼される。学科長会議での可決をもって、その政策は行政官が運用する実体としてブラウン・ハットへ渡る。そして、学科長会議の決裁権は学園長が持つ。
つまり、学科長会議が学園長の諮問機関という位置づけである以上、理論上は学園長がペルガナ市国のすべてを独裁的に差配することが可能なのだ。現実は迅速な決定からはほど遠いのだが、戒めというより、意にそまぬ案件への攻撃としてよく用いられる表現だ。
「私の提案を、体技科と史学科からの動議に対する修正案として提示する。国王が決裁なさる前に、我々の民意を汲むべく採決をいただきたい」
困りはてた議長が、学園長とスリッドの顔を交互にながめる。体技科長は腕組みをしたまま、じっと動かない。
しばらく沈黙が続いたあと、学園長がゆっくりと口を開いた。
「メンター・スリッドの修正案を承認します。議事を進行してください」
ざわめきの中、紙片が配られる。メンターたちは肘でつつきあい、どちらに票を入れたものか低い声で話しあっている。スリッドは腕を組んだまま傲然と胸をそらし、周囲が彼に向けるさまざまなささやきを受け止めている。大したヤツだ。
紙片を受けとるとき、体技科長がぼくをじっと見つめているのがわかった。ぼくを非難するようなものが視線に込められている気がして、思わず目をそらしてしまう。
たぶん、体技科長とぼくの抱える疑念は、お互いにかなり近いものだ。しかし、提示された動議への賛意を示すためにぼくが言える言葉は、あまりにもこの議場では荒唐無稽に響いてしまうに違いない。
無限へとつながる少女と、神出鬼没の異形たち。
そして、学園へ向けて南下する正体不明の群れ。
わずか数票の差でスリッドの修正案が可決される。状況が明確になり次第、次の会議が招集される旨が告げられ、散会となった。
誰もスリッドを責められまい。そのときの彼は、論理的には完全に正しかったのだから。
体技科の若いメンターが重傷を負って帰還し、まるで時を追って増え続けたかのように、報告される流民の数は二万を越えた。
再び招集された学科長会議の資料において、流民たちの特徴は次のように記述された。
「赤い髪、青い眼、尖った耳、そして大きく造作された顔のパーツは、まるで人を戯画するようである。そして、個体間の見分けが困難なほど似かよっている。近隣の諸国で同一の特徴を持った人種を発見することはできない」
この会議で、スリッドの発言はなかった。
ペルガナ学園は、二日間を完全に空費したのである。