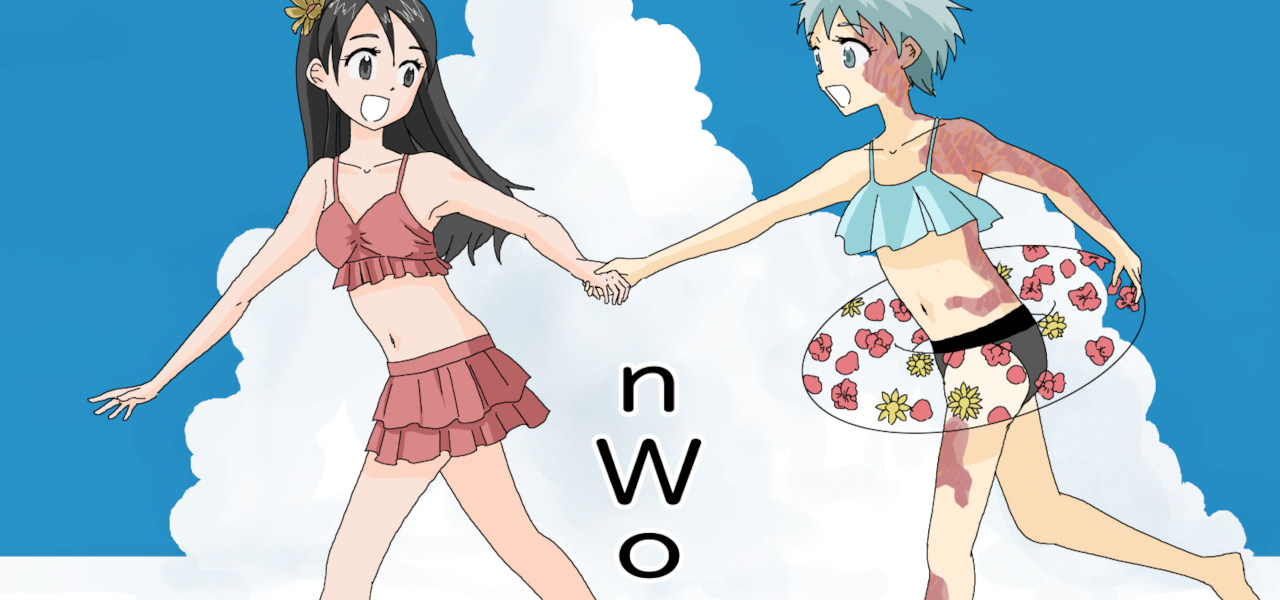ドッグヴィル

恩を仇で返す輩は、皆殺しだ! 西洋版「鶴の恩返し」という視点で見ると楽しい。私の中の何分の一かは、これの完結編のために生きてます。
月: 2007年7月
アバウト・シュミット
アバウト・シュミット

ジャック・ニコルソンの軌跡。あまりに有名な”It was shining.”の猟奇的笑顔と、この映画のラストシーンの笑顔を見比べたときに訪れる感慨は、ちょっと言葉にしにくい。
少女保護特区(4)
神の摂理とは人の摂理である。人の本質を否定するもの、そこへ疑問符を投げるものが悪と呼ばれてきた。しかし、人の存続を許さぬものが人より生まれ出づるのなら、それはいったい何と呼ばれるべきだろうか。
汚れた熊の人形を地面に引きずり、夜の街路へ身長を数倍する影を残しながら、一人の女児が歩いている。少女と形容するには、まだいくぶん幼い。街灯の投げる円錐の中へ立ち入ると、女児は立ち止まる。その顔は遠目にわかるほどの青痣を残し、鼻血の跡が両頬へ隈取りのように茶色く凝固している。爪のない素足は泥にまみれ、人形の破れた表面からは中身の綿が飛び出している。女児はほとんど自失しているようだったが、電球へ衝突を繰り返す一匹の蛾を見上げるうち、その瞳は次第に正気を宿し始める。口元がへの字に曲がり、表情は大きく歪む。しかし、にじむ涙がこぼれぬうちに手の甲でぬぐってしまうと、女児は再び歩き始める。
建て売りの住居が建ち並ぶ夜の住宅街は、どこまで歩いても表情を変えず、まるで終わりのない迷路のようだ。幾度も道を折れるが、どこかにたどり着く様子はない。爪のない素足が運ぶ一歩先だけを見つめていた女児は、何かの気配にうながされて顔を上げる。視線の先にあるのは、向かい合う住宅の狭間に長々と身を横たえた巨大な黒い固まりである。近くに街灯は無く、家々は雨戸を閉め切り、雲間からのぞく月明かりだけが照らす夜の底に、夜の黒より深い黒がその輪郭を際だたせている。かすかに上下する曲線は、それが生きていることを伝えている。二本の筋が曲線の囲む内側に生じ、やがて二つの球形へと転じる。大人たちよりもはるかに鮮烈で曖昧な女児の心に去来するのは、両親が手を振り上げるときの恐ろしい表情と――私を叱るときだけ二人は仲が良いのだと、いつも思う――図書館にある外国の絵本に描かれた、モノクロの深い森である。女児の両親はおそらく、自分たちが娘にしてきたことすべてを忘れたふうに、突きつけられるマイクの列を前に泣くだろう。記者会見で泣き、誰もいないリビングでさえ観客を意識して泣き、そして一定期間は娘のために心を痛めて泣いたのだという事実に、すっかり赦されてしまうに違いない。女児が抱いていた、数年の後には顕在化しただろう漠然としたある気分、自己抑制の外で行われる不条理への負の感情はついに言語化されないまま――この世界のどこにも残されないまま、消滅することになる。
言語を持たぬ者が力によって圧殺されることだけが、絶望と形容するに足る。千年の視座を持つ予は、鼓膜へわずかに振動を残すだけの時の泡沫には何ら痛手を受けることは無かったし、何より自身を言語化する以前に死を与えられることはなかった。無論、言語化した結果を十全の形で凡人に受容させることは極めて困難である。言語化しきれなかった、あるいは言語化したものを受け止めきれなかった余分は、身体の奥深くへ蜂の一刺しのように残り、その規模の小ささゆえに誰にも原因として指摘されることなく、ついには発症へと至る。しかし、大人たちは破局を回避する準備期間を十分に長く与えられているがゆえに、彼らが直面する事態は絶望というより危機と表現されるべきである。人類はいわばこの、精神の危機と幾千年に渡って格闘し続けてきている。然るべき観察と実行を怠りさえしなければ、救済への道はほとんどマニュアル化されていると断言してよい。だからこそ、鳥や動物や樹々や大地や、声を持たぬ子どもがこの世から消滅することだけが真に絶望と呼べるのである。
夜の街路に対峙したのは、誰も気づかぬ社会の毒素を蓄積させて真っ先に死ぬ存在とそれを吸い込むことで肥大化してゆく存在との象徴であり、両者は対極にして同一であった。
熊の人形がアスファルトの上に落ちる。続いて、女児の右手が熊の上に落ちる。女児と熊の手はしっかりとつなぎあわされたままだ。人形が見上げる先に、両脚をつなぐ腰骨の中央から白い棒状の何かをわずか屹立させたオブジェがある。奇怪なその外観は、極めて前衛的な芸術作品と呼べないこともない。女児が最後に見たのは黄色い乱杭歯と、濡れた赤の奥に広がる黒い虚無だった。
辺りに濃密な鉄錆の匂いがたちこめる。咀嚼音と液体のはねる音が夜の街路に響き、息を潜めたような静寂が惨劇を取り巻く。黒い固まりは皮膜に包まれた液体のようにゆっくりと、縦に長く変形する。濁った重低音が長く鳴り満足げな吐息が続くと、大気は腐乱した肉の臭気に満たされた。
雲が去り、月は地を照らす。
一糸まとわぬ巨大な女が、指に付着した液体を舐めている。家々の屋根を真上から睥睨する全長をもってして、それはなお女だった。膝にまで達する両腕を除けば、身体を描く曲線は未だ性徴を際だたせず、ほとんど少女にさえ見える。だが、全身を覆う肌は奇蹄目犀科に属するほ乳類のように硬質化している。
認可番号AA00001――仁科望美。青少年育成特区最初の少女殺人者。
彼女は同じ性別のものを好んで食餌とする。若い雌へ潜在的に抱く生物学的優劣に根ざした脅威が、顕在化した死との狭間に名状し難い何かを受胎させ、我々にとっては未知のその衝動が同類たちを殺戮の対象として選択させるのであろう。異様に長く発達した前腕で獲物の両足をすばやく押さえつけ、丸かじりに頭部へ食らいつく。そして、柔らかな腹部から背骨の周囲に付着した肉ごと上半身をこそげとるのである。奇しくも先ほどの獲物のように幼かった頃、彼女が愛好した棒付きアイスを食べるときと同じやり方だった。芸術を意図してというより、過って子宮や精巣を食ってしまわぬためである。それらを食餌とすることは、初潮の訪れを早めてしまうと彼女は強く信じている。実のところ仁科望美の最初の血と澱は、十数年の歳月を経て未だ彼女の体内に万力のような筋肉で閉じこめられているに過ぎない。しかしこの不条理に外部との連絡や整合性を求めることは、全く意味が無い。信念とは、時にこのような形をとるものである。
予は仁科望美の両目を正面からのぞきこんでなお命を残すという僥倖を得た、数少ない一人である。その両目は頭蓋の眼窩に張り付いた目蓋のせいで、常に眼球本来の球形で見開かれている。金縛りのようなあの数瞬、一秒を数百に分解したその時間は、彼女の身体能力を考慮するならば予を数回は殺すのに十分な長さだった。最初に感じたのは、喉元に溜まった嘔吐である。予に向けられた表情は、確かに微笑みであったと記憶する。もはや唇と呼べぬほど削れた肉の内側へ常にのぞく乱杭歯には、彼女が咀嚼した人体の滓がこびりついているのが見えた。いまなお、彼女の精神は我々の延長線上にあるのだという理解が予に吐き気をもよおさせた。予と同じ経験をするものは、例え明確に言語化できぬにせよ、同じ感慨を抱くはずである。彼女は、蝦や蟹のような甲殻類の感性を世界に対して構築していた。そして、一個の人間が世界に対して甲殻類のような感性を構築し得るという深淵が、見る者の心胆を寒からしめるのである。仁科望美は依然として、人間なのだ。
いつ彼女がその闇を心に抱いたのか、当局の記録は何も伝えない。役所努めの父親と教員の母親と二つ年上の兄と過ごした十四年間は、決して波乱に富んでいるとは言えない。しかし、少女が最初の合法的な殺人を犯したその日、平穏は終わりを迎えた。一家は、少女殺人者を身内に持ってしまった場合の典型的な転落を歩んでいる。迫害、転居、離散。予が追うことができたのは、そこまでだ。無数にある家々の内側で本当は何が起きているのかを知ることは、部外者へほとんど禁じられている。仁科望美の生家を訪れたが、取りつぶされて更地になっていた。漫画のような土管の上で、二人の子どもが背中合わせに携帯ゲームで遊んでいる。予は眩しさに目を細める。陽光は世界を漂白し、すべては色を失う。
伸ばした腕の先が見えないほどの闇の中で、ただ草いきれのみが山中にあることを予に告げている。夜の底に訪れる覚醒と続く混乱を、予は樹上から見てとった。仁科望美は腹の減っていない際に、獲物を生きたままねぐらへと連れ帰り、空腹が理性を凌駕するまでその恐怖を弄ぶことがあった。法を超えれば、法の庇護を失う。法を超えた者同士の間にあるのは、生き残った方がその正当性を主張できるという、戦争以前の純然たる暴力だけだ。特区法の理念は少女を異性から完全に隔離したが、少女を少女自身という脅威から保護することはかなわなかったのである。切りそろえられた前髪に顔の半ばまでを隠した少女は、後ろ手に折りたたみ式ナイフを取り出す。刃は仁科望美の爪の先ほども無く、人の崇高と滑稽がそこへ同時に表現されるかのようである。猫が毛玉を弄ぶ仕草の軽い平手で、少女を引き倒しては立ち上がらせる。獣は嬲らない。仁科望美がある種の遊戯として行為を楽しんでいることは傍目に明らかであり、この陰惨な宴の中にあってそれが逆に彼女の人間を証明していると言えた。巨大な掌をかいくぐり、少女は怪物のふくらはぎへナイフを突き立てることに成功する。だが、刃は柄を支点にして直角に折れ曲がっただけである。仁科望美は、あくびに似た動作をした。口腔からはき出される音波が樹々を激しくゆらす。少女はたまらずナイフを取り落とし、両手で外耳を覆った。ゆっくりと持ち上げられた巨大な右手が親指と人差し指の輪を形作る。丸太のような人差し指が恐るべき速度ではじき出され、少女の顎先を通過する。小さな顔が重力方向にぐるりと一回転すると、元通りの位置に静止した。口から蟹を思わせる泡が赤く吹き、少女は糸の切れたように倒れ伏す。仁科望美は立ち上がることのできなくなった獲物の腹部へ足をかけ、羽毛のようにそっと体重をのせる。たちまち少女は二つの肉に分かたれ、人であることをやめた。
仁科望美が立ち去ってから、優に二時間は樹上で待機したろう。好奇はしきりと予を促したが、予の生来である用心が行動を妨げたのである。生きているものと死んでいるものは、どうしてこんなにも違うのか。少女の口からは、何か赤黒いものが飛び出していた。目深に垂れた前髪がその両目を隠していたことは、予にとって幸いだった。死体と暗闇を共にする恐怖は極めて根源的であったが、何より一種の使命感に促され、予はそれの首からぶらさげられていたAvenger Licenseを接収せしめる。当局へ連絡する義務を果たすために携帯電話を取り出すが、電波状況は圏外を告げる。ふと気がつけば、いつの間にか固く閉ざされた鉄扉が眼前にそびえていた。視線を上げると、そこに仁科望美がいる。鉄扉と見えていたものは、女性の巨大な秘所であった。予は彼女の両目をのぞきこみ、彼女は予の両目をのぞきこんだ。その首が傾き、暗闇に浮かぶ二つの円形が半円に細められる。この怪物はすべてを了解していたのである。髪の毛が太くなり、予は爆発的に駆けだした。木々の枝が予を傷つけるのにも構わず、夜の山中をほとんど転がるように走る。仁科望美は予のすぐ背後まで迫り、口腔から荒々しく押し出される呼気が大気を揺らすあらゆる瞬間に、予の生命を刺し貫くかと思われた。地面にアスファルトの固さを感じたとき、予の足はようやく動きを止める。遠くからヘッドライトが迫ってくるのが見え、その接近にあわせるように背後にあった気配は次第に消滅した。予の威武をもって逃げおおせたとは言わない。ただ、食欲と嗜虐を満たされた後に諧謔を与えられ、彼女の精神はその晩、完全に満足していたに過ぎないのである。
動物たちの行動は特定の環境に対して特化しているものである。人間たちの行動は特殊化を指向する一定期間を過ぎると、普遍化へと向かう。世界の宗教を見ても顕著であるが、特定の環境や状況を前提としない行動、思考様式へ傾倒してゆくのである。生存を追求する上ではなはだ有効ではない全体性への指向が人間存在の本質に組み込まれており、それが人間を他の動物たちと峻別する唯一の要素であるのかも知れぬ。善にして全なる場所へ向け、背中から落下してゆく。ゆえに来し方は眼前へ遠ざかり、行く先は見えない。落ちるにつれて種々の執着や魂の輪郭が溶解してゆく放埒に包まれて、誰かの魂を傷つけ汚さなければ他の数十億から私を私と名指しすることはできない。仁科望美はいつもするように、左胸へ爪を立てた。私という名前の孤絶へ永遠に留まり続けるため、彼女が魂の所在と信じる左の乳房の上に強く爪を立てた。しかし、長い繰り返しの果てに堅くなった皮膚には、わずかも爪を食い込ませることはできなかった。この怪物は安息を得たいのか。安息とは全であり、彼女の願いは個である。両者は遠く矛盾し、何よりすでに殺しすぎている。孤絶が溶解することに気がつけないまま死ぬことが、地獄へ落ちるということだ。
膝を抱えてうずくまっていた仁科望美が顔を上げる。生存に特化した野生動物の本能のみが可能な、五感を超えた鋭敏さで自身の存続に対する脅威を感じ取ったのである。この破格の怪物を脅かす何かが地上へいったい存在し得るというのか。法から庇護されると同時に、単純に物理的な影響力で法そのものをさえ凌駕する最初の少女。彼女に対抗することが可能な実存を人類の叡智が仮定できるとするならばそれは、これまで地上に存在しなかった何かがこの瞬間、新たに生まれ出たことを意味している。
夜空へ向けて低くうなり声を上げていた仁科望美が、腰を深く落とした。まるで大地そのものと交接したがっているかのようだ。大腿筋がよじれ鋼鉄の如く硬化し、恐るべき力がそこへ漲ってゆく。仁科望美の足下はすり鉢状にへこみ、彼女の周囲だけ重力の仕技はその法則を変える。大気はゆっくりと渦を巻きはじめ、すり鉢の中心へ向けて収束してゆく。
次瞬、仁科望美の身体が消失する。山の稜線を形成する木々の間から恐ろしい数の鳥たちがいっせいに飛び立ち、近くの地震観測所は人が体感できるほどの揺れを記録した。逃げまどう鳥たちの群れを突き切り、黒い固まりが宙空を渡る。その巨躯が黄色い満月を横切る瞬間、この世を照らすすべての光は遮られ、ただ漆黒の闇が支配した。
予の少女と仁科望美との邂逅は、青少年育成特区が成立する基盤そのものへ決定的な影響を及ぼすことになるのだが、それはまだ少し先の話である。
永遠の命を疑えないものだけが、自らの始末を躊躇しない
事実に盲目であろうとする姿勢――より正確には養育者への憎悪に起因する混乱と不安が本来の対象を違えて照射されるとき、その転移を余人が芸術と名付ける実例は歴史上、枚挙に暇がない。音楽のみを真の芸術とするあの言説は、作曲家の傲慢ではなく、誰もが多かれ少なかれ持つこの地上の穢れの影響を受けにくいからである。
文学や絵画を構成する負の感情は、本来の原因とは別のところに成立するため、どこまで追及しようとも解けないという一点において、しかし不可解の深みを得る。そして通底する不全の基調は、誰もが味わったことがあるゆえに共有可能な体験となり、理解できないにもかかわらず一種の普遍性を持つという逆説的な結果を生むのである。
この仕組みを理解したとき、私はまず文字が読めなくなった。生きるものの書く文字は、あらかじめすべて汚されている。
我々は背に負った憎悪の根源に気づかぬまま、不全の解決を探し求める虚しい放浪を止められない。それは青い鳥以上の皮肉であり、地獄である。ただ、首を回しさえすれば、答えはそこにあるというのに。解答を探し求めるその過程こそが人生だという言葉は、真実から逃避した欺瞞である。根源を直視し、その先を見たからこそ私は言うのだ。
おい、知っているか。命の大半を占めた執着が消えた向こう側に何があるのかを。そこには上下も左右もない白い空間がある。自分の輪郭だけが唯一の、莫大な白い広がりがある。私はいまにも狂いそうだ。それを証拠に、この告解は私の心にさざ波ひとつ起こさない。