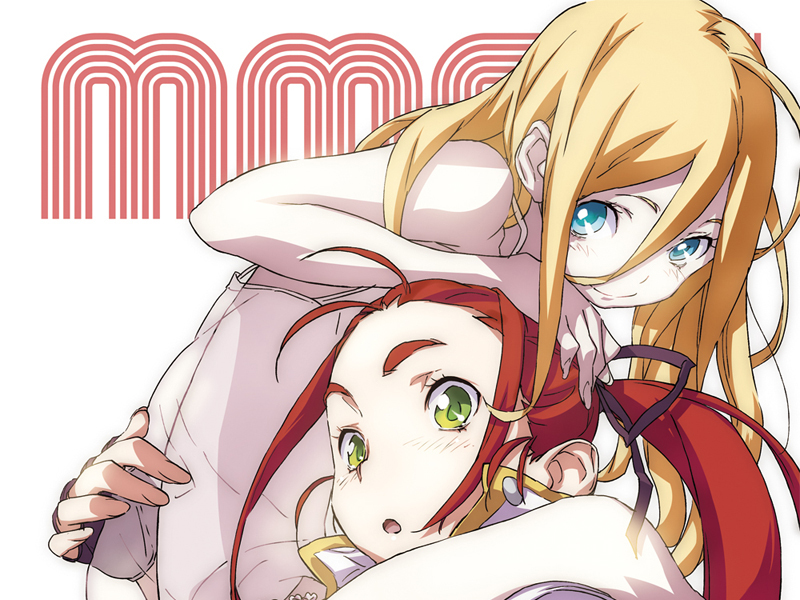*はじめに
今回の更新は「五十六万ヒット御礼小鳥猊下基調講演」での声明を元に書かれた、「少女保護特区(5)」のリライトバージョンです。ご要望やご不快に思われる点がございましたら、ただちに改変いたしますので、遠慮なくおっしゃってください。
最後に、これまでみなさまの味わわれた心痛に対して、nWoスタッフ一同、心から謝罪いたします。本当に、申し訳ありませんでした。
「あ……」
さくら色のくちびるから吐息のような声をもらして、少女が目をあける。
ほおにはひとすじ、涙のあと。
どうやら、かなしい夢をみていたようだ。
ぼくは親指でやさしくほおをぬぐってやる。マシュマロのようなやわらかさが、おしかえしてきた。
さりげなく、はだけた両脚にスカートをおろしてやりながら、そっとたずねる。
「夢を見ていたの?」
ぼんやりとみひらかれた少女の瞳に、焦点がもどってくる。
「こわい夢をみていたの」
安堵の表情が、ふたつの泉に満たされてゆく。
「ヨくんがいなくなってしまう夢……あたし、ヨくんがいなくなったら、きっと胸がさけて死んでしまうわ」
ぼくはほほえみながら、少女のひたいをかるくこづく。
「そんなこと、口にするもんじゃないよ」
「だって、ほんとうにそう思ったんですもの」
少女は心外だ、とばかりに口をとがらせる。
「言葉にしたことは、本当になってしまうからね」
感じやすい瞳が、みるみるうちにうるんでゆく。
「あたし、もうぜったい言わないわ。だってほんとうにこわかったんですもの……」
しゅんとして、肩をおとす少女。
お灸がききすぎたかな、とぼくはすこし後悔する。
「だいじょうぶだよ、ムンドゥングゥ。ぼくはずっときみのそばにいるから」
「ほんと? ぜったいぜったい、ほんとうに?」
ムンドゥングゥが目をかがやかせる。
「ああ、ほんとうだよ。ぜったいぜったい、ほんとうだ」
この先、どうなってしまうかなんて、だれにもわからないけど――
いまの言葉だけは、ほんとうだ。
「ねえ、ヨくん」
安心したのか、ムンドゥングゥがあまえた声をだす。
「ひとつおねがいがあるの」
うわめづかいにみつめてくる少女に、ぼくはうろたえてしまう。
「ぎゅーってして、いい?」
だきつきたいとき、いつもこうやってきいてくるのだ。
なによりぼくの心臓のために、いつもははぐらかすんだけど――
「いいよ」
罪ほろぼしをしたいような気持ちになって、うなずく。
ムンドゥングゥはおそるおそる、といったようすでぼくの背中に両手をまわした。
最初は、天使のようにかるく。
それから、息がくるしくなるほどきつく。
「ち、ちょっと、苦しいよ、ムンドゥングゥ」
「だって、まだ夢がさめてなかったらどうしようと思って」
ムンドゥングゥが、ぼくのシャツにうずめた顔をあげる。
あんまりつよく顔をおしつけすぎたのか、ほおにボタンのあとがついている。
ぼくは思わず苦笑してしまう。
そこぬけの無邪気さに、なんだかまた、からかいたいような気持ちになる。
「もしかしたら、まだ夢の中にいるのかもしれないよ?」
「あら、それはないわ」
ムンドゥングゥはうけあってみせた。
「だって、ヨくんのにおいがするもの。夢の中ではにおいなんてしないでしょう?」
とつぜんのふいうちに、顔が熱くなっていくのがわかる。
「ムンドゥングゥ、ヨくん、晩ごはんができたわよ。冷めないうちに食べにいらっしゃい」
リビングから救いの声がかかる。
ぼくは顔を見られないように、たちあがった。
ムンドゥングゥは、すっと、手のひらをぼくにすべりこませてくる。
きっと愛らしいその顔には、いたずらな笑みが浮かんでいるのにちがいない。
ぼくの名前は予沈菜(ヨ・チャンジャ)。大陸うまれの日本人だ。
ワケあって、ムンドゥングゥの家にいそうろうをさせてもらっている。
グウーッ。
1ぱい目のごはんを食べたのにもかかわらず、ぼくのおなかが音をたてる。
くすくすと笑いだすムンドゥングゥ。
「育ちざかりですものね。好きなだけ食べていいのよ」
ためらうぼくの茶碗へ2はい目をよそってくれた美人は、ムンドゥングゥのお母さん。
ほとんどムンドゥングゥとかわらない年にみえる……と言ったらいいすぎだけど、すごくわかくみえるのはほんとうだ。
「そのとおり! 私がきみくらいのときは、どんぶりでかるく4はいは食べたものさ」
がっはっはっ、と豪快に笑いながらわりこんできたのが、ムンドゥングゥのお父さん。
あさ黒い健康そうな肌は、テニスのインストラクターをしているからだ。現役時代は、ずいぶんとならしたらしい。
ふたりともいそうろうのぼくに、ほんとうによくしてくれる。食卓ではなんとなくだまってしまうけど、それは気まずいってわけじゃない。幸せな家族の時間を、ぼくなんかが邪魔しちゃわるいような気になるからだ。
「む、どうした。すこしもごはんがへっていないじゃないか」
娘の茶碗をみとがめて、お父さんが心配そうに顔をちかづける。濃い眉毛のかたちがムンドゥングゥとそっくりで、ふきだしてしまう。
「うん、なんだか胸がいっぱいで、のどをとおらなくって」
「むかしから、この子は食がほそかったから」
手のひらをほおにあてるしぐさがかわいらしいお母さん。
「生まれたときもふつうよりちいさくって、小学校にあがるまでバナナをはんぶんしか食べられなかったのよ」
ぼくを見ながら、苦笑する。
たちまち、ムンドゥングゥがまっかになった。
「もう、お母さん! ヨくんの前でそんなこと言わないでよ!」
お父さんとお母さんが、ほう、と声をあげた。そしてふたりで顔をみあわせて、意味深な目くばせをする。
「あー、母さん。ヨくんの茶碗がもうあいているじゃないか。山もりにしてあげなさい、山もりに」
「はいはい」
お母さんがふくみ笑いを隠しながら、炊飯器をあける。
「あら、やだ」
両手をほおにあてるしぐさが、妙にかわいらしい。
「白いごはんがもうないわ」
「なんだ、もっと炊いておかなかったのかい?」
「ほら、うちはムンドゥングゥひとりでしょう? 十代の男の子がどのくらい食べるのか見当がつかなくって」
「そいつは困ったな」
心の底から困ったという表情で、腕組みをするお父さん。筋肉がもりあがっている。テニスのインストラクターというよりは、重量上げの選手みたいだ。
「いいわ、ヨくん、あたしのをあげる。だってきょうはもう食べられそうにないから」
茶碗をさしだすムンドゥングゥ。
「あげるって……半分も食べてないじゃないか。もうすこし食べなよ。のこったときに、もらってあげるからさ」
ぼくの言葉に、ふるふると首をふる。
「ううん、もうきょうはごはんがはいる場所がないの」
手のひらで胸をおさえながら、ほほえんだ。
「だって、しあわせで胸がいっぱいなんですもの」
なんのくもりもない、とびきりの笑顔。
ぼくはまたしてもふいをつかれ、ごはんをうけとってしまう。
「なんだ、しあわせで食べられないなら、この家じゃ、飢え死にするしかないぞ」
がっはっはっ、とお父さんが笑う。
「じゃあ、ムンドゥングゥがすこしでも食べてくれるように、おこづかいをへらしましょうか」
おっとりと、お母さんが加勢する。
「もうっ、またふたりでからかってるでしょ!」
にぎやかな家族のやりとりを聞きながら、ぼくはなんだかみちたりた気分でごはんを口にはこぶ。
あ。
これもやっぱり、間接キスになるのかな?
「ちょっと仕事をもちかえってるんだ。顧客のリストを明日までにしあげなくちゃならない。おそくなると思うから、母さんも先に寝てていいぞ」
早々に食事をきりあげると、エクセルは苦手なんだよと頭をかきながら、お父さんは二階のじぶんの部屋へひきあげてしまった。
テーブルにはムンドゥングゥの焼いたパウンドケーキが、半円だけのこっている。
ずず、と日本茶をすする。濃いめに煎れるのが、この家の流儀みたいだ。
どうやら、すこし食べすぎてしまったらしい。ときどきこみあげるおくびに、食べものがまじってる気がする。
からだはすっかり重いが、気分は上々だ。ソファに身をあずけながら、やくたいもないテレビ番組をながめるのも、これはこれでわるくない。
とくに、かわいい女の子といっしょならね。
ムンドゥングゥがぼくのおなかを枕がわりにして、横になっている。クジラがぐるぐるまわる音がするよ、とつぶやきながら、目はとろんとしている。
ときどき、かくっと首がおちて、いまにもねむりそうだ。ねむったムンドゥングゥをベッドにつれていくのが、最近ではぼくの日課のようになっている。
いとしさにたまらなくなって、そっと、ちいさな頭に手をおこうとしたそのとき――
ドーン。
天井から大きな音がした。
おどろいたムンドゥングゥが、猫のようにはねおきる。
ドーン。またひとつ。
そして、しずかになった。
顔をみあわせるぼくとムンドゥングゥ。
耳をすませると、ぎしぎしという音とともに、天井から細かなほこりが落ちてくるのがわかる。
「お父さんの部屋だわ」
言うがはやいか、ムンドゥングゥはかけだしていた。
お父さんのことが心配なんだろう。なんて親孝行な娘なんだ。
思わず感動して、うんうんとうなずいてしまう。
が。
ぼくは事態を思いだすとはっとして、あわててあとを追った。
「お父さん、あたしよ、ここを開けて!」
ちいさなこぶしをふりあげて、ムンドゥングゥが扉をたたく。
涙をいっぱいにためて、階段をあがってきたぼくにすがりついてくる。
「たいへん、お父さん、くるしそう。どうしよう」
扉に耳をあてると、たしかに苦しそうなうめき声がする。
ドアノブをまわそうとするが、内側からロックされているらしい。
「すこしはなれていて」
ドカッ。
ムンドゥングゥをさがらせると、扉にキックする。
足はじーんとしびれるが、びくともしない。
さらに大きく助走をつけ、2発目のキックをおみまいする。
ドカッ。
「は……づッ……」
全身の骨が軋み、砕ける音。
灼けるような塊が喉めがけて駆け上がる。
やはり、僕では無理なのか。失望より先に浮かぶのは、自嘲。
はは、最後の最後まで、ダメなヤツだ。いつだってオマエは途中で諦めちまう。
そして、途切れゆく意識の中で浮かぶのは――
儚げな、ムンドゥングゥの横顔。
右手を壁面に喰い込ませ、爪の剥げる痛みに我を踏み止まらせる。
ゴクリ。僕は味蕾を浸す熱した海水を飲み下した。
まだだ、まだだ。
いま、ここで倒れたら――
誰がムンドゥングゥを助けられるっていうんだ!
オマエはこんなものか! 弱い自分を叱咤する。
俺は知ってるぜ、オマエはこんな程度じゃないはずだろ?
力を出せ!
力を出せッ!!
枯れた井戸の底が割れ、奔流の如くエネルギーが吹き上がるイメージ。
精度を上げる視界。およそ、人の視力では有り得ない程の――
扉の木目に沿って、黄金の光線が走る。
僕はすでに、“それ”が粉々に爆ぜる未来を“知って”いた。
一度は砕けたはずの右足に、再びパワーが漲ってゆくのがわかる。
確信という名のボルテージは、いまや最高潮だ。
そして、3発目のキック。
ズボアァッ。
それは名称を同じうするだけの、全く別次元の技と化していた。
バリバリバリ。
音の壁を遥か置き去りにする速度。
金剛石を粉砕せしめる莫大な威力。
がつッ。
なんと、扉は健在。
だが、技の威力も減衰していない。
「当てがはずれたな! 悪いが、俺のキックの半減期は二万四千年だぜ!」
僕は頭の中だけで考え、実際言ったことにした。
その方が気分が盛り上がって、遥かにパワーが増す気がするからだ。
最初の衝撃波は堪らず水平方向へ逃げ、中規模な地震の如く家屋を揺籃せしめる。
やがて扉の硬度と技の威力が同等のエネルギー波として干渉し合い、傍目には完全な均衡を生じる。
だが、分子レベルの振動は静電気を生じさせ、それはやがて複数のボール・ライトニングと化して扉と僕を取り囲んだ。
正に、天然の要害。ここからは鼠一匹、逃げられない。
「小癪な童め!」
僕は自分で言って、扉が言ったことにした。
その方が気分が盛り上がって、遥かにパワーが増す気がするからだ。
僕はニヤリと嗤う。
「さて――もう暫くだけお付き合い願いますよ」
こうなりゃ、もう技は関係ない。相手さえ関係ない。
肉体と魂の全てを盆に乗せて、神サマに裁定してもらうだけだ。
俺と扉――
どっちが上?!
「うおおおおーッ!」
メリメリメリ、ズドーン!
予想に反して、ちょうつがいだけがふきとんだ。
廊下に女の子座りで雑誌を読んでいたムンドゥングゥが、顔をあげる。
「お父さん、しっかりして!」
倒れた扉をふみつけに、部屋へとびこんでゆく。あとを追うぼく。
「きゃあ!」
そこには、しんじられない光景――
お尻をまるだしにしたお父さんが、ベッドで茶髪の女の子にのしかかっていたのだ。
ちいさくふるえるムンドゥングゥを、まもるようにだきかかえる。
ぼくはふたりをキッとにらみつけた。
お父さんはおどろいた顔で、こまかく腰をうごかしている。
女の子はといえば、まだらに茶色くなった髪の毛に、よれよれの制服。まるで野良犬みたいだ。
お父さんのうごきにあわせて茶色い髪をばさばさとゆらしながら、めるめるとメールをしている。
「あなた、いったいこれはどういうことなの!」
げ、まずい。
うしろには、まっさおになったお母さんがママレモンの泡もおとさずに立っていた。
わなわなとふるえ、手にもったお皿がまっぷたつに割れる。
「ちかごろ、すっかりごぶさたと思ったら、こういうことだったのね! わたしをだましていたのね!」
「ち、ちがう、それは誤解だ」
さすがに、腰のうごきをとめるお父さん。
「誤解も六階もないわ。もう、りこんよ! りこんよ……」
エプロンに顔をうずめながら、お母さんは背をむける。
「待つんだ、グィネヴィア」
声のトーンが変わっている。
お母さんの肩がびくり、とふるえた。
「まだ、わたしをそう呼んでくれるのね、アーサー」
前をまるだしにしたまま、お父さんがベッドを降りる。
「どうかわかってほしい。わたしにとって、おまえは神聖すぎる誓いなんだ。あまりにも清らかで、わたしぐらいでは汚すことのかなわない。わたしの汚れを、おまえに注ぐなんて、おお、考えるだに恐ろしいことだ」
涙を流しながら、お母さんがひざまずく。
「ああ、ああ、あなた! 浅はかなわたしをゆるしてください! あなたの苦悩を知らず、毎晩を売女に注がせていたわたしの愚かさをゆるしてくださいますでしょうか? そして、お願いします、どうかわたしを抱いてください! わたしはあなたに高められこそすれ、汚されるだなんて思ったこともありませんわ!」
ふたりは熱烈に抱きしめあうと、みているぼくたちのほうが赤面するような口づけをかわした。
お父さん――いや、アーサーはグィネヴィアをかかえあげると、優しくベッドへ横たえた。
そう、まるでナイトがプリンセスにするように。
「ねえ、ふたりだけにしてあげましょう……」
ムンドゥングゥが微笑んだ。
なぜか、とてもさみしそうな微笑みだった。
「ほら、あなたもいっしょにいくのよ!」
そう言って、茶髪の女の子の手をひっぱる。
「ねー、あちし、まだおカネもらってないんだけど」
伝説の王と王妃は、千余年の流浪を経て、いまお互いの正統な持ち主の元へと還ったのだ。
剣が必ず、収まる鞘を持つように。
ぼりぼりと茶色い髪をかきまわしながら、女の子がごちる。
「ねー、あちし、まだおカネもらってないんだけど」
聞こえないふりをした。
夜の戸外は、夏だというのに冷気をふくんでいて、ほてった身体に心地いい。
かすかに聞こえるのは、アーサーとグィネヴィアのむつみ声だろうか。
「そんなに走るとあぶないよ」
はしゃぐムンドゥングゥに声をかける。
「だって、夜のおさんぽなんて、ほんとうにひさしぶりなんですもの!」
スカートに風をはらませて、くるくると回転する。
「わたし夜ってだいすきだなあ。だって、もうあしたがはじまってるみたいで、なんだかワクワクするの。ヨくんは、そんなふうに考えたことない?」
ぼくはちょっと考えて、
「ないなあ。明日がこなければいいっておもうことは、むかしよくあったけど」
「ふーん、フコウだったんだ」
「どうかな。いや、幸せだったことがなかったから、不幸だってわからなかっただけ」
「あたしもフコウってよくわからなかったけど、いまはちょっとわかるかな」
後ろに手をくんだムンドゥングゥが、小石をけりあげるしぐさをする。
そして、とてもちいさな声で、
「ヨ君がいなくなったら、あたしはフコウになると思う」
聞こえた。
「え、なんて言ったの?」
でも、ぼくはいじわるに聞き返してみる。
みるみるまっかになるムンドゥングゥ。
不自然に視線をうろうろさせてから、
「あ、公園だわ!」
言うがはやいか、駆け出してゆく。ぼくはあわてて追いかける。
「ねー、あちし、まだおカネもらってないんだけど」
聞こえないふりをした。
公園の入り口で、ぼくは思わずたちどまる。
遠くからみるムンドゥングゥが、すごくきれいだったから。
茶髪の女の子がぼくの背中にぶつかってくる。ひじをつかって、邪険にふりはらう。
ムンドゥングゥは、ブランコのくさりに手をかけて、表情をゆるませる。
「ブランコって、ひさしぶり。ちょうど向こうに小学校があって、子どものころは帰りによく乗ったんだけど」
手についた赤さびに鼻をちかづける。
「そう、このにおい。鉄のにおい。なつかしい……ねえ、ちょっとすわっていかない?」
ふたりの女の子にはさまれて、ぼくは真ん中のブランコに腰かける。すこしきつい。
でも、ムンドゥングゥにはちょうどいいみたいだ。
「あたしってば、あんまり成長してないのね」
深夜の公園で、ブランコに腰かける3人。はた目には、いったいどんな関係にみえるのだろう。
遠くの外灯にはセミやかぶと虫がかんちがいをして、ぶんぶんととびまわっていた。
しばしの沈黙のあと、ムンドゥングゥが話しはじめる。
「あたし、ひとりっ子じゃない? お父さんとお母さんはとってもだいじにしてくれたけど、ずっとふたりのあいだには入れないような気がしてたなあ」
ぼくはなにも言わずに、さびしげな横顔をみまもる。
「学校の友だちでも、3人いるといつのまにか、なんかひとりあまっちゃうでしょ。あんな感じ。お父さんとお母さんが結婚して、あたしが生まれたんだから、あたりまえなんだけど、なんだかあたしだけ遅れてきたみたいに思ってた。――おたふく風邪で4月に1週間くらい休んだことがあって、クラスにもどったらみんな仲良くなっちゃってて。ぽつんとひとり座ってたら、お弁当のときとか呼んでくれるんだけど、みんなが楽しそうにしてるのを見てると、もう遅れたぶんはぜったいとりもどせないんだなあ、って――わかんないよね」
下を向いて、はにかんだように微笑む。
こんなに長く、ムンドゥングゥが自分のことを話すのをはじめてきいた気がする。
「わかるよ」
「ほんと?」
ぱっと顔を上げると、まるで花がさいたようだ。
「それとも、同情してる?」
「ぼくは4月に、水ぼうそうで休んだ」
鈴のようにころころと笑いだすムンドゥングゥ。よかった。
となりでは茶髪の女の子がくわえタバコで、カチカチとメールしている。
視線に気づいたのか、顔をあげると、
「ねー、あちし、まだおカネ……ぐほッ」
みぞおちに肘を突きこみ、吸いさしのタバコをとりあげる。これは間接キスじゃないな。
肺いっぱいに煙を吸いこむ。にがい。
「いけないんだ、不良みたいなことして」
あんまりきれいな告白に、ぼくは自分を汚したいような気持ちになったのだ。
アーサーの言葉が、よくわかる。
「わたしねえ」
ちいさくブランコをこぎながら、ムンドゥングゥがいう。
「ヨくんがいっしょにいてくれるとね、がんばろうって思えるの。もちろん、身長とか、胸がちいさいこととか、がんばってもダメなことはあるけど、がんばったら変えられるところは、がんばろうって」
ほっそりとした足がまげのばしされるたび、ブランコは大きくゆれうごく。
「だれかのことを考えたとき、ひとりのときよりも力がでるって、すごいことだよね」
ぼくをほんろうするように、声が前と後ろからきこえる。
それはぼくも同じだよ。
思ったけれど、声にはださなかった。なんだかこわいような気がしたから。
「あーっ!」
突然すっとんきょうな声をあげて、ブランコをとびおりるムンドゥングゥ。
声の大きさよりも、ころばずにひらりと着地したことへおどろくぼく。
「わたし、すっごいことに気がついちゃった!」
一筋の月光が、ムンドゥングゥの額から顔に流れる。
紅潮したほおは、夜の底でかがやく星のようだ。
ぼくはなんだか泣きたいような気持ちになって、やさしくたずねる。
「なにに、気がついたの?」
「あのね、お父さんとお母さんも、はじめは他人どうしだったんだよ!」
言いたいことがわからない。
ムンドゥングゥはおかまいなしで、興奮のきわみ、といったかんじで手をふりまわして力説する。
「だからね、家族って、他人どうしが作るものなんだよ。だからね、わたしたちが家族になっても、ぜんぜんふしぎじゃないんだよ! これって、すごい発見よね! カクメイテキだよね!」
ずきり。
痛ましいような想いが胸にささる。ムンドゥングゥは何もわかっていないのだ。
革命っていうのは、これまでにあるぜんぶを捨てること。たとえば、ぼくが大陸に捨ててきたぜんぶを、 ムンドゥングゥは知らない。
いずれこの世界の悪にであったとき、ムンドゥングゥの純粋さは手ひどく傷つけられてしまうのではないだろうか。あまりにも信じすぎるこの純粋さは、いつかムンドゥングゥを殺してはしまわないだろうか。
――だから、おまえがいるんだろ?
ぼくはおどろいて、あたりをみまわす。
――そのために、いたみ、くるしみ、よごれてきたんだ。
それは、天からふってきたような言葉だった。
なのに、ぼくの胸の真ん中へ、すとんと落ちた。
「こらっ! こんなおそくに子どもがなにやってんだい!」
ぼくたちは、いっせいにふりかえる。
公園の入り口で、むらさき色のパーマをかけたおばさんがぼくたちをにらみつけていた。
ピンクのネグリジェを着て、手にはなんと金属バットがにぎられている。
「たいへん!」
ムンドゥングゥが大きく目をみひらいて、両手を口にあてる。
「逃げましょう!」
言うがはやいか、駆けだしている。ぼくはあわてて追いかける。
ぼくの人生の先を素足でかけていく少女。
どちらがどちらをみちびいているのか。
もしもころんだら、そのときは優しく抱きしめてあげよう。
ぼくは少女のナイト。
このいのちは、すでにプリンセスへささげられている――
「このへんで民生委員やってるマスオカってんだけどね。アンタ、変わってるね。逃げないのかい?」
「ねー、あちし、まだおカネもらってないんだけど」
小鳥の唄
小鳥尻ゲイカ
――今日のゲストは、女優の小鳥尻ゲイカさんです。
小鳥尻(以下、尻):(仏頂面で)どもー。
――さっそくですが、今回なぜあのような更新をなさったのですか? そこに至る心理状況といいますか、経緯をお聞かせ願えますでしょうか?
尻:(そっぽを向いて)別に……。
――何か、昔からのファンへの裏切りだとか、そういう声も聞かれますが……
尻:(激昂して)ウルセエよ! うちあわせと内容がちがうじゃねえか! そのことには触れないんじゃなかったのかよ! オイ、カメラとめろ!
――落ち着いてください、生放送中ですから。ファンへの謝罪の言葉はないのですか?
尻:なま……(小声で)ちくしょう、いつもアタシをそうやって罠にハメやがんだ……(沈黙。ふるえる手で前髪をかきあげながら)オタどもの喜ぶようなものを書こうと思ったんだよ。奇抜な名前で精神遅滞のガキがする情緒たっぷりの世迷言や、神話の世界観を借用した奥行きのゾッとするような遠浅ぶりや、自動化された物語のする白痴的精神愛撫をオタどもにブチこんでやりたかったんだよ!(無理に笑い声をたてる)
――ごうごうたる非難を聞けば、その試みは少なくとも成功したとは言えないと思いますが?
尻:(びくり、と身体をふるわせて)も、萌えやら、ね、熱血やら、オマエらがオッ立つ要素はなんでも入ってんだろがよ! ぜんぶタダで読んどいて文句言うなんてよ、不法侵入の上で狼藉・乱暴しながら戸締りについて説教する強盗と変わらねえよ! ちがうかよ!
――(さえぎって)読者の方から一通のメッセージが届いていますので、読みあげさせていただきたいと思います。『私たちが変わってしまっても、貴方だけは変わらないでと、そう思うのは私たちのエゴなのでしょうか』。いかがですか? 真摯なファンの姿勢に、少しでも反省の気持ちは生まれませんか?
尻:ケッ、ソープに沈んだ昔のオンナにかけるブンケイの寝言じゃねえか。テメエが身請けしてやらねえから、生活のために仕方なくお客とってンだろ? それ、「ぼくには経済力がなく、そしてきみには処女膜がない」って意味でしょオ? ちがうのオ?(馬鹿笑いする)
画面の外でサングラスの男が「もっと挑発して」と書かれたカンペを掲げる。目の端でそれを見るインタビュアー。
――では、私の感想を述べさせてもらいますと、しかし重度の萌え不自由でしたね(笑)。
尻:(頭髪の薄い男があの単語を言われたように、顔面を硬直させる。何か言おうとして、泣き出す)ひっく、ひっく……ひどいじゃないの……わかっててアタシにそれを言うなんて……なにさ、かってにキレキャラみたいにあつかってさ……きょうだって、アタシがあばれだすのをみんなニヤニヤしながら待ってんでしょう? アタシ、女優なのよ……ネット界のおさわがせである前に、女優なの。でも、いまじゃ女優だからキレるのをゆるしてもらってるんじゃなくて、キレるから女優をやらせてもらってるみたい……こんなのって、ないわ……ないわよ……(両手に顔をうずめると、すすり泣く)」
インタビュアー、当惑してサングラスの男を見る。サングラスの男、身体の前で両腕をクロスさせながら、口パクで「つかえない」と言う。
――小鳥尻さん、ご自分で招いた結果です。泣いたってしょうがないでしょう。ほら、これ使って。
尻:ありがと……(ティッシュで鼻をかむ)バカだね、アタシ。オンナが泣くのって、サイテーだね。なんだか、ゆるしてくれって甘えてるみたいでさ……。
――落ち着かれましたか? みなさん、小鳥尻さんの言葉を待ってますよ。
尻:(前髪をかきあげる。鼻の頭が真っ赤である)あー、なんか、昔のこと思い出しちゃったわ。中学のときさ、ちょっとからかうと、ムキになってキモい反応するデブがクラスにいてさあ。イジメ、だったのかな、あれ。みんな、ソイツになら、なに言ってもいいってフンイキだったワケ。んでさ、国語の時間にウザいセンセーがさ、クラスの前で作文とか読ませんのよ。はは、ムナゲってあだ名だったわ、そういや。中身は忘れたけど、将来の夢とか希望とか、きっとそういう漠然と前向きなヤツ。みんなジブンの番が心配だからさ、まばらな拍手とか、ユルい冷やかしとかに終始すんの。もっと正直に意見を交換していいんだぞって、ムナゲがさ。公立だったし、ただ同じ地元だってだけで集まってる連中が、おたがいに深いとこまで通じるハナシなんて、そもそもできっこないじゃん。オカマバーにノンケをつれてってゲイの話をさせるって例えなら、だれだってムリだってわかんのにサ。でもまあ、ガッコってそういうトコだしね。でさ、毎時間、何人かずつ発表してってさ、ついにソイツの番になったワケ。ナニしゃべってたのかは忘れたけど、その日はみんなでしめしあわせてさ、黙って下向いてたの。クラス全員で。発表が終わっても顔あげずに、ただヒジでつつきあったり、クスクス笑ったり。そんで、これは一番うしろに座ってたアタシの役目だったんだけど、頃合いにとびきり大きなため息をついたわけ。ハーッ、って。そしたらさあ、ソイツ、いままでになかったくらい、ものスゴイ逆上しちゃってさあ。教卓を蹴りたおして、アタシのほうめがけて突進してくんの。さいわい、他の男子がとりおさえたけど、まえに座ってた女の子がひとり、倒れた教卓でおデコをケガしちゃってさ。結局、ソイツひとりだけ停学くらうことになるワケ。なんであんな怒ったんだろ。あれは、あと味わるかったわ……(内側へ沈み込むように、小声で)なんであんなに、怒ったんだろ……」
サングラスの男、空中をチョップする真似をしながら、口パクで「切って切って」と言う。インタビュアー、細かくうなずく。
――(わざとらしく腕時計に目を落としながら)えー、時間も残りわずかとなってきたようです。最後にファンへ一言だけ、お願いできますか?
尻:(聞こえていない様子で、ひとり言のように)アタシさあ、前にダンナに不倫されて殺すとこまでいっちゃう役やったことあんだけど、最近なんかそのことばっか考えるっていうか、すごいよくわかんだわ。内助の功ってえの? 影で支えてたダンナがさ、どんどん社会的に立派になってってさ、気がついたら築いた地位を利用して別の若いオンナつれてんの。当時は、なにこのうすっぺらなハナシって思ってたけど、いまは想像するだけで目の前が真っ赤になる感じがする。日の当たらない場所で耐えてきたアタシはどうなんのって。アンタは表の顔だけして生きてるけど、アタシがアンタの下着まで洗ってんだって。アタシがアンタの汚い部分をぜんぶ引き受けてきたから、いまのアンタのきれいな成功があるんだろって。だから、nWoの閉鎖が決まったりしたらアタシ――(臍を噛んで、三白眼で)きっと殺すと思うな……」
サングラスの男が台本を放り投げると、スタッフが撤収を始める。セットから順番に照明が落ち始める。インタビュアー、ソファへぐったりと身体を投げ出す。
――(興味を失った様子で)だいじょうぶですよ、たぶん、どうでも。
尻:(険のとれた表情で)あー、泣いて愚痴ったらスッキリした。なんだって出すとスッキリするのは、動物らしくてイイね。(立ち上がり)ゲイカ、次からはいつもどおりがんばります。みんな、心配かけてゴメンナサイ、てへっ(頭を下げ、舌を出す)。
――(失笑して)がんばるって、萌えを、ですか?
尻:(瞬間的に血涙が吹く)ブワッハッハーのハー!! けっきょく、アンタたちはアタシのこれが見たいだけなんだね!!
小鳥尻、インタビュアーの胸ぐらをつかむと、ともえ投げに投げ捨てる。テレビカメラは激突したインタビュアーごと倒壊し、画面は大音響とともに横倒しになる。サングラスの男、小さくガッツポーズをとると、スタッフに指示を出す。セットに照明がもどる。しらけた雰囲気から一変、にわかに活況を呈する現場。
お茶の間のテレビ画面。ガラスのテーブルにヒールで仁王立ちになり、何事かを宙空に向けて絶叫している小鳥尻ゲイカの口から、炎のCGエフェクトが発している。かぶせるように、怪獣の鳴き声。流れる血涙は、水色に塗りかえられている。BGMにはドリフのコントでオチに用いられる、例のスラップスティックな曲が流れている。大爆笑のお茶の間。
「ああ、よかった! メンタルヘルスみたいな告白を始めたときにはどうなるかと思ってドキドキしたけど、やっぱりゲイカ様ね! いつだって最後の最後には、私たちの期待どおりまとめてくれるわ!」
「(あからさまに戯画的な白人が流暢な日本語で、しかし英単語だけは極めて英語的な発音で)おっと、そこの君! そうそう、顔の造作に問題がないとは誰にも断言できない、ふくよかな脂肪の、そこの君のことだよ! もしかして、nWoがまた、死なない程度のヘルシー・リストカット、予定調和の大暴れで、従来の自閉路線に戻ったと安心してるんじゃないのかな? ノンノン、nWoの未来はいまだにたゆたっている……(雑木林が風になびくときのような擬音)。このウェブ2.0時代にいつまでも昔ながらのテキストサイト的運営じゃ、(そうでないことを確信する口調で)取り残されてしまうからね! 今回、nWoは来訪者のみんなへ向けたアンケートを実施することにしたよ! ホームページはインタラクティブ性が重要だからね、LDゲームのようなね! もちろんキミの匿名は完全に守られるので、「こんな下品なのが好きなんて、私ってやっぱりエッチなのかな?」と性に臆病な女性読者もひと安心だ! nWoの今後の方向性について、忌憚のない意見を聞かせてくれたまえ! なんの権威による裏づけもない、こんな場末の泡沫サイト、どっちに転んだところで人類は滅亡しないって寸法さ(腹を抱えて爆笑する)! (目尻の涙をぬぐいながら、真顔で)アンケート回答者が規定数に達しない場合は、ノーコンテスト。(暗い声で)そのときは、閉鎖します」
センサス at nWo概評
スーツに身を包んだ女性がヒールをカツカツいわせながら、舞台端の緞帳から現れる。同時に、舞台中央からマイクがせりあがる。
「アクセス数200/1日程度の弱小サイトで、アンケート回答数50を超えなければ閉鎖を行うと宣言した小鳥猊下。その無謀な挑戦も、同一人による複数回答というコロンブスの卵を得、ついに達成の朝を迎えた。胸をなでおろすnWoスタッフ一同、握りつぶされるIPアドレス一覧。気を良くした小鳥猊下はnWo社の次世代マーケティング部門にアンケート結果の分析を依頼する。500ページに及ぶ分厚の分析資料すべてを(顔を赤らめて)か、開陳することはおよそ150人の文盲を含んだ来訪者に対し、あまりに過大な要求にすぎはしまいか。苦悩する小鳥猊下は一晩のうちに分析結果を愉快な漫談形式に書き下ろし、臣下へ下賜することを決められた。おお、いと高き小鳥猊下、我々の膣に生まれた隙間がその御言葉で充填されんことを!」
一礼すると、ヒールをカツカツいわせながら舞台端の緞帳へ消える。
舞台の右端と左端からそれぞれ、ワンレンボディコンとしか表現できない時代錯誤の異装をした女性と、重たそうな布地の襞に埋もれた洋装の少女が、前傾姿勢で拍手をしながらマイクへとかけよってくる。
「どもー、小鳥尻ゲイカでーす」
「どもー、名も無き少女でーす」
「オイオイ、きみ。名も無き少女って、それごっつ言いづらいわ。インターネットの匿名掲示板とちゃうねんで、ここ。クオリティ・ホームページやねんで。本名はなんていうねん」
「あの、あたしのこと、コーデリアって呼んでくださらない?」
「ああ、あの表面にうねがある木綿地のことかいな」
「そら、コーデュロイやがな」
「ごめん、ごめん、ボケとったわ。オレゴン州ワシントン群の……」
「コーネリアスや」
「えっ、これもちがうんかいな。わかった、昔のファンタジーRPGにでてきた王様の名前やろ」
「ええ加減にしなさい」
洋装の少女、背中から金属バットを取り出し、小鳥尻ゲイカの後頭部を強打する。鈍い破砕音とともに白い液体と赤い液体と灰色の固体と眼球が四方へ噴射する。小鳥尻ゲイカ、顔面から舞台へ倒れこみ、尻を高くつきだした姿勢で痙攣をはじめる。洋装の少女の華麗なフォロースルー。2秒で直立の位置にハネ起きる小鳥尻ゲイカ。
「ちょ、じぶん、ツッコミが激しすぎるで。あやうく死ぬところや」
「なにゆうてんの。nWo構成体のウチらはしょせんテキストやから、死ぬのはお客さんの関心が尽きたときだけやがな」
「すっかり忘れとったわ。あんまり見事な筆致で描かれてるさかいなあ。それに、きょうの目的はアンケートの開示や。しょうもないつかみで死んだら、しゃれにもならへんで」
「せや。送られたコメントにふたりで返事してくんや。回答者は10代から30代。40代以上はひとりもおらへん。おたくの世代間断絶が浮き彫りになったかっこうやな。社会的立場は、文系仕事と理系仕事と学生がだいたい等分に入っとる。一方、20代と30代で読者の8割やから、こら計算があわんね。終わらない夏休みがまじっとるな。あと、読者の9割は男性が占めてるのが特徴や」
「あほぬかせ。内気で清楚な女性ほど、尻軽には投票でけへんのじゃ。潜在的にはもっとおるはずやで」
「ゆうとけ。送信日時の古い順に、まきでいくで。まずはこれや。『So it goes.』。うわぁ、異人さんや、ガイジンや。うち、食べられてまう、ご時勢的に」
「よっしゃ、あんたは下がっとき、年齢的に。不登校のなれの果てに海外留学へ逃避し、現地では学位も取らず主にアパートの内側で放蕩を繰り返した、英語に堪能なうちの出番やで。ユー・ファック・アナル・アフター・エレクト、オーケー? あとは塩まいたらしまいや」
「ああ、安心したわ。あんたがおってくれてほんまよかったわ」
「よしてや、そんな、親にもゆわれたことのない……」
「泣かんとって、うちが悪かったわ、泣かんとって」
「ごめんな、ほんまごめん。最近涙もろうなって、年のせいやねん」
「次いくで、しっかりしてや。『誰かが言っていましたが、詩人は救われてはいけないそうです。 たぶんぼくもあなたも、孤独と絶望とだけを道連れに生きていくしかないんでしょう。』。詩人やて。悪い気はせんなあ。自意識をくすぐるのがうまいで」
「この人、少女保護特区リライト版の方が好みって回答してはるねん」
「そんな追跡機能がアンケートに組み込まれてたんかいな。ちょっと見直したわ」
「ちゃうちゃう。アンケート結果のページで更新ボタンを押し続けて、コメントと回答者のつながりを目視確認していっただけや」
「うわー、じぶんそれちょっとひくわ。まるっきりストーカーか、そやなかったら引きこもりやん」
「もうひとり、職業欄にコピーライターて書いた人もリライト版が好きって回答してはるわ」
「なんや見透かされるみたいで、ちょっとドキッとするわ。通常版は“つこたらアカン言葉を選ぶ”更新のやり方で、リライト版は“つかう言葉を選ぶ”更新のやり方をしとるからね。スルドイわ」
「次いくな。『今後どうなってしまうか分かりませんが結末を迎えるまでnWoを見守らせて頂きたく思っております。 猊下、愛しております』」
「ゆうてるけど、みんなの関心が尽きたときが終わりどきやから、今後どうなるかはあんた次第やで」
「次。『ザ・ボイシズ・オブ・ア・ディレッタント・オタクが死ぬほど好きです。 いつか言いたいと思ってました。』」
「ギャグ漫画家は短命って話があるけど、ああゆうブラック系の更新は時間が経つとこっちへはねかえってくるねん。社会と思想と他人を無いようにコケしたら、残った我がを無いようにしない理由が見当たらなくなってまうからな」
「次。『確かにサイトの質と世間の評価(?)は不釣合いと思いますが、 何か変えたりする必要は無いんじゃないでしょうか? 私にはとてもとても面白いです。』」
「鬱のときは我がだけ見て更新できんねんけど、躁のときは気持ちが外むくから、誰かの承認なしにはいられんような感じになるねん」
「次。『萌え画像がんばります』」
「アンケートやっていちばんはげみになったんは、萌え画像を送る予定のある来訪者が5人もおったことやね。これから5枚も萌え画像が届くかと思うと、ワクワクで更新もでけへんわ」
「あんたそれ、矛盾しとんとちゃうか」
「次いけ、次」
「『すばらしい体験をいつもありがとうございます。』」
「どういたしまして。あなたこそ、いつもすばらしい孤独をありがとうございます」
「皮肉がきいとるな。『窮状なのか休場なのか分かりませんが、 私は大好きです。これからも楽しみにしてます。』」
「だれがうまいこと言えゆうた。“更新する、反応がない、落ち込む、更新しない、忘れる、更新する”がnWoの持ってる基本サイクルやからな。うちはわるないで」
「『持たざる者である私には祈ることしかできません。』。職業は、なしで回答してはったと思う」
「きみはとりあえず祈るだけでええわ。なんか積極的に動かれると、当局に押収されたパソコンからきみの愛好していたサイトとしてうちが発見されたりしそうや」
「くわばら、くわばら。『私はテキストサイトが好きなんです。 それをいちいち思い出すから、ここが好き。』」
「好きなのはあくまで“テキストサイト”としか読めないのが傷つくし、ムカつくわー」
「絶滅危惧種への哀れみやろね。『ふと思い出しては、読み返します。 過去に何度か掲示板へ書き込むべきかと思ったことはありましたが、 小鳥猊下の文章に受けた衝撃は簡単に言語化できるようなものではなく、 いい加減で空疎な賞賛の言葉など送りたくありませんでした。 ただ一言、私はnwo程文学的に見事な筆致でもって 「現代」「おたく」を真摯に捉えた文言を、ほかに知りません。』」
「まじめやな。うちもそう思う。そして、なのになぜ……という言葉が続くんや。ほんま、なんでやろ」
「『閉鎖?そんなバナナ・・・・いやいや洒落にならんやろ。』」
「あたりまえが、じつはあたりまえやないことに気づいてや。立っとるだけで人はカロリーを消費すんねんで」
「『小鳥猊下、愛しています。』」
「うちもやで。あんたが女性ならセックスしよう」
「しよう、しよう。『いつもありがとうございます。 『あの頃~の生き方をー、あなたはー忘れないで~』という ユーミンじみた勝手な思いを抱いています。 私にとってはたまに訪れて姿勢を正す場所といいますか。 “窮状”などと思わせてしまい申し訳ありません。 複数回答ができなかったので補足させてください。 パアマンの他には、 怪漢ブレイズ・小鳥の唄・ 生きながら萌えゲーに葬られ・高天原勃津矢 などが大好きです。 「こんな文章が書けたら!」と憧れてプリントアウトして 持ち歩いた時期もありますが、もう諦めました。』」
「怪漢ブレイズに一票も入ってへんかったから、ほっとしたわ。nWoみたいな文章かいても誰にも認められへんし、社会的な場ではいっこ役に立てへんから、あきらめて正解や」
「次。『長い間作品を書いていると好調不調の波が出てくる.それは仕方が無い. 「少女保護特区」は不調の作品であると思う. デキの悪い作品の評判が悪いからといって気落ちする必要はないのではと思う. 私はゲイカの作品を愛していますよ』」
「“輝く”って単語、英語で書いてみて。動詞ね」
「ふんふん」
「書けた?」
「書けたで」
「それをローマ字読みして」
「し……おっと、次いくわ。『がんばってください』」
「何を?」
「次。『ブログ形式に移行する前までの作品は全部2回以上は読んでいます。紙媒体に印刷したことはありませんが、ローカルには定期的に保存しています。今のnWoについて愚見を言わせていただけるのなら、タイトルの横に通し番号を付けるのはやめた方がいいのではないでしょうか。一見さんが(1)から読むのは敷居が高いと思います。あと、リライト版は勘弁して下さい。』」
「長いのが増えたから、通し番はしゃあないがな。いまさら新規読者が劇的に増えるとも思われへんし。劇的に増える方法があるなら、一考しまっせ」
「リライト版の方が時間かかってるんやけど……。『次の更新を楽しみに待ってます』」
「どうもどうも。萌え画像、楽しみに待ってます」
「次。『nWoが好きです。閉鎖して欲しくありません。 私を含めて、心を動かされたとしても、数行の感想も書くことのない人間が多いのではないでしょうか。甘い見返りが期待できないならばなおさらに。読み手として弱いのだと思います。』」
「こうゆう単純なうったえにぐっとくるねん。若い女性が書いてると想像して読むわ」
「nWo読者の9割は男性って統計があるで」
「あほか。内気で清楚な女性ほど、尻軽に投票できへんのじゃ。潜在的にはもっとおるはずや」
「矛盾しとるなあ。次。『届かない声を、いつでも上げています。』」
「届いてへん、届いてへん。罰としておまえは小鳥尻ゲイカ歓迎オフ会を主催せえ」
「首都圏で。次。『小鳥さんのテキストはおよそ目にする活字の中で一番好きです 読み手のレスポンスの無さに関しては、文章の完成度と崇高さが遠ざけているきらいがあるだけだと思っているので閉鎖しないでください 学生の頃から拝読していますが、ドープさを増して行く小鳥さんのテキストがどこへ収斂していくのか楽しみにしています』。職業、ベンチャーキャピタリストやて」
「カネやな。カネをもっとんのや。どこに収斂していくかなんて、そんな高尚なもんはおまへんのや。うちら、ネットの芸者商売やさかい、お客さんが呼んでくれればどこででも踊るし、こう踊れェゆうたら、そのまんま踊りますよってに。小鳥尻奴の欲しいのは、カネ、萌え画像、他者承認どすえ」
「めっちゃやらしいな、じぶん。ドープってなんやろね。次。『無理スンナよ』」
「してねえよ」
「身の丈にあったものを更新せえの意かもしれへんで。次。『小鳥さんは最高にカッコイイです。』」
「そっちの名前で呼んでくれる人もおらんようになったなあ。なんかなつかしいわ」
「『窮状なんですか?』」
「はい、それらはバナナです」
「あと少し。『わりと好きです。』」
「憎む、愛す、無視以外の選択肢があることが、すごい衝撃―」
「『他人の評価にそこまで固執するのが分からない。 芥川賞とればいいと思う、取りあえず。 ネームバリューで人が集まって、そしたらその中に本物の読者もいるのではないでしょうか。』」
「どうして父の間違った方の精子が母の卵子と結合したのか分からない。芥川賞の選考委員になってnWoを推薦すればいいと思う、取りあえず。それからプロ野球選手になって5年で二千本安打を達成すればいいと思う、取りあえず。ネームバリューで記者会見が開かれ、そしたらその中でnWoの宣伝もできるのではないでしょうか」
「どう、どう。『パアマンに衝撃を受けて以来ちょくちょく覗いてます。』」
「生きながら萌えゲーに葬られをおさえて、パアマンが一番人気なのよねー。ホームページとそれを更新する人物という枠組みに、更新されているキャラクターが接触を果たすという、シミュレーテッド・リアリティの走りみたいな展開がウケたのかもねー。世界、神、人間。次は?」
「ううん、これでおしまい」
「あら、そう。おしまい」
「オチはないの?」
「ない。考えてきたの、出オチ的につかっちゃった」
舞台に下りる沈黙。それが不自然なほど長くなる前に、襞のついた洋装の少女が、「きみとはやっとれんわ」と金切り声で絶叫する。二人、頭をさげると、観客席におりてくる。カメラの向けられた客席は閑散としており、人はまばらである。水筒の日本茶でせんべいを湿らせて食す老婆や、スポーツ紙を顔にかけて大いびきの中年男性や、接吻とペッティングを繰り返す男女や、思いつめた表情の書生風銀ぶち眼鏡。二人、何かのサービスなのだろうか、身につけた衣類の一部を客席に向けて放りなげるが、誰も拾おうとしない。客席の背後にある両開きから二人が出て行ったあと、思いつめた書生風の青年が衣類を拾いあげ、大急ぎでリュックに詰める。
「あそこで真っ白になるなんて、あそこで真っ白になるなんて」
両手に顔をうめてぐずぐずにすすり泣く大柄のボディコン女性。
「しょうがないわよ、できの悪い日もあるわよ」
大柄のボディコン女性を支えるようにして隣を歩く小柄な洋装の少女。二人のささやき合いは、しかし清掃員が濡れたモップをロビーの床へ叩きつける音にかき消される。
「だいじょうぶよ、芸の不安定さがあなたの売りでしょ」
二人が後にした建物には裸の女性の図画がいくつか大きく掲示されており、入り口にいるもぎりの男性は生来のものだろう、茫洋とした独特の表情を浮かべている。小柄な少女はなぐさめ続けるが、大柄な女性はいっこうに泣きやまない。
「ポルノ映画館で世界を革命したって、誰も認めてくれないのよ。私たちはこの世にいないも同然なのよ」
小柄な少女、大柄な女性の背中をさすりながら言う。
「あたしがいるじゃない、誰がいなくたって、あたしがいるじゃない」
真っ赤に泣きはらした目をむいて、大柄な女性、絶叫する。
「もう聞きあきたわ! あんたがいたって、私は寂しいままじゃないの!」
途方に暮れた表情で立ち尽くす小柄な少女。
「消えないのよ、その寂しさは消えないの。私たちは壊れてるから、その寂しさは消えないのよ……」
激情の冷めた大柄な女性は、小柄な少女を強く抱きしめ、小柄な少女はその抱擁へ一筋の涙を与え、やがて手に手をとりあった二人は「だいじょうぶ、きっと今頃は萌え画像が届いているはず。だからまだ、だいじょうぶ」と励ましあいながら、場末のネオンの中へ消えていく。
痴人への愛(1)
「またひとつ消えたわ」
コーデリアは菜につかう包丁の手をとめると、聞こえぬよう小さなため息をついた。今夜は荒れそうだ。
エプロンで手をぬぐい、右ひざを抱えたまま無表情で涙を流す女性の脇へ、そっと近づく。
視線の先には、Not foundと書かれたノートパソコンの画面がある。
「ずいぶんと前から更新なんてなかったじゃないの」
非難にひびかぬよう注意してささやきながら、コーデリアはその肩を抱き寄せた。子どものように胸元へと倒れこんでくる。
「消えたのよ」
いつものことだ。どんな言葉をかけようと、彼女が救われることはない。
コーデリアは黙って、白いものが混じりはじめた長い髪を手櫛にさすってやる。うながされるように、小鳥尻は短い嗚咽をもらした。
芸名・小鳥尻ゲイカ、本名・小島桂子。数年前に一世を風靡した芸人である。
しかし、巻きスカートをマントの如くはぎとりながら、肌色タイツの股間に接着した亀の子タワシを見せる芸を覚えている者は多くあるまい。タワシを右手ですりながら言う、「ワタシのタワシ気持ちいーで」は流行語大賞にもノミネートされた。だが、この健忘症的な世の中で一年に満たぬ期間のテレビ出演は、人々の記憶力に対して充分に長いとは言えない。
当時、コーデリアは小鳥尻の芸を客席から眺める一視聴者に過ぎなかった。熱狂はあったのだ、と思う。彼女が出演する番組のスタジオ観覧を申し込み、外れたときはテレビ局の外で待ちかまえた。他にも無数に芸人はいたのだし、そのうちの誰に同じ熱狂をささげても不思議ではなかったはずなのに。
司会者が、時事問題などのコメントを小鳥尻に求める。彼女は腕を組んで考えるふりをしたあと、奇声をあげてスカートをはぎとる。「ワタシのタワシ気持ちいーで」を連呼しながら司会者に体当たりをし、観覧席にダイブする。どの辺りに飛び込むかは事前にスタッフから指示があって、観覧者たちは悲鳴をあげながら避けることになっている。床に叩きつけられた小鳥尻が大げさに痛がり転がりまわるのをもって、一連の芸は幕となる。
あのときのことは、いっしょに観覧席へ座っていた友人が後々まで繰り返し話したものだ。もっとも、携帯電話を捨ててからこちら、すでに何年も音信はない。
「あんた、よけようとしないんだもん。それどころか、両手を広げて受けとめようとしたでしょ」
痩せぎすの小娘にすぎなかったコーデリアは、ダイブを受け止めきれず、そのまま小鳥尻の下敷きになって左手を骨折し、腰骨にはヒビが入った。
サングラスにトレンチコートの小鳥尻が、その長身を丸めるようにして病室の入り口に立っていたのを今でも鮮やかに思い出すことができる。小さな花束をぶっきらぼうに片手で突き出すのには、思わず笑ってしまった。
それが、世間でいうところのなれそめというやつである。
コーデリアはレズビアンではない。男とか女とかではなく、小鳥尻だからなのだ。しかし、両親も友人も、理解はしなかった。
この、台所つきの六畳間に越してきて、どのくらい経つのだろう。幸福は夢のように過ぎる。あっというまに過ぎる。苦しみの長さはすでにコーデリアの時間感覚を麻痺させていた。
「みんな私を置いて、行ってしまうのよ」
この台詞も毎度のお決まりのこと。コーデリアの中ではほとんど様式化してしまっている。しかし、それへ返答をするときは常に新しい創造を求められるのである。
声をかけようとして、小鳥尻の目じりに刻まれた皺が、前よりも深くよじれるのを見て、コーデリアは全身に鳥肌を生じた。その沈黙は、しかし小鳥尻の精神にとって有効に働いたようである。
「コーデリア、あなただけ。私には、あなただけ」
小鳥尻の手がエプロンの上からコーデリアの薄い胸をまさぐる。性的な昂揚を求めているわけではない。ただ、肉を感じることで寂しさを消したいのだろう。
ノートパソコンに映るのは、芸人たちのホームページのひとつである。最近はブログというのだろうか。所属する芸能プロが作成し、人気のあるうちはそれなりにファンとの交流の場に成りえる。しかし、落ち目になるほど更新の頻度は間遠となり、やがて自然消滅的な閉鎖へと至るのだ。
ひと握りを除けば、長く続けられる業界ではない。才能と時の合致を得た彼らは、やがて自分の番組を持ち、そのメジャー級の選抜の中でさらなる競争に身をやつしていく。膨大な分母から、総当りのリーグ戦を経て、真の勝者となるのはほんのわずかである。
そして、勝つ見込みの薄いこの業界へ早々に見切りをつけ、全く別の分野に才覚を見出す者も少なくない。だから、芸人のホームページが消えるのは、彼らが現実の中へ居場所を見出したということの裏返しにすぎない。確実なのは、いつまでも残される連中はひとからげに例外なく、何らかの点で欠けている、劣っているということである。
小鳥尻の芸を他の者たちと分かつ要素があるとすれば、それは思考の奇形性であり行動の奇形性である。深まらず、拘泥しないことが流動性を担保する。人生という変化に対処するとき、それは偉大な戦略である。だが、奇形性ゆえに小鳥尻は小鳥尻であり、奇形性ゆえにその芸が真の意味で大衆に受け入れられることはない。簡単に言えば、下ネタでは天下をとれないのである。
しかし、それでも――コーデリアは思う。
王様に対する道化師のように、既存の枠組みをゆさぶることで可視化するという特権を与えられた社会装置が、本来の芸人ではなかったのか。この国の芸人たちはほとんど例外なく、すべて体制の側にいる。彼らの目指す最終的な到達は政治家であるのだから、無理からぬことかもしれない。
この一点においてだけ、小鳥尻は間違いなく芸人である。コーデリアが彼女に引かれた理由もそこにある。
一汁一菜の質素な昼食を終えると、小鳥尻はもそもそと寝巻きを脱ぎはじめる。一張羅のスーツに着替えるのを手伝いながら、コーデリアは彼女の豊満な胸にいまなお残る、横に並んだ細いソーセージのような青黒い色素の沈着を痛ましい思いで眺めた。“風船爆弾”の痕跡である。
“タワシ”が飽きられはじめ、テレビへの出演依頼も減りはじめた頃、小鳥尻が必死に考え出した新しい芸だ。それは、「風船爆弾、風船爆弾」と連呼する相方が、彼女の豊満な胸をパンチングボールよろしく、拳で殴打するというもの。関西の男性芸人からヒントを得たという。最初は上着を脱ぐだけだったのが次第に過激化し、ついにはブラジャーまで外して行うようになった。その相方というのが、何を隠そう退院後のコーデリアである。
詳しい経緯を語っても仕様があるまい。あらゆるメディアからフェードアウトしてゆくという窮地にいた小鳥尻は、国営放送でこの“風船爆弾”をやらかした。生放送中に、生乳でやらかしたのである。謝罪の記者会見で、平身低頭する事務所の社長を尻目に一言の謝罪も発さないばかりか、コーデリアを含む関係者全員が頭を下げる中、小鳥尻はひとり傲然と胸をそびやかした。社会正義に悪酔いした記者があげる社会性を逸脱した怒号に、事務所のスタッフが無理矢理に小鳥尻の頭を長机へ押さえつけ、ようやく謝罪の形を作った。だが、隣にいたコーデリアには、頭を押さえつけられ鼻血を流しながら、にらみつけるように真上へ視線を向ける小鳥尻が見えた。この瞬間、小娘らしい恋の憧れが、大人の愛情へと変わったのだ。
玄関先でブーツに足を突っ込みながら、今日はお客さんに呼ばれてるから遅くなる、と小鳥尻が無表情でぼそぼそ言う。舞台の上のハイテンションどころではない、普段の小鳥尻はほとんどしゃべらないし、感情を露にすることさえまれである。コーデリアはできるだけ明るく返事をするよう努めると、アパートの出口までついてゆき、長身の背中が曲がり角の向こうへ見えなくなるまで立ちつくしていた。
部屋に戻り、玄関の扉が閉まる音を背後に聞く。小鳥尻はいない。当たり前だ。この部屋は、もはやコーデリアにとって何の意味も持たない場所になっていた。小鳥尻がいるからこそ、この空虚な住処がかろうじての避難所として成立する。六畳間をうろうろと周回すると、コーデリアは小鳥尻のいた場所へ呆然と座り込んだ。
私たちふたりが破滅しない方法はなにか。最近、コーデリアが考えるのはそのことばかりである。
週に一度もないような、場末のスナックへの営業ぐらいでは、とうてい食いつないでいけるはずがなかった。コーデリアは相当にいかがわしいアルバイトへ手を染めたこともあるが、小鳥尻が部屋にいる間は磁力のように離れられなかったので、食うに充分な稼ぎを安定して得ることはできなかった。
昨日はついに、母が積み立ててくれていた学資貯金を切り崩した。小鳥尻はそのことを知らない。生活保護のことを相談したときの狂乱を思い出して、恐ろしかったからである。
小鳥尻はただ自分であることをやめられず、他人の夢の残骸に埋もれたコーデリアは身動きさえ取れずに貴重な若い時間を空費してゆく。地獄。そう呼べる場所があるなら、まさにコーデリアの住所はそこであった。だが、角を生やし赤い肌をした官吏たちは空想にすぎない。人はただ、己の意志において地獄に己を閉じ込めるのである。
新宿オフ始末書
「包茎チンポ?」
ビールの中瓶を撫でさすりながら弱々しくつぶやいて右隣をうかがうも、ファンだと名乗ったはずの婦女子2名はベネズエラの描く春画に嬌声を挙げており、すでにこちらへ心を残していません。左隣ではぼくに対しては終始不機嫌だったガンジャが「ええッ、じゃあ“くろのだんしょう”(クロノ男娼? 時をかけるBL話と推測するも、詳細は不明)の作者なんですか!」と身を乗り出し、「いや、いまは猊下のいちファンとしてここにいますから」とまんざらでもない表情のオーツキが中指で眼鏡の位置を直しながらぷくぷくと小鼻を膨らませています。顔を上げると正面には小首をかしげた子鹿が子鹿のような黒目がちの瞳でこちらを見ており、ぼくはいたたまれなくなってそっと視線を外した。これは何の集まりでしょうか。小鳥猊下を歓待するオフ会ではなかったのでしょうか。十年という歳月に過去の失敗を忘れ、浮かれたネットハイで再びオフ会などを企画した一ヶ月前の自分を殺してやりたいです。いや、――うつむいて噛んだ臍から生暖かい血がアゴを伝うのを感じながら――その前にこいつらは全員まとめて呪殺だ。
◇登場人物紹介
小鳥さん……テキストサイトというムラでは大いばり、最近ではほとんどの管理者が現世での成功を手に入れて卒業していったがゆえの長老的な位置に複雑な気分。もはや新規のファンを呼ぶ力も無く、流行りの炎上でアクセス数が回復することを夢見る過去の人物。
オーツキ……プラズマとは関係ない。目の下に黒々と隈が浮いており、能条純一の某漫画に登場した「見える見えるおまえが見える」の人を想像すると近いかも知れぬ。蛍光色の頭髪にグラサンアロハ、体表はピアスで埋めつくされている、くらいを想像していたので逆にフツウで驚いた。
ベネズエラ……南米からやってきたカポエラの達人で、日本語がひどく堪能。本邦での職業にはなぜか萌え系の春画描きを選択しており、nWoにトップ画像を寄贈するなど外見を裏切らぬ精力的な活動ぶりである。既婚者らしいので、おそらく特別帰化を申請したと推測される。
黒子……ホクロではない方で読む。ブログ形式以降のnWo運営担当であり、俺が大臣なら事務次官に相当する。オフ会でさえ、事務方に徹した。「ニコニコ動画はワシが育てた」「酔わないと話ができない人もいるから」の2つを、彼がキャラクターの片鱗をうかがわせた台詞として記録したい。
どどめ鬼……百目鬼ではない。手入れの行き届かないアゴヒゲにどどめ色の上着という、外見だけで正気を疑われる逸材。それを証拠に、ガンジャと職質談義で盛り上がっていた。つごう8時間、どこから金をもらったのかという勢いでnWoを褒めまくり、逆に俺の肛門を警戒で狭くさせた。
BL学園……男子間肛門性愛話をこよなく愛するにも関わらず、nWoのファンだという矛盾を体現する謎の婦女子その1。男子と男子が正常位を行う際、肛門と男性器の位置関係はどうなっているのかという質問を準備して個人的に胸をワクつかせていたが、二次会の途中であっさり帰った。
子鹿……思想系のブログを開設し、喧々諤々の議論を展開する人物。きっと俺のペニスをSuckせんばかりの勢いで議論をふっかけられると脅え、理論武装のため開いた思想書を顔面に乗せて睡眠しながら上京したが、その心配はたちまち霧消した。1時間しかいられないと言いつつ、結局8時間いた。
県知事……似ているわけではないが、そのアクションがなぜか俺に宮崎県知事を想起させた。十年前の東京オフ会で参加を表明したにも関わらず、当日連絡なしに欠席した前回のA級戦犯。理由を尋ねると、「友だちと遊んでて、気がついたら時間を過ぎてました」。俺の怒りは有頂天である。
マコリ……nWoをほとんど読んでいないにも関わらず参加を表明した謎の婦女子その2。指輪で人妻を偽装することで小鳥猊下との対話を性交なしで成功させるも、実は現在彼氏募集中とブログで表明しており、オフ会参加男子全員の性を著しく去勢した。俺の怒りはすでにヘヴン状態である。
ガンジャ……某新興宗教の教祖にそっくりの麻薬密売人風デイトレーダー。終始不機嫌なのはリーマンショックの影響か。毛糸の帽子がお気に入りで、オーツキの大ファン。“生きながら萌えゲーに葬られ”のエンディングに対して批判的なメールを送信した人物であり、今回のA級戦犯。
ちなみに、この並びはアイウエオ順ではない。nWoへの貢献度に基づいたもので、何の恣意も無く公明正大であることをあらかじめ付け加えておく。
ぼくは極太マッキーでnWoと大書きした画用紙を掲げながら、新宿駅の東に位置する交番の前にひとり立ち尽くしていました。日はすでに暮れはじめており、都会の寒風は身を切るようにぼくへ吹きつけます。「アルタビル前は人が多いので」とのアドバイスを受けて設定した集合場所でしたが、駅からは続々と大量の人たちが吐き出されて続けています。おそらく人口過密地帯の東京では、このくらいの数は多いうちに入らないのでしょう。誰もがぼくの薄ら笑いに一瞥をくれると、足早に、まるで競歩のような速度で左右に分かれてゆきます。お笑い番組の企画か何かとでも考えているのでしょうか。あるいは、精神薄弱と思われているのかもしれません。交番を目の前にして、相当に奇矯な行為に及んでいるのではと恐れを抱いていましたが、この程度のエキセントリシティでは淫獣都市・新宿において少しでも己の存在を際立たせることはできないようです。
集合時間のちょうど15分前に、ネット耽溺が形成した何かが顔面の多くを占拠している男たちが「猊下ですね」「猊下ですね」と双子のようなツープラトン攻撃で問いかけてきたので、すっかりうろたえたぼくは右手の小指と薬指と中指と人差し指を口の中に入れて「アワ、アワワ」といった音声で返事をしたが、意外に通じたみたいで安心した。よくよく見るとネット臭以外の共通点はそんなになかったので、落ち着きを取り戻したぼくは、宮崎県知事を思わせるほうへ「どちら様ですか」と質問したのですが、すごい早口で返事をされたので「え、何?」と言うとまたすごい早口で返事をしたので、その場では神妙にうなづいてなんかわかったふりをした。のちにこの男が前回のオフ会へ参加を表明し、表明してから懇切丁寧にブッちぎるという父殺し的行為で精神的愉悦を得た人物だと判明しますが、わかってたらその場で秀でた額にワンパンくれて「ひぎぃ」と声をあげさせていた。もう一人はnWoの管理者でドメイン名とか自腹でとってくれてるファビュラスな人材だったので、周囲には後光が差し両肩には裸の天使がとまっていた。ぼくは抱きしめてチュウしてやろうかと意気込みましたが、値踏みするかのような眼光がグラッスィーズの下で異様にするどかったのでぼくはブルッてしまい、チュウはやめることにした。いずれにせよ、15分前に到着したという事実はぼくのオフレポをきっちり読みこんできたという証拠なので、2名の偏差値は飛躍的に高まりぼくを1万とすると35くらいになった。
いきなり耳元で「土日は案外ここも人が多いな」というつぶやきが聞こえたのでぼくがハリウッド・ジャンプで飛びすさると、肩ごしに振り返った視界に白いジャケットの不健康そうな男が立っていました。それは、メールでぼくが衆人環視のうちに幾度も辱められた遠因をつくった人物のオーツキだった。そして、銀のピアスがネオンを照り返してぼくの目はするどく射られたのです。両腕を上下並行にして顔面を守るポーズで「想像と違いました」と正直なぼくが言うと、眼鏡の位置を神経に中指で直しながら「いま人生で一番ファティな時期でして」と言うオーツキの様子は健康を誇示する言葉の内容とは裏腹の有様で、サラリーマン二人組がまじまじと彼を注視しながら、「どうしたンですか…御気分でも」「いえね、先日知人が交通事故で死んだんですが、それとそっくりですわ…膚の色が。あなた知ってます!? 死んだ人間って“白い”というより、蒼く透き通ってるンですわ」と言葉を交わしつつ通り過ぎてゆくほどです。なので、雑踏で強要されたすごい廉恥をレンチの顔面殴打で難詰しようとする気持ちは急速に冷え、ぼくは後ろ手に鈍器を隠してできるだけ刺激しないよう、「そ、そうなんですか」と保身にかすれた声であいづちをうつ他に方法がありませんでした。
そこへ、公開の遅れている某福音漫画映画の監督にそっくりの風貌をした男が、ショッキングピンクのスウェットに身を包み、常軌を逸脱した者だけに許される確かな足取りでまっすぐにこちらへ向かって来るのが見えました。ぼくは「東京は怖いところじゃ」とつぶやいて視線を外しましたが、案の定その男はぼくの真ン前に立ち止まり、「小鳥猊下ですね」とすごく大きな声で言ったのです。ここはネットじゃないのに! ぼくはたぶん、殺される寸前の小動物が最期にあげる鳴き声と同じ弱々しさで「はい」と答えたのではなかったかと思います。
ほどなく、手首切っちゃいました、意図的に、といった風情の女子と、はいからさんが通った後を踏みにじった、といった風情の女子が順ぐりに現れ、ぼくにあいさつをしたりいきなり触ったりしました。周囲のネット男子たちはことさらに無関心を装い、装うことが関心を裏書きするという、当人だけが看過されていないと信じるあの状態に陥っていた。ぼくは状況へ羞恥するあまり思わず下を向いた。初対面とはいえ、きっとすぐにファン同士の会話が始まり打ち解けるだろうと期待したが、ぼくを囲んで楕円形になった人々はお互いに一言も発さず寒空の下でびっくりするほど無言だった。すごい人ごみの中でネット臭のする人材たちが車座になり、その中心が自分であるという事実に悶絶しそうになりました。ぼくは沈黙に耐えられなくなって、手首を骨まで切った方の女子に「えっと、あのピンクの上着の人、実はエヴァンゲリオンの監督ですよ」と冗談めかしてどどめ鬼を指さすと、「ええッ、本当ですか!」と意外に大きな反応が返ってきたため、ぼくはいまさら嘘だと言えなくなってしまい、「破ではアスカを殺すんですよね、監督?」とノリツッコミをうったえる視線でかぶせると、桃色の関東人が怪訝な表情で首をかしげたので、ぼくは自分の家が大金持ちだと自慢した小学生が次第にエスカレートする己の嘘に追いつめられてゆくような絶望に身をよじったのです。
そして、大きなラジカセをブレイクダンスの両足で蹴り上げながらやってきた明らかにDNAが南米の男により集りのグローバル感とサンバ感は強まり、唇を動かさないまま「ガンジャあるよガンジャあるよ」とつぶやきながらやってきた教祖風の男という加速装置を得て集りのアンダーグラウンド感とクライム感はいっそうに速まった。むしろ、ぼくがオフ会の実施を表明したことが早まっていた。
あと一人こないなー、と思っていたらこの都会の雑踏の中で、ボクとカレだけが天然色で、他の全員はみんな灰色とでもいうようにからみあう二つの視線。それがオフ会参加者最後のひとり、子鹿とボクの出会いだった。
ぼくがキリッとした表情と文体で「アングラサイトのオフ会なのだから、アングラ系の店で」とどどめ鬼に予約を依頼しておいたのに、案内されたのは極めて一般的な居酒屋だった。安普請に前後左右の音声は筒抜けであり、冒頭のような猥語を伝達するのに社会性の最高に高いぼくは小声になった。そこへ、場末の居酒屋特有の客層が織り成す低劣な雑音があいまって、ぼくの小声は最高に聞き取りにくい状態になって、ぼくは自己への嫌悪とどどめ鬼への憎悪で死にたいと殺したいが二重で同時に訪れたので目を白黒させました。
死体遺棄現場の刑事たちのようにテーブルを眺めたまま誰も座ろうとしないので、わざとらしく「どこが上座かなー」などと発話しますも、ネット臭ふんぷんたるチェリーボーイどもは薄ら笑顔を崩さないまま、誰もぼくに席を勧めようとはしません。すると突然ベネズエラが流暢な日本語で「シャチョサンノセキハマンナカネ」と発話したので、ぼくは非常に驚きながらも「ソ、ソリー、アイシットダウン(表記:”So sorry, I shit down.” 和訳:「とてもすいません、私はうんこをします」)」と流暢な英語で発話して真ん中に座りました。するとマコリがぼくからいっこ空けて座り、すかさずガンジャが太いのをぼくとマコリの間にねじこもうとして、そんな太いの入らないと拒否られ、ぼくの反対の隣に不機嫌に座りました。現実では気を遣う性質のぼくが傷心のガンジャをなぐさめる意味でそのたくましい膝を撫でさすりながら「見てくれ。nWoをどう思う?」と尋ねたら、まるで街頭で宗教的なアンケートを求められた人のような、一種異様な素っ気なさで「いや、面白かったですよ」と過去形で返答したので、本当のことを指摘されると人は怒るの法則でぼくのブレイブハートは怒髪天を突いた。表向きは「ハハッ、ワロス」などと巨大掲示板から仕入れた今風ヤングの発話で平静を装い続けたが、ぼくのブロークンハートは血と涙にてらてらと濡れていました。
いつのまにかぼくとマコリの間に細いのをねじこんだBL学園が、熱くたぎった密壺から良く煮えた貝を箸でつまんで「これ見て下さい」と言うので、相手の望むボケを裏切らない関西人のぼくは「イット、ルックスライク、膣」と流暢な英語で発話すると「共食いですね」と得意げに、金髪のわりには流暢な日本語で発話しました。そんな三次元世界から垂れ流される濃密な廃液、いわゆる萌えの原液にチェリーボーイどもで形成された戦線は乱れかけた。しかし、どどめ鬼だけが「きたない、さすが三次元の女きたない」と言わんばかりの心底不快そうな表情ひとつで戦線を維持してのけたので、ぼくは、こいつは本物だぜ、個人的に近寄りたくはないがな、と内心思った。
ビールでのまばらな乾杯と散発的な発話があったのみで、気まずいまま宴は進行していった。最初に気つけで空にしたマイグラスの底はすでに渇き始めていたが、誰も積極的にそれを満たそうとはしませんでした。隣の婦女子たちはもはやケータイ遊びに夢中ですし、対面の子鹿は子鹿のように黒目がちな瞳で小首をかしげ、ただぼくを見つめるばかりです。個人主義の押し詰まった魔都・東京では、手酌が基本なのでしょうか。ぼくを歓待するオフ会のはずなのに! ぼくは一縷の望みをかけて、弱々しい声で「秒速5センチメートルでー」と発話しながらビール瓶へ極めてゆっくりと手を伸ばしたのですが、誰も気づいた様子はありません。絶望的な気持ちになりながら必死に声を張りあげて、「秒速5センチメートルでー」と再び発話しますと、どどめ鬼が「ああ、あれ最悪ですよね」と非常な早口でかぶせて来、己の意図が正確に伝わらない絶望へ拍車をかけたのです。たまらなくなってうつむいたぼくは、眼球からの体液でしっとり濡れた卓へ影が差すのを見ました。顔を上げると、ベネズエラが「シャチョサン、イッパイイクネ」と浅黒い肌へのコントラストのせいか、ひどく輝いて見える真白な歯を誇示しながら、いささか乱暴なやり方ながらマイグラスへビール瓶を傾けました。なんという如才の無いガイジン、あるいは婿養子でしょう。しかし他人を見下さずにはいられないぼくの高貴な性向はその酌を受けながら、ラベルを下に向けて片手でつぐような礼儀の無さは、ぼくの最高に高まった社会性とつりあわないなと考えさせた。
県知事が時折、てんかん発作を疑わせる激しい仕草で笑いながら倒れこみ、周囲へ多大な迷惑となっており、BL学園とマコリの向ける視線は明らかな生理的嫌悪と侮蔑に満ちていた。県知事の笑い声は黒ベタ白ヌキで「ギャヒーッ!!」であり、熱湯風呂から飛び出して床を転げまわっていた頃の宮崎県知事を想起し微苦笑を浮かべていると、県知事は黒い何かに覆われた太くて固いものをぼくにしきりと押しつけて、「この処女雪のような純白を汚すんだ、お前自身の手でな」と強要しました。ぼくがごめんね、ごめんね、と言いながら純白の表皮をわずかに汚すと、特殊性癖の県知事の興奮は最高潮に高まり、一度汚れればあとはいくら汚れても同じと言わんばかりにみんないっせいにそれを汚しにかかったので、ぼくは素面でいることが辛くなって店員に赤ワインを注文すると、黒子と子鹿が無言のまま「わかります、ルネッサンスですね」という表情を見せたので、ぼくの表情はたぶん曇りました。
そして、冒頭のやりとりに話は戻るのだった。加えて、ベネズエラがエルフと関わりがあった旨をさらに発話し、数名がどよめいて、わずかに漂っていたぼくへの関心の残滓は永久に虚空へと失われました。くやしいけど“かたあしだちょうのエルフ”は、ぼくも傑作だと認めています。三十年以上も前に亡くなった小野木学先生と面識があるなんて、嫉妬を通り越してむしろ羨望をしか感じません。詳しいことを聞きたかったのですが、瞬発力に欠けるぼくがおろおろしているうちに、ぼくの知らない小野木作品であるドウキウセイツウ(童貞精通? 同衾生活? 表記は不明)に話題が移動してしまっていたので、ぼくはただお得意の薄ら笑いを浮かべることしかできなかった。ぼくの大切なレゾンデートルはこの時点で死亡した。
しかし、まだだ、まだ終わらんよ。このままでは何のためにオフ会を招集したのかわからない。そう考えたぼくは、極限まで追いつめられた上京もとい状況で、なお尽きせぬ己のパロディ気質に励まされながら、万勇を鼓して参加者全員に問いかけたのです。それはびっくりするほど甲高い、この陰鬱な集まりでぼくが発した数々のうめきの中からようやく意味のある大きな声となって、みなさん、ぼくの更新の中で印象に残ったフレーズを教えていただけませんか、と響きました。それぞれの会話に没頭中だった人々はびっくりしたようにぼくを見、これがぼくを囲むオフ会であることをいまようやく思い出したふうな表情をした。
「あー、パーやんのエンディングの、『いつか愛が誕生するだろうか?』かな」
それ、ぼくじゃなくてトーマス・マンです。あとタイトルが間違ってます。パアマンです。
「祈りの海の最後の一節です。『それでは生きるのがあまりに辛くありませんか』」
グレッグ・イーガンです。それはグレッグ・イーガンが書きました。
「『君は激しく勃起したな』」
……大江健三郎からの引用ですね。
「うーん、じつはあんまり読んでません」
なんでここにいるんだ、オマエは。男あさりか。
全員がうんざりした、もういいですか、という表情をしたので、ぼくはうつむくことで、もういいです、という気持ちを表現しました。うなだれたぼくの後頭部の真上でオーツキとベネズエラが名刺交換を始め、この集まりに意味づけをしようと必死だったぼくの方寸にどよもす騒擾は、ようやくにして止むを知ったのです。ああ、今回のオフ会はエロ業界に生息するこの二人を出会わせた触媒としてのみ、後の世に記憶されるのだな、と。残念、ジョショ(徐庶)の奇妙な冒険はここで終わってしまった!
すっかり意気投合したみなさんが大盛りあがりで二次会へと移動していく後ろを、ぼくはとぼとぼとついてゆきます。二次会が提案されたのは、関西人的痩せ我慢のええかっこしいで、誰かが止めてくれると半ば期待しながら「ここはぼくが払います」と発話するとそれまでぼくの発話すべてを聞き流していた人々がいっせいに会話を中断して、「なに当たり前のこと言っちゃってんの?」という爬虫類のような視線をぼくへ向けたからです。もはやこれは「おい、猊下、ジュース買ってこいよ」の世界であり、求められたのは小銭と紙幣でみっしり充填されたぼくの蜜袋であることが痛感され、繁華街のネオンは水中から見るように滲んだのでした。
ネット臭ふんぷんたる陰鬱な会合へ、終電のある時間帯に見切りをつけた婦女子2名が「じゃ、これからもがんばってね」「感想送るから」と心にもないお義理の発話をしながら退出すると、ほどなくベネズエラがそわそわし始め、「ソロソロカエラナクチャ。オクサンコワイネ。リコンサレタラ、ニホンイラレナクナッチャウ」と告げるが早いか上着をひっつかんで駆け出していきました。察しの良さだけで世渡りをしてきたぼくは、南米の血が持つ奔放な性への志向をうらやむと同時に、こんなアングラサイトのオフ会に参加を表明しておきながら、一瞬でも無事な貞操と共に帰宅できることを夢想した婦女子2名の愚かさが粉々に砕かれることへ、心中、喝采を送ったのです。ぼくはサイトの更新が示すようにエロゲー愛好なので、自分ではない剛直に秘貝が原形を失うことに何より興奮を覚える性質なので、沸騰した欲望にぼくの目は赤まった。なに、泣いてるの、とでも問いたげに子鹿が首をかしげてぼくを見ましたが、そんな猥劣な内心を悟らせることで子鹿の純情を汚すのははばかられたので、ぼくは長い睫毛をふかぶかと伏せた。
そして、この陰鬱な宴も――もしそんな瞬間があったならばのことですが――たけなわを過ぎ、気がつけばぼくは一人で狂躁的にしゃべり続けていた。どどめ鬼がレンタルビデオ店(おそらくAVコーナー)で数名の警官に取り囲まれたときにそうだっただろうギラギラする眼差しでこちらを見ており、黒子が「この人物は果たして忠誠に足るや足らざるや」といった値踏みするグリコ犯の眼差しでこちらを見ており、子鹿が小首をかしげ何を考えているかわからぬ子鹿のような濡れた眼差しでこちらを見ており、秀でた額を脂で輝かせながら県知事がぼくの許可を得ないままぼくの動画撮影をはじめており、徹夜明けで月曜に締め切りが2本あると言っていたオーツキは腕組みしたままの半眼で涅槃に魂を浮遊させており、ガンジャは先ほどオーツキの隣で活き活きと話をしていたときの様子とはうってかわった倦怠ぶりで机につっぷしたまま動かなかったからです。話せども話せども場の空気は冷えてゆくばかりで、ぼくを歓待する会だったはずなのにぼくをエンターテインさせようとする人物はもはや一人もいませんでした。無理もありません。ここで行われているのは、対等の知性がする軽妙な会話のキャッチボールではなく、舞台の芸人が面白ければ笑い、面白くなければ席を蹴る、あの場末の演芸場のやりとりだったからです。それを証拠に、わずかの沈黙を縫うようにして、つっぷしていたガンジャが無言で上着を着始めたことが散会の合図となりました。小便というよりは涙を排泄するためのトイレを済ませて店を出ると、もはやそこには誰もいませんでした。地方在住の人間が深夜の歌舞伎町に取り残される気持ちがいかなるものか、説明してもきっとおわかりいただけないでしょう。恐怖と憤りがぼくを疾駆(sick)させました。すでに排泄を済ませたはずの涙袋から、再び止めようもなく涙が盛り上がり、そしてスローモーションで風に運ばれてゆきます。
来るんじゃなかった、東京。やるんじゃなかった、オフ会。
誰かがアテンドしてくれることを期待していた東京観光(興味が無いふうで連れ込まれる秋葉原のメイド喫茶、といった甘い夢想!)はもはや煙と消え、ぼくは始発の新幹線で頬袋をシュウマイに充填させつつ帰阪するのでした。
諸君、ガンジャは2回、残りの連中は全員1回ずつ呪殺である旨をここに宣言する。
痴人への愛(2)
「いいお湯だったねえ、おまえさんっ」
底抜けに無邪気な声音に、ふとつられてふりかえった。
「あんまりはしゃぐとあぶないよ」
洗面器を小脇にかかえた女の子が、楽しそうにくるくると回る。苦笑しながらかたわらでいさめているのは、兄だろうか。両目が隠れるほどに前髪をおろしている。上着を脱ぐと、さりげない仕草で女の子の両肩へと乗せた。たちまち不満そうに口をとがらせるのが可笑しい。
「もう、保護者きどりなのね! そんなカッコじゃ、寒いでしょ」
タンクトップから健康な二の腕がのぞいていた。春が近づいたとはいえ、夜の大気はまだ冷たい。
「このくらいなら、へいちゃらさ。大陸はもっと寒かったからね。それより、――に風邪をひかせて、あとでお父さんにしめあげられるほうがこわいよ」
めずらしい名前だったが、一回では聞きとれなかった。とたん、ころころと鈴のような笑い声がひびく。
もし、きょうだいでないとすれば、輝くばかりの桃色に染まった頬は、湯ばかりが理由ではあるまい。なつかしい、痛いような気持ちが喉元へこみあげた。なんとなく立ちつくしたまま、この幸せなやりとりをながめる。
ふたりの後ろ姿が曲がり角に消えると、コーデリアは寒さを思い出したかのように襟元を寄せた。小鳥尻とのあいだにも、たしかに蜜月はあったのだと思う。また、あんなよろこびはやってくるのだろうか。
問いかけるように顔を上げた先に、答えが見えた。カーブミラーに映るゆがんだ鏡像は、すでに百年もうみ疲れているようだった。
そして、先ほどの女の子はもしかすると、じぶんとそれほど変わらぬ年齢かもしれないと思いいたり、コーデリアは身内に真冬のような底冷えを感じたのである。
小鳥尻が一週間ぶりにもどるというその日、コーデリアは近所の銭湯へ出かけた。もともとあまり汗をかかない体質に質素な食生活があいまって、風呂の無いアパートでの暮らしは苦にならなかった。ときどき、小鳥尻が酒を割るさいあまらせた湯で身体をふいた。
切りつめた生活のなか、正直かたちに残らない三百円の出費は痛い。しかし、久しぶりに帰宅する恋人に、最良の姿を見せたいという想いがまさった。つまるところ、失望されたくない、捨てられたくないという共依存が、ふたりの関係へ力学として作用しているのだが、幸いにもというべきか不幸にもというべきか、コーデリアはそれを言葉にできるほど賢明ではなかった。
オレンジ色に射す西日の中で味噌を溶くと、鍋からふわりと暖かさが広がる。この、幸福に満たないぬくもりをコーデリアは愛した。むくわれて然るべきと感じられるこのささやかさが、願いのはかなさによくみあうからだろう。
卓上の夕食はいつもより一品、菜が多かった。小鳥尻の帰宅は、すべてが冷えてからだった。案の定、ひどく酔っていて、そして舞台にいるときのように上機嫌だった。
「ごめんね、昔のファンが集まって、宴会になっちゃってさ……でもすごいのよ、もう大盛りあがりで、私ひさしぶりにすごく楽しくって」
玄関でひさしくなかったような熱い口づけをすると、コーデリアに菓子袋を押しつけた。
「ファンのひとりにもらったの、すごく上等なお店のケーキなんだって」
袋には、大量生産で有名なチェーン店のロゴが刻印されていた。だまされているのか、だまそうとしているのか、コーデリアにはわからなかった。気が高ぶらぬよう、声がかすれぬよう、ゆっくりと唾を飲みこんでから、言った。
「お水くんだげるから、座ってて」
蛇口をひねると、白く濁った水道水がプラスチックのコップへ満たされてゆく。この上機嫌は良くない兆候だ。こころはまるで振り子のように、上がったぶんだけかならず下がる。なぜみんな、そっと静止させておいてくれないのだろう。
「もうすごいのよ……みんなずうっと私のことをほめてくれてね、アンタはすごい芸人だって、大好きだって、愛してるって……だから、うれしくなってね……みんな私のオゴリにしちゃった……」
語尾をひそめてうかがい見るのは、やはりすこしは後ろめたいからか。おそらく酒が言わせたのだろう、ファンと名乗る人物たちの無責任な発言を、コーデリアは呪いたいような気持ちになった。ふだんは臆病で人嫌いの小鳥尻なのに、どういうわけか己を肯定してくれる言葉だけはびっくりするほど素直に信じこんでしまう。
わずかばかりを節約したところで、破滅への秒読みはいつも大幅に繰り上げられる。コーデリアはじっさい視界が狭まるような錯角を感じ、わずかに首をふった。やさしくて純粋なこの人は、左右からふたりを圧しつぶそうと迫る絶望の壁へさしわたすつっかい棒が、この世に金銭しかないということがわからないのだ。いっしょにいられるなら死んでもいいと思ってついてたきたはずなのに、いざそれが現実的な結末として近づいてくると、なぜこんなにも悲しくてつらくて、胸が痛むのだろう。
後れ毛をはねのけるふりで、そっと目尻をぬぐう。笑顔を作ってふりかえったところで足に力が入らなくなり、コップを抱えたまま膝からその場にへたりこんだ。
「怒ったの? ねえ、怒ってるの?」
小鳥尻は台所の板敷きに正座する形のコーデリアへいざり寄ると、膝に顔を埋めて腰へ手をまわした。コーデリアは思う――この人がじぶんからやってくるのは、だれかにゆるしてほしいときだけだ。
「でも、聞いて! 集まりに局の人がいてね、十年も同じ芸でもつのがすごいって言ってくれて……で、私の芸はあんまりすごいから、いっしょに仕事してみたいって。だからきっと、またテレビに出られるわ……そうしたら、こんなアパートひきはらって、ふつうの人みたいに……」
小鳥尻の声はそこで小さくなっていった。
「ねえ」
――落ちる。
コーデリアには次の言葉がもうわかっていた。こぼさぬようコップをかたわらへ置くと、広い背中をさすってやる。
「死のっか」
魅惑的な負の演技に引きこまれぬよう注意しながら、じゅうぶんな間をとって、言った。
「テレビ、出るんでしょ」
「出れるわけないじゃない」
驚いたことに、小鳥尻は即答する。妙にきっぱりとした口調だった。
しかし、続く言葉は夢見るようにかすんだ。
「私ね、舞台に上がる前は奇跡が起きるような気がするの。もし、この舞台をうまくやり終えたら、みんなが私に拍手をして、そうして次の日からは誰からも愛されるように、誰からも必要とされる私になれるんじゃないかって思うの」
「うん、うん」
小鳥尻の求める愛は、無条件の愛だ。赤子が母親に求めるような、本人にとっては生命の存続にかかわる重大な愛だ。けれど、この世のだれがその重さを引き受けてくれるというのか。
「でもね、私わかってるの。それは祈りみたいなものなの。いつもかならず、裏切られるの」
コーデリアは黙って背中をさすり続けた。
「昔ね、みんなが私を見て笑ってるときにね、いま心臓マヒとかで死ねたらなって、よく思った。だれか、私の芸でみんながいちばん盛りあがってるときに、撃ち殺してくれないかな。みんなが私だけを見て笑ってるときに、うしろからぱぁんって」
まばたきすればこぼれそうで、コーデリアはただやさしく目を細めた。
「じゃ、こんどテレビ出たとき、殺してあげる」
「うん、殺して。きっと殺してね」
曖昧な、子どものような口調でそうつぶやくと、小鳥尻はそのまま眠りに落ちた。
月光が照らすその横顔は、死人のように青白かった。きっと、小鳥尻という存在はとうの昔に死んでしまっているのだ。人工呼吸器につながれた脳死患者のように、むなしい希望を永らえさせているだけなのだ。
だが、またひとつの危うい瞬間を乗りこえ、小鳥尻の生命を明日へとつないだことに、コーデリアはある種の満足を覚えているじぶんに気づいた。そしてそれは、ひとつの決意へと昇華する。
この人の、最期の瞬間を看取る。できるだけ長く、小鳥尻を生かしてやろう。
そう、まるでひとつの季節をしか生きない昆虫が、虫かごという牢獄で越冬するように。
MMGF!~もうやめて、みんなゴア表現に震えてるわ!~(外典・狂都奈落鏖断阿修羅地獄変)
わたしの名まえは、琴理香(こと・りか)。どこにでもいるふつうの女の子。
でも、わたしにはヒミツがある。小鳥猊下(ことり・げいか)ってハンドルネームで、「ねこをおこさないように」っていう名まえのちょっといけないホームページを運えいしているの。ともだちも知らない、お父さんとお母さんにも言ってない、わたしと、そしてあなただけのヒミツ。
いま、わたしは京都にむかうでん車にのっている。ネットでの知りあいに会うためだ。
かの女の名まえはSMD虎蛮(さめだ・こばん)。ひょんなことから「ねこをおこさないように」にイラストを描いてもらうようになった。いつものことだけど、ネットでしか知らない人とはじめて会うのってドキドキする。いったいどんな子なんだろう。もしかして、わたしたち、ともだちになれるかな?
そんな楽しい空そうにひたっていると、ビートルズのイン・マイ・ライフのイントロが、たんたんたたたたん、とひびいた。
ケイタイの着メロ。あ、虎蛮ちゃんからだ。
「アンタ、いまどこにいんの?」
まえおきもなしの不きげんそうな声に、わたしの体はビクッとなった。まだでん車のなかだよってつたえると、
「ハァ? なにそれ? こっちはもうとっくに着いてんだけど?」
わたしはあわててじぶんのうで時けいを見て、それからでん車のなかの時けいを見た。まちあわせまで、まだ1時間いじょうもある。
すごくきつい口ちょうだったので、もごもごと言いわけみたいなへんじになった。そしたら、ケイタイのむこうがわでハーッと大きなためいきがした。
「これだから、ネット界隈でひきこもってる人種とやらは……」
ちいさな声だったけど、たしかにそう聞こえた。すっごく気にしてるネットひきこもりのことをズバッと言われたので、わたしはなみだがジワッとでてきた。
「あんたさあ、もしかしてイタリアかどっか、日本じゃないとこの出身なわけ? 私の担当編集なら遅くとも2時間前には待ちあわせ場所に来て、背筋のばして正座してるわよ。もう信じらんない!」
30分まえには着くつもりだったのに、虎蛮ちゃんのギョウカイでは2時間まえに着くのが常しきだったなんて! そうぞう力のないじぶんのダメさにガッカリしたら、もうなみだがポロポロととまらなくなった。
「ごめんね、ごめんね、いそぐから、ごめ」
んね、を言いおわらないうちにプツッとつう話がきれた。
わたしはすっかりうろたえて、とおりかかった車しょうさんに、「もっとはやく着きませんか」とたずねたら、「電車ですからねえ。時刻表どおりにしか着きませんねえ」と、にが笑いされた。
さしむかいの席にすわっていた上品そうなおばあさんが、そのやりとりを聞いてホホホと笑った。
わたしはバカなことをたずねてしまったじぶんがはずかしくなって、でん車が京都駅に着くまでまっかになって下をむいていた。
ドアのまえで足ぶみしていたわたしは、でん車がとまるとすぐにみやこじかいそくをとびおりた。はあはあと、いきをきらせて駅のかいだんをかけあがる。
まちあわせばしょは、しんかんせんの改さつがある中おう出口。そこに、わたしとおない年くらいの女の子が立っていた。ツイッターのにがお絵そっくりで、わたしはそれがSMD虎蛮ちゃんだって、すぐにわかった。
「虎蛮ちゃん!」
虎蛮ちゃんにかけよると、わたしは地めんにおでこがつくぐらい、おもいっきりあたまをさげた。
「おくれてごめんなさい!」
きっと、すっごくおこられるんだろうって、かくごしてた。でも、虎蛮ちゃんはいがいそうに、
「へえ、あんた、女の子だったんだ! あんなホームページやってるから、私はてっきり」
どうやら、あんまりおどろいたので、おこってたのをわすれちゃったみたい。
ホッとするとなんだかうれしくなって、わたしは虎蛮ちゃんにまくしたてた。
「うん、はじめて会った人にはよく言われるんだー。わたし、琴理香。リカってよんでね!」
「リカぁ?」
けげんそうな顔。近くだと、たしかににがお絵そっくり。
でも、よくよく見ると目のしたはうっ血してまっくろで、目つきはすさんだ感じをしていて、すこしこわかった。
「あんた、猊下でしょ? 小鳥猊下。ちがうの?」
これもいつものしつもん。
「えっとね、じつは小鳥猊下って、ふたりでつかってるハンドルネームなの。『ねこをおこさないように』ってね、10年まえにネットで知りあったパイソン・ゲイってアメリカ人といっしょにやってるの。かれがギャグたん当で、わたしがリリカルたん当。もう気づいたかしら? コトリゲイカって、コト・リカとゲイのアナグラムなんだよ!」
わたしがみぶり手ぶりでいっしょうけんめいせつ明すると、きびしかった虎蛮ちゃんの表じょうがすこしゆるんできた。
「へえ、ゆでたまご方式ってわけね。ようやくガテンがいったわ。じゃなきゃ、あんな精神分裂みたいなホームページの説明、つかないもん!」
虎蛮ちゃんのことばはとてもするどくて、わたしの心にグサッとつきささった。
(表げんをする人って、みんなこんなかんじなのかな……)
わたしはまたジワッとなみだがでてきたけど、なんどもまばたきをしてごまかした。そして、キズついたことをさとられないよう、できるだけ元気にたずねる。
「ねえ、あなたのこと、SMDちゃんってよぶべき? それとも、虎蛮ちゃんってよぶべき?」
すると虎蛮ちゃんは近くのまるいはしらに背なかをあずけて、ちょ者近えいのときのお気にいりのかっこうみたいなポーズをした。
「そうね、私のことは……ダコバって呼んで」
「だだだ、ダコバぁ?」
思ってもみないへんじにおどろいて、すこしどもってしまう。虎蛮ちゃんの顔はひらべったくて、どう見ても日本人ってかんじだったから。もしかして、いまはやりのドキュンネームってやつかな? 堕枯馬、とか書くのかしら。
そうこう考えているうち、虎蛮ちゃんの顔にみるみる不きげんがもどってきたので、わたしは大あわてでまくしたてた。
「ダコバ! すっごくステキな名前ね! 秋の夕ぐれみたいな! わたし、夕日が麦わらにてりかえすのを想ぞうしちゃった! そういえば、ふんいきもダコタ・ファニングってかんじ?」
虎蛮――いや、ダコバちゃんの小鼻がすこしふくらんだ。この方向でいいみたいだ。
「はじめてあのホームページを見たときから、なんていうの、センス? とにかくあなたはちょっと他の管理人たちとはちがうなって感じてたわ。本当に奇遇なんだけど、SMD虎蛮もね、じつはふたりの共同ペンネームなの」
「えーっ!」
わたしがほんとうにびっくりして声をあげると、ダコバちゃんはすっごくとくいそうな顔をした。うん、やっぱりこの方向でいいみたい。わたしは心のなかで、すこしホッとする。
「アイツ、不法入国者なんでちょっと国の名前はかんべんしてほしいんだけど、中東出身のサメン・アッジーフって男とコンビで漫画やってるの。私がストーリー担当で、かれが作画担当」
「あー、わかった! サメダコバンって、ダコバとサメンのアナグラムだ!」
わたしが胸もとで手のひらをパチンとうちわせると、ダコバちゃんはくちびるのはしをまげてフフッっと笑った。
「ご明察、こわい子ね……。あなたのこと、ただの時間を守れない、社会不適応のだらしないネットひきこもりだって思ってたけど、なかなか頭の回転が速いじゃないの。私たち、なかよくなれそうね。改めてよろしく、リカ」
ダコバちゃんはそう言いながら、右手をさしだしてきた。わたしはまた、ダコバちゃんのするどすぎることばがグサッと胸にささっていた。
わたしはなみだがジワッとでてくるのをがまんしながら、その手をにぎりかえした。ダコバちゃんの手のひらは、ちょっとにちゃっとしていた。
「ねえ、トウキョウから長たびだったでしょう? おなかすいてるんじゃない?」
わたしはまず、ダコバちゃんをお昼につれていくことにした。ダコバちゃんをよろこばせたかったのと、「リカ、人間はおなかがいっぱいのときには不きげんになれないよ」って、おばあちゃんからいつもおそわってたから。いっぱいいっぱい考えて、京都駅ビルのいちばんうえにあるお店を予やくしてあった。
「うわーっ、すごい!」
ふうがわりなビルの外見に、ダコバちゃんが子どもみたいなかん声をあげる。そのようすに、なんだかわたしまで楽しくなってきてしまう。
「これって、リカがホームページに書いてたところよね」
大かいだんをチョコレート、パイナップルって言いながら1だんとばしでのぼっていたダコバちゃんが、ほっぺをまっかにしてふりかえる。
「えーっ、ダコバちゃん、そんなのおぼえてるの?」
「リカの書いたことならなんだっておぼえてるわよ」
ダコバちゃんがいたずらっぽくくちびるのまわりをペロッとなめるのを見て、わたしはなぜかドキッとする。
「たしか、たくさんのガラスがまるで処女膜みたいって書いたのよね!」
わたしはとたん、じぶんがまっかになるのがわかった。
「もうっ、ちがうんだから! あれを書いたのはわたしじゃなくて、パイソンなんだから!」
「がおーっ、ガメラだぞー! ちんぽだぞー!」
ダコバちゃんはすっごく大きな声でさけぶと、ふざけてわたしを追いかけてきた。まわりの人たちがこっちを見てヒソヒソ話をしているのは気になったけど、いまのわたしたちって、とてもいいかんじじゃない?
「もう、ダコバちゃん、やめてよ! はずかしいったら!」
笑いながらふりかえると、大かいだんのまんなかでダコバちゃんが右のわきばらをおさえてうずくまっていた。
「ダコバちゃん、どうしたの!」
わたしの声は悲めいみたいだった。心ぱいに胸がつぶれそうになりながらかけよると、ダコバちゃんの顔は花輪和一の漫画みたいにオッサンになっていた。首をかきむしりながら、うわごとのようになにかつぶやいている。
「うう、手が、手がふるえよる……ワシ、漫画家なんやで。右手一本でかせがなあかんねんで……」
どうしよう、ねっ中しょうかもしれない。
「すずしいところでよこになったら、きっと楽になるわ。がんばって!」
わたしはダコバちゃんにかたをかすと、予やくしていたお店までひきずるようにしてはこんでいった。
お店に着くと、ダコバちゃんはそれまでくるしんでいたのがウソみたいに、じぶんでカウンターまであるいていって、ながれるようにスツールへこしかけた。
それから、すごくナチュラルに生ビールを3はい、ちゅう文した。顔は女の子にもどっていた。
わたしがあっけにとられていると、すぐにしゅわしゅわとアワをたてる金いろのビールがはこばれてきた。わたしののどが、ゴクッとなった。
「1ぱいは私に、1ぱいはあなたに。そしてもう1ぱいは――」
かっこよくグラスをかたむけてゆかにこぼしかけて、
「やっぱり私に」
ダコバちゃんはそのままいきもつかずに、2はいのビールをグーッとあけた。
6月にしては、すごくあつい日だった。わたしはビールにまほうがかかってるみたいにさからえなくなって、ダコバちゃんを追いかけてグラスをグーッとあけた。
ぐ、ぐふぅ。
わたしはそのとき、じぶんが花輪和一の漫画みたいに顔だけオッサンになっているのがわかった。ヒゲをじゃりじゃりいわせながらくちびるのアワをぬぐう。
うふふ、でも平じつの昼からアルコールをのむハイトクカンで、リーサラにとってのビールはますますおいしくなるなんて、自ゆうぎょうのダコバちゃんにはわからないかもね。
なんて考えながらダコバちゃんのほうを見ると、編集王でマンボ好塚が自販機のとなりで酒を飲んでいるときみたいな顔で右手を見つめながら、「へ………へへへ。見てみィ………へへへ……。震え……止まりよったで……」なんてつぶやいているんです。すると、じしん(ふきんしん!)みたいにブルブルしていたダコバちゃんの手のふるえが、みるみるおさまっていったのです。
しろ目のところがきいろくなってるのが見えて、わたしはゾッとして目をそらしました。
「うーん、やっぱり外はあっついわね! ねえ、ダコバちゃん、どこか行きたいところはあるかしら?」
アルコールくさい息で大きくひとつのびをすると、わたしはうきうきしながらダコバちゃんにたずねました。
京都には、お寺とかむかしのものがたーくさんあって、ダコバちゃんといっしょにそういうばしょをかん光できると思うと、なんだかしゅう学りょ行のときみたいでとってもワクワクしたからです。
そのときダコバちゃんの目がするどくなり、なにかだいじなことをおもいだしたみたいな表じょうになりました。
「あるわ。三条河原町まで出るわよ」
「あっ、かわらまちなら地」
下鉄、と言いおわらないうちに、
「ヘイ、タクシーっ!」
ダコバちゃんはサルまんの編集者みたいに、すごくナチュラルにタクシーをとめていた。そ、そうよね。ダコバちゃんはうれっ子なんだから、金せんかんかくがちょっとブッとんでても、すこしもヘンじゃないよね。
ダコバちゃんはながれるようにタクシーへのった。わたしがさいごにタクシーにのったのはお母さんが急びょうのときだったので、すごくドキドキしながらあとにつづいた。
かばんからアイパッドをとりだすと、ダコバちゃんは「ここ。ここ行って」とタクシーのうんてん手さんへ、画めんをカツカツいわせながらゆびさしました。
いっしゅんチラッと見えたアイパッドの画めんには、まっくろなはいけいにデザインかな? いろとりどりの草があしらってありました。でも、どうしてまん中に大きなドクロマークがついてるんだろう?
「元ヤン……学校内ヒエラルキー……ナウシカ……パイオツでかい……幕末や新撰組……手垢のついた題材……あるいは……」
タクシーにのっているあいだ、ダコバちゃんはまどのそとをながめながら、ずっとひとりでブツブツ言っていた。
わたしはなにか単ごが出てくるたびに「うん、そうね、そのとおりね」とあいづちをうったが、りこんすん前のじゅく年ふうふのように、かい話はせい立していなかった。
かも川ぞいをしばらくはしると、タクシーは京都にもこんなばしょがあったのかって思うぐらいすさんだかんじのうらろじにとまりました。
黒ネコがダコバちゃんとわたしを見て、フーッと毛をさかだてながらはしっていきます。お昼なのにかんばんのネオンがぴかぴかするホテルがあって、すぐ目のまえですごくふつうじゃない服そうのカップルがなかへ入っていきました。
「ねえ、なんだかこわいよお」
わたしはダコバちゃんの服のはしっこをつかんで、小さくなってついていきます。
ダコバちゃんははじめての土地なのに、すごく自しんにみちあふれた足どりでよごれたビルのかいだんをのぼっていき、いくつめかのとびらで立ちどまりました。
「ここね」
そこはかんばんもなにもあがってなくて、マンションかアパートのふつうの1室ってかんじです。
「リカ、あなたはここで待ってなさい」
「え、でも」
「いいわね?」
ダコバちゃんはきゅうにわたしをだきよせると、うむをいわせないかんじでおでこにキスをしました。
わたしがボーッとなってるうちに、ろう下の左右に目くばりしてから、うすくあいたとびらのすきまに体をすべりこませました。
いっしゅんチラッと見えたへやのなかのようすは、むかし夜のえい画で見たアヘンくつのようにけむっていました。ガリガリにやせたスキンヘッドの男の人がソファであおむけになって、「ねえさん、このハイゴウ、サイコウやわー」と、ろれつのまわらないようすで言っています。
バタンととびらがしまると、わたしはひとりきりになりました。このビルのかんけい者らしいモヒカンの男の人が、わたしをにらみながらかいだんをのぼっていきます。
わたしはこわいのと心ぼそいので、なみだがジワッとでてきました。
すごく長い時かんをまっていたような気がしましたが、時けいを見ると10分くらいのことでした。ダコバちゃんが草の入ったスーパーのふくろをかた手に出てきました。
「待たせたわね。どうしたの、あなた、泣いているの?」
やさしくだきよせられるとボーッとなって、こわかったのもぜんぶどうでもいいみたいな気もちになりました。
「ダコバちゃん、その草は……」
「ああ、これ? アシスタントへのおみやげ。京野菜らしいわ」
話だいをうちきるように早口で言うと、ダコバちゃんはスーパーのふくろをわたしからかくしたいみたいにカバンのおくへとねじこみました。
「ねえ、せっかくはるばる来てくれたんだし、もっと京都っぽいところをかん光しましょうよ」
わたしはかん光ガイドをとりだしながら言いました。
それに、もうこんなこわいところはたくさんだわ。
「そうね、せっかくあなたとふたりきりの時間なんだしね」
ダコバちゃんがやわらかな表じょうでうなづき、わたしははじめてまともに話を聞いてもらった気がしました。
でも、すぐにそれは気のせいだったことがわかりました。
おたくのせい地・きょうと(狂屠)アニメーション(通しょう・狂アニ)は、各ていしかとまらないふつうの駅のふつうの住たくがいにありました。ピロリンって音が聞こえて、それはダコバちゃんがスマートフォンで狂アニのたて物をさつえいしているところでした。
「ちょっとツイートしてみるわ。『狂アニなう』っと。人生初なうー」
いっしょにお寺をめぐったり、まいこさんの衣しょうを着て写しんをとったり、そういうしゅう学りょ行みたいなのを期たいしていたわたしは、じつはない心ひどくガッカリしていました。
でも、はしゃぐダコバちゃんのすがたを見ると、これはこれでいいかなって気になってきます。でん車にのっているときのダコバちゃんは、ハンターハンターの幻影旅団の団長みたいな人殺しの表情で、「狂アニ……ふむ、狂アニか……少し、興味がわいてきたな……」などと気のないふうでした。なのに、いまは大よろこびですもの。
それにしても――
げいおん(鯨音)!のポスターがはってなければ、ふつうに見のがしてしまっていたかもしれない、ふつうのたて物です。ただ、正めんのかべはピカピカするきいろでぬられていて、わたしは同じいろのきゅう急車を町でみかけたことがあるのを思いだした。
となりのおばさんがうつむいたむす子さんをのせながら、「この子、20年くらい外でてなくって」と、なぜかすごくスッキリした顔で言ってたっけ。
わたしは、狂アニにはってあるポスターをまじまじと見つめました。ネットサーフィンくらいの知しきしかありませんが、女子高生4人ぐみが反ほげいかつ動に青春をささげるアニメで、この冬のげきじょうばんでは、グリーンピース本ぶへゲバぼうでカチコミをかけるのだそうです。
ドカッ、ドカッ。
首をまよこにかしげながら、なぜこんなアニメが大ヒットするのかしらと考えていると、うしろで大きな音がしました。
ふりかえればスマートフォンをにぎりしめたダコバちゃんが、近くの水ぎんとうになんどもなんどもナガブチキックを入れています。キックのたび、水ぎんとうはでんげんの入ったバイブみたいに大きくゆれました。
「やめて、ダコバちゃん!」
わたしがうしろからだきつくと、ダコバちゃんは花輪和一の漫画みたいに顔だけオッサンになっていました。
「4000人もいるくせに、雁首そろえてだんまりかよ! この、おしフォロワーどもめが! 俺がツイートしたら5秒以内に『オッ! SMD先生、ついに狂アニと仕事ですか! やっぱすげえなあ!』くらい気のきいたレスつけるのが礼儀だろ、フツー! 俺がツイートしたら5秒以内に『SMD先生と狂アニのコラボ、濡れちゃいます! 抱いて!』くらいのレスしながら自画撮りマンコの写メ送るだろ、フツー!」
ダコバちゃんのはつ言はまったくふつうどころではありませんでしたが、たしかにツイートしたのにまったくはんのうがないときの、せかいにひとりぼっちのかんじはさい悪です。みんなにサービスしたくってたくさんツイートしたらフォロワーががくんとへったときのことを思いだして、わたしはなみだがジワッとでてきました。
「ダコバちゃん、もうじぶんをキズつけるのはやめて……フォロワーなんて、そう、コクゾウムシだと思えばいいのよ」
「ダイオウグソクムシ?」
「いえ、コクゾウムシ。フォロワーなんて、4000びきのコクゾウムシと思えばいいの。そしてダコバちゃんはお米。お米がないとコクゾウムシは生きていけないのよ!」
わたしは、テキストを中しんとしたホームページをやっているだけあって、気のきいたなぐさめを言うなあと思われてると思って、言いながらすこしとくいになっていた。
でもダコバちゃんは、耳がとおい人のようにすごい大きな声で、
「え、おめこ? おめこどこ?」
とききかえしてきた。このテのおたくたちにはすっかりなれっこですよというかんじの近じょの人たちが、なかばほほえみながらこちらを見ていた。
すっかりはずかしくなったわたしは、花輪和一の漫画みたいに顔だけオッサンになって、「なにがおめこだよ! クンニしろよ、オラァ!」とあらあらしくさけぶと、「あのね、みおたんのTシャツを着て上から自分の乳首をまさぐると、みおたんを犯している気がして興奮する」などと意味不明のうわごとをくりかえすオッサンをでん車にむりくりおしこみました。
「もしジャンプで連載もてたら、五重塔の上で妊婦と神父がバトルする漫画描くわー」
こうふく寺のがらんをさつえいしながら、ダコバちゃんは上きげんでした。わたしは、わがままなこい人にふりまわされる気もちでそのようすをながめていた。
日もくれようとするころ、わたしたちはなぜか奈良にいました。
それにしてもダコバちゃん、なんで奈良にやどをとったんだろう。もしかするとトウキョウの人にとっては京都と奈良と五島れっ島のあいだに、大きなちがいなんてないのかもしれません。
でも、せっかく奈良まで足をのばしたんだし、あしゅらぞうが見たかったわたしはダコバちゃんをこうふく寺へつれていくことにしたのです。でも、それが大きなまちがいだったみたい。
国ほうかんに入るやいなや、みるみるダコバちゃんの表じょうはくもっていき、花輪和一の漫画みたいなオッサンの顔になった。
「なんだよ、このギャラリーフェイク、エロ要素ねーなー」
などとつぶやきながら、パイプいすにすわっているショウワみたいな顔だちをした黒メガネの学げいいんに「あれ、あなた知念さん? 国宝Gメンの?」などとなれなれしく話しかけはじめた。
わたしはなんとかダコバちゃんの気をそらそうとして、
「ねえ、これ地ぞうぼさつよ! ダコバちゃんの大すきなまどか(円広志?)にも出てたんでしょ?」
言いおわるか言いおわらないかのうちに、ダコバちゃんの顔はみるみる特攻の拓に出てくる不良みたいにけわしくなっていった。りゆうはわかりませんが、どうもふれてはいけない話だいみたいでした。
わたしはすっかりうろたえて、「あの、お花をつんでくるね!」と言いのこしてそのばをはなれました。
お手あらいからもどってくると、大あばれしてるかと思っていたダコバちゃんは、ねっ心にみろくにょらいざぞうを見あげていた。わたしはすこしホッとして、
「ミロクさま、ステキなお顔をしてるわよね。ダコバちゃん、気に入ったの? 絵ハガキかう?」
そのときわたしは、ダコバちゃんの右手が、ハンターハンターでネテロ会長が百式観音・零をはなつときみたいに、親ゆびと人さしゆびがわっかをかたちづくり、中ゆびが立ったじょうたいになっているのに気づきました。
口をふさぐいとまもあらばこそ、ダコバちゃんは、
「コイツの左手、なんか手マンみてえ」
とすごい大きな声で言いました。わたしはそくざにもっと大きな声でさけびました。
「そうね、みごとなけまん(華鬘)よね! さあ、もう5時よ! へいかんする時間だわ!」
うしろからヘッドロックぎみに、わたしはダコバちゃんを出口のほうへひきずっていった。
あしゅらぞうのまえをとおるとき、「ヘソの下の肉、すげえエロい」などとうわごとを言いかけたので人中へ1本けんをいれると、ダコバちゃんはえのもとの死体みたくはいいろになった。
けいびいん2人が大またでこっちにあるいてきてたけど、へいかんの追いだしのためかどうかはわかりませんでした。
できるだけこうふく寺からとおいところにと、ならまちの外れにあるお店のこしつまでつれこんだところで、ダコバちゃんはキン肉マンのジェロニモが心ぞうマッサージをするみたいにしてそ生した。
きっとわたしの強いんさが不まんだったのでしょう、ダコバちゃんはしばらくのあいだひと言も口をきかずにくちびるをとがらせていた。
でも、ビールがピッチャーではこばれてくるとたちまち上きげんになって、
「じゃあ、ふたりの出あいにかんぱーい!」
なんて、かんぱいの音どをとってくれました。でも、いっ気にのみほしたあと、つくえにジョッキをたたきつけるようにおくと、編集王でマンボ好塚がホテルに編集者を集めて土下座してからビールを飲んだときの表情で「…旨え。」と言ったので、わたしはゾッとして目をそらしました。
たくさんあせをかいたせいか、ほどなくしてわたしにもよいがまわってきました。
「ねえ、ダコバちゃんはどこまでけいけん、あるのかな?」
ダイタンなしつもんをしてしまったのは、たしかにアルコールが言わせたせいもあるけれど、1日いっしょにあるきまわったのに、まだダコバちゃんのことをなにもしらないような気がして、さみしかったからでした。
ダコバちゃんは首をかしげ、トロンとした目でわたしをみつめかえしてきた。
「わ、わたし? わたしは、び、ビーまでかな」
なんでわたし、はじめて会った子にこんなこと言ってるんだろう。じぶんでも、顔がまっかになるのがわかりました。
じつは1どだけ、ダコバちゃんが描いているマンガを見たことがあった。とってもエッチな内ようだった。あんなマンガを描くぐらいだから、ダコバちゃん、きっと――
「んあ? 敬虔? ああ、なんだ、経験か。おかしなこと聞くのね。ディーよ、ディー」
「ででで、ディぃー?」
わたしは思いがけないこたえにすっかりうろたえてしまった。(もちろんAがキスで……)(……はじめての……チュウ)(君とチュウ)(Bは当然、アレ……)(ペッティング!)(Cって、もちろん)(セ……セックス……!!)(やってやるッ!)(でも、D……?)(頭文字……イニシャル……?)(え、セックスの次って……なに?)(快ッ感ッ)(ドライオーガズム的な?)(……ッッッ!?)わたしのあたまのなかは板垣恵介の格闘漫画で1秒が何分にも感じられる演出がかけめぐりました。
ダコバちゃんはすっかりかたまってしまったわたしをあきれたようにながめて、
「あんたさあ、あんなホームページやってるくせに、ディーも知らないの? 堕胎に決まってんじゃん、ダタイ」
ダコバちゃんは、ダタイにぼう点がついてるみたいにはつ音しました。(ダ…タイ……)(ダタイズム?)(ダタイオサム……的な……?)あたまのなかにかけめぐるわたしの板垣恵介的おどろきをしり目に、なにかスイッチが入ったのか、ダコバちゃんは花輪和一のマンガみたいに顔だけオッサンになると、いっきにまくしたてた。
「なあ、おまえ、いったい俺が何のためにエロ漫画描いてると思ってんだよ。いい女とファックするために決まってんだろ。あんたがしかつめらしくホームページ更新するのだって、そんなご高尚なもんじゃねえ、いい女とファックするためだろ、え? あれだけの奉仕をしてんだから、ファックぐらいの見返りがあって当然じゃねえか。てめえの指で濡らしてからまたがって、アニメ見てる俺がイクまで腰ふって、身ごもったらソッコー、セルフ堕胎パンチであとくされなく身をひくだろ。おまえさあ、いま笑って聞いてるけど、それぐらいやってもらって当然の社会奉仕をしてんだよ、俺たちは。くそ、メスどもが! 身ごもったらソッコー堕胎パンチやろが! 女ぐらいにできることで、俺たちのサービスに匹敵するのは、セルフ堕胎サービス以外ないやろが!」
オッサンの顔をしたダコバちゃんは大きな声でダタイパンチ、ダタイパンチとさけびながら、ボディーブローでだれかのおなかをなぐるマネをしました。
でも、なかいさんがしょうじをスッとあけたしゅん間、ダコバちゃんは元のような女の子の顔にもどった。
「さて、じゃあ酔っぱらっちゃわないうちに例のうちあわせしとこっか」
そう、すっかりわすれかけてたけど、今回ダコバちゃんがわざわざカンサイまで来てくれたのは、じゃっじゃじゃーん、アリアケのコミケトーにふたりで同人しを出すうちあわせのためだったのだー! えへへ、おどろいた?
わたしはすまし顔で、ゆっくりとビジネス手ちょうをとりだすと、とがらせてきたエンピツの先をペロッとなめた。でも、心のなかは、はじめての「うちあわせ」にすっごくドキドキしてた。
ダコバちゃんはいきおいよくぐーんとりょう手をひろげて、
「あんたはバーンと300ページくらい書いて。わたしはドーンと5枚くらい? いや、3枚くらいはイラスト描いたげるから。仲居さん、いちばん高い白ワイン持ってきて! ボトルで!」
うちあわせは8びょうくらいでおわった。わたしの口のなかに、にがいあじがひろがった。さっきなめたエンピツの黒えんがりゆうではないみたいだった。
これがうちあわせ? わたしが期たいしてたのと、なんかちがう……。でも、なにも知らないウブな女と思われるのはイヤだった。
「わかったわ、バーンね」
わたしはまっ白な見ひらきのページに“バーン”と大きく書くと、みけいけんの女の子がはじめてのエッチのあと、それを男の子にさとられたくなくてすぐパンツをひきあげるみたいに、サッとビジネス手ちょうをカバンへしまった。
「あなたのしじってわかりやすくて、すごくてきかくなのね。びっくりしちゃった」
わたしは、みけいけんの女の子がはじめてのエッチのあと、それをさとられたくなくてむかしのエッチとくらべて男の子のテクニックをほめるみたいな言いかたをした。
ダコバちゃんはとたん、小鼻をふくらませて、
「でしょ。あんたが賢い子でよかったわ。シロウトはすぐ勘違いするんだけど、多すぎる言葉って、逆にインスピレーションを阻害するのよね」
高きゅうな白ワインなのに、かけた茶わんにどぶろくをそそぐときみたいにそそぐと、いっ気にあおった。
「くっはー、タダ酒の味はたまんねえぜ!」
ダコバちゃんは花輪和一の漫画みたく、顔だけいっしゅん、ひどいオッサンになった。そしてつづけざま、サイフからとりだした紙まきに火をつける。
「ダコバちゃん、たばこやめたんじゃなかったの?」
わたしはみけいけんの女の子が1かいのエッチでにょうぼうヅラをするときみたいに聞こえないようちゅういしながら、ダコバちゃんをたしなめました。
「ん、煙草? ああ、やめたわよ。タバコはね」
タバコにぼう点がついているみたいにはつ音すると、ダコバちゃんはわたしの顔へふーっとけむりをふきかけた。
もう、やめてよ。わたし、たばこきらいなの。せきこみながらこうぎしようとすると、ダコバちゃんのかばんからスーパーのふくろに入った草がのぞいているのが見えた。
とつぜん、ダコバちゃんのうしろのしょうじがスーッとひらいて、なかいのかっこうをしたピンクのゾウが入ってきた。そして、2ほん足で立ちあがると、「ぱおーんぱおーん! 黎明、黎明、との、殿、れーめーにござる! 電柱ですぞ! どどどどかーん!」みたいなことを富山敬の声でさけびました。
とたん、目のまえがぐるぐるしはじめ、ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイアモンドのアニメみたいないろのこう水がやってきて、わたしは気をうしなった。
気がつくと、わたしは全しんずぶぬれでアスファルトにねていました。くすぐったさに体をよじると、ダコバちゃんがわたしのむねに手をつっこんでいます。
「あ……やめて、こんなところで……」
わたしはかろうじてていこうをしめしましたが、じつはすこしきもちよくて、きもちいいのにどうしてかジワッとなみだがでてきました。
「はは、アオカン願望でもあんの? さすがテキストサイトの管理人、自意識だけは売るほど持ってんのね。でも、あんたは私を選んだつもりでいるけど、私にも選ぶ権利はあるのよ。そこ、忘れないでね」
ダコバちゃんの手には、いつのまにかわたしのサイフがにぎられていました。数まいの万さつをぬきとりながら、
「これは御車代といったところね。あなたもいい勉強になったでしょ。ネットだけの関係で、誰かを頼んじゃいけないってね」
言いながら、ダコバちゃんは力がぬけて立ちあがれないわたしのおでこに、すごくやさしいキスをした。そして、かたごしにかがやくネオンサインを見あげて、
「まあ、御車代というより、こりゃ御花代に消えそうやな! まいったわ、またカカアにしかられてまうがな! おとうちゃん、後生やさかい、おめこはウチでだけにしてや、ってな!」
花輪和一のマンガみたく顔だけオッサンになったダコバちゃんは、声をあげて笑った。ネオンサインには“トップレディー”と書いてあり、トゥハート2のキャラが無だんで転さいされていた。体はつめたいのに、なみだだけがあつかった。
さて、わたしの話はこれでおしまい。え、それからおこったことをもっとくわしく知りたいって? ううん、ごめんなさい、お話したいのはやまやまなんだけど、お医者さまからとめられているの。なんておっしゃったかしら、ぴーてぃーえすでぃー? そういうのがいつまでもなおらないからって。のら犬にでもかまれたと思って、わすれなさいって。
え、イラスト? うん、イラスト。えへ、うふふ、あはは、アハハハハハ。らんらんらららんらんらーん、らんらんらららーん、らんらんらんらららんらんらーん、らららららんらんらーん。
MMGF!~見て、みごとなガテン系のファックよ!~(在庫駄駄余解消祈念C80漫遊記・前編)
これはnWo社所属の日系アメリカ人、パイソン・ゲイによる英文レポートをカンボジア人スタッフの協力で日本語へ翻訳したものです。日英のパラフレーズが困難な単語をカタカナで表記したり、一部文意の不明瞭な箇所があることをあらかじめご了承下さい。なお、このレポートに記載された内容に関するご質問・ご要望・ご批判は、弊社広報室宛のメールでのみ受付けております。なお、英語以外の言語には対応できかねますので、あらかじめご了承下さい。
十年来のペンパルであるリカが原因不明のディズィーズに倒れ、ステイツのnWo本社から奈良ブランチ所属のミーにアージェントリィ、至急トキオのコミケトー・エイティに向かえというオーダーNo.66が下りマシタ(当社のプレジデントはシスの暗黒卿そっくりのいけすかない野郎デス)! オーッ、ネオ・トキオ! ミラクルという名のパラダイス! スリー・ツー・ワン・ゴー!
ミーはスーツケースに白青のバーティカル・ストライプのトランクスを押しこみながら(なぜって、ジャパンのギークスの間では、白青のホライゾンタル・ストライプのパンティが大人気と聞きましたカラ!)、胸の高鳴りをプット・アップ・ウィズできなくなっていマシタ! オーッ、サード・トキオ! セカンド・トキオ・ユニバーシティを擁する、エンジェルたちの誘蛾灯! オダワラ防衛線、突破されマシタ! オールモスト寝つけないまま、ミーはバレット・トレイン上のパーソンになったのデシタ!
トキオ・ステーションから意気揚々とキャブに乗り込み、行き先をトキオ・ビッグ・サイトと告げると、初老のドライバーのフェイスが侮蔑的にディストートするのがわかりマシタ! プアーなジャパニーズのフェイシャル・エクスプレシオン(ミーのマザーはフランス系移民なのデース!)とは思えぬほどのディストーションだったので、ミーはひどくサプライズしまマシタ! ジャパンにおけるギークスへのヘイトは、ステイツにおけるジューズ、ユダ公どもへのヘイトとセイム・クオリティであることをペインフルに実感させられたのデス!
トゥエニィ・ミニッツ・レイター、ニードルのむしろを思わせるキャブ内のアトモスフィアーからリリースされた先に、シュガーのランプに群がるアンツの如くくろぐろと、ギークスどもがビッグ・サイトを取り巻くのが見えマシタ! まさにシュガーの粒をネストに持ち帰るワーカー・アンツみたいデース! 会場から出てくるギークスはノー・エクセプション、例外なくモエ・ガールの描かれたブックをホールドしていマス! ストリクトリー・スピーキング、厳密にはブックというよりマガズィーン、ガールというよりはベイビーのようデシタ! モエ・ガールたちの表情はいずれもステイツならノー・ダウト、間違いなく寿命をはるかに超えたセンテンス、刑期を食らいこむだろうペドフィリア感をかもしだしていマス! 加えてギークスどものフェイスに張りついた表情は、いずれもステイツならジュリーズ、陪審員たちが数百年の懲役を求刑することにわずかのヘジテイトも感じないだろうクライム感をかもしだしていマシタ!
オオーッ、あれこそがワールドワイドにノトーリアスな土人誌なのデスネ! ミーを包むディープ・エモーションは、ジャングルの奥地で幻のバタフライを発見したときの昆虫学者のイットに似ていたと思いマス! オップス、本社へのレポートは正確を期さなければなりまセン! 土人というのは、ファースト・ネイションを表すジャパニーズの単語なのデース! ジャパンはポリティシャン(ミーがステイしていたときは、The Demonic Party of Japanとかいうロックンロールな名前のパーティが与党デシタ!)も広言するように、モノ・エシック・グループから成る国家なのデス! 土人誌というネーミングはジャパニーズのプライド・アンド・プレジュディズが混ざりあった複雑なセルフ・コンシャスネス、自意識を体現しているのデショウ!
ゼアフォー、ゆえにミーのようなフォリナーのメイドした土人誌は、ジャパニーズのデフィニション、定義では土人誌とは呼べないのデス! イン・ショート、つまりコミケトーではフランスワインなみの厳しいクオリフィケーション・ジェスティヨン(ワタシのマザーはフランス系移民デース! ラブ・マミー!)、品質管理が行われているというわけなのデス! ステイツならばレイシズムと呼ばれかねない偏狭さ(辺境さ?lol)デスが、マザーがフランス系移民のミーはそのナローさがカルチャーの正体であることを知っていマース! (ファック、マクダーナルズ!)
バット、コントラディクティング、矛盾したことにジャパニーズにおけるコミケトーのサウンドは「混み毛唐」と同じなのデス! ザットイズ、すなわち「外人たちで混みあっている」の意味をもインプライしていることになりマス! 民俗学のオーソリティー、クヒオ・ヤナギダ大佐が存命であれば、さぞやこの難問に頭を悩ませたことデショウ! ミーの推測はこうデス! ジャパニーズとネイティブ・アメリカンは同じアンセスター、先祖を持っているという仮説デス! オーッ、汝「混みあう毛唐ども」よ! ネーミングのセンスが似ているのもうなずけマース!
ギークスのウェイブに流されるままトキオ・ビッグ・サイトに入ると、すさまじいヒートとスメルにノージア、ミーは軽い吐き気とめまいを覚え、思わずシルク製のハンカチーフで口元をカバーしマシタ! すさまじいヒューマン・ガベッジに、もはや進むことも戻ることもままなりマセン! このままではファイナル・デスティネーションにたどりつく前にファイナル・デスティネーションにたどりついてしまいそうデス(訳者注:「最終目的地」と人生の終着である「死」をかけていると思われるが、同名の映画に言及している可能性も否定できない)!
バット、ドント・ウォリー、ノー・プロブレム! リカのビジネス・パートナー、ダコバのエージェント、代理人サメン・アッジーフのセルフォン・ナンバーをあずかってきているからデス! ミーのヴィジットの目的は、リカとダコバの土人誌、MMGF!(Modified Mason Gain Formula? 奇ッ怪極まるタイトルデース!)の販促アクティビティなのデシタ! コミケトーにおける裏技、セラーがバイヤーに優先してバックドアーから入場できるシステムを今こそメイク・ユース・オブ、利用するのデース!
ハウエバー、なかなか電話はつながりマセン! ジャパンはセルフォン・デベロップト・カントリーなので、奈良のようなカントリー・サイドのマウンテン・トップでも電話はつながりマス! トキオのようなアーバン・シティで電話がつながらない、こいつはミステリー、エクストリーム不可思議デス!
何度ものトライと長い長いコーリングの後、ファイナリー、ついに不機嫌そうなボイスのガイが電話に出マシタ! オーッ、ユー・マスト・ビー・サメンサーン! ハワユー!
「忙シイカラ要件ヲ手短カニ言エ!」
ドスのきいたボイスは、なぜかミーにハイスクールでのヒエラルキーを思い出させマシタ! ハイッ、手短に言わせていただきマース! リード・ミー・トゥ・バックドアー・プリーズ!
「ハア? テメエドコノ王様ダヨ? 売リ子モシタコトガネエトーシロニ貴重ナサクティケヲ渡セルワケネーダロ! 正面カラダラダラ歩イテ来ヤガレ!」
サドンリー、突然電話は切れてしまいマシタ! きっとビッグ・サイトに固有の電波シチュエーションが原因にちがいありまセーン! それにしても、サクティケとは何なのデショウカ? サクリファイス・ティッツ? ユーギオー的な? 俺はこのたわわな双乳を生贄に捧げて、胸の貧しいアーク・ペドフィリアを召喚するゼ?
そもそもイングリッシュ・ワードではなく、ライスを畑に植える作業、ソー・コールド「作付け」のことにリファーしていた可能性さえ否定できマセン! フロム・エンシェント・タイムス、古来よりジャパンではライスのアマウントが非常にインポータントなミーニングを持ち続けマシタ! コミケトーのバックドアーを使うには、イーチ・ファミリーのガーデンで栽培しているライスを持ってくる必要があったのかもしれまセーン! オーッ、日本の常識世界の非常識! 働かざるもの食う寝る遊ぶ! さすがはワールドに冠たるニート大国デース! ミーは文化の違いにソー・インプレスト、強い感銘を受けつつも、今回のミッションが想像以上に困難なものになることを感じていマシタ(弊社のプレジデントはシディアス卿そっくりのいけすかない野郎デス! アンリミテッド・パワー!)!
ほどなくして、ギークスのウェイブはミーを建物のインサイドへと運んでいきマシタ! ビッグ・サイトの中は、イグザクトリー、ステイツのスラム街を思わせるアウト・ローぶりデス! 壁際でシットダウン(sit down)しているものもいれば、壁際でシットダウン(shit down)しているものもいマス! コミケトーへ参加するために仕事をジャックイン(jack in)したことを公然と自慢するものもいれば、土人誌を片手に公然とジャックオフ(jack off)するものもいマス! 各ブースに掲げられたポスターはクリスタニティをビリーブ・インしているなら、ビッグ・サイトごとヘルファイアに焼き尽くされることを望むほど冒涜的な図画で彩られていマス!
その、サタニズム的な祝祭を体現する見かけとは裏腹に、ギークスたちはキューを乱さずに整然とならんでいるのデス! パスポートを持たないステイツのファンダメンタリストがこの会場を見たならば、あらゆるホーリーとアンホーリーが混在するありさまに、地上へヨハネのアポカリプスがアピアーしたと感じるかもしれマセン!
ハウエバー、フランス系移民の息子であるミーにとってこの程度のエンタルテテ・クンスト(祖父はドイツ系移民デス! ラブ・グランパ!)、退廃芸術はパリの路地裏でエッフェル・タワーの先端を見ながらアルジェリアンにアヌスを突き出して言うファック・シルブプレ、昼下がりのコーヒーブレイクと何ら変わらない平穏なものデース! ミーはギークスどもを持ち前の体格でオーバーフェルムしながら、サメン・アッジーフのブースを目指しマシタ!
バット、なかなか目的のブースを見つけることができマセン! シック・イン・ベッド、病床のリカが手を握るミーへ息も絶え絶えに、「これ……ダコバちゃんの……おっきなポスターにして……はってくれるって、そう、約そくしてくれたの……」と言いながらあずけてくれたイラストを元にブースを探すのデスガ、いっこうに見当たりマセン! ダコバのサークルはウォール・サークル(ウォール・マート? ウォール・ストリート? 意味不明デース!)なのでアット・ワンス、すぐに見つかると聞いていたのデスガ……
イヤ、見つかりマシタ! 会場のウォール沿いへセグリゲートされたエリアに、リカからもらったイラストを発見したのデス! どうりで見つけにくかったはずデス! なぜなら――
二枚の大判のポスターの下に、ひと回り以上小さなサイズで掲示されていたからだ。加えてテーブルの奥、山積みになった在庫の裏側へすっぽりと隠れてしまっており、よほど近くから注意深く見なければ気づかないだろう。段ボール製のつけ鼻を貼りつけるセロテープの下の皮膚にしりしりとしたかゆみが生じる。私は自分の気持ちが急速に冷えていくのを感じていた。地元のだんじり会を軽蔑し、地域の夏祭りを嫌悪する私も、コミケという場でならば祭りの一員になれるかもしれないと信じていた。しかし、待ち望んだ祭りの只中にあって私の胸を満たしているのは、一種の諦念と虚無感である。結局、私はこの人生において「いま」「この場所」に実在することを忌避し続けてきただけのことだったのか――
オオップス! あぶなかったデース! あやうくオサム・ダザイ的なノー・イグジット、出口の無いデプレッションに引きこまれるところデシタ! 気を取り直していつものようにチアフルにいきマース! ハーイ、ディス・イズ・パイソン・ゲイ! ホエア・イズ・サメンサン?

呼びかけに応じて、ウォールを背にしたテーブルの向こうから、ミドル・イースト風の容貌をした男が不機嫌そうにミーをギロリとゲイズしマシタ! その瞬間、ミーの背筋にはハイスクールでの理由なきヒエラルキーの感じと同じ種類の悪寒が走ったことを認めなくてはなりマセン! 口髭にターバン、イエローのアロハという正気をダウトするいでたちのこの男が、リカの言っていたサメン・アッジーフなのデス!
サメンはショルダーズをアングリーさせて隣のブースを占拠するロトン・ガールズ、腐女子ども(これは注釈が必要デショウ! ステイツのゾンビムービーのように身体が腐っているわけではありマセン! 腐っているのはその性根の部分でアリ、精神そのものなのデス! 魯鈍ガールズ、デース!)を押しのけて出てくると、ミーに向けて両手をあわせマシタ! アンドゼン、「あら、アクバル?」みたいなことを言ったのデス!
オーッ! ソレ、知ってマス、知っていマース! ミーはたちまちマイセルフがフルフェイスの笑顔になるのがわかりマシタ! ソウ、これはファースト・ガンダムからの引用に間違いありマセン! ミーはギークスとして試され、合格したのデース! ハートのボトムからハッピーな気持ちになったミーは、サメンのショルダーをバンバンどやしながら「アックバル兄サーン! アックバル兄サーン!」と連呼しマシタ! すると、サメンのフェイスはなぜかたちまち険しさをインクリースし、ミーはハイスクールでの理由なきヒエラルキーの感じをアゲイン、思い出しマシタ!
サメンは再びロトン・ガールズをかきわけテーブルの裏側へと戻っていきマス! ミーは両手でアス・ホールをカバーしながら、サメンとミーを見てウケとかセメとか(ハレとかケのような民俗学用語に違いありマセン!)ひそひそ話をする魯鈍ガールズと視線を合わさないようにしてブースに入りマシタ!
インサイドから見るとスーサイダルな狭さで、在庫のバレーに二人の売り子がひしめいていマス! 一人はエクストリーム猫背のヤングマンで、リアルをゲイズする時間よりもスマートフォンの画面をゲイズする時間の方が明らかに上回っていマシタ! 聞けば、このヤングマンもサメンのブースを間借りして土人誌を販売しているとのことデス! オーッ、フェローシップ・オブ・ザ・コミケトー! ホワッツ・ユア・ネイム?
ミーの問いかけに、ヤングマンはコリア製のペドフィリアだかセクスフォビアだかいうスマートフォンから一秒も目を離さないまま、リプライしマシタ! そのボイスにはミュートとブラーがかかっており、ジャパン在住歴三十余年のミーにとって久しぶりにリスニング力を試される良いオポチュニティーとなったのデス! ヤングマンの名前はオットマン・ゲイリー、栄枯盛衰みたいな名前のマガズィーンに、ソワカ反吐みたいなタイトルのカートゥーンを連載しているとのことデス! ジャパンのコミック・アーティストの多さはルーモア、噂には聞いていマシタが、すでにこのシット狭いブースだけで漫画家占有率は50%を越えていマス! オーッ、まさに「狂うジャパン(ギーク・カルチャーを推進するガバメントの標語)」デスネ!
そしてもう一人はシャドーの薄いカレッジ・ステューデントで、ティピカル・ジャパニーズがオーフンするところのネックをチルトさせるだけのインギン・ブレイなおじぎでレスポンドしてくれマシタ! 苦虫をイートしたような顔でサメンが言うには、このカレッジ・ステューデントがリカとダコバの土人誌をエディット、編集したとのことデス! オーッ、アナタが――
漫画と小説の余白設定を勘違いし、文字密度の高い、極めて読みにくい紙面を作り上げた張本人なのか。生涯に一度とまで思い詰め、本業に影響を生じるほど睡眠時間を削った校正の一部を反映させないまま製本に出した張本人なのか。売れるほどに赤が膨らむ、採算度外視の同人誌を、家人に使途を明かせぬまま土下座して捻出した虎の子の金子による同人誌を、不満の残る形で世に出さざるを得ない状況を作った張本人なのか。段ボール製のつけ鼻を貼りつけるセロテープの下の皮膚にしりしりとしたかゆみが生じる。一瞬、板垣恵介の格闘漫画の如く顔面の中央が陥没するほど右拳をねじこんでやりたい衝動にかられたが、そうしなかったのは単純に怒りを諦念が上回っただけのこと。私の人生に馴染み深い、消極的な惰性による問題の回避だった。
オオオップス! ステイツ・オブ・デプレッション・アゲイン! いまのは本当に危なかったデース! 気を取り直していつも通りチアフルにいきマショウ! ミーはエクストリーム愛想よくシャイシャイとハンドクラップしながら、「ヘイ、ボーイズ! ミーが来たからにはもうダイジョブヨー! 売って、売って、売りまくるネー!」とシャウトしマシタ! ハウエバー、返ってきたのはジャージャー・ビンクスを見るときの古参スターウォーズマニアと同じ中身の視線デシタ! ミーはたちまちマイセルフのフェイスがシリアスになるのを感じマシタ!
オーッ、アウェイ! すさまじいアウェイ感デース! ミーはヘルプを求めてサメンを見マシタが、「オイ、ボサット突ッ立ッテンジャネエヨ。狭イブースニデクノボーヲ入レテオクスペースハネエンダ」とアンチ・ソーシャルなピクチャーの土人誌が山積みされているテーブルへとミーを激しくプッシュしたのデス!
確かに、ミーに売り子の経験はありまセン! ハウエバー、ミーはガイシ(骸死)系企業にふきあれたリストラクチャリング・ストームを生来のチアフルネスのみで切り抜けたほどのガイなのデス! 売り子? プロバブリー、売女の親戚みたいなものに違いありまセン! ミーは肩幅に足を開くと、アスホールをワイドに構えマシタ! サア、ムカイ、どこからでもかかってきなサーイ! ミーの耳元では「帝王V!」の連呼が実際に聞こえるようデシタ!
バット、マイセルフのチークにキアイの平手を打ちつけながら顔を上げると、そこには生気の欠落した目をしたリビングデッドの群れが、内臓疾患を疑わせる土気色をした無表情で棒立ちにスタンドしていたのデス! そして、ケイオスそのものの見かけといでたちをしたギークスが、整然とした二列のキューでコスモスそのものを体現するかのように並んでいるのデス! サド性向を持つデブ専ホモのネクロフィリアならば、あるいは両手をクラップして大喜びするかもしれない光景デス! ハウエバー、いずれの性癖にも該当しないミーはそのとき、ベジタリアンが人食い族の村をヴィジットしたとき感じるだろうディープでマッシブなカルチャー・ギャップに、マイセルフのアスホールがきゅっとシュリンクするのを感じていたのデシタ……!!
To be continued…
MMGF!~見て、みごとなガテン系のファックよ!~(在庫駄駄余解消祈念C80漫遊記・中編)
前回までのあらすじ:亀頭と包皮を結ぶ紐状の生体組織で、別名を陰茎小帯と言う。ボブは敏感なその部分を嫌がるマギーの口元へあてがった。「ウッ、むグッ」、キッと一文字に結ばれたピンクの唇をボブのうらすじが強引に割って――
ミーがアスホールのイグジット(ロトン・ガールズにとってはエントランスでショウカ?lol)を引き締めると同時に、テーブル越しに立つ土気色をしたリビングデッドが、「なかいいですか?」と発話したのデス! ミーは一瞬、ソー・コンフューズド、何を尋ねられているのかわからず、ひどく混乱してしまいマシタ! 言語には文化的なギャップによって、シンプルなワードがまったく別の意味を持ってしまうケースがありマス! フォー・イグザンポー、例えばエクストリーム一般的な「持つ」という他動詞さえ、ジャパニーズとイングリッシュの間には違いがあるのデス! オブジェクトをラック、目的語を欠落させて自動詞的に用いた場合がソレに当たりマス! ジャパニーズで「持ってる」と表現すれば、それは運か才能を持っていることを意味しマス! オン・ジ・アザー・ハンド、一方イングリッシュで「ドゥー・ユー・ハブ?」と表現すれば、それはレリジャス、信仰の有無を訊いているのデス! 異国の地の、さらにコミケトーという異境では「なかいいですか?」という単純な問いかけにイエスと答えることが、実は肛門性愛へのアグリーメント、合意を表してしまう場合さえテイク・イントゥ・コンシダレーション、考慮に入れなくてはなりマセン! ミーのチークに緊張のあまり一筋のスウェット、汗が伝い落ちマス! 小売業のセラーがバイヤーにここまで追い詰められるなんて、ステイツでは考えられない事態デス!
「カスタマー・イズ・ゴッド」が持つ真の意味をミーがペインフルに体感していると、隣にスタンドしていたサメンが「ア、ドゾドゾー、遠慮ナク見テッテ下サーイ」と陽気に返答しマシタ! そのアブノーマルなまでのインギンさは先ほどまでミーにスクール・カーストの存在をリマインド・オブさせていたのと同一人物とは思われないほどデス! ギークス風にエクスプレスするなら、「コイツら、自在にインギン力を変化させやがる」デス!
サメンの言葉に応じて、眼前の土気色リビングデッドはゾンビらしからぬクイックネスで土人誌のパイルから一冊を取り上げると、しばしパラパラとコンテンツを確認しマシタ! アンドゼン、「ありがとうございました」 の言葉とともに、元のパイル上へ無造作に土人誌をスロー・バック、投げ戻したのデス!
エクストリームリー・ショックト、ミーはデルビッシュ有、この悪魔的な慣習にひどく衝撃を受けマシタ! ミーは土人誌のオーサー、作者がファンへダイレクトに販売を行うという手弁当感がコミケトーの魅力だと考えていたのデスガ、いまミーの眼前で生じたフェノメノン、現象にはミーが想像していたようなハートフルさは少しも含まれていませんデシタ! 作り手のすぐ目の前で作品を品定めした後、その購入を好きにリジェクトできるというシステムは、ミーが奈良のカントリー・サイドで日々エクスペリエンスしているジャパニーズのバーチュ、美徳とはほど遠いものデス! フォー・インスタンス、例えるならばストリートにスタンディングする売女に、「膣内(なか)いいですか?」とアスクした後、背後で休憩中のオットマンがコリアのセクスペリアへしきりとするフィンガー・ジェスチャーで公衆の面前にその膣口をクパチーノしてからやはり買春しないことを大声で宣言するような、人倫を外れた背徳の仕組みデス!
「他人のために最も怒れ」――ミーのファーザーは家訓としてそう言い続けてきマシタ! このときミーは、土人作家に与えられる侮辱に対して行き場の無い怒りを感じていたのデス! ところが義憤にかられるミーの隣でサメンはヘラヘラと愛想をふりまいていマス! ミドル・イーストではこのくらいのことは屈辱でも何でもないのかもしれマセン! 絶え間なく噴出するオイルに比べれば、しぼり出す妄想の価値など何ほどでも無いと思っているのかもしれマセン! イフ・ユー・ゴー・イントゥ・ゴー・オベイ・ゴー、郷に入っては郷に従え、ミーはとっさにジャパニーズ特有のベイグネスに満ちたスマイルを浮かべマシタ! その瞬間、これまでの三十余年で見てきたジャパニーズの曖昧な微笑みの裏にはサポージング、もしかしすると活火山のような憤怒があったのではないかと思い至って戦慄を覚えたのデス!
ミーのインサイドでうずまく葛藤をよそに、土人誌のパイルはその高さをデクリースさせてゆきマス! アット・ラスト、ついにリカの土人誌のラスト・イシュー、最後の一冊が売れマシタ! ワオーッ! ソールド・アウト、ソールド・アウトデース! ミーは病室で言を左右し続けたリカがファイナリー、「あの……わたしは10さつくらいって言ったんだけど……ダコバちゃんが……ぜったいだいじょうぶだからって……あの……500さつ……」と大粒の涙をポロポロと流して告白したのを思い出していマシタ!
「リカ、ダイジョーブ! ぜんぶミーにまかせるネー! ガイシ(骸死)系の営業部長の肩書きはダテじゃないヨー!」
ミーの空約束に泣き笑いでうなずいたリカの消え入りそうな表情! リカの墓前にようやくいい報告ができマース!
「オイ、ボサット突立ッテネエデ、ホンヲ追加シネエカ! マダ何箱モアルンダ! 早ク積マネエト、客ガ逃ゲチマウゼ!」
両手を突き上げてディライトネス、歓喜の中にいるミーの背中へ険しい声が飛びマシタ! サメンがカッターで切り裂いた大きな箱の中には、みっしりとリカの土人誌が詰め込まれていたのデス! ダヨネー! ミーの鼻段ボールが湿気を増し、一瞬のデプレッションがとばりのように心へ降りかけマシタガ、ミーは一流選手が強い自己暗示によって失敗をノーマルの状態としてとらえるメンタル・スイッチング技術を利用しマシタ! ダヨネー、ミーやリカみたいにネットでの声は大きいくせにリアルではチキンで何の知名度も無い連中の土人誌が、いきなり500冊も売れるワケないヨネー! 鼻段ボールは乾き、両のマナコは濡れ、ミーはたちまち平常心を取り戻していマシタ!

ソウソウ! ミーのコミケトー来訪は、本社へのジャパニーズ・カルチャーに関するレポートを兼ねていたのデス! 土人誌の販売はゲストとしての片手間に過ぎないのデシタ! ケアフリー、注意深く観察を重ねると土人誌がうず高く積まれたテーブルには大きなビニル袋が貼りつけられていマス! リビングデッドが支払った紙幣はゴミクズをダストビンへするときと同じ所作で次々に放り込まれていきマス! ステイツにいた頃ならその様子を見ても何も感じなかったデショウ! それはジャパン在住歴三十余年でなければ感じなかったようなかすかな違和感デシタ! サドンリー、突然ミーのインサイド・ブレイン、脳内にいる栗色の髪をした新聞記者の女性が寿司屋のカウンターでいきおいよく立ち上がり、「お金なのにもらって捨てる動作が汚らしいのよ!」とシャウトし、ミーの違和感はアイスメルティング、氷解しマシタ! こんなふうにマネーが扱われるのを見たのは釜ヶ崎のチンチロ賭場でコンビニ袋へ紙くずのように丸められた札が詰め込まれるのを見たとき以来デス!
「勝負が終わるまでァ、こんなナァ鼻ッ紙でもネェのサ」
ミーは勝ち頭の労務者が酒焼けした鼻を手のひらですすりながらボヤく場面をまざまざと思いだしていマシタ! ジャパンではアニメはシーズン毎に大量生産されマス! それは本当にサプライジングなクアンティティで生産され、この国ではアニメは湯水以下の価値でマーケットに供給され続けるのデス! ジャパニーズのブルーワーカーにとってアニメは日常の退屈をまぎらわすための、ハシシより安価で手軽なドラッグの一種なのデス! ジャパンの土人誌オーサーたちは無数のアニメからそのシーズンのヘゲモニー・アニメ(訳者註:ヘゲモニーとは覇権の意味だが、アニメを修飾する語としては不適切。誤字か?)がどれになるかをチョイスしマス! そのチョイス次第で土人誌の売上は一桁ほど変わってくるのデス! 土人誌オーサーたちにとって土人誌メイクは、釜ヶ崎の労務者と同じギャンブルなのかもしれマセン! だとすれば、売上の確定するコミケ三日目の終了時まではマネーを紙クズのように扱うのは至極当然と言えマース!
サドンリー、ミーは土人誌のプライス設定が五百円刻みであることをファインドしマシタ! ジャパンは生活必需品にまでタックスを課すことで有名なエコノミック・アニマル・ガバメントを有していマス! フォリナーにとっては、コンビニでスモール・チェンジを要求されるのは実にイリテイティング、イライラさせられる体験デス! 土人誌のコンサンプション・タックスはどこで課されるのデショウカ?
「ヘイ、サメン! 土人誌のタックスの仕組みはどうなっていマスカ? それともコミケはエアポートのようにデューティ・フリーなのデスカ?」
ミーが持ち前のボトムレス、底抜けな素朴さで尋ねると、とたんにサメンは満面の笑顔を浮かべマシタ! 次の瞬間、眉間で火花がスパークし、ミーの意識はダークネスへとフォールしていったのデス!
テン・ミニッツ・レイター、鼻に血のにじんだティッシュを挿し込み、すべての疑問をオブリビオン、忘却の彼方へと消し去ったミーの元気な青タン姿がそこにありマシタ!
疑問を封じるというのはブレイン・ウォッシュのファースト・ステップ、第一歩デス! ミーはいまや1984年のようなマナコで売り子ワークへ従事していマシタ!
「ヘイ、テメエニ客ガ来テルゼ」
苦虫を噛み潰したようなフェイスでサメンがミーに言いマス! まるで日雇い労働者にトイレ休憩さえやりたくない現場監督みたいデス! ロトン・ガールズの間へ身をねじこんでブースの外へ出ると、そこにはニット帽を目深にウェアした青年が思いつめた表情でスタンディングしていマシタ!
「小鳥猊下ですよね! ぼくです、ポロリです!」
フー・アー・ユー? バット、ザ・モーメント・ヒー・セッド、言うや否や、青年は抱きつかんばかりのディスタンスにまで間合いを詰めてきマシタ! ステイツやヨーロッパに在住する狩猟ピープルは他人と世界に対して深い猜疑心を抱いていマス! 初対面での過剰になれなれしいビヘイビアーはジャパニーズ特有で、それは基本的に他人と世界が自分に危害を加えないことを信頼する農耕ピープルのものデス! ミーはたちまち警戒心をマキシマム・レベルにインクリースさせマス!
エスペシャリー、特にミーの出身であるステイツでは、パブリック・プレイスでニット帽をかぶったりマスクをしたりするのは、心に後ろ暗い部分を持っていることの表明、変質者の証デス! 公然とニット帽をかぶりマスクをするのは、ステイツではマイケル・ジャクソンくらいしかいマセン!
「本当に感激です、猊下とお会いできて」
クネクネと両腕をもみしぼりながら熱狂に目を潤ませるポロリの様子は、インギンな語り口とあいまって、ノンケでも喰っちまう、決してヘテロではない感じを濃く醸しだしていマス! バット、セクシャルなテンデンシーだけではない、メンタルに潜むディズィーズを、ミーはこの青年のうちに見出していマシタ!
「オーッ、イグザクトリー、その通りヨー! ミーが小鳥猊下ネー!」
ミーは内面に生じたさざなみをハイドするスマイルを浮かべて大げさに青年の問いかけを肯定しマシタ! トゥ・テル・ザ・トゥルース、小鳥猊下はミーとリカとのユニット名なのでいささかアキュレイシー、正確さをラックした返答デシタガ、この種のメンタルヘルス青年はいったん思い込んだ情報を外部からコレクトされると途端にアプセット、逆上するという傾向がありマス! ミーは適当にあいづちをうつことで穏便にこの場を切り抜けることにしマシタ! バット、メンタルポロリはミーにアクセプトされたと思ったのか、とたんに饒舌に語り始めマシタ!
「猊下の文章すごい好きなんですけど、今回のMMGF!ですか、あれはぜんぜん感心しなかったな。なんか説明がくどくて、八十年代のラノベみたいで。もっともっと説明を減らさなくちゃ。物語なんだから」
同心円状のクレイジーを記号化した目で一方的にまくしたてながら、メンタルポロリはじりじりとミーとの間合いを詰めてきマシタ! それぞれの民族は、適正な文化的距離というものを持っていマス! どこまで接近されると不安感や不快感をいだくかというのは、イーチ・カルチャー、文化ごとに異なっているのデス! ジェネラリー・スピーキング、一般的に言って北米出身のミーは日本出身のメンタルポロリより近い位置までのアプローチをアラウ、許容できるはずデス! ハウエバー、メンタルポロリのアプローチはミーを不安にさせるほど近かったのデス!
不安感に耐えかねてミーがわずかに下がると、メンタルポロリはミーが下がった分だけ間合いを詰めてきマス! ミーは長大なコリダー、廊下をラテン民族に握手を求められた北欧民族が延々とリトリート、後退していくというあのジョークを思い出していマシタ! ファイナリー、気がつけばミーは壁ぎわへと追いつめられていマシタ! メンタルポロリはスティル、まだじりじりと間合いを詰めることをやめマセン!
「あ、でもこないだのオフレポはすごい面白かったです。ジュブナイルやるなら、あの文体で書けばいいのに。なんでああいうふうに書かないんですか」
内容のルードさを除けば穏やかな語り口デスガ、狂気と正気の間にあるのはア・シート・オブ・ペイパーだと言いマス! ミーのアスホールが恐怖にきゅっとシュリンクしマシタ! 北米出身のビッグなミーが、日本出身のスモールゲイ(訳者註:ガイの誤字か?)に追いつめられ、いまや貞操の危機さえ感じているのデス!
「あの、小鳥猊下でいらっしゃいますか?」
ミーの危機をレスキューしたのは、やはりインギンな口調の声かけデシタ! 中肉中背でグラッスィーズをウェアしたその男は、ティピカルなジャパニーズビジネスマンといった様子デス! カンパニーにエンプロイされているという事実は一定のサニティを保証しマス! ミーは不自然にならないよう注意しながらメンタルポロリをかわして、ビジネスマンにシェイクハンドの右手を差し出しマシタ!
「オー、イエス! アイアムゲイカコトリ、ネー! ウェルカム・トゥ・マイブース!」
ジャパン在住暦三十余年のミーはフルーエントなイングリッシュでリプライしながらネームカードを取り出しマス!
「わ、わたくし、キムラと申します。えっと、あの、そ、そうだったんですか」
アルファベットの並んだネームカードとミーの鼻段ボールへ交互に視線をやりながら、キムラはあきらかな挙動不審のステイトに陥っていきマシタ! 知ってマス、これ知ってマース! ジャパニーズに特有のフォリナー、外人に対するこのレスポンスは実は珍しいことではありマセン! ワールド・ウォー・トゥーで連合軍へノー・パーフェクト・スキン、完膚なきまでにたたきのめされてからこちら、ジャパンは深刻なフォリナー・フォビア、ガイジン恐怖症に罹患しているのデス! エンド・オブ・ウォーからモアザン半世紀、ノウ、時間が経過すればするほどオールモスト遺伝的な情報としてジャパニーズのインサイドにフォリナー・フォビアは書き込まれていっているようデス! そのモスト典型的な症状が、いまのキムラが見せている状態デス! ゴールデン・ヘアー・グリーン・アイのイングリッシュ・ユーザーであるミーに、理由もなくあからさまな気後れを表していマス! もはやこれは高所やコックローチへの恐怖にも似て、本能のレベルにまで昇華されていると言っても過言ではないデショウ! アンド、ジャパニーズのこのフォビアはジャパンに学歴も能力も低いフォリナーがライク・モス、蛾のように集まってくる理由にもなっていマス! なぜって、マザー・タン、母国語の読み書きができるだけで現人神のように崇められ、本国で従事する単純労働よりはるかにましなペイメントが期待できるカラデス! ジャパンは実のところ、不良ガイジンの格好のプール、溜まり場になっていマス! ジャパニーズだけがそれに気づいていマセン! オフ・コース、ミーはエグゼクティブなので違いますヨー!
「ヘーイ、キムラ! ウェイク・アップ! ソレはジョーク名刺ネー!」
フォリナー・フォビアに思考を奪われた状態になっているキムラの目の前でミーは親指と人差し指を数回スナップさせマシタ! イン・ファクト、キムラに渡したネームカードはジャパンの商習慣にあわせたカムフラージュ、記載された情報はすべてデタラメなものデス! ステイツ生まれでパリ育ちのミーは、コミケトーのような反社会的プレイスでマイセルフのプライベート・インフォメーションを開示するほどピース・ボケしてはいないのデス! 路上でチュニジアンに話しかけられてもインギンな返答をしながらも決して足は止めないといったような生得の警戒心、ワールドへのディープな猜疑心を処世のネセシティ、必須として持ちあわせているのデス!
ハウエバー、ミーのような毛唐ピープルに特有のディフェンシブなスマイルも、ベーシカリー異質の存在しないジャパニーズ・カルチャーで生育してきたキムラにとって、緊張をメルトさせるに充分なものだったようデス! キムラはオールレディ、すでにリカの土人誌を購入しており、ミーは会話の糸口として感想を尋ねることにしマシタ! ミーはそれをすぐに後悔することになりマス! なぜなら――
木村裕之は私の問いかけに対して、購入したばかりなのでまだ読んでいないと答えたからだ。今回の同人誌はネットで大部分を先行して公開し、その完結編を収録するという手順を経ている。初めての同人誌販売であるから、少しでも売上を伸ばしたいという苦肉の策だ。その旨を伝え、さらに木村裕之に問い詰めると、わざとらしくページを繰りながら「え」とか「あ」とか母音を繰り返すだけの状態になった。夏のコミケを目指して一月から更新を行なっていたから、木村裕之は少なくとも半年は私のホームページを閲覧していない計算になる。十年来のファンと称し、わざわざコミケのブースに足を運ぼうと思う人間でさえ、こうなのだ。最も熱心なファン層でさえ、この程度の執着なのだ。段ボール製のつけ鼻を貼りつけるセロテープの下の皮膚にしりしりとしたかゆみが生じる。私は自分の気持ちが急速に冷えていくのを感じていた。いつまで経っても商業に回収されない最古参のテキストサイト運営者が、完全な持ち出しで苦手分野に媚びた同人誌を作成したところで、彼が望む深さの受け手は世界中のどこにもいないのだ――
オオオオオップス! ワーニング、ワーニング! 我、まさにフォール・イントゥ・デプレッションせんとス! コミケトーはフル・オブ・トラップ、罠がいっぱいデス!
「ヘーイ、ポロリー、キムラハヒドイヤツネー! ナントカ言ッテヤッテヨー!」
深刻なアンガーをジョークにまぎらわせようとして話をふると、ミーとキムラのチアフル・トークの横でメンタルポロリはそわそわと、あからさまに挙動不審のステイトに陥っていマシタ!
「ヘーイ、ポロリサーン、ドウシタノ? 顔色悪イヨ?」
ミーのジェントルな声かけにメンタルポロリはビクリと肩を震わせると、深夜の空き地でのレイプ未遂を通行人にファインドされたような顔をしマシタ! 「じ、じゃあ、ボクはこのへんで」と小声の早口で言い、さっきまでの執拗なインファイトぶりはどこへやら、アウトボクサーのステップで会場の人ごみへまぎれ去っていこうとしマス!
ホワット・ア・カワード! これはジャパニーズに特有の神経症、タイジン・キョウフショウ・シンプトムの表れデショウカ! ミーは持ち前のヒロイック、英雄的な気質を前面にプッシュして、メンタルポロリを引き止めると、ふたりにセルフ・イントロデュースをうながしマシタ!
「ヘイ、ポロリ、キムラ! キムラ、ポロリ!」
ミーのジェネラスなスマイルにうながされて、ふたりはようやく鏡あわせのように後頭部へ手をやりながら互いに会釈をしマシタ! 人間関係こそが仕事にとって最大のキャピタル、資本であることをモットーとするミーはその様子にグラティフィケーション、強い満足感を得ていマシタ! バット、このときのディシィジョン、決断をミーは後になって死ぬほどにレグレット、後悔することになるのデス! なぜなら――
後日、仲介者である私を抜きにして、この二人が急速に親交を深める様をツイッター上で発見することになるからだ。二人で飲みに行き、すっかり意気投合したらしい。おまけに、互いのビジネスにとって互いが有益な関係であることを確認したようだ。もちろんコミケ後、この二人から私への音信は全く途絶えていた。私はそのやりとりを半ば呆然と眺めながら、分厚いガラス越しにヒロインが悪漢にレイプされるのを見せつけられている主人公のような気持ちになった。エッフェル塔を見ながらのファック・シルブプレにチュニジア人が乱入し、下半身を露出した私を差し置いてアルジェリア人とよろしく始めてしまったのを指をくわえて眺めるような感じ。正に、慟哭ゲーである。段ボール製のつけ鼻を貼りつけるセロテープの下の皮膚にしりしりとしたかゆみが――
ウオァァァァァッ! レポートのくせにクロノロジカル・オーダー、時系列がめちゃくちゃデス! そんな未来のことを現在のミーが知る由もありマセン! イフ知っていたらいま気弱げに会釈を交わすふたりの後頭部をわしづかみにして二つの頭が一つになるほど打ちつけた後、持ち前の体格を利用した地獄レスリングで金輪際アリアケでコミケトーが開催できなくなるほどの陰惨な流血ショーを演じたに違いありマセンカラ!
ふたりが作成したという土人ソフト(訳者註:softの表記。土人誌の一種か)をスーベニア、みやげに受け取りながら、このときのミーの胸中はブッディズムのハイプリーストほどかくやというほどに穏やかデシタ!
グリーティングを済ませた後も二人はサプライジングリー寡弁で、ミーの提供するトピックが少しもデベロップしマセン! これはさらなるアイスブレイキングが必要デス! インファントとさえ小一時間はカンバセーションを継続できるコミュニケーション力を使って、ミーは場をウォームしていきマス! 人と人との間に通底するのは不信だと考えているミーのようなフォリナーが、人と人との間に通底するのは信頼だと考えているジャパニーズより、こういった際のスキルに長けているのは実に示唆的デスネ!
グラデュアリー、次第に緊張がほどけると、二人ともミーのことを絶賛しはじめマシタ! アンド、どちらがより多く小鳥猊下を褒め称えることができるかのコンテストの如き様相を場は呈していきマス! 知らぬがブッダ、やがて訪れる未来を未だ知らない愚かなミーは、まんざらでもないとスモール・ノーズ、小鼻を膨らませて悦に入っていたのデス!
二人に関する断片化したインフォメーションをミーの高機能ブレインでデフラグしたところ、ポロリは年齢制限の必要なダウンロード専売ゲームのシナリオを、キムラはソーシャル・ゲーム(奇妙なネーミングデス! ソーシャル・ウィンドウ?lol)の製作をプロフェッション、生業にしているとのことデス! オーッ、これはリカを売り込むチャンスデース! キムラサーン、ポロリサーン、ユーたちがスロートからハンドが出るほど欲しがっている人材をミーは知っているネー!
「え、いや、それはちょっと」
先ほどまでの調子のいいほめ殺しぶりはどこへやら、キムラはとたんに口ごもりマシタ! アンドゼン、メンタルポロリが目深にかぶったニット帽の下からジットリとミーを見上げながら、唇の端を歪めて言いマシタ!
「いや、そこはほら、わかりましょうよ。キムラさん、困ってるじゃないですか。仕事なんだから、やっぱり実績が無い人にはお願いしにくいですよ」
アウッ、ポロリのインギンな低姿勢はオール子羊のパフォーマンスだったのデス! その表情には、既得権を持つ者の優越が隠しようもなくにじんでいマシタ! 先ほどまでのぎくしゃくとした関係はどこへやら、キムラとポロリは互いに顔を見あわせてニヤリと、長年の共犯者のスマイルを笑ったのデス!
オーッ、ジャパニーズ・コマーシャル・カスタム、日本の商習慣は文筆のようなエリアにまで及んでいたのデス! ミーはデザインのフィールドに関わるガイシ(骸死)系企業にいマスガ、過去の実績の有無がデザイナーの採用に最も大きく影響を与える日本の商習慣がリセッション、不況によりエンフォースされて新人の食いこむ隙間が無くなっているのデス! 実績によるリスクの回避というエントリー・バリアー、参入障壁がデザイナーの平均年齢を高齢化させた結果、既得権の維持がいまや業界そのもののシュリンクへとつながっていマス! シリアスな不況による相対的な発注量のリダクションが、最もクリエイティブの必要とされるはずのフィールドでカンパニーとそのデザイナーたちにビューロクラティック、官僚的なふるまいをさせている状況に、営業担当のミーはいささかの滑稽さを感じていたところデシタ!
アンドゼン、高い識字率を誇るジャパンにおいては同じ理由がファー・レス・クリエイティブな文筆産業に従事する者たちにさえ、アンコンシャス、無意識のうちに官僚的なアグリー・スマイルを浮かべさせているのデス! 高度成長のみを前提にしてきた日本経済の歪みを目の当たりにし、そのダーク・アビス、薄暗い深淵にミーは心底からスケアード、ゾッとさせられたのデシタ!
ミーはサドンリー、突然ふたりにフェアウェルを告げなければならない気分になりマシタ! オフ・コース、ブース越しにミーたちへ向けられるサメンの視線が中東でテラーのプランニングをしていたときのように険しくなり始めたこととは全く関係がありマセン! ミーに対する先ほどまでの陰湿な共謀ぶりはどこへやら、ミーとのカンバセーションが終わってしまうことを二人はひどく残念がりマシタ! ポロリが熱に浮かされたように言いマス!
「ボク、実家が関西なんです。猊下も関西に住んでらっしゃるんですよね。年内は仕事で難しいですけど、年明けに帰省する予定なんで、そのときは必ず連絡します!」
「オーッ、モチロンネー! マタ会エルノヲ楽シミニシテルヨー!」
イメディエットリー、即座にミーはその申し出を快諾しマシタ! ネット上では気難しいキャラ作りデスガ、その様をフィクショナル・ダイアリー、虚構日記と称しているのだからリアルのミーが話し好きで気さくなパーソナリティであることは容易に推測できるデショウ! このとき、ミーは求められる快楽にすっかり上機嫌デシタ! ビコーズ、この段階では桜が散り始める時期になってもアポイントどころか連絡のひとつも無いなんて思いもよらなかったカラデス!
ポロリに負けじと、リーマンヘアーのキムラが新人研修で秋葉原の通行人に自己紹介をしていたときのようなシャウトをしマス!
「必ず感想書きますから! 必ず!」
この男、失地を挽回しようと必死デース! コミケトー終了からワン・ウィーク・アフター、サラリーマンらしいデッドラインへの誠実さでキムラはリカの土人誌の感想を送ってきマシタ! この男のビジネスが成功することをミーは確信していマス! リーセントリー、ツイッターをななめ読みするに、最近のキムラはシェアハウスとやらにハマッているようデス! 独身のヤングマンが集まり、地縁的つながりのロストしたアーバンシティで新たなコミュニティをクリエイトする試みデス! ハウエバー、それを読んだとき、ミーのヘッドにはクエスチョンマークが乱舞しマシタ! 婚姻と育児を前提とせずにそれは持続的なコミュニティと呼べるのデショウカ? 宗教を前提としないコミュニティにはジャパン在住歴三十余年でようやく慣れたつもりデシタガ、あいかわらずジャパニーズ・カルチャーは世界の最先端を独走していマスネ!
ブースに戻ったミーがシット暑いブースで土人誌をリビングデッドに手渡すライン工に再び従事していると「オイ、マタオマエニ客ダ」、サメンが実に苦々しげな表情を浮かべて、ブースの外へ出るようミーをアゴで促しマシタ! ゲストとして来場したはずなのにサメンはミーのことを時間給のレイバー、労働者としてとらえ始めているようデス! ミーをブースの外へやることで時間あたりの労働対価がインクリースすると本気で考えているキャピタリスト、資本家のように見えマシタ!
ミーは生来のオプティミストなので先ほどの憂鬱な自称ファンどもとのやりとりはオールレディ意識のアウトサイドにあり、オールモストうきうきとした気持ちデシタ! ガイシ(骸死)系企業の営業部長であるミーは、人と会って話をすることがスリー・ミールズ・ア・デイ、三度の飯より大好きなのデス! イン・アディション、リカのファンには女性が多いと聞いていマシタ! 野郎が二回も続いたのデス! スタティスティクス、統計的に判断して、今度こそ女性に違いありマセン!
シュア・イナフ、まるで白魚で作った魚肉ソーセージのような指にリカの土人誌を抱えて立っていたのは、はたしてジャパン・ギークスの完全なる中央値で形成されたティピカルなおたく野郎デシタ! シィット、アゲイン! ミーは心の底からのディスアポイントメントを完全にシール、秘し隠して「アー、ヨク来テクレマシタネー、アリガトー、スゴイウレシイナー、ヨロシクネー」と張りのあるバリトンボイスで歓待しマシタ!
「いやー、これは思いつかなかったなー。すごいデブの中年おたくか、すごい引きこもりのウラナリか、すごい深窓の美少女かのどれかとは思ってたけど、こんな人を殴りそうなタイプだとは夢にも思わなかったなー」
視聴中のアニメをタイムラインで実況するときのような、出すべきではない心の声をあらわにしてそのギークは自己完結的に発話しマシタ! エスペシャリー、美少女の下りでは言いながら自分の言葉に失笑しやがったのデス! ミーは表面上、あくまでポライトネスをキープしましたが、こめかみには血管のクロスが青く浮かんでいたはずデス!
「あ、いや、わたしですか。ゴトウと申します。いやー、それにしてもほんと意外だったなー、これは」
そう、このギークスのティピカル中央値こそあの、独身おたくの自虐ネタで一世を風靡し、いまや数千万のアクセス数を叩きだす有名人気ホームページの管理人なのデス! ミーはシェイクハンドのために右手を差し出しながら、「十年前、ホームページを開設したばかりのユーからリンクの依頼をされたことをリメンバーしてマス! あれをアクセプトしなかったのは、ミーのネット人生の中でも最大のリグレットのひとつネー!」 努めて陽気な社交辞令として発話したつもりデシタ! しかし――
いったん口にすると改めて自分がそのことをひどく後悔している事実に気付かされてしまった。聞けば、ゴトウ氏はパソコン関連の商業誌に愉快なおたく4コマ漫画を連載しており、近々単行本化される見込みだと言う。それに引き換え、我が身がひねり出す文章は未だに一文にもならない、誰からも顧みられない、ネット上のアーカイブにのみしんしんと蓄積されていくクラップに過ぎないのだ。
あのとき、この男と相互リンクの関係を築いておきさえすれば、こんな惨めな現在ではなかったかもしれないのに! 深刻な後悔が後から後からやってきて、私のひざがしらをふるわせた。
「いやー、あの頃のテキストサイトの管理人たち、みんな有名になっちゃいましたからねー。☓☓☓さんとか、○○○さんとか……」
そう、一見は平等な参加を約束しておきながら、本当に才覚のある者たちはネットの外から見出され、あるいは自分の力でテキストサイトという過渡期的なカテゴリを離れていった。
この十年というもの、私は現実での立場を作るために時間を使いすぎた。小鳥猊下という名前のもう一人の私は、日々の生活の中でより重要ではない一隅へ追いやられ、その存在を希薄化していった。
自分のことを「透明な存在」と評したのは、いったい誰だったろう。いま、小鳥猊下としてここに立っている私は、本当に何者でもない、透明な存在だった。
「いやー、ぼくなんか全然っすよ。△△△さんとか覚えてます? あの人、もう成功しすぎちゃって……」
どの業界でも、成功者ほど腰が低い。ゴトウ氏が低姿勢でへりくだればへりくだるほど、傲慢を売りにしてきた私は結局のところ、自分の非才を認められないがゆえにそうしてきたことへ気づかされる。私はネットに出自を持つ偉大な成功者の一人を前にして、恥ずかしさに耳朶が染まるのを感じた。
「でも、本当に書いてないんですか? どこにも?」
商業誌など、金銭の発生する場で文章を発表しているかどうかという意味の問いだろう。もちろん、書いていない。もし書いていれば、コミケで持ち出しの同人誌を販売などするはずがない。本当に他意なく、不思議そうに聞いてくるその様子がかえってグサリと胸に刺さった。私は視線をそらしながら、口元をひきつらせて「書いてません」とだけ答えた。声がかすれないようにするのに必死だった。耳に届いた自分の言葉が、自分の心を切り裂く音を確かに聞いた。
「いやー、信じられないなー。本当かなー」
腕組みをしながら、愛嬌のあるいたずらっぽい視線で見つめてくる。悪意はないのだろう。しかしいまや私は動揺を見透かされないよう、わずかに首を横へ振るのが精一杯だった。
ゴトウ氏と私の間に横たわっている目に見えない何か。これが、これこそが、格なのだ。十年経っても数十万ヒットそこそこのサイトと、数千万ヒットを軽々と越えていくサイトの違いなのだ。一流ホームページと二流ホームページの違いなのだ。誰が見ても明らかな、圧倒的ヒエラルキーなのだ。
ずたずたの自尊心は、私に思わぬ言葉を口走らせた。
「あの、百万ヒットを達成したら、サイトを閉鎖しようと思ってます」
この瞬間ゴトウ氏の顔に浮かんだ、困惑と嘲笑と憐憫が入り混じった表情を私は一生忘れないだろう。きちがいを見る視線と、あざけりに半笑いの口元を、とまどいが結びつけた表情だった。
「はあ? いまは2011年ですよ? まだアクセス数とか言ってんですか?」
それは童貞を捨てた者が、童貞にコンプレックスを抱く誰かにかける言葉と似た響きを持っていた。手に入れば、価値を無くしてしまう何か。そして、それを焦げるように求める誰かがいることへの想像力は永久に失われる。
私はもう恥ずかしさに死にそうになって、ゴトウ氏から自分の同人誌を取り上げて、有明の海へ投げ捨ててしまいたいような気持ちに駆られた。ただ、表紙に描かれたイラストがそれを止めた。自分を貶めるのはいい。だが、このイラストを描いてくれた人を貶めてはいけない。
それが、私にかろうじて矜持を保たせた。
そこからどうやってブースに戻ったのかはよく覚えていない。
何度も出入りしてんじゃねえよ。ブースに戻る際、フリルのついた服を着た三十がらみの女性たちが嫌悪に満ちた視線を私へ投げたのはわかった。
「おう、遅かったじゃねえか」
中東出身の――いや、この男は服装こそ少々奇抜だが、ただ彫りの深いだけで外人ではない。猫背の青年と眼鏡をかけた大学生がちらりとこちらを見る。特に何の感情も伴っていない視線だった。コミケが終わりさえすれば二度と会うこともない人物に、どんな気持ちも抱きようがない。たとえば、旅先の電車で隣に座った誰か。人の中にいるがゆえのあの孤独が、胸へ迫る。私は曖昧に微笑むと二人に、 「売り子、かわりますよ」と言ってテーブルの前に立った。
「なかいいですか」「ええ、どうぞ」――それにしても暑い。
単調なやりとりを繰り返すうち、昔なじんだあの感覚が身内に戻ってくるのがわかった。背後から、もうひとりの私が私を見下ろしている感じ。機械のように日常のルーチンを繰り返すうち、自分という主体が消えてなくなる、あの感じ。
頭皮から伝い落ちた汗が、鼻に貼りつけた段ボールへ浸潤していく。頭の芯がぼうっとして、天と地の場所ももうわからないのに、釣り銭をわたす作業が少しも滞らないのを不思議な気持ちで眺めた。
周囲で歓声が上がり、拍手の音が鳴り響く。その騒ぎで、私はようやく我に帰った。どうやら終了の時間が来たらしい。待ち構えていたかのように会場に小さなトラックが入って来、椅子と長机を積み込んでいく。
はやくも祭りの後の寂しさが漂いはじめ、鼻の奥がつんとする。
ああ、まただ。いまを楽しむということを拒否し続けてきた私は、終わりの瞬間にいつもそれを後悔する。楽しむことで、愛することでより大きくなる喪失が怖いのだ。
こうして、私のコミケ初参加は幕を閉じた。
鼻腔をくすぐる風に塩気を感じるのは、海が近いせいか。縁石に腰掛け、来場者たちが三々五々、帰路につく様子を眺める。同人誌のたくさん詰まった荷物を手に、彼らの表情からは幸福感と満足感が伝わってくる。
結局のところ、私はあちら側の人間でもこちら側の人間でもないのだ。残ったのは疲労感と、在庫の山。私は両手に顔をうずめた。家人にどう借金の言い訳をしよう。私の心には、明日から再びはじまる終わりのない日常がすでに忍びよっていた。
「ここにいたのかよ」
彫りの深い男が座っている私に声をかけた。
「知り合いの編集にもおまえのホン、何冊かさばいといたぜ。まあ、ヤツら、読みゃしねえんだがな」
言いながら、豪放に笑う。やめてくれ。鼻に貼りつけた段ボールは汗と湿気を含んで変色し重くなり、セロテープは端から剥がれ始めている。
返事もしないまま力なくうつむく私に、男はあきれたふうだ。
「なんだ、在庫のこと気にしてんのかよ。ハハ、尻に敷かれてやがんな。俺も人のことは言えねえがよ」
ペットボトルを傾けながらの優しい軽口。もう、やめてくれ。私にそんな価値は無いんだ。
「心配すんな。俺たちのコミケはまだ終わっちゃいないぜ。あれを見ろよ」
私はのろのろと顔を上げる。そのとき、一陣の海風が強く吹き、濡れた鼻段ボールを一瞬のうちに乾かした。そこには果たして――
グルーサム、陰惨な風貌の男たちが五人、ロード・オブ・ザ・リングに登場するナズグルのようなたたずまいで路上にギャザリング、蝟集していマシタ!
「オレノ知リ合イノエロ漫画家連中ダヨ。コノ後、コミケノ“打チ上ゲ”ニ“ヤカタブネ”デナイトクルージングッテ趣向ダ」
打チ上ゲ? 割礼済みの下半身をエクスポーズしながらロケット状のサムシングに縛られたミーの周囲を、黒い肌をした土人がファイヤーダンスで取り巻くビジュアルが一瞬脳裏をよぎりマシタ! コミケトーの終了後に行われるセレモニーの一種らしいことは理解できマシタガ、それにしても、ヤカタブゥネとは何デショウカ? ジャパンにおいてヤカタとは血縁関係で結ばれた集団のリーダーを表していマス! そしてブゥネとはオフコース、あの大悪魔にして地獄の軍団を率いるデューク、ソロモンの魔神の一柱を示しているのに違いありマセン!
「イッタン乗セチマエバ、二時間ハ逃ゲラレネエ。アトハオマエノウデ次第ジャネエカ。サバイチマエヨ……在庫ヲ……アイツラニナ……!!」
中東出身のサメンの顔には、偃月刀を片手に洞窟で仲間とテラーの計画を練っていたときにそうだったろうと思わせる、歯を剥き出しにした凄絶な笑みが浮かんでいマシタ! ファウストを誘惑するメフィストフェレスが如く、ミーが破滅を宣言するのを待っているかのようデス! エターニティとイコールのサイレンスが流れ、ミーはスローリー、ゆっくりと、それがディステニーだったかのようにサメンへうなづき返しマシタ!
「ソウ来ルト思ッタゼ。売リ子ダケヤッテ、トットト帰ロウナンテタマジャネエッテナ! ココカラガ本当ノコミケッテワケダ!」
夏の夕空に響き渡るサメンの哄笑を聞きながら、ミーは武者震いにマイセルフのアスホールがきゅっとシュリンクする音を確かに聞いたのデシタ……!!
To be continued…
痴人への愛(3)
痛んだ傘を折りたたむのにてまどって、ちょっとぬれてしまう。舗装の悪い道路には、雨が何か所も水たまりを作っていて、いくども足をとられかけた。
その店は、目ぬき通りからすこし路地裏へ入ったところにあった。どぎつく明滅するネオンサインを水たまりが照りかえし、コーデリアはなんだか異国の地に迷いこんでしまったような気がして、かるいめまいをおぼえた。
やせぎすのからだをあずけるようにして重いスチールの扉を開けると、手すりのないひどく急な階段が地下へとつづいている。
せまいおどり場にあるさびた傘たてには、すでに傘が何本か入れられている。そのうちのひとつに、見おぼえがあった。「背の高い人用」と書かれた購入時のラベルがそのまま柄に貼られている。
コーデリアが、小鳥尻の誕生日に贈ったものだった。
小鳥尻は傘を持つことをきらっていた。どんな大ぶりでも、コートひとつで出かけていき、海の底を散歩してきたみたいになって帰ってくる。
「なんか雨にうたれてると、すこしだけ気もちが楽になるの」
なぜ傘を持たないのか、いちどたずねたことがある。さいしょ、小鳥尻はじっと黙ったままだった。その反応はとくだん珍しいことではなかったので、コーデリアもそれきり黙ったまま、つくろいものをはじめた。
ゆうに五分は経ったろうか、そう小鳥尻が答えたのである。
「どうして楽になるの?」
小鳥尻の両目が一瞬、遠くを見るようにさまよって、やさしくゆるんだ。
「私ね、子どものころ、悪いことをするとよくお母さんに家の外へ追いだされてね。そんなときはなぜか決まって雨が降ってたわ」
コーデリアはいちど、小鳥尻の母親に会ったことがある。
このたびは、うちの娘がたいへんなご迷惑をおかけしまして――
病室の敷居にきっちりとつま先をそろえ、定規をあてたような深いお辞儀をする姿をおぼえている。示談の話しあいにきたのらしかった。ぜんぶ両親が対応したので、コーデリアは二言三言を交わすきりだった。
印象は悪くなかった。すこしやせすぎのきらいはあったけれど、品のいい、知的な女性だったと思う。
いっしょに暮らすようになったさいしょのころ、小鳥尻が母親のことを悪しざまに言うのを何度か聞いたことがある。それはあまりに病室での印象とちがっていて、コーデリアが「冗談でしょう」とか「思いちがいじゃないの」とか相づちをうつうちに、いつしか小鳥尻は母親の話をもちださなくなった。
「雨の音ってやさしいでしょ。知ってる? 雨ってね、あったかいのよ。家のなかはうるさくて冷たくて、雨にうたれてるほうが、ずっとよかったわ」
コーデリアには、小鳥尻がなにを言っているのかわからなかった。それどころか、すこし意地わるく、「ちょっと悲劇ぶってるわ」と考えたりもした。
「でも、雨にぬれると風邪をひくでしょ。もう子どもじゃないんだから、雨の日は傘をさしてね。こんど、プレゼントしてあげるから」
コーデリアの言葉に、小鳥尻は悲しそうにほほえむきりだった。
玄関の傘が二本になり、この話題はそれきりとなった。
壁に手をつきながら、すべらないように一段一段をふみしめる。階段のつきたすぐ右手が、喫茶店のようになっていた。できるだけめだたないよう、すみのテーブルに腰をおろす。
すわったことにホッとすると、人心地がもどってくる。
コーデリアは、前かけにサンダルをつっかけているじぶんに気づいた。大またに前を行く背なかを見うしなわないようにするあまり、気がまわらなかった。はずかしさに顔があつくなる。
いすの背もたれは毛羽がたっていて、なにかの液体がかわいたようにゴワゴワしていた。手をふれたテーブルの表面はわずかにねばっている。いまさらながら、ひどく場ちがいなところにいる気がした。
口ひげをはやした小太りの店員が、水をもって近づいてくる。コーデリアは手ぐしに髪をなでつけた。
「ご注文は?」
あわてて前かけのかくしをさぐると、がまぐちに指がふれる。すっかり紙のくたびれたメニューをひらくと、よくわからないカタカナがならんでいた。アルコールのたぐいらしい。
「あの、ウーロン茶をください」
一週間分の食費と同じ値段だった。店員が失笑めいた鼻息をもらしたような気がして、コーデリアは思わずうつむいた。
それでも注文をすませてしまうと、居場所をえたような気もちになった。
まわりには、すでに何人かの客がすわっている。奥にひとつ高くなったところがあり、左右にカーテンのようなものが下げてあって、どうやらかんたんな舞台になっているらしい。
ウーロン茶がはこばれてくると照明がさらにしぼられ、カーテンのそでからだれかがあらわれた。かん高い声の、ふたり組の女性だった。
すぐにかけあいがはじまる。漫才のようだ。言葉が多すぎて、どんな内容なのかコーデリアの頭にはまったくはいってこなかった。あたりを見まわしても、客たちはだれも舞台を見ていない。どういうお店なのだろう。
すぐ目の前のテーブルに、若い男がひとりですわっている。ゲーム機なのか携帯電話なのかよくわからないもので、アニメを見ていた。画面の中では、馬に乗った制服姿の少女が刀をふりまわしている。場面が変わるたび、ちがった色の光が横がおにうつりこむ。
なんだかコーデリアは、ひどく正しくない、ふつうではないことが行われているような気がした。
まばらな拍手に、はっと我へかえる。ふたり組の女性は大きく一礼して、舞台のそでへとひっこんでいった。
入れかわりに、セーターに巻きスカートの女性が、グラスとビンを片手でひっつかみ、小さなテーブルをひきひきあらわれる。
とたん、コーデリアの心臓ははねあがり、あたまの芯にはしゃきっとしたものがもどってきた。小鳥尻だ。
すでにひどく酔っているようで、足もとはふらつき、目は赤く充血している。
「飲めば飲むほどおもしろく、ってわけにはいかないけど、しらふでできる芸でもないのよね」
卓上にグラスを置き、こはく色の液体をそそぐ。
「とりあえず、きょうの出会いに乾杯」
客たちへむけてグラスをかかげると、いっきにあおった。とたんせきこんで、ほとんどを床にこぼしてしまう。長身をおりまげてせきこみ続けるようすに、コーデリアはそばへかけよりたい衝動にかられる。
やがて口もとをぬぐいながら、
「それじゃあ、はじめましょうか」
小鳥尻が巻きスカートをはぎとり、客席へと投げる。それはだれにも触れられることなく床に落ちた。肌色のタイツには、股間のところに亀の子タワシがはりつけられていた。
「わたしのタワシ、気持ちいーでー、わたしのタワシ、気持ちいーでー」
芸をはじめたとたん、酔いに正体をうしなっていた小鳥尻の声がぴんと張った。家でのぼそぼそと聞きとりにくい話し方とはまったく違っていて、コーデリアはファンとして観客席にいた昔を思い出して、胸がつまるような気もちになった。
「なーなー、わたしのタワシ、気持ちいーでー、わたしのタワシ、気持ちいーでー」
がにまたで上半身をそらせ、いくどもタワシをこすりあげる。やはりだれも舞台を見ようとはしない。ただひとり、目の前のテーブルの若い男だけが、アニメから目を離し、食い入るように小鳥尻を見つめていた。
「うるせえぞ!」
さけび声とともに、客席から舞台へグラスがとぶ。酔っぱらい相手の舞台には、よくあることなのだろう。
けれどこのとき、運の悪いことにそのグラスは小鳥尻のこめかみを直撃した。たまらず長身を折りまげ、卓に手をつく。こめかみを押さえた手のすきまから赤いものがしたたり、小鳥尻の両目はむきだしの、凄惨なものをたたえていた。
思わず、コーデリアは席を蹴って立ちあがった。椅子の背もたれが床にたたきつけられて、大きな音をたてる。まわりの客から、いぶかしげな視線が向けられた。
「いってーなー、おい! いってーなー、おい!」
ことさらな大声が、みなの視線を舞台へともどす。小鳥尻は背中で床をそうじするみたいなオーバーアクションでおどけて、のたうちまわっていた。その表情は、すでに芸人のそれにもどっている。
観客から笑い声があがる。たちの悪い笑い声だった。
コーデリアはもう見ていられなくなって、狭い階段をかけあがるようにして店を出た。
「傘、忘れてるわよ」
看板のネオンが消えると、背の高い人かげが細い路地から出てくる。傘をさしだすコーデリアを肩ごしにちらりと見ると、そのまま何も言わず歩きだす。
「ねえ、傷はだいじょうぶなの」
うしろをついていきながら、声をかける。小鳥尻は、猫背に首をうめるように両肩をもちあげて、話しかけられるのをこばんでいる。コーデリアは一瞬、ひどく悲しくなった。しかしすぐにそれは、むかむかとした怒りにとってかわられた。
「こんなに心配してるのに、その態度はなによ!」
じぶんでもびっくりするほど大きな声だった。
その剣幕におどろいたのか、小鳥尻は足をとめてふりかえる。こめかみにはガーゼが雑にはりつけてあった。
「仕事のときはくるなって言ったじゃない。それに、あんなのいつものことだから、心配なんていらないわ」
先ほどの舞台とは別人のように、ぼそぼそとした言いわけだった。それがますます、コーデリアをいらだたせる。
「わたしをなんだと思ってるのよ! 猫のせわ係じゃないんだから! わたしにだって、心配する権利くらいあるんだから! こわいんだからね! わたし、怒ったらこわいんだから!」
むちゃくちゃを言っているなと思ったが、もうとまらなかった。
体はおおきいくせに、小鳥尻にはひどく気のよわいところがある。このときもうろたえたふうにコーデリアから目をそらして、「これはわたしのことだから」とつぶやいた。「ぜんぶ、わたしひとりで証明しなくちゃいけないのよ」
「だれに証明するのよ! なにを証明したいのよ! だれも見てない舞台で、みんなわすれた芸をして、どうやって証明できるのよ!」
小鳥尻が大またに近よってきて、手をふりあげた。これだけ言われれば、そうするしかないのはわかっていた。山のように大きくてまっ黒なものがおおいかぶさってくる。
わたしは逃げない。逃げてたまるもんか。
コーデリアは小鳥尻を受けとめるように、両手をいっぱいに広げた。いつかまえにもこんなことがあった、と考えながら。
のけぞるあまり、ふんばった足がぬれた地面にすべった。
ネオンにふちどられた空が見えたかと思うと、すぐにあたりはまっくらになった。
「ごめんなさい、ごめんなさい」
目をあけるとコーデリアのかたわらに、ぬれるのもかまわずすわりこんで、小鳥尻がすすり泣いていた。
「私、きょうね、本当はね、すごくうれしかったの。はじめて、家族が舞台を見にきてくれたから」
体には力がはいらず、頭のうしろは割れるように痛んだ。小鳥尻を心配させまいと、コーデリアはなんとかあいづちをうつ。
「昔、なんども行ったじゃないの」
「あれはファンとしてでしょ!」
口をとがらせるようすがひどく幼く見え、コーデリアの胸はしめつけられるように苦しくなった。視界がじわりとにじむ。
「どっか痛むの?」
具合のわるい親を心配するときの子どものような、あどけない表情。コーデリアはなぜか、カッコウの托卵のはなしを思いだした。
「ううん、だいじょうぶよ。ねえ、さっきの話、くわしく聞かせてくれる? だれに証明したかったの?」
恋人どうしのはずなのに、対等ではない気がしていた。ずっと一方通行なかんじがしていた。それはきっと、小鳥尻の想いが、親を求める子の想いと同じものだったからだ。
のどの奥にうまれた氷のような嗚咽のかたまりを飲みくだすと、コーデリアはやさしくたずねた。
小鳥尻は視線をさまよわせて、しばらく考えるそぶりをみせた。
「やっぱり、パパ、かな」
「お父さん?」
意外な答えだった。父親のことを聞くのは、これがはじめてかもしれない。
「うん。わたしのパパ、すごいのよ。……の社長でね」
だれでも聞いたことのある、少し大きな会社の名前だった。
小鳥尻はどこか浮世ばなれしていて、芸人なのに、生活によごれた感じがなかった。良くも悪くも、お金に頓着がない。それは裕福な家庭に育ったことが理由なのかもしれないと、コーデリアは思った。
「小さいころからずっと、パパのこと、自慢だったなあ。でもね、わたし、勘当されちゃったの」
小鳥尻の口もとが、泣くのをがまんする子どもみたいに、への字にまがった。
「お母さんが、わたしがこうなのは、こころの病気のせいだって。育て方とかじゃなくて、病気なのが悪いんだって。プロだから、わかるんだって。わたしのことでパパとケンカするとき、いつもそう言ってた。病気なんかじゃないのに」
頭は熱いのに、手足が冷えてきて、みぞおちのあたりには吐き気があった。小鳥尻は気づいたふうもない。
「プロって、なんのプロ?」
かろうじて、そううながす。わたしはいつでも聞き役だわ、とコーデリアは思った。
「私のお母さん、こころのお医者さんだったの。パパと結婚してから、働くのはやめたみたいだけど。じぶんの生まれた家はケッソンカテイだったって、いつも言ってた。ねえ、知ってる? そういう壊れた家庭にそだつと、子どものころの失敗をとりかえそうとして、大きくなってからも同じ環境を作ろうとするんだって。絶対にうまくいかない人間関係を、のぞんで作ろうとするんだって」
ああ――
小鳥尻は、いまじぶんが話していることがどういう意味なのか、わかっているのだろうか。
「わたしずっとヘンだなって。子どもだったから、言葉にできなかったけど、病気の人が病気の人の病気をみるってすごいヘンだなあ、って思ってた。お医者さんになるために病気になるみたいで、すごいヘン」
小鳥尻の母親はきっと、成功しないことに成功したのだ。呪いを、次へと手わたして。
「わかったわ。お母さんの言ってたことがまちがいだったって、お父さんに証明したいのね」
「そうそう!」
うまく伝えられない話を大人が先回りしてくれたときの子どものような、とびきりの笑顔だった。
「ねえ」
「なあに?」
コーデリアはあらためて、この一方通行な関係を悲しく思いながら、言った。
「これだけは信じてほしいの。わたしはあなたを本当に助けたいと思っている。しあわせになってほしいと思っている」
小鳥尻をまっすぐに見つめる。
「わたしは、あなたのことが好き。でもね、すこしだけ、つかれちゃった」
まぶたを閉じると、とたんに全身が重くなって、背中から地面にすいこまれるような感じがした。小鳥尻の泣き声が遠のいていくのを心地よく思うじぶんにぞっとしながら、コーデリアは意識を手ばなした。