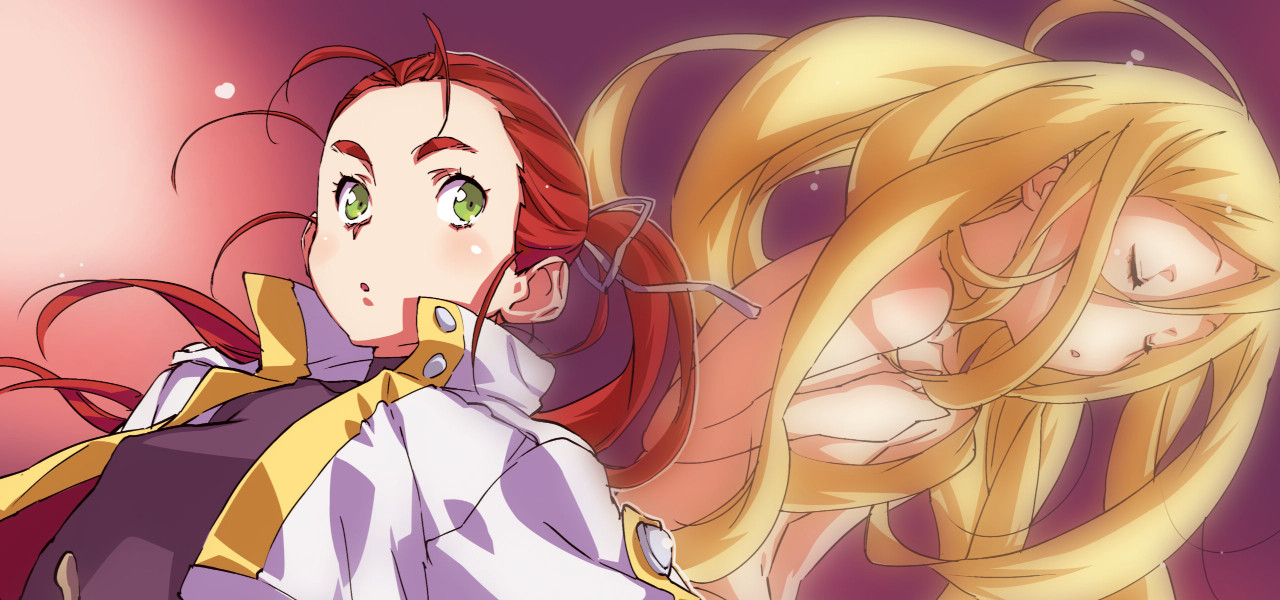雑文「2023年のnWoテキストまとめ」
昨年の慈愛からスタートしたnote記事による年度のふりかえりを、今年も行っていこうと思います。いま記事を数えたら、52個ありました。1週間に1記事ほどをアップしてきた計算になります。では、2024年をダラダラとふりかえっていきましょう。各記事の紹介に付記する星マークの5段階評価は、作品ではなく自分のテキストに向けたものです。
凡例:★★★★★(5点・最高)
★☆☆☆☆(1点・最低)
No.01:アニメ「16bitセンセーション」感想(最終話まで) ★★★☆☆
エロゲー業界に対する複雑な気持ちはいまもどこかあって、もし人生の分岐として選択していたら生き残れなかったと冷静にわかるがゆえの、羨望に近い嫉妬です。
No.02:ゲーム「バルダーズゲート3(1章)」感想 ★★★★☆
結局、2章の終盤あたりで放りだして、クリアにはいたっていません。主にシステム部分へ「西洋人の精神構造の、鼻フック的な異形さ」を見ることができます。
No.03:アニメ「スナック・バス江(1話)」感想 ★★★☆☆
「ラーメン屋で麺をすすりながら、雑誌で片手間に読む」ぐらいだった好きの温度感が、どうしてエスエヌエスでは、是も非も強火の狂熱になっちゃうんでしょうね。
No.04:アニメ「ぽんの道」感想(あるいは、麻雀とはずがたり) ★★★★★
麻雀なる遊戯への想いについて、小鳥猊下がネット生活25年でほとんど初めて語ったという意味で、貴重なテキスト。界隈の客層は、依然として悪いと思いますよ。
No.05:ゲーム「鉄拳8」感想 ★★★★★
格闘ゲームへの想いについて、小鳥猊下がネット生活25年でほとんど初めて語ったという意味で、貴重なテキスト。彼/彼女はあの時間を、理科系の勉強にあてるべきでした。
No.06:ゲーム「崩壊スターレイル・第3章前半」感想 ★★★★☆
三体とならび称すべき傑作SFなのに、イマイチあつかいが悪いのは、もしかしてゲーム分野を下に見てます? 油断すると理系への恨み節が混入するのは、悪いクセです。
No.07:映画「ナポレオン」感想 ★★★☆☆
小鳥猊下の流麗なテキストを読ませたいのに、あつかう題材のマイナーさで伝播にキャップがかかってしまった好例。「なんで妊娠しねえんだよ、チャクショーッ!」
No.08:ゲーム「風来のシレン6」感想 ★★★★★
正直、SFC版シレンにあてる時間を勉強に使っておればとの後悔もなくはないですが、美しい思い出は残りました。「とぐろ島の真髄」は、まだクリアできていません。
No.09:ゲーム「ファイナルファンタジー7リバース」感想(開始20時間) ★★★★★
FF7Rebirth感想4部作・その1。下半期に登場する、赤の他人の若造が作ったDQ3Rに比して、老獪なクリエイター本人が持てるすべてを注いだ、愛あるリメイク。
No.10:雑文「ドラゴンボールとはずがたり」 ★★★☆☆
あまりに有名すぎて逆に言及しにくい作品であり、「Z」以降の世界的な客層の悪さも、それに拍車をかけました。ここで恩人を公言している人物は、ヤマグチノボル氏です。
あけましておめでとうございます。
今年も、よろしくおねがいします。
慈愛は、大閑散継続中です。何卒。
No.11:漫画「ブルージャイアント・エクスプローラー9巻」感想 ★★★★☆
創作者が創作物に謝罪するような作品を見るのは、もしかすると初めてかもしれません。ちなみに、創作者が創作物に言い訳をする作品は、呪術廻戦の最終巻です。
No.12:ゲーム「ファイナルファンタジー7リバース」感想(ゴールドソーサー到着) ★★★★★
FF7Rebirth感想4部作・その2。前作に引き続き、「夜の街関連」の表現がじつにすばらしく、クリエイターの人生および性癖と骨がらみになった、名リメイク。
No.13:雑文「続・ドラゴンボールとはずがたり」 ★★★★☆
ある世代の構成員が現役か現世から退場することによって、マジョリティの価値観が大きくシフトするのを見てきましたが、そこに陰謀論的な主体が存在しないのは恐ろしいです。
No.14:雑文「猫を起こさないように(nWo)・復活のテキストサイト」 ★★★☆☆
復活したんですけど、反響は絶無でした。昔なじみで現世の権威となったキミとかキミとかが、裏アカ以外で言及するだけで、バズる素地はあると思うんですけどねえ。
No.15:ゲーム「ファイナルファンタジー7リバース」感想(コスモキャニオン到着) ★★★★☆
FF7Rebirth感想4部作・その3。雇われ人として、クリエイター人生の黄昏をむかえただれかが歌いあげるエレジーのような、しっとりとした味わい深いリメイク。
No.16:アニメ「バーンブレイバーン」感想 ★★★☆☆
ものすごい速度でバズって、ものすごい速度で消費しつくされた印象です。ループものとして出来がよかったとは言えませんが、もう少し創作物を大切にあつかってほしい。
No.17:ゲーム「ファイナルファンタジー7リバース」感想(初回クリア) ★★★☆☆
FF7Rebirth感想4部作・その4。源氏シリーズを収集して、ギルガメッシュを倒すところまでプレイしました。リメイク3には、一抹の不安を抱きながらも期待しています。
No.18:雑文「政治的アべンチュリン礼賛(近況報告2024.4.20)」 ★★☆☆☆
「春の鬱による生真面目さ」が、にじみでているテキスト。説教したい気分の中年からは、距離を置きましょう。ここでファンを公言している人物は、デスポカ氏です。
No.19:映画「オッペンハイマー」感想 ★★★★★
「創作者のカルマ」みたいな悲壮感にガンギまって気持ちよくなっているの、すずめの戸締りと同じですよねー。「メディアの責任」なる言葉からもただよう臭みですよねー。
No.20:映画「アステロイド・シティ」感想 ★★★☆☆
中途半端にファッションでさわりにきたあげく、メルトダウン事故を起こすぐらいなら、テーマ性なんていらないんじゃないの? ケトゥ族がどうあつかったって、軽妙洒脱にはならんよ。
No.21:ゲーム「ステラーブレイド」感想 ★★★★★
どれだけ聖人君子のふるまいをする御仁でも、女体からの性的なアトラクションは退けられないことを痛感しました。カルメン伊藤氏によるイイネが印象に残っています。
No.22:雑文「SHINEVA, STARRAIL and FGO(近況報告2024.5.20)」 ★★★★☆
シンエヴァについては、存在しない周囲の期待にしゃべらされてしまっている感があり、自重せねばとは思っています。あらためて、2024年のファンガスは大車輪の活躍でしたねー。
No.23:アニメ「ウマ娘プリティーダービー・新時代の扉」感想 ★★★★★
ウマ娘界隈とは、個人的にかなり温度差ができてしまっているので、フェアな感想とはとても言えません。のちに語ることとなる「ポコチン着脱問題」は、強く感じました。
No.24:映画「マッドマックス・フュリオサ」感想 ★★★★☆
興行収入にしか興味のない、作品の出来なんて二の次な剛腕プロデューサーと矜持をかけて行う、血を吹くような激突の火花が、いまの映画界には足りていない気がします。
No.25:書籍「麻雀漫画50年史」感想 ★★★☆☆
「男性が創作物を評価するとき、脳髄からポコチンを外せるか?」は、オタク界隈に古くからある命題でしょう。この記事で多くを敵に回したような気がしていますが、とてもいい本です。
No.26:雑文「中年が終わって、パーティが始まる」 ★★☆☆☆
昭和のドぎつい家名ベースな価値観を擁護したい気分がムラッとわいて、つい挑発的に書いてしまいました。シロクマ先生の類似本の感想を書こうとして、止めました。
No.27:アニメ「ルックバック」感想 ★★★★☆
原作漫画には、「SNSを通じたクリエイター業の神格化」が煮つまった末の作品という印象を持ちました。永遠のワナビーたる小鳥猊下が抱く感想としては、穏当なほうでしょう。
No.28:ゲーム「エルデンリングDLC:シャドウ・オブ・ザ・エルドツリー」感想 ★★★☆☆
テレホーダイは遠くなり、ネットへの常時接続が当たり前の時代、触れる時期によってゲーム体験がまったく変わってしまうのは、良し悪しだと思いますね。
No.29:雑文「FUNGUS, HOYOBA and FGO(近況報告2024.7.25)」 ★★★★☆
近年のFGOはバイオレンスジャック化しており、過去作キャラの登用が頻回となってきた印象ですが、第3部からファンガスがディレクションから離れる可能性はあると思います。
No.30:漫画「ハイキュー!!」感想 ★★★★☆
読んでいない有名漫画が無数にあるのですが、人間のベースがミーハーなので、オリンピックに影響された結果です。結果、「正しく終われなかった物語」カテゴリに入りました。
No.31:ドラマ「地面師たち」感想 ★★★★★
古い慣習によるキャップさえ外せば、本邦の脚本・演出・撮影・俳優は、ここまでできるのだという、ある種の希望となった作品で、ピエール瀧の生存確認にも最適です。
No.32:映画「ザリガニの鳴くところ」感想 ★★★★★
エロゲーを愛好する男性が抱える「認知の歪み」について、女性サイドからミラーリングした内容になっています。頭文字Fに対する批判の橋頭堡を得たい向きは、ぜひ視聴を。
No.33:ゲーム「黒神話:悟空」感想 ★★★★★
第2回の最終ボスがたおせず、投げだしました。ストーリーの先は気になりますが、自キャラ強化よりアクションの習熟に強い力点があるゲームを遊びきる体力は、もうないです。
No.34:映画「ドント・ルック・アップ」感想 ★★★★★
この時期に神テキストが連発されているのは、仕事の進捗や精神の状態がよかったせいでしょうか。「題材のマイナーさが、記事の拡散にキャップをかける」典型例になっています。
No.35:ゲーム「原神5章・ナタ編」感想(少しFGO) ★★★☆☆
原神のプレイ歴も3年に近づきつつありますが、成功も失敗もすべて次の改善につなげていく、「生成のダイナミクス」を強く感じます。現代ゲームの最高峰のひとつと言えるでしょう。
No.36:映画「きみの色」感想 ★★☆☆☆
まず考えをザッと出力したあと、3日ぐらいかけて徐々にテキストを修正していくのですが、この記事は書いた当日にほぼそのままアップしており、塩気のききすぎた中身になっています。反省しています。
No.37:漫画「呪術廻戦」感想(27巻まで) ★★★★☆
本作の両面宿儺にせよ、キメツの鬼舞辻無惨にせよ、「強大な能力を持ちながら、達成すべき目標は不明瞭、または不在である」という、悪の魅力を欠いたラスボスが増えてきていませんかねえ。
No.38:ゲーム「FGO奏章III:アーキタイプ・インセプション」感想 ★★★★★
ファンガスへのよく書けたラブレター・2通目。いまを生きる市井の感情をここまで見事に物語へと落としこめるなら、小鳥猊下はこんなnote記事の群れを書いてはいないでしょう。
No.39:映画「ボーはおそれている」感想 ★★★★☆
すべてを親子のトラウマに紐づけたいアリ・アスターと、すべてはそれと関係ないともがき苦しむホアキン・フェニックス、監督の意図が俳優の演技を原色ペンキで塗りつぶした駄作。
No.40:雑文「シン・ヤマト(仮)制作発表に寄せて」 ★★★☆☆
すべての事象に「こうあるべき」を持つ、やっかいなオタクが権力を掌握してしまったゆえの悲(喜)劇。けれど、人の死をダシにおもしろテキストを書いてはいけませんね。
No.41:ゲーム「原神5章4幕・燃ゆる運命の虹光」感想 ★★★☆☆
新マップ導入の順番やイベントのクオリティなど、5章は制作進行の乱れを感じることが多かったのですが、5幕におけるドラマツルギーの大爆発ですべて帳消しにしました。詳細は、また。
No.42:映画「ジョーカー2:フォリ・ア・ドゥ」感想 ★★★★★
この年始に、初見の家人たちと2度目の視聴をする機会があったのですが、画面の縦横比率が変わる妄想ミュージカルでのホアキンのムンムンな色気に比して、ガガの演技はスッカスカだなーと思いました。
No.43:映画「室井慎次・敗れざる者」感想 ★★★★☆
地面師たちの対極にある、本邦の悪い慣習の煮こごりみたいな作品。かつてのキャラ愛にすべてをのみこんで、血涙のエールを送ったファンたちのことが、一瞬でも脳裏をよぎらなかったのでしょうか?
No.44:ゲーム「ロマンシング・サガ2:リベンジ・オブ・ザ・セブン」感想 ★★★★☆
最近の記事でも言及しましたが、Switchのロースペックさに引きずられる形で、本作のグラフィックは非常にショボいと感じます。大手がインディーズ以下って、どうなの。
No.45:雑文「Update of Romancing S…TARRAIL」(近況報告2024.11.7) ★★★★☆
2周して、最高難度のロマンシングに挑戦する手前までハマッたのに、後述するうんこリメイクへの怒りに気勢をそがれてしまいました。いつか再び、「リベンジ」したいです。
No.46:ゲーム「ドラクエ3リメイク」感想 ★★★★☆
おのれの魂と不可分に癒着した3への偏愛を、いまさら再確認することになるとは、想像だにしていませんでした。そして、このテキストを書いているときは、まだどこか期待する気持ちが残っていたのです。
No.47:雑文「THE ODORU and DQ3 LEGEND ALREADY DIED」(近況報告2024.11.28) ★★★★★
ファンの存在を完全に無視した踊る最新作と、恐怖を感じるほどずっと下げ止まらない3リメイクへの評価。2つの記事に分ければよかったと後悔しております。
No.48:雑文「そしてPC版へ…(DQ3R哀歌)」 ★★★★☆
新年を迎え、mod界隈が冷えきっているばかりか、いまだバージョンアップさえ行われないまま放置されており、かつてのレジェンドへのひどい仕打ちに、泥酔しながらオイオイと声をあげて泣いています。
No.49:雑文「STARRAIL, DQ3R and FGO」(近況報告2024.12.13) ★★★☆☆
女神転生とFateシリーズの関連って、みんな気づいてて黙ってるの? 筒井康隆と小鳥猊下の関連を、優しさから指摘しないようなもの? よく訓練されたフォロワーシップなの?
No.50:漫画「推しの子16巻」感想 ★★★★★
「転生」が物語をビルドアップするギミック以上の「世界の謎」として、ストーリーの中心に置かれた作品って、存在するんですかね? もしご存知なら、こっそり耳うちしてください。
No.51:ゲーム「ドラクエ10オフライン」感想 ★★★★★
新しいのに、ちゃんとドラクエしてて、心の底からホッとします。それにひきかえ、とりやま・すぎやま両氏の実質的な遺作となったタイトルに、あそこまで泥をぬったのはゆるせない。
あれ、昨年に続いて、また1記事たりないなー。年末年始はだいたい酩酊してるから、小鳥猊下の本質である「振り子のような正確さ」が乱れちゃうなー。
No.05.5:ゲーム「原神・閑鶴の章」感想 ★★★★★
「発表! 毒親選手権!」みたいな本邦の創作界隈に向けた痛烈なるカウンター。制作者の属性が私文学士か国立博士かの違いでしょうか。人生の節目に、深く刺さりました。
ありました。個人的に、昨年を象徴するようなコメントです。慈愛は明日いっぱいまで開けておきますので、コメントやご依頼や萌え画像などあれば、ぜひ。