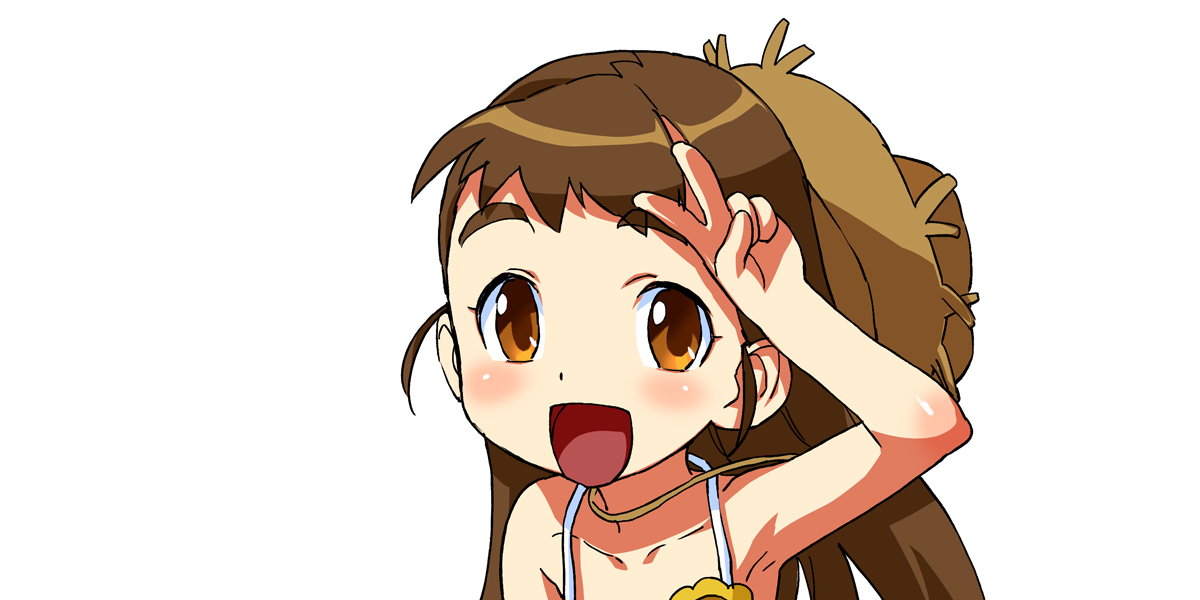すずめの戸締まり、愛最大(アイマックス)で見てきた。nWoからおずおずと提案させていただいた持続可能な創作目標であるところの「地方行政と結託したご当地巡り」を素直に受け入れた九州を舞台とするオープニングから、四国・神戸・東京を順に旅していくロードムービー感がたいへんにすばらしく、何より女子高生からスナックのママまで女性の描き方があらゆる年齢層で過去最高に気持ち悪くない。おそらくよくできた奥さんと、たぶん中高生になった娘さんと日々むきあう中で、彼の中にあった「おたく特有の女性に対する偏見」が希釈されていった結果なのでしょうね。カタカタ椅子の走り回る奇想天外な序盤も、奥さんが娘さんに読み聞かせた「ふたりのイーダ」なんかが着想の原点なのかな、などと微笑ましい気持ちで眺めていました。じっさい、物語の中盤までは「新海誠の集大成にして最高傑作!」というタガの外れた宣伝文句に同調していく気分さえあったのですから。それを、民俗学をフレーバーとした類似ケースの匂わせに止めておけばいいものを、突如「ボクは覚悟を決めました!」と絶叫するやいなや、懐メロをバックにフルスロットルで不可触ゾーンへと特攻していったのです。これには、前半の好印象がすべて蒸発・気化するレベルで吃驚仰天しました。東京が水没していないことからもわかるように、本作は意図というより結果として「君の名は」「天気の子」と舞台やキャラを継続させた「東京3部作」ではなく、テーマだけを引きついだ「震災3部作」の完結編であることがここで明らかとなります。
新海誠が公には言えないほど重度の「異常福音戦士偏愛者」であることは「ほしのこえ」の昔から有名な話で、本作もミミズ消滅の演出など、映像的にはエヴァ序破ーーと、たぶんシン・ゴジラーーの強い影響下にあります。しかし、それは表層だけの話であり、根深いのは空虚な駄作にすぎないエヴァQから、真剣に意図を読み解こうとする過程で被った思想的な侵蝕です。彼はエヴァリブート第3作目が無惨にも大失敗した理由を真摯に考え続け、同作が東日本大震災との関連を明示しなかったために「依拠する現実を失った荒唐無稽な作りごと」へ堕したのだという結論に至った。そして、エヴァQができなかった東北の災禍と震災孤児を真正面から描くことを「逃げずに」やらねばならないと、真面目な監督はついに「決意して」しまったのでしょう。商業サイドからの要請に過ぎない、いくらでも回避できる外挿的な圧力を、例えば「作家の宿業」などといった言葉で内在化して、自己陶酔的に「覚悟を決めた」様子が物語の後半からありありと伝わってきます。さらに指摘しておくと、本作は九州から東京までがエヴァ序破の映像的オマージュ、東京から東北までがエヴァQが隠蔽した裏テーマへのアンサーという構成になっているのです。
「天気の子」の感想に、「フィクションなんだから街のひとつやふたつ壊したって構わない」と書きましたが、それはその災害がフィクションだからこそです。「この世のすべての問題の当事者であり、いずれにも関与して解決することができると信じる」のは極めて少年漫画的、もっと言えば幼児的、あるいは昨今のSNS的な誇大妄想に過ぎません。人の世を生きていけば否応に立ち位置は生じてくるもので、この作品のメッセージを受け止めた上で肯定的なまなざしを送れるのは、陰キャのクリエイターを焚きつけて理性のネジを外させた陽キャのプロデューサーか、現世のあらゆる事象から等距離を保つ独居ディレッタントぐらいしか思いつきません。「批判は覚悟の上で、被災児童と里親との関係性を鋭くえぐりだした」みたいな言い方は、この世には軽々に部外者が踏み込んではいけない場所があることを意識的に無視した暴挙であり、人としての無神経とデリカシーの欠如について、興行収入を盾に「作家の覚悟」と読みかえる傲慢さのあらわれでしょう。昔からのファンが「異常性欲者」なる言葉で揶揄するように、嬉々として「あの場面の力点は適齢期を逃した叔母の心情ではなく、どれだけ女子高生の心を深く傷つけられるかというサド的性癖によるチャレンジだ」などと語れる規模の作家ではもはやなくなっているのを、他ならぬ当人が自覚すべきでしょう。
物語の終盤、震災孤児へと送る励ましのメッセージがでてきますが、医者に呼ばれた親族だけの病室へ見知らぬ人物が闖入し、「それでは、健康優良かつ五体満足かつ赤の他人である私から、末期ガンで名前も知らない病床の君へ、心づくしのエールを送らせていただきます!」と叫んでフレーフレーとやりだしたとき、親族の一員である貴方の行動がどんなものになるか想像してみてください。それと同質のものを、美麗な映像と壮大な音楽で逃げられない劇場の椅子へ押さえこまれて聞かされる怒りと失望ったらないですよ。エヴァQへの批判に「けたたましい鎮魂があるものか」と書きましたが、本作の終盤はまさに「ひどく神経にさわる、けたたましい鎮魂」となっていて、もはや作家性という言葉では擁護できないほどの、現実のだれかに対する厚顔無恥な狼藉の域にまで達しています。
さらに最悪なのは、真面目で小心な監督が自ら選んだ結末へどんな非難が向けられるか不安になったのでしょう、来場者全員に同人誌を配布して等身大の己を見せることで、観客へのエクスキューズとしたことです。冊子のタイトルが「すずめの戸締まり読本」ではなく「新海誠読本」となっているのがミソで、これはシンエヴァが本邦の創作界隈に残してしまったバッド・イグザンプルの最たるものでしょう。作品に語らせるのではなく、作家個人に対する共感を観客に引き起こし、瑕疵のあるーーと本人が疑っているーーフィクションへの強い風当たりをあらかじめ弱めようとする無様な試みで、もっと言えばクリエイターの敗北なのです。どうも舞台挨拶で「本作がこうなったのは、皆さんにも責任がある」とか言ってるみたいで、真面目すぎる性格の人物が身の丈を大きく越えた題材を扱ってしまった結果、それに潰されないための精神的高揚と攻撃性を無理に作りだしているように見えます。人為的な躁状態は簡単に反転しますので、彼を焚きつけた周囲の大人たちはちゃんと精神状態をケアしてあげてくださいよ! マコト、大丈夫だから、震災孤児とその里親以外は、だれも本作を正面から受け止めて「世の悲惨をエンタメ化する手つきの、なんという醜悪さか」なんて言わないから(言ってる)! 問題作を世に問うてしまったことへの鬱状態から回復した監督の次回作は、間違いなくコロナ禍を題材としたものになるでしょうし、シンエヴァで庵野秀明から送られた目配せに頬を赤らめながらウインクを返す内容になるだろうと予言しておきます。おい、こんなのは二人で喫茶店とかでやれよ! おたくどうしの気持ち悪いやりとりを、全国の劇場を占拠してやってんじゃねえ(幻視)!
しかしながら、「ほしのこえ」のときにはこの世におらず、「君の名は」にドはまりしてノートに「お前は誰だ?」と大書きし、「天気の子」にはさして興味を示さず、いまはもうここにいない人へ想いをはせると、同じアニメ作家を20年以上追い続けることの普通でなさを客観的に自覚させられますねー。