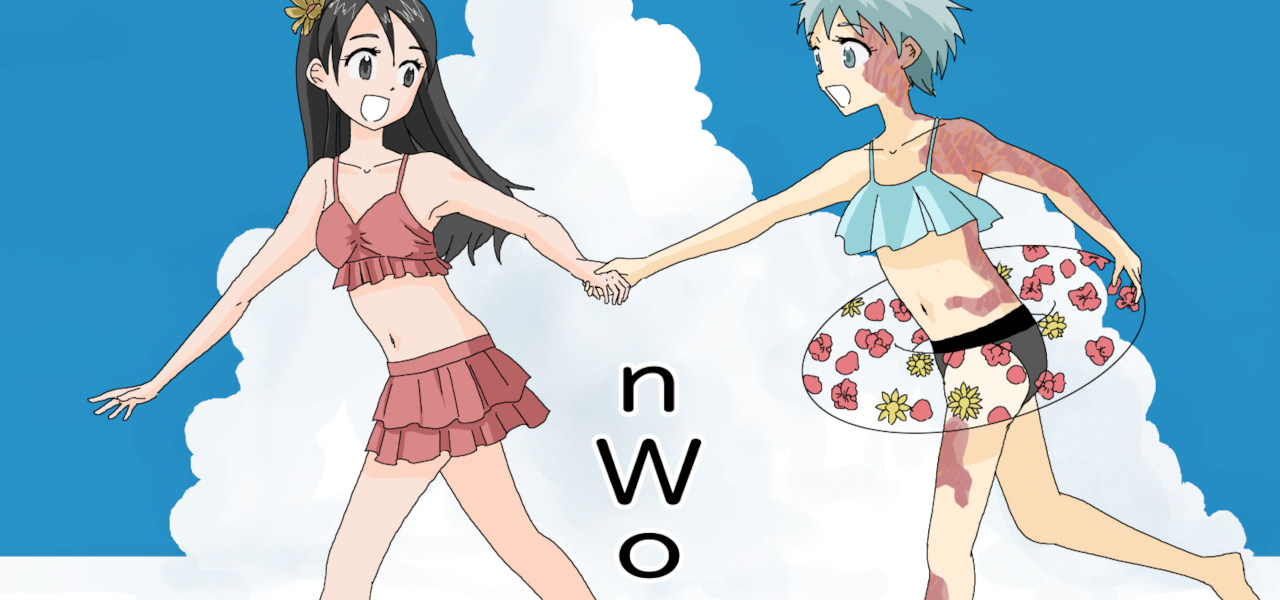ベルセルク42巻を読了。本作の熱心なフォロワーではなくなってひさしく、特に単行本の刊行に1年以上の間が空くようになったあとは、前巻までのストーリーを忘れたまま流し読みして終わりくらいの温度感でいました。新たな体制によるベルセルクへの雑感を述べますと、台詞が少なくなり、コマ割りが大きくなり、背景ではなく人物が中心の作画ーーほぼほぼマシリトの指摘どおりーーになったなあぐらいのもので、狂信的な方々がツバをとばしておっしゃる「まったくのベツモノ」やら「ほとんど同人誌レベル」やらの指摘には、まだ本作に対してそんな熱量が残っているファンが存在したことへ、純粋に驚く気持ちが先に来ました。すでに「絵画作品」と化していた原作のストーリーがこの速度感で畳まれていくのなら、まことに不謹慎な言い様ながら、むしろ作品にとってよかったのではないかとさえ感じております。つくづく思うのは、特に10年を越える連載期間を持つマンガは、作者にとっては次第に人生そのものと癒着して不可分になっていくのに対して、読者にとってはどんどん人生と乖離してどうでもいいものになっていくということです。
かつての長期連載マンガとは、「美味しんぼ」とか「ゴルゴ13」とか「浮浪雲」とか、”大人としての個”がすでに確立した者へ向けた、青年誌のものばかりだったように思います。「マンガやゲームなどは文化未満の、くだらないもの」と断じて一顧だにしなかった世代が現役をしりぞき、現世からも退場することで、人生のステージが変遷する際に、「マンガを帯同して持ちあがること」への抵抗感が社会全体で薄れ、徐々に「一定の年齢でかならず卒業すべきポンチ絵」から「一生涯にわたって楽しむことのできる文化」へと変質していったのでしょう。ことほどさように、社会の変化とは旧世代の死によってしか引き起こされないものなのです。個人的には、スケートボードやブレイクダンスがもてはやされる近年の風潮を、唾棄すべきものとして心の底から嫌悪していますが、私の世代の死によってそれらの文化は「社会が当たり前に受け入れるもの」として完成するにちがいありません。
それた話を元へ戻しますと、マンガが社会に受け入れられる過程で失われたのが「少年マンガ」というカテゴリであったのだと、あえて断言させていただきます。いまや10年を越える連載も珍しくはなく、20年になんなんとする作品が雑誌の看板をはっているーーこの状況に、私は「少年マンガ」なるものの消滅を見るのです(「クリエイターがクリエイターに向けて作品をつくるようになった」ことも影響していると考えていますが、長くなるので割愛)。偉大なるコロコロコミックが小学生のみをターゲットにしぼり、「児童マンガ」のカテゴリを堅守し続けているのに対して、「週間少年ジャンプ」はもはや大人相手の商売に変わってしまっている。私の定義する「少年マンガ」とは、「コロコロコミックを卒業した中学1年生が、受験や就職をむかえる高校3年生までに体験し終えるもの」であり、これを満たすためには連載期間は長くとも5年以内に収まらなくてはなりません。近年では「鬼滅の刃」がこの定義に該当し、中学1年生でキメツに出会った少年は、少年という属性を失う前に物語の終わりまでを体験できたがゆえに、彼の心の中でその後に通過するあらゆるマンガとは異なった、特別な場所を与えられることになるのです。
因果を逆にして言えば、我々の社会が「大人」を喪失して、ネオテニー的な未成熟を許容するものに変質していっているのは、20年を越える長期連載マンガがその元凶であると指摘できるでしょう。不惑を過ぎたオッサンが、毎週月曜日に「ゴム人間の展開、アツい!」とか言ってるんじゃあないぞ! むしろオマエの尻のほうに火がついて、人生が熱くなってるんじゃないのか? みんな、マンガ連載の長期化には、これまでのように消極的な黙認ではなく、ガンガン積極的な「ノー」を編集部へ突きつけていこう! 興味はあるけど、寿命とのレースが怖くて、「じゅぢちゅ廻戦」に手をつけることができない、舌の短い美少女オジサンとの約束だぞ!