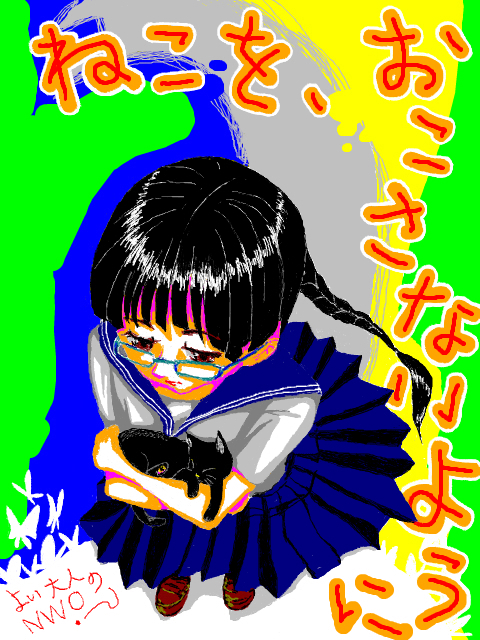ロマサガ2リメイクのベリーハードを最終皇帝で放りだし、ドラクエ3リメイクに鞍がえしてプレイ中。個人的なことから言うと、オリジナルのファミコン版は、人生ではじめて発売日前日の深夜行列にならんだ作品であり、シリーズの中でも特に思い入れが深い。冷静に考えれば、6千円ほどをにぎりしめた小中学生が、オモチャ屋の前に大挙してならんでいるのは、強盗やカツアゲの養殖漁場みたいなもので、その野放図さが昭和だと言われれば反論の余地はないが、令和の感覚に照らすと、なぜ親たちがあれを許可したのかわからないし、教師や警察や補導員もいったいなにをしていたのか不思議に思う。そして、朝日の差す社宅の居間で、興奮にふるえながらカセットをさしこんで電源を入れると、真ッ黒な画面に白抜きで「DRAGON QUEST III」とだけ表示されたときの気持ちを想像してみてほしい。当時、全国の母親たちがとまどいをもってゲームを「ピコピコ」と表現したように、ファミコンの隆盛は多くの良識ある大人にとって、理解不能の病原体に我が子の精神を狂わされてしまうような経験だったと推察する。さらに、個人が経営する町のゲームショップなどは、つど流行りものに便乗するだけの、まっとうな仕事につけない悪い大人がする商売という感覚も多分にあったため、「だまされて、パチモンをつかまされた?」という考えが、まずはじめに脳裏をよぎった。あとからふりかえれば、カセット容量をギリギリまで捻出するための「ロムの伝説」だったのだが、背後に流れるかすかなノイズを聞きながら、しばし茫然とした時間を過ごしたことは、いまでも忘れられない。そんなわけで、ファミコン版ドラクエ3は現実での経験や感情と強くひもづいた、魂の深い部分へ不可分に癒着する、良性だか悪性だか判然としない腫瘍みたいなものなのである。余談ながら、もっとも印象的なドラクエ音楽のひとつであるこの「ボー」というノイズが、どのCDにも収録されず、ドラクエコンサートで演奏されたためしがないというのは、どうにも信じられない。ただ観客席に「ボー」というノイズが流れ続けるのを、「4分33秒」ばりにシレッとやってほしいところだ。
さて、思い出ばなしはこのくらいにして、ファミコン版は数十周、スーパーファミコン版は数周、ゲームボーイカラー版は1周だけした程度のドラクエ3ファンの中央値から、今回のリメイクの気になる点(穏当な表現)を順にあげていこうと思う。まず、36年という長い歳月を経て、スーファミ版がドラクエ3の定本のようなあつかいを受けているのに、一抹の寂しさを禁じえない。本リメイクもご多分にもれず、システムの根幹部分はスーファミ版のガワを巻きなおしたものになっていて、より正確なタイトルは「SFC版ドラクエ3リメイク」であろう。正直に言えば、辛辣きわまる性格診断の導入があまり好きになれなかったし、もしかすると近年の若人の目にはどの結果も、異様なネガティブさで響いてしまうのではないかと危惧している。なので、勇者の性格はほぼ唯一、精霊ルビスがベタ褒めするところの「ごうけつ」一択であり、仲間には「きれもの」と「セクシーギャル」しかいなかった(ところで、セクシーギャルって性格なの? ホーリー遊児の性癖じゃないの?)。ロマサガ2リメイクと同じく、本作でも3段階の難易度が用意されているのだが、あちらはオリジナルの超難度をどうにか現代に再現するための、やむをえない措置だった。万人むけのバランス調整で鳴らすドラクエでこれをやるのは、高級料亭へ入ったはずなのに、卓上に塩・胡椒・醤油・ケチャップ・マヨネーズ・ニンニクのすりおろしなどが置かれており、ゴシック体でデカデカと「ご自由にご調味ください」と印字された黄色いテプラが、ベッタリ貼られているようなものだ。料理人がギリギリの、これ以上はない調整を行った最善と信じるものが客に出され、各自の口腔にて一期一会のケミストリーを起こす。それは接待の席かもしれないし、なにかの記念日かもしれないし、はたまたフラッとのれんをくぐっただけかもしれないが、至高の品々とそれぞれの人生が交錯するからこそ、一晩かぎりの唯一無二な体験が起きあがるのである。ゆるい軟便のようなイージーや、骨を抜いた魚のようなノーマルは言うにおよばず、ハードでさえファミコン版に比べるとプレイヤーに有利な要素が多すぎ、オリジナルのドラクエ3体験を再現しているとは言いがたい。レギュレーションが選手全員に対して同一であるからこそ、自由度の高さから工夫の余地が生まれ、その試行錯誤から達成感やドラマが生じるのであって、難易度をいつでも変更できる本作の仕様は、誤解を恐れず言うならば、パラリンピックと同じ競技性に堕しているのである。つまり、「車椅子ホニャララで生涯無敗って、ギアが高価すぎて競技人口が限られていて、そもそもまともな対戦相手がいないだけじゃないの?」みたいな疑問を投げかけられた選手のような気分にさせられるのだ(絶対に勝てるニッチ分野を探しだす嗅覚はすごい)。
つい興が乗って言い過ぎてしまったが、難易度変更以外の部分でも、「ダンジョンの奥深くで半壊するパーティ」「体感蘇生率30%以下のザオラル」「枯渇するMPと1回の使用で砕ける祈りの指輪」というヒリヒリ感はのぞむべくもなく、「魔法以外の多様で多彩な全体攻撃」「体感蘇生率80%以上の謎呪文ザオ」「レベルアップで全快するHPとMP」というぬるま湯のような仕様になっているのである。ファミコン版のドラクエ3は、「とぼしいリソースを管理して、なんとかやりくりする」ゲーム性だったのに、本作は「豊富なリソースを、好き放題に蕩尽する」方向へ、その本質を変じてしまっていると指摘できるだろう。次にゲーム全体のルックス(笑)ーーリメイクを重ねるごとに戦士の価値が減じていくが、その問題はまた別の機会にするーーへ触れていくと、精緻に描きこまれたグラフィックは、「光と影の明暗」「水のきらめき」「そよぐ風」「大気のゆらぎ」までもが豊かに表現されており、全体的な縮尺が上がったーー建物の壁が高すぎる問題はあるーーのもあって、壮大な冒険”感”を演出することに、成功しているとは言えるかもしれない。ただ、「HD-2Dリメイク」という珍奇な表現で先行的に言い訳が成されているのだろうが、3D空間なのにいっさいカメラを回すことができず、おまけに障害物の背後に移動しても透過しないため、慣れないうちは町中でしばしば自キャラを見失うハメになった。いきおい、ミニマップばかりに目がいくようになり、おまけに初めて訪れるロケーションにおいても、完全に踏破された状態の地図が表示される(なんで?)ものだから、探索の喜びとグラフィックの価値は大幅に毀損されてしまっている。
また、自キャラとモンスターは、だれのどういうジャッジか、解像度の高い背景から浮きまくりのドット絵で描写されており、「オリジナルの持つ暖かみを大切にした」みたいに喧伝しているのだが、これを喜ぶのは36年前に小中学生だったオッサンとオバハンだけだろう。あらゆる仕様において、親切を大きく越えたプレイヤーへの甘やかしを敢行し、令和の新規層へバチバチと目くばせを送りながら、肝心かなめの部分で安易な昭和レトロ(笑)に逃げているのである。例えるなら、ラップも容器も使わず素手でじかに握っていた当時のオニギリを「オフクロの味」と表現するみたいなもので、令和の衛生観念からすれば、とても口に入れられるようなシロモノではない。「ばあちゃんのオニギリはあったかくて、特別な味がした」ってそれ、ボットン便所で用を足してから八切りの新聞紙で尻をふいたあと、モンペを引きあげた手を洗わずに握ったため、手の常在菌と黒インクと大腸菌が米の表皮に付着しているだけですからね(ちなみに、うちのオニギリは化粧水の味がした)! バトルに関しても、モンスターのドット絵による動きを作りこんだ時点で力つきた感じで、制作中の画面でだれもが期待したような、プレイヤー側の攻撃や魔法がクォータービューでとびかうことはなく、コマンド入力時にキャラの背中だけを見せる「予告編詐欺」みたいな仕上がりになっている。正直なところ、ドラクエ11の素材とデータをそのまんま流用して、適宜2Dと3Dを切りかえられるあのシステムで作ったほうが、はるかに安あがりで工期も短くすんだのではないかと真剣に疑っている。
さらに細かい点をあげれば、ルーラが天井無視でMPゼロの単なる「どこでもファストトラベル」ーーダンジョンを含めたすべてのロケーションがリスト登録されるのも気にくわないーーと化したせいで、キメラのつばさとリレミトの役割が完全に死んでいたり、バシルーラの効果が「酒場へ強制送還」ではなく「その戦闘のみ離脱」になっていたり、ガイドマーカーと「おもいで」の機能が完全にカブッているのに閲覧頻度の高い「つよさ」を押しのけてウィンドウの上位階層に入っていたり、ゲーム性の核の部分を変更しておきながら何の調整もせず放置された残骸が散見され、「本当に日本人はゲームを作るのが下手になったなー」と、思わずため息がもれてしまった。追加要素も首をかしげるものが多く、テドンの新規ボスは3回以上攻撃しないとたおせない高体力なのに仲間を無限呼びーーアルファベットが一巡してAに戻ったときは、コントローラーを投げつけそうになったーーしたり、サマンオサ初回訪問時の印象的な葬式シーンになぜかボイスがついていなかったり、おそらくホーリー遊児がこれまで担っていた「ゲーム全体を見通す一貫的な視点」が欠けているように感じられるのだ(1メッセージ中に「時」と「とき」の表記が混在するのを見つけたときは、暗澹たる気持ちになった)。これだけブツブツと文句を重ねながら、3日ほどでネクロゴンドまで進行しているのだから、ここまでに指摘した部分以外(どこやねん!)は、もしかするとよくできているのかもしれないことは、最後に付記しておく。
昭和のやっかいなオタクによる、陰鬱なダウナー批評という印象を結部で弱めるため、当時、関西局所で流行っていたドラクエ3のフィールド音楽の替え歌を披露しようと思う。冒頭部分から、いっしょに歌ってほしい。さんはい、「ナワでーしばりー、ムチでーたたく、これがほんとのーマゾなのー、おねがいー、おねがいー、すてーえなーいでー……(ドラクエとは似ても似つかぬ転調)ってなこと言われてその気になって、女房にしたのが大まちがい! 炊事洗濯まるでダメ! 食べることだけ3人前! ひとこと文句を言ったなら! プイと出てゆき、はい、それまーでーよー……ぼーくーは泣いちっち、横むいて泣いちっち」。脳内で勝手に転調したあとの歌詞の正体がなんなのか、いまだにサッパリわかっておらぬのだが、記憶の澱として記述して終わ……なに、シルエトだと? バカモノ! 女戦士の乳当てなどより、こっちのほうがよっぽど大問題だわ! 変更することで、逆に「ホログラム幽霊」以上の意図があったように思われるだろうが! いっそ、バーン・ゼム・オールとかに改名してやろうか(ゼムの指すものを答えよ)!