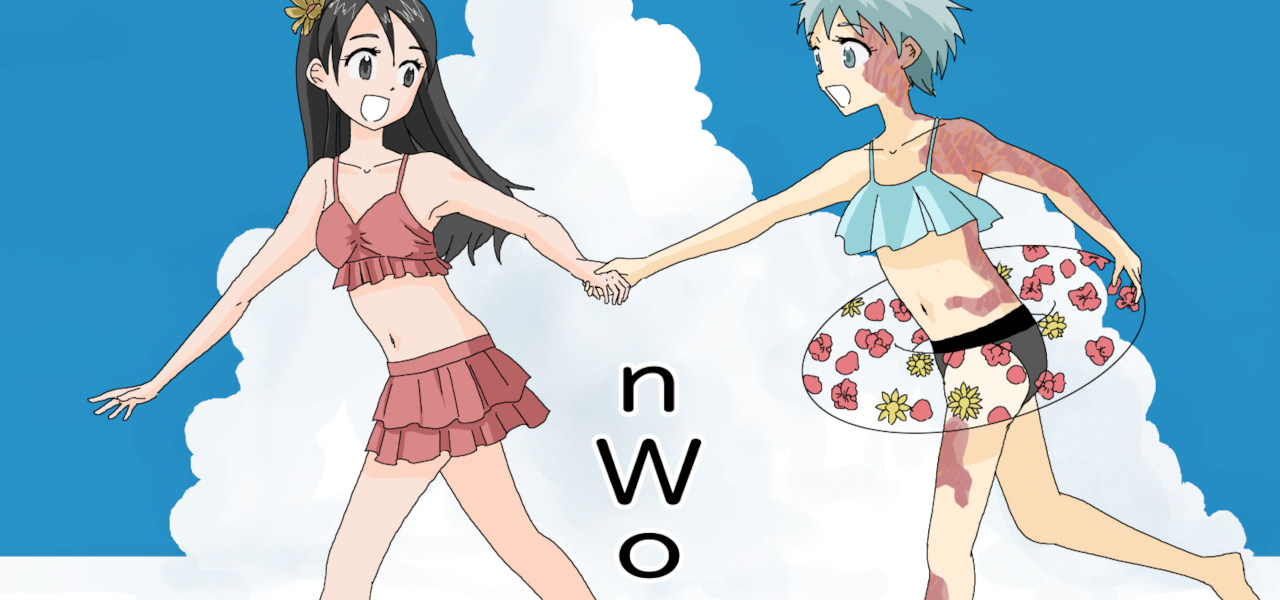崩壊スターレイルの最新バージョン3.4を読了。メインストーリー部分は、もはやゲームとして遊ばせる努力を放棄しているが、ナタ編後半で投入されるシナリオがことごとく失速ぎみの原神に比べると、たいへん高い熱量がこめられていて、大いに作品世界へと引きこまれた。先に予測していたように、オンパロスは無限の演算能力を持つ装置による”シミュレーテッド・リアリティ”であることがついにあきらかとなり、これまでに体験してきた「世界の崩壊へとむかうギリシャ悲劇」は、登場人物を同じうして3355万335回くり返されてきたことが示される。「膨大なテキストと細密な演出でつむがれてきた人々の想いは、それでもなお、プログラムされたフィクションにすぎず、現実との連絡は絶無で少しの影響もあたえられない」という絶望は、おそらくホヨバという会社が市場での規模を拡大させる過程にいだき続けてきたもので、神の被造物である人間を似姿とした人形が、ハードロックをBGMに神へ一矢むくいるという手描きのアニメーションは、「若く青くさい、熱情の切実さ」ゆえに強く胸をうった。この「虚構から現実への反逆行為」の実行者であり、のちにオンパロス世界の観測主体だとわかるファイノンというキャラクターは、壮麗かつ破天荒な綺羅星の如き他の英雄たちとは異なり、勤勉かつ実直な良識人として描かれてきた。失敗にいっさいの言い訳をせず、おのれの弱さを認めた上で、日々の鍛錬でそれを克服しようとする姿勢は好ましいものの、いささか生真面目すぎて人間的な魅力にはとぼしいと言わざるをえない。「親は婿として欲しがるが、娘は恋人に選ばない」タイプの、やや面白みに欠ける人物なのである(崩スタ未プレイ勢には、ジークアクスのエグザベ君を想起してもらうとわかりやすいと思う)。のっぺりとしたその特徴のなさは、じつのところ、驚愕の謎解きへと転化するための、「ミステリー小説における、真犯人からの視線そらし」であったことが判明し、アベンチュリンを前例に経験していたにもかかわらず、まんまと同じ手口にひっかかってしまったわけである。
さらに、3355万335回のニーチェ的”永劫回帰”を追体験するパートは、古いオタクのたとえながら「エンドレスエイト」を想起させ、薄暗いシアターでプレイしていたことと相まって、ほとんど気がくるうかと思った。「観測者にとって”正しい”世界を求めて、無限個の試行をくり返す」物語ギミックは、太古のエロゲーであるデザイアがその原型を考案し、まどマギなるコピーキャットによって爆発的に人口へと膾炙させられたものだ。同様の物語類型として、直近ではジークアクスが記憶に新しいが、本作においては明確に次回のコラボ先でもあるFateの本歌どりを意図したのだろう。ここでまた、ジークアクス方向へ脱線しておくと、総集編による劇場版やブルーレイ販売の予告が、不自然なまでに避けられている現状について、いまにしかできない予想を述べておく。各話タイトルに話数の表記がないことから考えて、ズバリ、テレビ放送した12話へ新作の12話プラスアルファを挿入した「全26話の完全版」制作が、水面化で進行しているのではないだろうか。スタジオの体力面と金銭面での不安は、今回のメガヒットによって払拭され、パッと思いつくままにならべると「省略されたクランバトル回」「コモリ少尉とエグザベ君の交流”回”」「主人公とコモリ少尉の親睦”回”」「主人公失踪後の母親・同級生・運び屋回」「主人公とヒゲマンの特訓回」「アルテイシアと本ルート生存者の暗躍回」「最終話のエッセンスを3話に拡張(シュウジのループ回含む)」「登場キャラそれぞれの後日談」ぐらいのエピソードを、完全版において物語の大きすぎる余白へ埋めていくはずだと放言しておこう。
ここからさらにアポカリプスホテル方向へと脱線し、本テキストは崩壊スターレイルという本筋から離れて、複線ドリフトしたまま終わると思われる。同作を最終話まで見たのだが、ゲストキャラにとどまると考えていたタヌキ一族が物語の中心にすえられて、主人公の属性である”永遠と停滞”の対比として「時間経過による成長と変化」を担当することになったのは、意想外の展開だった。6話までの感想にも書いた「昭和の風俗紹介」という印象は当たっていて、未確認飛行物体を召喚する呪文からはじまり、セーラー服反逆同盟(!)を思わせるスケバンのいでたちーーパーマネント、紫のチークとアイシャドウ、足首までのロングスカート、風船ガムという徹底ぶりーーまで、あると信じていたメインストーリーそっちのけで、徹底的に脇道のスラップスティックをつらぬく”ひらきなおりっぷり”には、もはやある種のすがすがしささえ感じたぐらいである。やがて、その「ドタバタ無法」は、結婚式と葬式を同時に挙行したあげく、祖母の遺体を手品の余興でもてあそぶという、往年の筒井康隆を彷彿とさせるブラックユーモアの絶頂へと達するのだった。ロボットたちの創造主である地球人が帰還する最終話にも、期待していたような”コッペリア的悲劇”はみじんも混入せず、最後の最後まで人をくった展開のまま、物語は幕を閉じてしまう。全体として、昭和末期から平成初期に国営放送で全52話が放送されていたアニメのサブシナリオだけを集めたような構成になっていて、これはもう国営放送で全52話のアポカリプスホテルを制作するしかない(政治家の名を冠した、例の構文)。終わる。