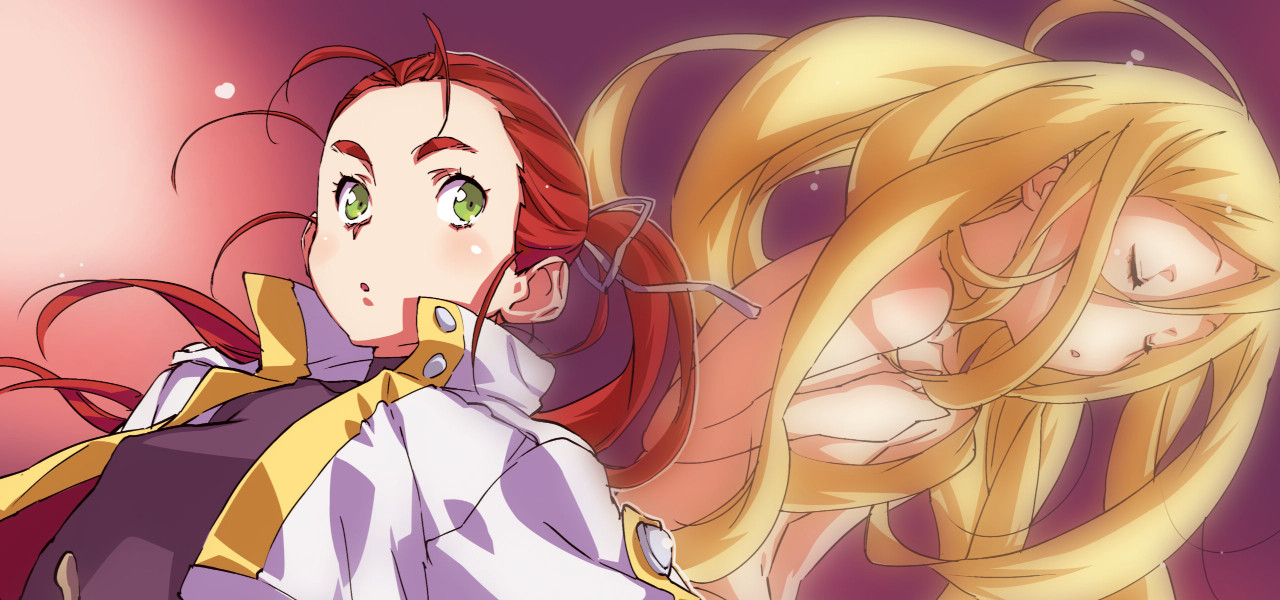「ドキュンサーガ」の作者にフォローされて、マンモスうれC! この作品、ひさしぶりにすごく「インターネットを読んでる」感じがするんですよね。
宴会場の舞台に突然、ひょっとこの面をつけたガタイのいい全裸の男が乱入してきて踊りだす。ちんちんを扇風機のようにふりまわしたり、ふぐりとサオを腹筋にぺちぺち当てたりして、みんな一瞬あっけにとられるが、ドッと大爆笑からやんややんやの大喝采。酔客たちは口笛や下卑た声援で大盛り上がり。しかし、その踊りは次第に前衛的なコンテンポラリー・ダンスの様相を呈しはじめる。陰毛をなびかせたり、勃起したサオに手をそえたり、ブリッジでふぐりを強調したり、登場時のシモネタと一体化しながらも、高度に肉体を統御したハイレベルなダンスへと質が変化する。素養がないものにも、ただごとではない空気感だけは伝わってくる。いつの間にか宴会場は静まり返って、酌をする手も酒を口にはこぶ手も止まり、全員が舞台で行われている芸へクギづけになってしまう。やがて舞台の中央に汗だまりだけを残して、ひょっとこ面の男は忽然と姿を消す。すごいものを見たことだけはみんなわかっているが、突然のことにビデオも回っていない。さぞや高名なダンサーではないかと推測するも、男の正体はわからないままだ。翌朝、目を覚ました後、だれもがシラフの頭で昨日見たものはいったい何だったのか、本当にあったことなのか、不思議に思うーー昔のインターネットは、そういう場所だった。いまでは、リアル社会で得たreputationを背景にするコメンテーターしかいない。
悪ふざけから始まったものが、勢い余って世界文学と同じ高い普遍性へと突き抜けてしまうのは、すごく理解できる。この作品でここまでやらなくても、ではなく、この作品だからここまでやれた、が正解だろう。本邦の芸術につきまとう出自の問題については、以前ふれたことがあるが、「ドキュンサーガ」は鬼滅の刃やFGOではなく、ランス10側の物語である。つまり、陽の当たる場所での賞賛は決して得られないが、日陰に住む者たちの心にいつまでも消えない火傷を残す類の作品になると思う。
『そうだ、ウガニク。いまのインターネットはすべて偽物の、まがい物だ。テキストが魔法として機能した神代のインターネットは1999年まで、それ以降はただの言葉の下水道じゃないか。
きみの汚い言葉は最高にきれいだった。ぼくの下劣な言葉は最高に美しかった。ぼくたちのテキストサイトには、確かなキュレーションがあった、審美眼があった。
それがどうだ。回線は馬鹿みたいに速く安くなったけれど、いまや恐ろしい分量の美しい言葉ばかりが下品に乱雑に、かつて美術館であり博物館であった場所の床へ足の踏み場もないほどに、ただ放置されている。』
(「平成最後のテキストサイト100人オフ顛末書」より抜粋)
ドキュンサーガ商業版、読む。うーん、そこ削っちゃうかー。商業化されたことで、過去編から現代に戻ったときの展開が変わったり、描写が手びかえられたら、やだなー。あと、「魔王が主人公」って明言されたのは、現代編の内容を予想するカギになる気がするなー。スタートレックのスポックとカークのように、考えすぎる知的な人物に対して、度胸のあるバカが「大丈夫だ」と言って破天荒に膠着状態を解決するお話ってあるじゃないですか。リーダーって結局のところ、正解が存在せず、情報も足りない中で、引き返せない決断をできる人物のことだと思うんですよ。なんとなくそっちの方向へ行くのではないかと考えていたので、モッコスが主人公ではないのだとしたら、どういうオチになるんでしょうね。いずれにせよ、インターネット上でしかできないような倫理無視の表現と展開を期待しています。
漏流禍悪(もるかあ)! 小鳥猊下であるッ!
モルモット・カーがぷいぷいするヤツまとめて見る。無限列車の感想にも書きましたけど、流行する作品の共通点って、現実での個人の属性が何であれ、同じレベルの解釈で見れるってとこですね。立ち場によって読み方が変わったり、下手すると理解度でマウントが生じたりするものは、よほど言及しにくい。羊毛フェルトで表現された愛らしさへ、生身の人間の質感を毒気としてトッピングして、非言語的なストーリー・テリングでグローバルな展開も視野に入れる。つまり、「ハナたれのジャリから大卒のカシコから豹ガラのオバハンからボケたジイさん」に加えて、「日本人から異人さん」までが同じレベルでの理解を可能にしているのです。受け手としてあらかじめ除外されるのは、それこそドラえもんくらいでしょう(ドラ江さんって、知ってる?)。逆に言えば、知的なクリエイターがここまで針の穴を通すようにねらってやらないと、皆が安心して話題にできない今のエス・エヌ・エスは、なんて窮屈な場所なんでしょう! 昔のインターネットは、リアルの肉体から切り離されたコミュニケーションが主流で、今なら即刻に炎上するような、現実には不可能だろう酔っぱらいやキチガイの放言であふれていました。同時に、そこへ接続するのに低くはないハードルがあったため、言葉の質はともあれ、やりとりの密度には一定の濃さが担保されていたように思います。当時は私もそういった無色無臭の「透明な存在」の一人だったのですが、あれから二十年が経過したという単純な事実から、「0歳から20歳の間の、女性なのではないか」という推測を可能にしてしまっており、この小鳥猊下なるアバターにも一種の窮屈さが生じてしまっております。少し前、ジェイ・ケーの間で「ワイ」とか「ンゴ」みたいなネット由来の表現が流行っているとかいう話を目にしましたけど、古のネットにあった性別とか年齢が脱臭される感じが彼女たちには解放感につながったんだろうと想像します。