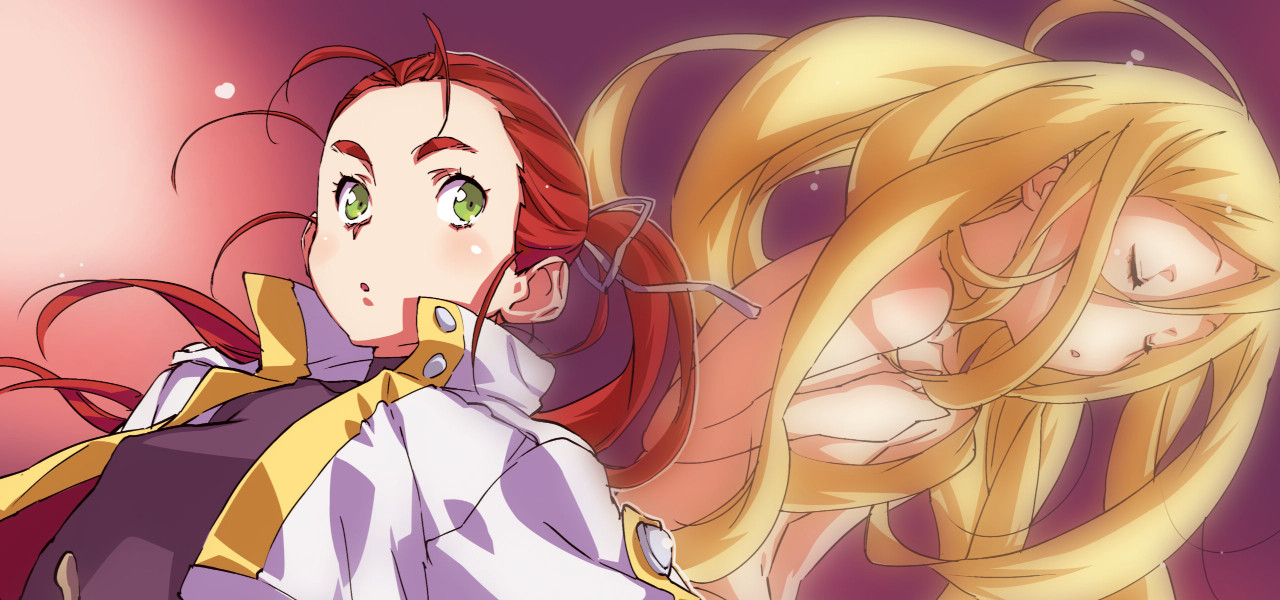この年末年始に、泥酔の底で思い出した映像を書き留めておく。昔、町の老人たちは戦争経験者ばかりだった。エヴァのカントクも言ってたけど、人を殺したことがある老人がすぐそばで生活していた。まだ幼かった頃、手の甲を怪我したのをほうっておいたら膿んでしまい、元軍医というふれこみの町医者のところへ連れて行かれたことがあった。浅黒い痩せぎすの老人で、背骨が鉄でできているかのような身のこなしだった。おそるおそる差し出した患部を一瞥すると、私の手首をぐっとつかんだ。静脈の浮いた細い手なのに、万力ような力だった。メスを使って患部を周りの皮膚ごと正方形に薄く切って、ベロリと剥がし取る。もちろん、麻酔なんてない。消毒、軟膏、ガーゼ、包帯と淀みない一連の流れで処理していく。母の膝に抱かれた私は涙を流していたと思うが、痛みはほとんど感じなかった。治療を終えた医者はカルテになにごとかを書きこみ始め、背中で退室をうながした。部屋に入ってから、彼は一言も発さなかったように思う。その峻厳な様子は、いまでもかすかに記憶に残っている。あの老人は、もしかして最前線の野戦病院にいたのではないかと夢想する。次々と運ばれて来る兵士たちの負傷に、感情を廃した最速で最善の処置を繰り返し続ける。私が受けた治療には、個の命に敬意を向けると同時に無価値とみなす、そんな凄みがあった。昔、老人たちに抱く感情は尊敬ではなく、畏怖だった。あの軍医も、多くの人々の死と怨嗟を眺めながら、すべてを呑み込んで、一言も発さずに消えていった。世代の断絶が叫ばれて久しいが、我が身の百年を物差しとした年齢階層の最上部には、あの世代が凝と黙したまま座している。かつて、老人たちはいるだけで怖い存在だった。いまの老人たちも、私たちが迎える老年も、決してそんなふうにはなれないだろう。
猫を起こさないように