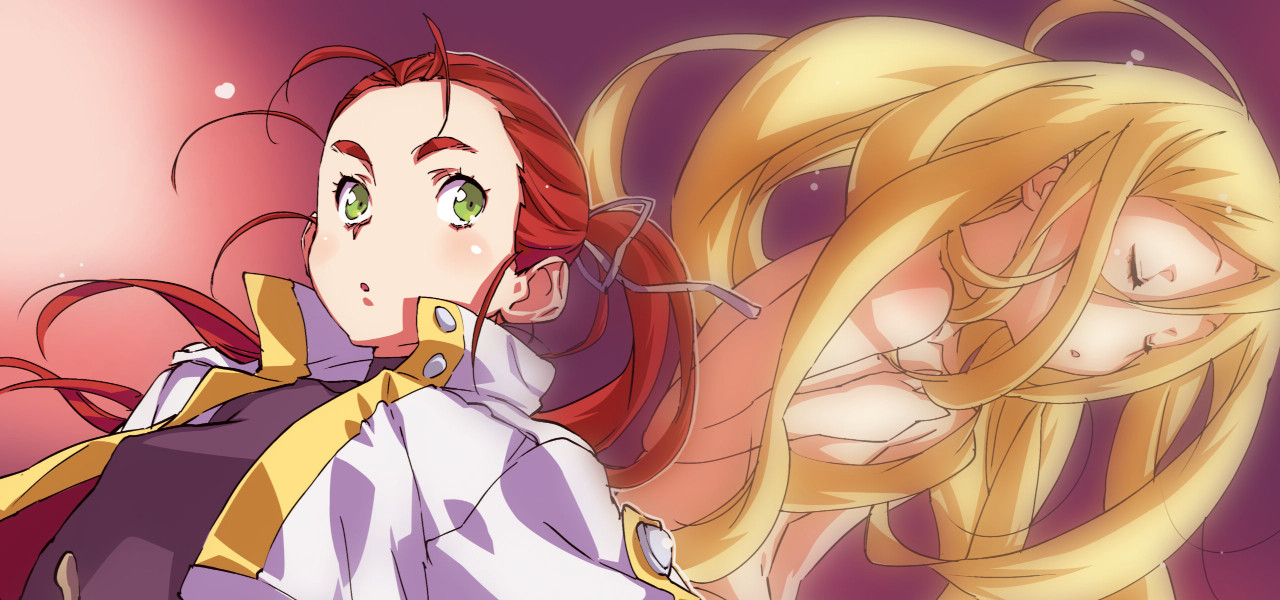原神4章を最終幕までクリア。言わば、「原爆投下1日前のヒロシマ」を旅人とパイモンがそぞろ歩くシーンでの、モブによる「明日おなじものを食べられないとしても、今日はおなじものを食べる。それが生活ってものでしょ?」というセリフに、またしても号泣させられてしまいました。いつも感心してしまうのは、大所高所から語られるストーリーに対置された、こういった市井の一市民による素朴な感情を細やかに描いている点であり、「今日の食事」という極小の視点から百年を優に越える極大の時間ギミックへとカメラを引き上げる際の落差は、前者の連続で後者が成り立っていることにハッとした気づきを与えてくれます。そして、真の神が人間を愛するようになるまでの数百年を、一介の個人が偽りの神としてウソと演技による「時間かせぎ」をする苦悩は、いかばかりだったでしょう。いつ終わるかさえ知らされていないその苦しみを、異邦人へとすべてうちあけて楽になるチャンスを目の前にしながら、「利己的になってはダメだ、もう少しだけ考えよう……」とすんでのところでふみとどまる場面には、我が身に照らしての嗚咽がほとばしりでました。
このフリーナというキャラクターのことは、登場した最初の瞬間から「軽薄で底の割れた演技者」として、どこか好きになれない気持ちがありました。「原神にしては、魅力に欠ける造形を持ってきたものだな」などと冷めた視点でずっとながめていたのに、その感覚の正体が同族嫌悪や自己嫌悪と同じ種類のものだったと判明したときの衝撃たるや! 私自身が「身の丈よりも大きなもの」を日々、演じることを強いられており、「すべて投げだして、終わりにしたい」という欲求と毎秒をせめぎあって生きているのですから! メインストーリーが幕を閉じ、彼女の後日譚ーー「僕はもう、二度とだれかを演じるつもりはない」ーーが終わる頃には、フリーナのことを心から愛おしいと思うようになっていました。個人を翻弄する大きな物語の渦中に落としこまれた小さなキャラクターたちが、それでもどうにか生きようとあがく様は、なんと彼らを魅力的に見せることでしょうか。いつの時点からか、キャラクターが物語のサイズを凌駕してしまうようになった本邦のフィクション群の失ってしまったものを、原神はいまだに脈々と受け継いでいるのです。
どこか洗練されていない部分や、強引な展開、つたない手つきがまったくないとは申しません。けれど、いまを生きるだれかの熱を帯びたドラマツルギーが、すべてを「是」「好」へと変じていくのです。原神4章の最終幕を通じて、中華の若い世代が語る「旧エヴァ劇場版の先の先」を確かに見届けさせてもらった気分になりました。あなたたちは、「旧劇の最終局面で碇シンジが取るべきだった行動」と「新劇による再話で選ばれるべきだった結末」を、このように考えたのですね。先日、地球外少年少女の感想を再掲したところ、監督本人にRTされてビックリしましたが、彼の元へも土地と世代を超えたアンサーが届くことを願っています。いつものごとく、「アカの手先」となってベタ褒めしてしまいましたが、まあ、ロシア相当の組織の構成員たちが急に好意的な様子で描写されはじめたり、不安を感じる部分もなくはないんですよ。
オマージュをわずかに越えたド直球の引用もチラホラ見えてきて、「第三降臨者」なるワードもすごく旧エヴァっぽいなーと感じます。今回、公子の師匠としてスカークなる人物が登場したのですが、FGOのスカサハと設定や見た目ばかりか声優まで同じ(!)になってて、「ああ、メッチャ好きなんやろうな……」と、思わず生あたたかい視線を送ってしまいました(「呑星の鯨」から剥離した物質のフレイバーテキスト、メッチャ好きです)。ともあれ、原神4章の最終幕を通じて、本邦のフィクションを弱くしているのは、家族を解体する「毒親」や 「親ガチャ」なる概念と、大きな物語を一個のキャラクターに矮小化する「VTuber」なる存在であることを確信いたしました(ぐるぐる目で)。みんな、そんなつまらないマガイモノは窓から投げ捨てて、中華ファンタジーから「物語の王道」を逆輸入していこうぜ!
最後にぜんぜん話は変わりますけど、遅ればせながら劇光仮面の4巻を読んだんですよ。えー、「本物が現れ」ちゃダメじゃん! そんなのいつも通りじゃん! 本物がいない世界だからこそ、例えば「ゆきゆきて神軍」のような文学性や批評性を帯びていたのに! 本作へ向けていた興味関心の熱が、一気に冷めてしまったことは、残念ながら認めざるをえません。本物がいない日常だからこそ、我々はなんとかしてその虚無をやりすごそうと、もがき苦しむというのに……。