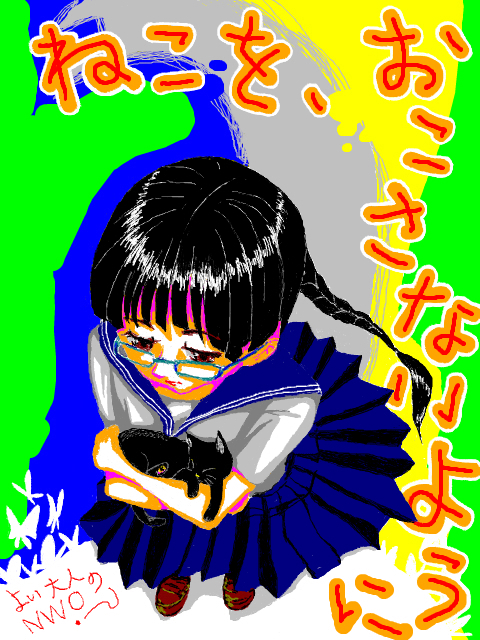ロッテントマトの見たこともないような低評価と、初日視聴組の自分語りと大喜利合戦がタイムラインに垂れ流れるのを横目に、ジョーカー2をIMAXで見てきました。どんなグズグズの映画未満がお出しされるのか、かなり警戒して身がまえていたのですが、実際のところは「脚本よし」「演技よし」「撮影よし」で、一定以上の水準を満たしたクオリティに仕上がっており、ひどく拍子抜けしました。ふりかえれば前作は、ホアキン・フェニックスの超絶的な一人芝居が、DCコミックスの大看板であるジョーカーを完全に凌駕し呑みこんでおり、その後の彼の俳優人生に避けがたい影響を与えてしまうことになった、映画史へ燦然と刻まれる傑作中の傑作でしたが、続編である本作は、その「ホアキン・ジョーカーの解体」をかなり明確に意識して作られていて、「前作ジョーカーのファン」「原作ジョーカーのファン」「バットマン・シリーズのファン」にとって、極めて不愉快な内容だったであろうことは、想像に難くありません。わたしの観客としての立ち位置は「ホアキン・フェニックスのファン」なので、次になにがとびだすかわからない彼の演技に集中して見たため、緊張感は2時間20分を途切れることなく続きました(じつは一瞬だけ途切れたのですが、後述します)。
冒頭のあの「異形の背中」を見たとたん、ネット情報からの懐疑的な気分はふきとび、「ボーはおそれている」の主人公と同一人物とはとうてい信じられない、マシニストばりの身体のしぼり方に、一気に作品世界へと引きこまれます。小鳥猊下の自認は「失敗した演技者」であるため、母のかけた無意識の呪縛によって、おのれの特性と致命的に反するコメディアンの道を選んだアーサーの挫折と苦しみは、ある種の「自分ごと」として、切実さをもって胸に迫るのでした。映画館の観客席と裁判所の傍聴席で「巨悪の出現」への期待が強くシンクロする中で披露された、アーサーによるジョーカーの演技は、「小人の元同僚が持つ、一般市民の善性」を前にすると、いたたまれなさに目をおおいたくなるような大根役者のそれになっていて、ホアキン・ジョーカーの魅力を徹底的に排除し無化するための「演技の二重性」は、すさまじいレベルにまで達しています。レディ・ガガの起用について言えば、「解毒か解呪のため、観客に飲みこませなければならない、苦い苦い黒色の丸薬」を包む糖衣としてのミュージカル要素を導入するにあたり、ある意味での必然だったと納得はしています。前作の提示するメッセージに激しく共鳴してしまった、学の無い「ストレート・ホワイト・アンド・プア」へと監督の用意した解毒剤を届かせるために、大衆歌謡の人気シンガーの登用は”うってつけ”だったと言えるかもしれません。ただ、彼女に役者としてホアキン・フェニックスへ互する力量があるかと問われれば、はなはだ疑問を呈さざるをえず、引退したケイト・ブランシェットあたりとミュージカル抜きでする、凄絶なメソッド演技対決を見たかったというのが、正直なところです。
また、ゴッサム・シティとか、ハービー・デントとか、ハーレイ・クインとか、バットマンに由来する設定がもはや雑味にしかなっていないのも悩ましく、その極めつけはジョーカーのシンパによる裁判所の爆破事件でしょう。伏線ゼロからの唐突な爆発の瞬間、「ボーはおそれている」で屋根裏の”おCHINPOモンスター”を見たときと同じくらい、虚構への深い没入から強制的にキックアウトされましたもの! この展開は、「前作の象徴となった長く急峻な階段で、恋人から別れを告げさせたい」という監督のワガママーー必然性が絶無なのでーーをかなえるためでしょうが、この場面を含めたラスト20分の展開は、ちょっとフィクション然としすぎています(アーサーの「歌うのをやめろ」というセリフは、あまりにメタっぽくて微苦笑してしまいました)。ラストシーンにおいて、「ジョーカーの死を、執拗な長回しで観客に確認させる」のも、前作の解体という監督の意志が全面に出すぎており、個人的には「トゥレット症を想起させる例の哄笑が、絞首刑の瞬間に途絶える(ダンサー・イン・ザ・ダーク!)」ぐらいで収めてくれれば最高だったのにと思います。ここまでの感想を最新のネットバズ・ミームでまとめますと、「アーサー48歳、DCコミックス設定なし、ミュージカル要素なし、ケイト・ブランシェットあり……」だったなら、わたしの好みにド・ストライクの映画になったでしょうが、前作ジョーカーのファンa.k.a.低学歴の白人貧困層へは届かなかったにちがいありません。本作への驚くべき低評価は、監督の思いどおりに罹患した人々へと解毒剤がゆきわたった結果であり、いまごろ役者ともども失望する観客たちを見て、ほくそ笑んでいるのではないでしょうか。
最後に、本作でも提起されている、良家の子女がDV男や犯罪者へ、なぜか好意を寄せてしまうことがある文明のバグにふれて終わります。最近、ユヴァル・ノア・ハラリの「サピエンス全史」を読んでいるのですが、「文明の発展はあまりに速く進んだため、遺伝子の変化を置き去りにした。ゆえに我々は、農耕時代の習慣に生きながら、狩猟時代の脳と身体のまま、都市生活を営んでいる」との指摘は、身の回りの様々な事象に説明がつき、いろいろと腑に落ちる感じがありました。すなわち、「逸脱と暴力による資源の獲得」は、生存と繁殖に大きく寄与する要素であり、古い遺伝子の乗り物たる私たち人類が、そこに言語化不能の誘引力を見いだしているのでしょう。くれぐれも若いメスのみなさんは、「狩猟時代なら食いっぱぐれがないだろう、粗暴なアルファ・オス」にどうしようもなく引かれる遺伝子の陥穽へと自覚的になり、現代社会での生存に特化ーー繁殖は知らないーーした理系のオメガ・オタクを伴侶に選ぶよう心がけましょう! それでは、みなさん、ごいっしょに「解呪の真言」をご唱和ねがいます! ふぉりやー、どゎー!(おわり)