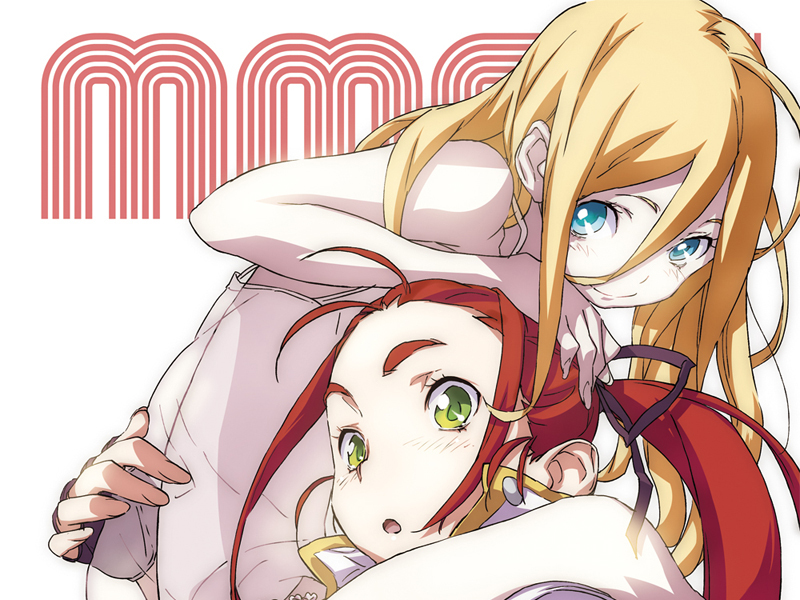ネトフリでローワン・アトキンソンのヒトvsハチ、見る。キリスト、ビートルズに続き、その誕生以来、年齢・性別・人種・国籍・言語を超えて、ネット動画の誇大タイトルどころではない、文字通り「全人類を楽しませた」のがMr.ビーンであり、本作は言わば、そのスーパースターのカムバック公演なのだ。「ビルドアップがダルいな」とか、「話のオチが小賢しい気がする」とか、「10分9本じゃなくて90分1本でいいんじゃねえの」とか感想未満の印象を述べるのは、それこそ「キリストが異性愛者なので傷つきました」ぐらいの難クセであり、まさに抱腹絶倒、ひさしぶりに涙が出るほど笑わせてもらった。オックスフォード出身の英才が演じる、このビーン型のキャラクターは、現代においてたぶん正式な診断名(アスペルガー?)がつく特性の持ち主で、いったんひとつのこだわりが生じると、他のすべてが見えなくなってしまう。グッタリした犬を床に放り投げて「ゴトッ」と音がする場面などに狂笑しながら、やがて自分の内側にも同じ性質が潜んでいることに気づかされるのである。
休日の朝、ディアブロ・イモータルのプレイに本腰を入れて取りかかるも、2時間もしないうちに、もうゲーム内ですることがない。デイリーでクエストを規定数こなし、ウィークリーで1、2回レジェンダリー宝石のガチャを引く。パラゴンレベルは毎日2ほど上がるから、進捗の感触がないわけではないし、はるか遠方にうっすら目的地も見えている。けれど、それは日本列島を徒歩にて縦断するような道程であり、しかも重課金者は初日にプライベートジェットでゴールを済ませているのだ。エンドゲームの全容が俯瞰できてしまったあと、ディアブロ・イモータルのために予定をすべて空けた休日が残された。そこで、「そういえば、艦これのイベント海域を3の3で放置してたな……」と思い出してしまったのが運の尽き。ゲージを破壊できず、友軍の到着を待っていたくせに、「支援艦隊と基地航空がキチンと仕事をして」「通称・ながもんタッチが敵旗艦に当たって」「夜戦までに4隻以上が中大破を逃れ」「魚雷すべてが敵旗艦にクリティカルする」という奇跡を、なぜ一瞬でも信じることができたのか。頭ではわかっているのに、いったん着手するともう身をもぎ離すことができない。
連合艦隊の全隻が幾度も中大破で帰港し、数週間をかけて再備蓄したバケツと資源がおそろしい勢いで虚空に消滅していく。攻略情報を検索して見かけるクリア報告に、得体のしれぬ焦燥が高まっていく。これはおそらく、独身女性が友人から結婚や出産のハガキを受け取るときと同じ感情だ。「たかがゲームなのに、みんなふつうにこなしているのに、なんで私はちゃんとできないんだろう!」という己への失望と、世界への絶望。イベント海域のプレイ中には、私の人格の中で最も低劣な部分が表層へと浮かびあがる。激情、狂乱、絶叫のうちに、バック・グラウンド・ビジュアルとしてパリピ孔明を見終え、ヒトvsハチの配信に気づいて、乱暴に再生をはじめる。はたして、そこには、私がいた。
自然とマウスから手が離れ、私が私の痴態を笑っているうちに、全身を包んでいた怖いような執着は、いつの間にか消えていた。艦これを走らせていたブラウザを終了しながら、私はこうつぶやく。ありがとう、ローワン・アトキンソン。狭量な時代がこの作品に何を言おうと、あなたは私にとって、永遠のジーザス・クライスト・スーパースターだ。