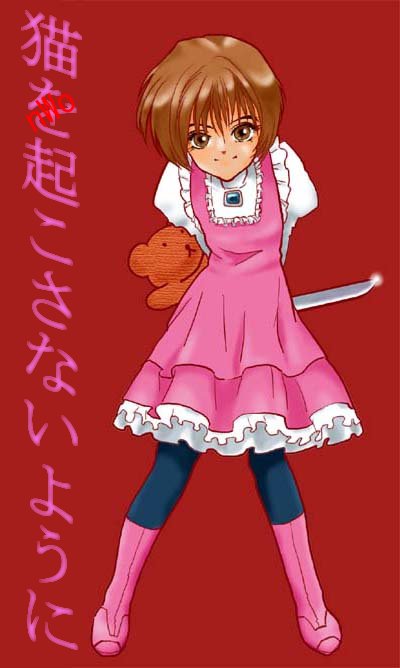オブリビオンのリマスター版、まさかの「制作発表、当日販売」という気のくるった手法に完全に”幻惑”されて、スターフィールドをPCの新調にまでおよんで発売日に購入したことへの強い反省から、「もうベセスダゲーには、数ヶ月かけてmod界隈が成熟するか否かを見きわめてからしか、手を出すまい」とかたく誓っていたのに、即座にダウンロードしてプレイを開始してしまった。今回のリマスターは、ディアブロ2リザレクテッドと同じ仕組みになっており、オリジナルのプログラムに新たな描画エンジンをかぶせただけで、令和のルックスをまといながらも、往年のプレイフィールはもちろん、裏技やバグや進行不能やパンパカCTDするところまで、そっくりそのまま移植されている。「どうせ新規層なんぞ、プレイすめえよ」とばかりに、バカラグラスで片あぐらにドブロクをあおるみたいな、居なおり強盗めいた仕様になっているのである。20年ほど前に発売された本作は、まさにすべてのオープンワールドRPGの始祖となる存在で、他分野で言えばビートルズやリドリー・スコットのような、後続たちが知らず影響下にある、車輪や雨傘の形状にだれも意識を向けないのと同じ、もはや世界と同化した「原初の原形」を無から生みだすことに成功した、真性にオリジナルなクリエイティブなのだ。
modまみれのスカイリムに十年以上を汚染された人種にとっては、「クエストとロケーションに密度感の薄い、簡素なタムリエル」とうつるのかもしれないが、そもそもオブリビオンは、スカイリムとは根本的に設計思想の異なった別モノと考えたほうがいい。スカイリムが前作への反省から、「より直感的に理解しやすい遊びやすさ」を志向して、従来型のRPGにシステムを寄せていったのに対して、オブリビオンはまさに「先行者のいない地平で、ゼロからの世界構築」を行ったのだから。その試行錯誤はシステム面により大きく現れていて、ファイナルファンタジーで例えるなら、3というよりは2のような作りになっているのである。すなわち、「ゲーム内におけるプレイヤーのすべての行動が数値として蓄積してゆき、ステータスの上昇は行動の種類に依存する」という、RPGの名の本来である”ロールプレイ”をどうゲーム体験に落としこむかへの、深い思考が存在する。具体的には、スキルレベル10回の上昇と全体レベル1がイコールになっていて、10回の内訳がどのスキルだったかを参照して、全体レベルアップ時にいずれのステータスがあがるかが決まる。この仕組みによって、「天井の低い洞窟でジャンプし続ける」とか「隠密状態で壁に向かって前進し続ける」とか「ウマの尻に魔法をかけて素手でなぐり続ける」などの、制作者が”そう遊んでほしくはない”狂人ロールプレイーースキル上げとてウマの尻をなぐらば、すなわち狂人なりーーの数々を生んでしまったことは、みなさまご存じのとおりであろう(このリマスター版では、手動でステータスにポイントをふりわけられるよう改変されて遊びやすくなったが、「キミはウマの尻をなぐってもいいし、なぐらなくてもいい」というサイコパスめいた自由度は、いっさい損なわれていない)。
ファミコンとその後継機までの時代は、日本製のゲームに圧倒的なアドバンテージがあり、洋ゲーは「バランス調整のできていない、手にとる価値がない大味で大ざっぱなシロモノ」にすぎなかった。それが、初代ディアブロ、ウルティマ・オンライン、バルダーズ・ゲートあたりから、「辞書と首ッ引きでも、まっさきに遊ぶべき作品」ーー当時はsteamによるオンライン配信など存在せず、ローカライズにも大幅な時間差があり、輸入したパッケージ版をプレイするしかなかったーーに変じてゆき、衝撃的なオブリビオンの登場によって、ゲーム業界における和洋の攻守と優劣が、完全に逆転した印象を持っている。あれから20年が経過し、本邦のゲームはさらに半島や大陸のクオリティに追い抜かれてしまった(脳内で「四半世紀で2度も負けるバカがあるかッ!」と吠える例のキャラ)。個人的な体験を申せば、オブリビオンはプレステ3でふれており、modの存在も知らないまま、牧歌的なバニラで延々と遊んでいた。かなり長い時間をプレイしたはずだが、ほとんど内容はおぼえていない。ゲーム内のできごとで記憶しているものといえば、「ハープをつまびくようなフィールド音楽」と「カメラの操作を強制的に奪われてからの『スタアァァップ!』」と「暗闇に浮かぶ紫のエフェクトをまとったウマの尻と両手」ぐらいである。20年前のオブリビオン発売当時は、人生が劇的に変転する季節をむかえており、現実への対処に大きなリソースを割いていた。それこそモンゴメリではないが、家人の寝しずまった深夜に、部屋の電気を落としたまま、苦しみから逃避するためのセラピーとして、シロディールをねり歩いていたのだと思う。
なにか言及が残っていないか、復活したnWoの過去テキストをさぐっていたら、次のような短い文章があった。『ぼくわシロディールだけがありばいーのです。シロディールわぼくおどーよーさせません。シロディールのひとわぼくみたいなばか人げんでもびょーどーにあいしてくれます。げんじつわシロディールよりもおもしろくありません。ぼくわもうげんじつわいらない』。あの頃の心情をしのばせる矮テキストながら、そもそもが「アルジャーノンに花束を」のパロディからの孫引きになっていて、現実での生活に創造的な思索を徹底的につぶされた、言うなれば轢死体の下からあげる、かぼそい悲鳴のような中身になっている。現在、20年後のシロディールでフィールド音楽を聞いているのは、それとはもはや完全に異なった存在であり、「人生への対処を知らない、荒波に巻かれるばかりの哀れな若造」は、もはや遠い過去へと消え去った。さあ、さっさとそのエロmodを導入しろ。オレはもう、バニラには関心がない(審問を受けるモーガン・フリーマンのキメ顔に続く、「REJECTED」のハンコ)。