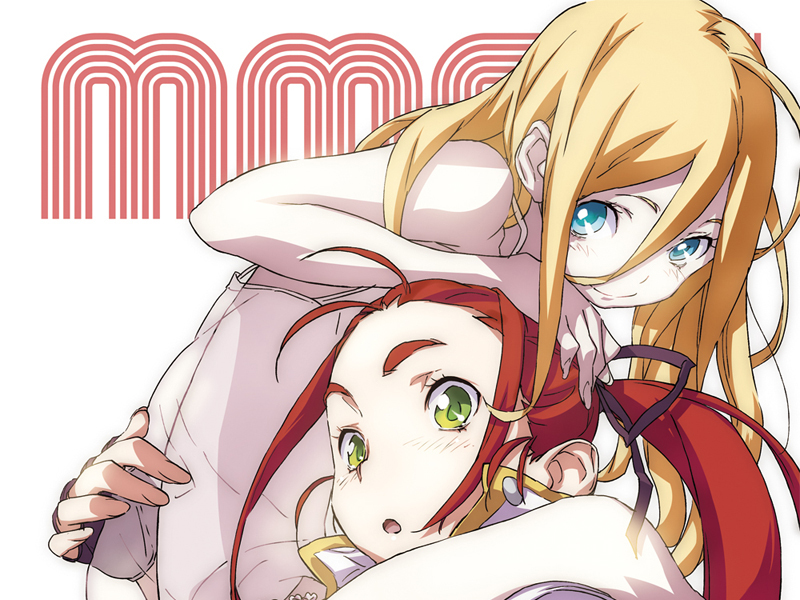ジ・アクト・オブ・キリング

千人を手にかけたかつての殺人者を題材とすることが無謀だという声に、私は同意しない。このアメリカ人監督はむしろ、ドキュメンタリーという手法の、そしてアクト、「演じること」の持つ力の魔性を熟知した上で、アンワル・コンゴの精神を意図的に壊しにかかっているからだ。本作を見て思い出した作品が二つある。一つ目は、ドイツ映画の「エス」。我々はだれもが与えられた環境に応じて役割を演じているに過ぎず、個性や自己同一性と呼ばれるものは一種の幻想、揺れる大地の上のかりそめである。ゆえに演じるという行為、「ジ・アクト・オブ・アクティング」を通じて私たちはあらゆる人物になれるし、あらゆる心理を追体験することができる。二つ目は、邦画の「ゆきゆきて神軍」。このドキュメンタリーでカメラを向けられたことが主人公を躁的に狂わせていくのと対照的に、本作ではカメラを向けられた人物が演技を通じて正気を取り戻してしまい、罪悪感ゆえの絶望へと転がり落ちていく。私は、無辜の千人を殺したという事実を前にしてなお、彼に対して最後まで同情する立場を崩すことができなかった。同じ立場に置かれたら、たぶん、私たちのだれもが殺していたと思うからだ。ひとりの老人に殺される側の味わった恐怖と絶望を「主体的に」体験させる手法は、千人を殺すほどに残酷ではないというのだろうか。階段の踊り場に取り残された、かつての殺人に嘔吐するだれか。そして、数多くのANONYMOUSが並ぶ異様なエンドロール。監督が映画を通じて行う残虐は、アンワルの行った残虐に勝るとも劣らない。れこそが、世界にするアメリカの残虐の正体だと思う。知恵の実を食べたものが、知恵の実を食べなかったものに行う、悪魔の残虐である。
猫を起こさないように