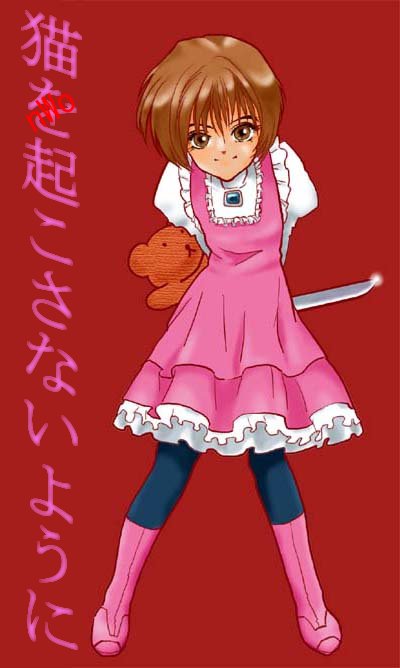FGO第2部終章、レイド戦の手前までを読了。殺された側がいだいていた気持ちをたっぷりと理解させた上で、プレイヤー自身の手によってFGO世界の”運命の確定”を強制する冷徹さは、なまくらどころの話ではなく、突きつけられた匕首がふれるだけで喉元の薄皮を裂くその斬れ味に、ゾッとさせられました。作家としてのファンガスが一貫して保持し続けるテーマは、「網膜を焼くまばゆい生命の輝きと、喪失の痛み(いちど失われたものは、二度と元へはもどらない)」であり、FGOの築いた巨大な経済圏の終焉を宣言する本章においても、その姿勢はまったくブレることがありません。冷静に考えてみてほしいのですが、50代も半ばを過ぎて、昔ながらのファンはもちろん、テキストや物語のクオリティなんて薬にもしたくない大人たちからも、「大先生、大先生」とあがめたてまつられるいまの立ち場を作家人生の余録として、それこそ死ぬまで引きのばすことだってできたはずなのです。キャバクラで若いネーチャンたちにかこまれて、高い酒を毎晩カッくらい、帰りには編集者から高級娼婦のお持ち帰りをあてがわれて、仕事はアシスタントがほぼすべて完成させた原稿に瞳を描きこむだけの、「御大も劣化したな」に類する陰口を黄色い白目で聞き流す、大御所漫画家みたいな”アガリ”の余生を過ごしたとして、もうだれもおもてだって文句は言わないと思うんですよ(社長は言いそう)。ヤマトやエヴァのように、その社会的な誘惑をふりきれず、グッズ販売は好調なれど、物語としてはグズグズの「集金装置IP」へとFGOが堕してしまうことを、しかしファンガスは敢然と拒否したのです。同じ立ち場に置かれときに、現代を生きる他の創作者のうち、いったい何人が彼/彼女と同じふるまいをすることができるでしょうか。
第2部終章の内容について、思いつくままに感想を述べてゆきますと、「地球上に無数の銀河を生成することで、世界そのものによって認識されている法則が自己改訂し、結果として宇宙全体が順に白紙化していく」という理屈は、フェルマーの最終定理の証明における「無限の数学的ドミノだおし」を想起させ、「数式に依らない文系概念による、世界法則の統御」こそが、ファンガスにとっての”魔法”なのだろうなと思いました。それがときに、「横断歩道のアスファルト部分は溶岩になっていて、触れると死亡する。1秒以上を白線上で立ち止まっても、やはり死亡する。ただし、素数行のアスファルトは3秒毎に0.1秒だけ実体化する」のような、小学生の遊びの脳内ルールを厳密に言語化するがごとき滑稽さへと傾いてしまうことがあるのは、玉に瑕と言えましょう(筆力でごまかされますが、今回は魔術回路と万能繊維?のくだりが、特にそう)。第2部終章を読んでいて感じたのは、シンエヴァや宮﨑駿のレイトワークのような「結末を決めずにライブ感覚で作りはじめ、着地点は劇場公開日から逆算して決まる」作品群とは異なり、結末をしっかり定めてから語りはじめられた物語の、すべての伏線が一点に向けて収束していく、得も言われぬ快楽です。トラオムで粗雑に処理されたホームズが再登場するシーンでは、大の大人が夜中に心からの歓声をあげ、笑いながら泣いてしまいましたもの!
全体としての評価は、レイド戦の終わりを待つことになりますが、ここまでの印象でもっともまさっているのは「さいとう・たかをの机の引き出しにしまってあるとウワサされる、ゴルゴ13の最終回原稿を見せられた気分」でしょうか。第2部終章は、ミステリの解決編としては極上ながら、第1部終了から7年を経て、第2部5章後半、6章、7章、そして奏章IIIを描くことで到達した「作家としての円熟」の延長線上にいないような気がするのです(ずいぶん前に、もう「書いてあった」のかもしれません)。ともあれ、「人生でもっともカネをかけた趣味」であるところのFGOの終わり、そしてファンガスの描く「喪失の果てに残る、美しいもの」を、いちファンとして、みなさまとともに見届けたいと思います。あと、フォーリナーたちを介して、さんざんクトゥルフやらアウター・ゴッズの存在をほのめかしてきたのは、「宇宙白紙化」という究極の大ネタから目をそらせるための、ミスリードだったわけですか? それって、あまりに不誠実なやり方だと思いません?