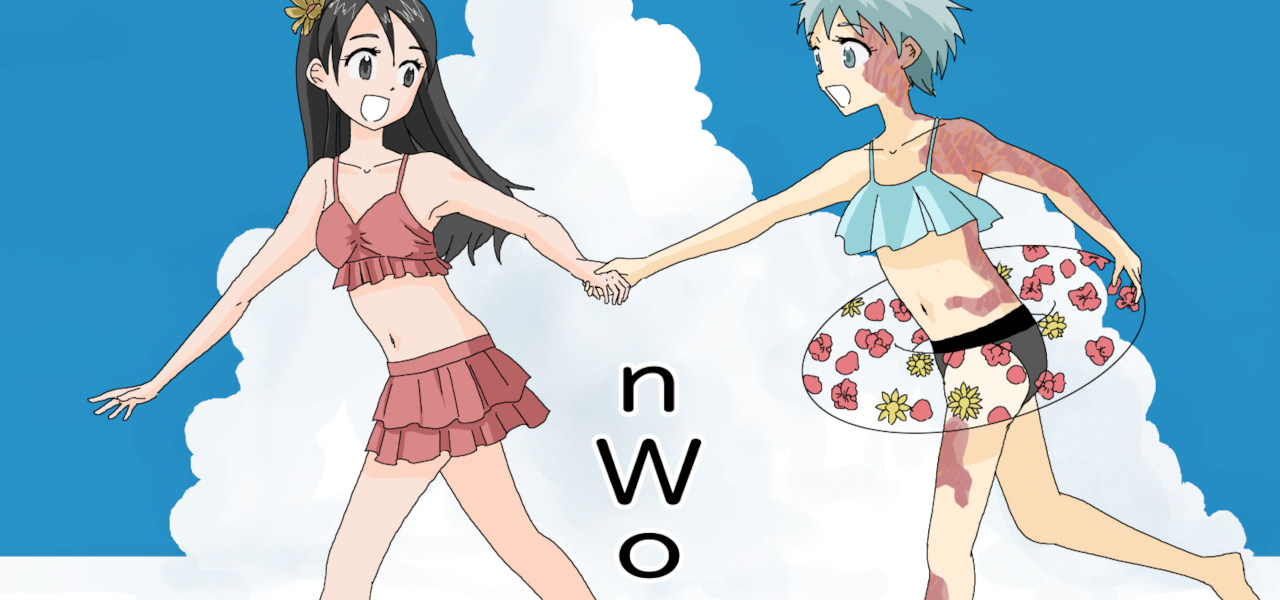クリード

前回のファイナルから相当度の自己模倣が行われていたものの、あくまでロッキー・バルボア個人の物語であったため、作品テーマそのものがぶれることは無かった。しかし本作では、新人ボクサーの話をしたいのか、引退したボクサーの話をしたいのか、最後までどっちつかずのまま進行していく。過去作の名曲をフレーズのみで引用し、頑なにフルコーラスを流そうとしないことを考えれば、おそらく制作者のつもりは前者なのだろうが、オールド・ファンは射精直前の寸止めを幾度も食らった気分に陥り、イライラは募るばかり。そしてポッと出の新キャラが偉そうに愛する旧キャラをディスる様は、そう、まるでエバー・キューにおいて桃色タラコ唇がシンジさんを見下す様を想起させ、小生の怒りのボルテージは否応に高まるのであった。父親の名前を借りたのではない、自らの能力を証明するというテーマは、いまさらオリジナルの新規ボクシング映画を売る自信が無いという制作者の怯懦により、完全に裏切られている。さらに言えば、主人公が金持ちのホワイトカラーとか、恋人の難聴設定とか、ロッキーが癌になるとか、いくらでも刈り込める不要な枝葉が多すぎ、全体のバランスはグダグダである。あとさあ、試合に負けて勝負に勝ったっていうの、もうエエから。主人公のレガシーとやらの継承にテーマがあるなら、物語の必然として勝たせるべきちゃうん。ロッキー方向に日和っとるから、作品の自走性を信頼できずに自己模倣になるねん。ホンマ、けったくそ悪いわ。
年: 2019年
シン・ゴジラ
シン・ゴジラ

西日の差す四畳半の自室の辺縁をぐるぐる周回しながらする、齧歯類と猛禽類しか登場せぬポケットモンスター・ゴー(毛唐語で“CHINPOイッちゃう!”ぐらいの意)にも飽いたので、貴様ら大騒ぎのシン・ゴジラとやらをアイ・マックス(毛唐語で“AIが止まらない!”ぐらいの意)で視聴してきた。貴様らもご承知おきの通り、本邦の悲劇を気楽な創作に流用したエバー・キューなる凄絶の冒瀆を世に問うたあげく、それへの非難から逃れるためのファッション鬱で周囲の同情さえ買おうとしたカントク(cunt-Q)を所謂絶許(いわゆるぜつゆる、小粋なジャパニーズラップの一種)だった小生である。鑑賞前は1メートルはあろうかというリーゼントに2メートルはあろうかという長ランで、前の席でブヒブヒゆうおたくの背もたれに両脚を投げ出し、粗探しでクソミソにけなしてやろうとの構えであった。しかしながら2時間後には、背筋をすっくと伸ばしたゴスロリ美少女が真剣な眼差しでそこに正座していたのである。前の席のおたくは別の意味でブヒブヒゆっていたので、一瞬だけヤンキー姿にもどってチョウパンしておいた。もう公開から1週間も経過しておるので、おそらくどこかですでに語られてしまっている内容かも知れぬ。しかし、だれが言うかが問題となる時代であるので、屋上屋を架すを承知で予のお気持ちを貴様らに述べたい。ゴジラというキャラクターの本質とは、無意識の奥底でつながる我々全員の足元を浸す水のような、民族的とさえ言える恐怖とその共有である。先の戦争において死と破壊を共有した人々にとって、初代はひとつの映画を越えた滅びの追体験となった。我々は先の震災による国難をすべからく(皆を意味するエヴァ語)共有するがゆえに、今作において初代を視聴した人々がどのようにゴジラを眺めたかをついに知ることができたのだ。また、本作では冒頭より連続する会議場面が出色の仕上りである。その面白さは本作のテーマを補強しており、否応にカメラの中心に置かれる主人公格への物語補正を弱め、登場人物たちの扱いに一種の公平性を担保する機能を果たしている。いまは亡き小鳥猊下の名同人誌「MMGF!」に、この構造の類似を指摘しておきたい。かつて、同作者がノーラン監督のダークナイトとその続編、ライジズに対して述べていたことは、エヴァQとシン・ゴジラの関係性にも当てはまるだろう。震災の悲劇を皮相的に流用したエヴァQに対して、今作はゴジラという舞台装置を、明確な意志をもって利用することで、本邦の抱え続けている長い国難を描き切った。エヴァQでの批判がシン・ゴジラにつながった事実は前者のファンにとって非常に苦々しいが、私はここに監督の真摯な反省を見る。また、無人在来線爆弾など終盤のCGの不出来を批判する声があるようだが、それは制作側の意図を汲むことができていない。現実の重さを虚構の軽さの側に引き寄せるというメタ的な方法でしか、ゴジラという厄災に対する勝利を日本に与えることができなかったのである。しかしながら、次の国難を望むことは決して無いと言いながら、ゴジラがその時代が抱える恐怖の象徴として都度、復活し続けるメタ的な可能性の土壌が生まれたことに関しては、たいへん喜ばしい。そして、シン・ゴジラを経たシン・エヴァンゲリオンにおいて、生みの親から長く放置されたあの少年が、ついにはトラウマ電車を降りることをひとえに念じ、ここに私の気持ちをお話しいたしました。皆様の理解を得られることを、切に願っています。
シン・ゴジラ追記。まだ2回しか見ておらぬ不熱心なカントク(Cunt-Q)ファンだが、浮かれ騒ぐ交尾犬の貴様らにバケツで水をぶっかけ(Bukkake)ておきたい。東日本大震災に感情をゆさぶられ、クリエイターとしてこの国難を作品に反映させねばならぬと奮い立ち、自らに引き出しの無い、現実に依拠した完全なオリジナルをぶちあげたがゆえの大失敗作、エバー・キューが無ければ、シン・ゴジラの成功は存在せぬ。「自らの感情」と「オリジナルへの色気」を完全に廃し、彼の本来である「編集の執拗さ」と「コピーのリファイン」へ徹したからこそ、シン・ゴジラは空前絶後の大傑作となったのだ。頼みにならない己の主観、独創性のつまらなさ、この2つのマイナスがかけ算となり、プラスへと転じたのである。エンターテイメント作家でありながら、すべての作品に私小説的な動機が内在するところがカントクの魅力であり、シン・ゴジラを絶賛する貴様らは、エバー・キューを4回も劇場で見た俺様の偏愛にこそ、まずひざまずくべきである。
スターウォーズ7
スターウォーズ7

スペオペ好きの小生もご多分に漏れず旧三部作、新三部作とも二回は通して視聴し、さらにザ・ピープル・バーサス・ジョージ・ルーカスを神妙な顔つきで鑑賞してから劇場へと足を運んだ次第であるッ! 新スター・トレック派の小生としては、パトリック・スチュアートが出演していないことが残念だったくらいで、旧作の構成を模しながら少しずつ位相をズラし、ついには全く違う場所にたどりつきそうな展開にワクワクさせられた。あれっ、以前もなんか同じような感想を抱いて興奮したのに、手ひどく裏切られた経験があったなー、なんだったかなーと思ってたら、エヴァの序と破だった。大胆に予想しておくならば、新たなシリーズはカイロ・レンのライトサイドへの転向がひとつの焦点になるように思う。なぜなら、未熟さと育ちの良さを感じさせるこのキャラクターの造形は、ISISに身を投じる英米の若者の迷いを投影しているように見えるからだ。思えば、3で描かれた「万雷の拍手の中で息絶える民主政」も、当時の政権の対外政策に向けた批判を濃く反映していた。もうひとりの主人公・レイに関しては、ルークの娘かミディ・クロリアンの落とし子か、はたまたシスの末裔かはわからないが、否応に手に入れた強大な力を行使するという事実だけで、当人の意志に関わらずそれはダークサイドとなり得ることを描かれるのではないか。ライトサイドがダークサイドに勝利したことで、フォースにバランスがもたらされた旧作の結末は、いまや現代世界の実情に対してあまりに単純すぎる解決である。おそらく両サイドを二つの文明に見立てた、両者の中庸的な混郁としての落としどころが模索されるはずだ。本邦の時代劇から多くの着想を得た本シリーズが、我々の精神性を汲んだこの結論にたどりつくことは必然とも言える。2017年、2019年に答え合わせをするとき、私の言葉を思い出して欲しい。