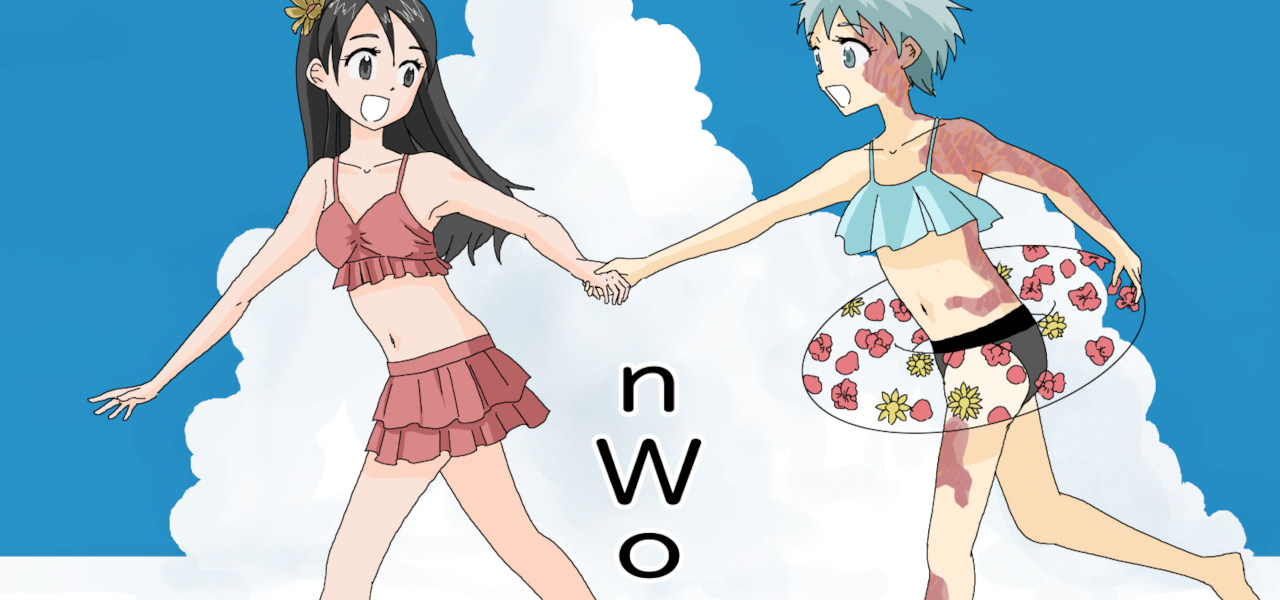遠い海の向こうで、旅客機が摩天楼へと激突する。
ぼくは知らず手をうち、快哉を叫んでいた。
ブラウン管の中で繰り返し炎上し、繰り返し崩落する巨大なビルを見て、ぼくは死んだ祖父が熱っぽい目をして戦争を語るときに必ず感じた、あの言いようのない劣等感を久しぶりに思い出していた。ぼくは、それに対しての快哉を叫んだのかもしれない。
あのとき、ぼくは本当に心の底から興奮していた。ぼくが生まれたときすべては終わってしまっていて、世界は情事を済ませた後の娼婦みたいに、ぼくを拒みもしないかわりにぼくを受け入れもしなくなっていた。世界の揺るがなさは、例え百万年生きたところで、一千万年生きたところで決して変わることはないと、ぼくはそれを歴史の教科書に載っているような無数の確定した事実のひとつとして理解していた。
突然番組が切り替わり、旅客機が摩天楼へと激突する。緊迫した様子のキャスターが告げる。「みなさん、たいへんです。この世の終わりがやってきたのです、あろうことか私たちの生きているこの時代に!」
終末の幻視。一番最初にぼくに浮かんだ気持ちは、同情でもなく、悲しみでもなく、まして憤りですらなく、そのあと生まれたすべての良識的感情を越えて、そう、快哉だった。世界という名前のゆるやかなあきらめに生じた亀裂を見た者の、変容への期待に満ちた快哉。世界が再生するための死のイベントへ向けた、心からの喝采だった。
ぼくは、異常者なのだろう。どれだけ強く殴れば人が死ぬか、どれだけ深く刺せば人が死ぬか、最も秘すべき性の知識でさえも湯水以下の価値の情報として氾濫する中で、本来なら生物がすべて持っているはずの、その命への実感がぼくには決定的に欠落している。ぼくの知っている血は、瞳に照り返すゲームのモニターの赤でしかない。ありとあらゆる知識をあびるように与えられ、肉を養うすべての栄養をふんだんに与えられ、そうしてぼくは、命の実感とは最も遠いところで自分さえもわからぬまま立ち往生している。
空が落ちてくることを恐れて、家に閉じこもった男の話を思い起こす。その男は間違いなく空が落ちてくることを望んでいたに違いないと、ぼくは思う。そんな破格の災厄ででもなければもう世界とはつながることはできないと、彼は思っていたに違いないのだ。
だが、破格の災厄にさえ、ぼくの日常はゆるがされなかった。
現にぼくは、ここで未だにどこへも動けずにいる。
いつも焦燥感だけがあった。みながぼくを非難するのとは正反対に、何かをしなければいけないという思いは強くあった。でもそれは、両親が求めているのだろう、世間とコミットするというレベルのものではなかった。
ぼくは、たったひとりで世界を救わなくてはいけないと思いこんでいたのだ。
完全な自由は発狂と同じように機能する、という言葉を聞いたことがある。では、ぼくは完全に狂っているのかもしれない。選択肢は常に無限に用意されていて、その無限という広がりを保つためだけに、ぼくはどれも選ばなかった。無限の未来が約束していたのは永遠の保留で、ぼくの感情はその一片一片を怒りとか悲しみとか名付けることが不可能なまでに細分化されていた。浮揚するすべての電波を同時にひろうラジオが、ラジオという名前の役目を果たさないように、ぼくもぼくという名前の役目を果たしてはいなかった。
ぼくが求めていたのは、鍬をひく牛のような鈍重なゆらぎの無さだった。
けれど、誰もぼくにそれを許してはくれなかった。暗がりにうずくまっているぼくの手をとり、ぼくの盲をとき、ぼくに自由と理性の素晴らしさを教え、この世の苦しみのすべてを理解する透徹した視力を与え、そして手を離した。
ぼくはこの世界のすべての可能性とあらゆる美しさを生まれながらにして与えられていたのだから、残されているのは世界を破壊するか、世界を救済するか、それしかなかったのだ。
そして世界を壊す手段も救う手段もなかったので、ぼくはどこへも動けなくなった。
ぼくには思考も言葉も助けにならない。ぼくに好悪はなく、ぼくの意識はぼくが世界を理解することを疎外しない。人生を踏み出すのに不可欠な偏見や思いこみが存在しない。ぼくの心はあまりにも歪んでいなさすぎるので、すべての働きかけはどこへも引っかかることなく心の表面を滑っては落ちてゆく。
ぼくの前にはほとんど哲学のような圧倒的普遍性が広がっていた。
大地を耕す牛の視界には、わずかの土しかないだろう。そこから始めなければならなかったのに、ぼくは初めからすべてが等しく大切であり、無価値であるその地獄のような場所に放置されていた。足すことも引くことも必要のない完全な楽園がぼくに与えられた最初の、そして最後の居場所だった。
例えば、ゴールに立たされたマラソンを知らないマラソンランナー。
ぼくはずっと、そういう存在だった。
毎晩、夢を見る。決まった夢だ。
細長い岬を多くの人間たちが一列になって、粛々と歩いてゆく。
その左右は崖になっていて、底は見えない。
周囲を白いもやが取り巻いていて、見通しはほとんどない。
列を乱す者はいない。列を乱せば、墜落するしかないからだ。
進むにつれて、足下はどんどん狭くなってゆく。
ときどき、谷底へと落ちてゆくものがいる。
黙って落ちてゆくものもいれば、泣き叫びながら落ちてゆくものもいる。
しかしどちらも、ただ落ちてゆくのだ。
次第に、周囲を取り巻いていた白いもやが晴れてゆく。
岬は先細りの果てに、ついにその先端へと収束している。
もうその先に道はない。
ひとり、またひとり、岬の先端から落ちてゆく。
黙って落ちてゆくものもいれば、泣き叫びながら落ちてゆくものもいる。
しかしどちらも、ただ落ちてゆくのだ。
やがて、ぼくは自分がその緩慢な行進の最突端にいることを知る。
ぼくは大きく後ろを振り返り――
いつもそこで目が覚める。
全身が寝汗で濡れていた。
正体のない頭で視線をさまよわせると、枕元に置かれた名刺が見えた。意識がクリアになる。
高天原勃津矢。それは、ここから脱出するためのチケットだった。高天原と名乗る男の申し出は、絶対にあり得ないと思っていた、ここからの出口だったのだ。
世界を革命する!
ただ座したまま一切と関わりの無い場所から世界を観察する以外で、世界を救済し、あるいは破壊する以外で、世界を革命することがぼくに唯一可能な行動の選択肢だったのだ。
ぼくはベッドから起きあがり、階下のトイレへと向かった。
そこで、家人とはちあわせた。
いっそののしりあいになれば、どんなにか楽に物事は運ぶことだろう。両親を殺す同年代の事件を見て、ぼくはいつもうまくやりおおせた彼らに嫉妬を感じたものだった。全員が等しく選ばれており重大で、無限の可能性を秘めているこの世界で、ぼくは誰かに明確に自分を断罪させたかったのかもしれない。この生活の繰り返しの中で両親が世界と同義になったとき、ぼくは両親を殺すのだろうと思い続けてきた。ぼくにできるのは、世界を救済するか破壊するかしかなかったのだから。
ぼくと目を合わせないように、「コンビニに行ったのかとばかり……」と寝間着の上に半纏を着込んだその人影は言った。
いつもならば身の凍るようなその場面に、もはやまったく何も感じない自分に気づいた。
夜の淡い空気の下に、にぶく光を放つ五百円硬貨。ぼくは取ることも、取らないこともできる。
それは、これまでの永遠が嘘のような明快さだった。ぼくの生は、高天原に見いだされたことで革命したのだ。
五百円硬貨に背を向けて自室に戻ると、ぼくは名刺に記されたアドレスへメールを送信した。
猫を起こさないように