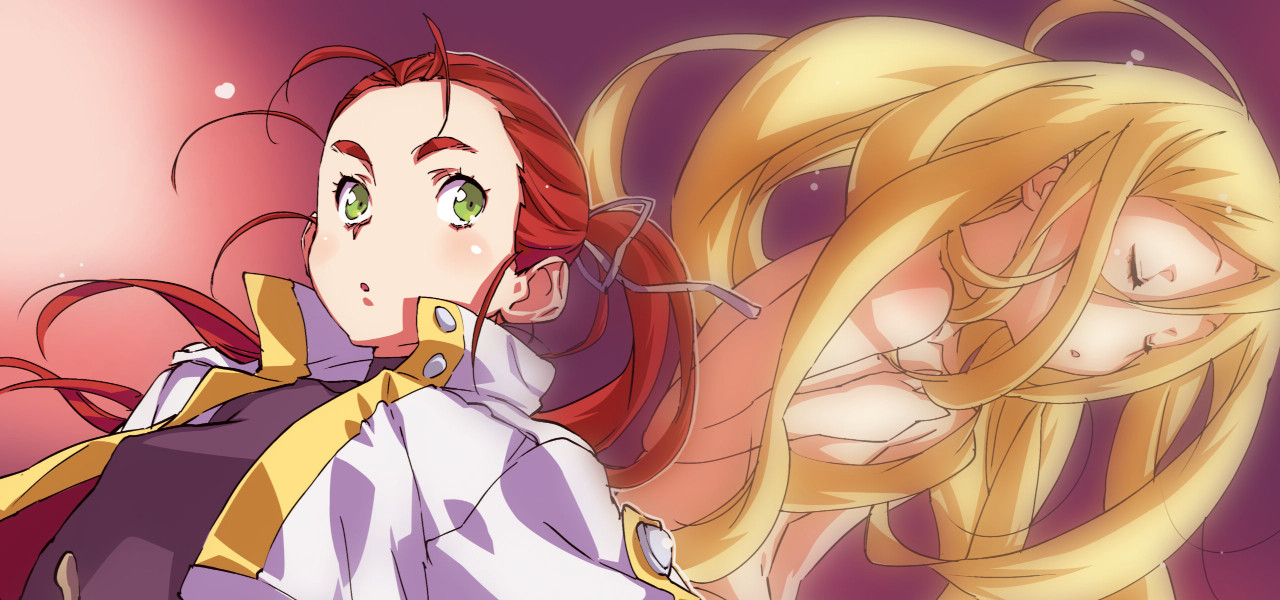「哲学者はいかなる観念共同体の市民でもない。そのことが、彼を哲学者たらしめるのである」
萌えゲーおたくについて考えるとき、上田保春の中に惹起するのは、もう遠い昔にどこで読んだのかも忘れてしまった、その一節だった。哲学者を萌えゲーおたくへ置換せよ。萌えゲーおたくとはこの文脈の意味する哲学者であり、誤解を廃するよう付け加えるのならば萌えゲーおたくとは思索をしない哲学者のことである。自分自身のことを振り返るとき、上田保春は家族という最小の観念共同体においてさえ、自分が異邦人であったことを思い出す。思えば三十数年にわたる上田保春のダンテ的おたく遍歴において、両親のことへ自然に言及できるおたくに出会ったことは一度だってない。おたくにとって両親とは文字通り、語義通りの鬼門である。手にした受話器の底で、遠慮がちに上田保春の近況を尋ねる母親の声が響いている。母親と会話をするとき、上田保春はいつもするようには自分の求められた役割を選択することが出来なくなってしまい、つまり母親が自分に求めている役割とは「いまの自分であってはならぬ」という目眩さえ伴う哲学的命題であり、そうして上田保春は思索できない哲学者だったので、ただの空っぽな魂の容器として吃音にくぐもった声でぼそぼそと、申し訳に応答するしかなくなってしまう。そのときの自己嫌悪といたたまれなさの大きさは、受話器を握る手の反対に苦しまずに生命活動を停止できる錠剤を手渡されたとしたら、その感情から一時的に逃れることを求めるためだけに、その永遠の死を迷わず嚥下するだろうほどである。――申し訳ない。三十路も半ばを過ぎようとしている独り身の息子へ母親が持ちかける話題として恋人とか結婚とか、萌えゲーおたくである上田保春には内面に構築した疑似的な世間知から推察するしか方法が無いのだが、もしかすると見合いなどが一般的には高い確率で出現するのかもしれなかった。しかし上田保春にはその種の話題を母から持ちかけられたという記憶が、完全に無かった。よもや、まだ間に合うと思っているのではあるまい。その推測は萌えゲーおたくである上田保春にとってあまりにも希望を含みすぎており、微温的にすぎた。息子の性的嗜好の露骨な顕現に至る過程と以後の変遷を余すところなく知る母親であるから、自分の息子が捧げてしまっている得体の知れぬ何かへの遠慮からか、世間知において我が子を鑑定しての絶望に近いあきらめからか、もしかすると――この想像が一番上田保春を苦しめる――愛情と優しさから、それらを口にできないのではないか。――申し訳ない。母親との会話でいつも感じるのは、「隣の部屋に血塗れの死体が転がっているのを知りながら、ティーポットへ付着した赤い染みに言及できないまま、紅茶ごしに談笑する男女」の醸成するだろう雰囲気である。誰もが知っているが、誰かが口に出すとすべてはそこで終わり、という状況がこの世に決して少なくないことを彼は知っている。太田総司の巨体が脳裏をよぎった。だからこそ、上田保春は母親の真意に対する想像を、人間存在を極小化するあの宇宙的恐怖から、直接に確かめたことはない。
上田保春が学生時代に愛好したある作家の小説に、「もし全世界が云われてしまえば、全世界が救われて、終わってしまうわけです」という台詞があった。萌えゲーおたくにとっての両親とは、きっとそういう存在なのだ。自分がこのようにある理由を、存在の秘話を、神話的でも哲学的でもなく、その後の人生の存続を難しくさせるほど完全な整数として割り切ってしまうのだ。ただ両親に言及しさえすれば、小難しい理論や引用をひきならべるまでもなく、すべては平穏かつ平板な日常の用語でいたって容易に、余すところ無く言語化できてしまうのだという事実。その事実を再確認するたび、上田保春を取り巻くすべてへの実感は温度を無くし、まっさらに漂白されたようになる。そんなとき、彼は大げさではなく、魂そのものがそれなしでは生きてゆけぬパン、キリストの肉として萌えゲーを渇望していることに気づき、呆然とするのである。両親と正対するとき、萌えゲーおたくの抱える世界は言われて、救われて、厳然たる形を持つ苦悩だったはずのものはその境界を曖昧にして、全部終わらされてしまうのだった。だが、上田保春はこのように明確に思考したわけではない。もしそんなことをすれば、彼の現状を伴うならば、自殺するか発狂するかしかないからだ。しかしこの場合の発狂とは、萌えゲーおたくにとっては修辞的な脅迫にしか過ぎない。言葉が覆うことのできない脳の範囲まで意識が拡大してしまうことを発狂というのであって、上田保春の意識は脳の隅々へと余すところ無く広がり、アメーバ状に浸食してゆく彼の意識は完全に過不足なく言語化されることができた。おたくの苦悩の本質とは発狂するべき点で発狂できないことであり、彼らの異常さが一般人の許容度をはるかに越えてゆくように思えるのは、発狂するべき自意識の点にいたっても未だに言語というフェイルセーフが有効に機能し、発狂し切ってしまうことが不可能な点にある。母の電話を受けた上田保春の無意識はすべてが言語化された瞬間、脳内のフェイルセーフを機能させ、彼の意識と言語化された内容との連絡を即時に断った。つまり彼の無意識は、母親からの電話によって日常の底に開いた完全な虚無から逃れようと反応した。自己憐憫という逃避先を新たな思考経路として、上田保春の識域へ設定したのである。――申し訳ない。上田保春は受話器を右の外耳に押し当てたまま電話機の前でうなだれながら、考える。逃げてはいけない。彼はこの段階ですでにして逃げているのだが、その逃避はあまりに、ほとんど霊的なまでの高次元において行われていたので、巧妙なおたくの脳細胞は逃避そのものの存在を本人にさえ気づかせることはない。上田保春と名付けられた個体が生物的つながり、時間的つながり、空間的つながり、それらすべてから切り離されて在る究極の実存であることを、何の夾雑物も無い意識で受け止めることよりも、現実の惨めさの中にその理由を落とした方がまだ、彼の否定しつつ求める人間とのつながりを軽蔑や非難という形であったとしてさえ感じることができ、無意味が言語化されたのを見てしまう自我崩壊の危険を回避することができるのだった。――申し訳ない。自分がこのようになったのに、誰を責めるわけにもいくまい。両親はカッコウに託卵された巣の宿主であり、肉と遺伝子という連続性よりも強く我が子を規定する外的情報因子が世には氾濫し、それを拒絶できないほど自分が弱かったというだけ。結局、自分の脳髄が腐っていただけ。ただ、本当にそれだけ。何かへの所属を通じて手に入れることの尊さや、「皆で団結して、懸命に作り上げる」ことの素晴らしさを理解する。本当に、それを想像するとき涙が浮かぶほどに切望する。その憧憬のような、マスゲームの埋没への希求を上田保春は誰よりも強く持っている。しかし、真実その場所に触れることができたとして、自分が笑顔をその瞬間のままに張りつかせてたちまち嘔吐するだろうことをまた知っている。我が身を駆けめぐる毒を浄化する血清にアレルギーを持った瀕死の冒険家。それが、上田保春だった。誰に指摘されるまでもなく、自分が救われる道を上田保春は知っている。ただ、それを有効化する手段をあらかじめ封じられているのだ。母と話す限りにおいて萌えゲーおたくに革命は必要なく、あの少年との関わりにおいて昂まっていた全人類的な愛情は行き場をなくし、あるいは行き場をとりあげられて、急速にしぼんでいくのが感じられた。
しかしながら、母の言葉はその内容がどのようなものであれ、常に上田保春に自責を含んだ特定の感情を引き起こすというだけで、母の持ち出した話題が何か深遠な命題を伴っていたわけでは全くない。母が話したのは、祖母のことだった。上田保春の中へおたくの特異さを刷り込んだあの祖母である。数年前に祖父が亡くなってから、しばらくは長女である母が自宅に引き取って面倒を見ていたのだが、祖母はいま老人介護の施設で生活をしている。母に愛情はあり、少なくともあらゆる事象に対して破滅の瞬間を先送りに長引かせるほどは愛情があり――上田保春がその典型例と言えた――、彼女が介護の負担をいとうたわけではなかった。祖母自らが、施設に預けて欲しいことを母に申し出たのである。母から伝え聞いたその契機となるできごとについて思い至るとき、上田保春は祖母への畏敬の念を新たにせざるを得ない。萌えゲーおたくが身に纏う人間存在への侮辱や軽蔑を圧倒する厳粛さが身内に湧きあがるのを上田保春は禁じ得ない。ある晩、就寝中に祖母は失禁した。翌朝、汚れた布団の横に正座した祖母は、部屋に入ってきた母が声をかけようとするのを制し、昔人の語彙でこう言ったのだった。私が自分以外のものになる前に、お前や孫たちの目の届かないところにやって欲しい。ほとんど気づかせないように振る舞っていたが、祖母の痴呆はその時点でだいぶ進んでいたようだ。毛糸玉がほどけてゆくように喪失してゆく自己、その恐慌を誰へも漏らさず現状へと踏みとどまり続けようとする祖母の克己を想像するとき、上田保春の倒錯した共感は彼に愛さえ感じさせた。自我の抑制を失った自分は、いったいどのように振る舞うのだろう。それは遺伝学的に考えても、全く意味のない仮定とは言えないと思われた。上田保春は祖母と同じ老年に達した自分を想像する。その想像はいつも、ほとんど絶叫したいような醜悪さへと逢着した。夜尿の染みを自分のものだと気づかず、男性を握りしめて息を荒げる年老いた自分。現在の自分をかろうじて人間の形に規定している社会性のたがを失い、孫ほどの園児の登校を眺めながら目を細めるのではなく頬を赤らめ、そこがまるでインターネット上ででもあるかのように通りで興奮に奇声をあげる年老いた自分。それらをありありと自身の延長上として幻視するとき、上田保春は膝が抜けるような緊張と恐怖を感じざるを得ない。太田総司を見よ。自己を律する強い意志が無ければ、萌えゲーおたくはたちまちにあのような肉の塊と化すのだ。ああ、この清らかな世界では、ただ正気を保つだけのことがなんと困難を伴うことであるか! 逆にその努力を放棄さえすれば、楽になれるのだろうこともわかっている。しかし、彼にそれはできない。なぜなら、上田保春の中には祖母がいる。彼女は上田保春の見えない背後にずっと正座して、彼の来し方、彼の行く末をじっとその澄んだ瞳で見つめている。その深い瞳をのぞきこんでも、彼女が正気なのか狂気なのか、傍らの者たちにうかがい知ることはできない。彼女の強い克己心は、誰の同情も共感も許さない。
一度だけ、上田保春は母には告げないまま施設へ祖母を訪ねたことがあった。その理由について言えば、祖母のことを心配してなどという人並みのものでは全くなかった。母に連絡をしなかったのは、その動機が全く自己中心的なものでしかないことを知っていたからだ。上田保春はただただ、彼におたくの特異性を刷り込んだあの事件の真相を知りたかったのである。国道を少しそれた山の中腹に祖母の入所する施設はあった。駐車場はバスの停車場所をも備えた広大なものだったが、訪問した曜日と時間帯もあったのだろうか、寒々しいほどに車の数はまばらだった。車を降りると真っ先に、漂白されたように清潔な平屋の建物が視界に入った。いったい心のどの部分からなのだろう、自分と世界との意味のつながりを寸断する不可思議な感情が湧き上がってくるのを押さえつけるために、上田保春は立体視の要領で両目の焦点部分をずらしながら脳内に猥褻な単語を連呼した。予想していたのに反して、受付では二三の質問があったきりで不審そうな素振りすら無かった。イレギュラーな訪問客には慣れているのかもしれない。施設の職員は上田保春を案内しながら、「偉いですよ、あのおばあさんは」と述べたが、その言葉は要するに「手間がかからない」の社交的な言い換えに過ぎなかった。割り当てられた個室で祖母はベッドの上に正座をし、窓の外をじっと眺めていた。上田保春が近づいて来るのに気が付くと、皺に顔のパーツを埋没させるやり方でにこりと微笑み、「こんにちは」と言った。長い萌えゲーおたく生活の中で、抱いた感情に相手が名前をつけるよりも先に察知することに長けた上田保春は、その表情の様子、声の調子だけで祖母が自分のことを全く認識していないのがわかった。会釈して、ベッドの傍らにある椅子に腰掛けた孫へ、祖母はその日の天候のことに始まり、他愛の無い話題を次々と投げかけてきた。しばらくそれへ相づちを返しながら、やがて上田保春は祖母の話題が彼女のベッドの上から実際に見えるものだけに限定されていることに気づく。そして、その質問は相手のYesかNoの返答をだけ予期すればいいものばかりだった。ほんのかすかな涙が膜のように眼球の表面へ張る。視界に歪む祖母。上田保春は萌えゲーの少女を見るときのような哀切に、胸が締め付けられるのを感じた。祖母はこの世のすべての干渉を拒絶して、あらゆる人間に対して他人のように振る舞うことによって、この世界に正気を保ち続けているように見せかけていたのだ。上田保春には、それを滑稽と断じることはできなかった。上田保春が日常で行っている操作と、祖母の行動はいったいどこが違うというのだろう。その操作はあまりにも強い自制心によって行われていたので、肉親以外ならばきっと彼女の正気を疑わないだろうと思えた。偉いですよ、あのおばあさんは――上田保春の抱いた感情は施設の職員と全く同じ言葉で表現されたが、両者の間には目眩を伴うような長大な距離が横たわっているのが感じられた。弱い違和感と表現してもいいだろう上田保春のその感情は、おそらく永久に誰とも共有されることがない。発される形は同じ言葉として何ら変わるところがないのに、そこに含まれる本質はもはや絶望的に違ってしまっている。その差異は、一見して認識できないほど細分化されてしまっているので、現実には存在しないと仮に定義したところで、この世のすべての場所において何の不都合も生じないだろう。地上で最後の言葉を話す語り手、覆しえぬ圧倒的なマイノリティ、しかし彼でさえその存在を異なるものとして認知されて死んでいくことができたのではないか。上田保春は、誰とも異ならない。なぜならその差異を表現する手段はどこにも無いので、誰にも見ることができないから。気がつけば目の前に、まるで萌えゲーの少女のように澄んだ瞳をした祖母が、上田保春をのぞきこんでいる。しかしその瞳はすべてを拒絶しており、言語として記述されたシナリオ以上の背景を持たない萌えゲーの少女と同じ空漠を、虚無をたたえていた。上田保春は両腕をもみしぼりたいような焦燥感に襲われた。しかし、その中身を言語において表現される具体的な形として同定することは、ついにかなわなかった。あなたの孫だと切り出せないまま時は流れ、やがて面会の時間は終了した。無言で立ち上がる上田保春に祖母は、「お帰りになるんですね」と微笑んだあと、昔人の語彙でこう付け加えた。もう来ない方がよろしいですよ、次にお会いするとき、いまの私はいないかも知れませんからね。上田保春は祖母に背を向けて足早に病室を出ると、トイレの個室へと駆け込んだ。扉を閉めた瞬間に、口から嗚咽がほとばしった。それが自分のためだったのか、祖母のためだったのか、上田保春は未だにわからないでいる。
だから、祖母が正気を取り戻したと母が告げたとき、上田保春はまさにこの世の奇跡を聞かされた気がしたものだった。祖母は、祖父の死んだ家へ戻ることを望んでいるのだという。上田保春の心には少年時代の夏の記憶を多く占める、山中に通い馴染んだ藁葺き屋根の一軒家が想起された。あの場所での記憶が、墜ちていこうとする自分をこの清浄な世界へ最後の一線で足止めしている。私はそこで死ぬことが決まっているから、連れていってくれるだけでいい、最期の始末は自分でつけるから。そう言って祖母は聞かないのだそうだ。姥捨てでもあるまい、まさか老女をひとり山の一軒家に置いていくわけにはいかない。しばらくは、いっしょにそこで暮らすことになるだろう――祖母が再び自分を失うまでは。どのくらいの期間になるか見当もつかないし、生活に必要なある程度の荷物を持ち込みたい。この週末に車を出してくれないだろうか。それが萌えゲーおたくの息子にする、母のささやかな要請だった。上田保春は電話口に母の声を聞きながら、動悸が早まっていくのを感じていた。あの自責と罪悪感は、いつの間にか消えていた。上田保春の聖地へ、いま託宣の巫女が帰還を果たそうとしている。はるかな昔、上田保春の鼻先で閉じられた扉が、彼がいま現在見ているようではない正しい世界へと続いているはずのその扉が、神話的にさえ思える長い長い時間を経て、再び開こうとしているのだった。扉の向こうにあったものを手に入れられなかったがゆえのディアスポラ、それがようやく終わりを迎えようとしているのかもしれない。生返事に受話器を置いた後も、上田保春は意識をそらせばたちまち霧消してしまうほどかすかな、希望のようなものにとらわれ続けた。そこへ、充電中の携帯電話が自宅でのみ可能な最新のアニメ系着メロを鳴らした。上田保春はほとんど無意識で携帯電話を取り上げ、着信の番号を見るいとまもあらばこそ、電源をオフにした。上田保春は自分自身へあまりに深く没頭していたので、電話の相手が彼のことをまさにその瞬間に、他の誰よりも強く求めていたのかもしれないことへ思いを巡らすことができなかった。若い時代には、生死さえ分ける苦しみが訪れる特別な晩がいくつか存在するものだ。後になって、上田保春はこのときのことを幾度も思い返すことになる。上田保春の罪はナルキッソスの罪。自分の内側へと閉じこもり他人を見なかった罪。世界より重大な自分、世界に優先する自分。しかし現状を看過することさえ困難な人間の視力の中で、誰がそれを罪と言うことができるのだろう。世界の本質に対する宿命的な弱視と、つかんだ手をただ引き上げることができないほどの脆弱さと、失敗したという事実だけが音も無く水底に積もってゆく罪悪感と。眼前へ並べられた血塗れの自殺器具、傲慢な神が信仰を得るためだけにそろえた大きな自己否定を前に、人間の意識はきっと罪へと陥れられるようにできていた。だが、少なくともこの夜の上田保春は、狂おしく求め続けてきた、そしてすべては虚しく終わるはずだった、自己存在の秘儀が明かされるのではないかというかすかな希望のようなものに、歓喜と畏れの狭間を揺れ続けたのだった。
日: 2005年11月6日
だれも傷つけたくないのに……
”マイミクシィへの追加リクエスト”の件名に胸を躍らせながら、盛り上がった上腕筋に壁が終始接触するほど狭い廊下を抜け、裸電球のひもを引っ張って、玄関の引き戸を開けた。すると、そこに立っていたのは、昔ネット上の社交界で影響力を発揮していた人物だった。件のうんこコミュニティが主催するパーティ会場の窓から、幾度かその姿を見たことがあったので、覚えていたのである。
しかし、今ではもはや、あの頃の栄耀の残滓すらうかがうべくもなく、ムシロ一枚を身体に巻き付けたきりの、”お笑い漫画道場”の土管に住む貧乏人役のような風体だった。やせ細ったその人物は、もじもじと両手をひねりあわせて頬を赤らめ、卑屈な笑みを浮かべたまま、「あの、入れてほしいんです」と小声で言った。
その表情を見、声を聞いた瞬間、私の頭の中は激甚な怒りで沸騰し、全身の筋肉は瞬時に青筋を立てて盛り上がり、身につけた一枚きりのTシャツを粉々の布片へと裂け飛ばした。
「おまえ、どのツラ下げてきやがったッ!!」
私の怒りは、まるで諸君がNHKの集金人にするような、もの凄まじい勢いで爆発した。ネット上でだけは超つよい私が丸太ほどもある右腕で顔面を殴りつけると、その人物はきりもみ状に回転しつつ、鼻血を漫画の効果線のように噴出しながら、人間の良識にセキュリティを委ねるネジで閉める式の薄い引き戸を破壊して、戸外へとスッ飛んでいった。
薄い引き戸が象徴した乙女の部位については、ミクシィにおいて私が作り上げようとしている清純なイメージを壊さぬよう、ここでは更に言及しないでおく。
廊下を立ち去ろうすると、足下に抵抗を感じる。振り返れば、長く血の跡を残しながら這いずってきた簀巻きのその人物が私の両足にすがりついていた。
「入れてください、入れてください」
ひしゃげ、軟骨を飛び出させた鼻から大量の血を流しながら、青紫に腫れあがるまぶたを開くこともできないまま滂沱と涙を流し、その人物はさらに哀願を繰り返した。
「そんなに俺に入れてほしいのか」
露悪的なキャラクターで売っている私だが、実のところ根はとても優しい。弱っている者を放っておけぬ、乙女のような性質を心の奥底に秘めているのだ。
その人物の哀れな様子に私はしばし逡巡するが、ついには優しく抱き寄せ、ずっぽりと入れてあげることにしたのでした。
(絡み合う二人のシルエットから暗転する場面)