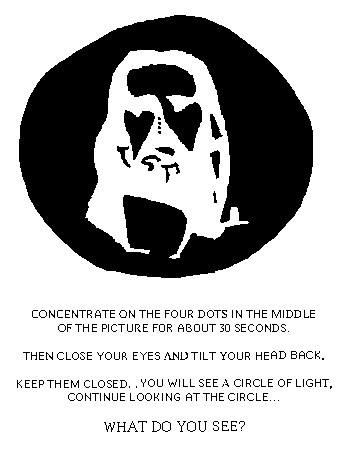(乳首と股間が丸く切り抜かれた暗色のスーツにカクテルグラスで)前回はアルコールに耽溺するあまり、主に婦女子のみなさんを不快にさせる記述を繰り返すなど取り乱した様子を見せてしまい、この小鳥満太郎、お恥ずかしい限りである。今日はファンの諸君と理性的に話をしたい。
諸君、言いたいのはこうだ。私はいつも死ぬつもりで、あるいは殺すつもりで書いている。サラリーマンである私にとって時間的には片手間だが、その集中と密度においては片手間どころではない。そして、特定の誰かを傷つけたり、攻撃したりする意図は無いが、結果としてその意図しない効果を生み出してしまっていることもわかる。しかし、誰も傷つけないものが誰かを救うはずはない。これは信念に近い。次第にその憎悪が積みあがり、ネット上で私は孤独になった。無論、孤独を愛しているわけではない。
今回の更新は、意識的にせよ無意識的にせよ、当ホームページの依拠してきた場所を完全に叩き潰す意味合いを含んでしまっている。つまり、某格闘漫画家風に裏話を語るとすれば、今回の更新は「ジャイアント馬場の回転胴廻し十六文キック」なのである。そのため、「これを書いたらもう先は無いのではないか?」「小鳥猊下、このお話が終わったら、nWoを閉鎖しちゃうの?」などの不安を抱いた諸君が涙を浮かべて私の元へ殺到し、「おいおい、子猫ちゃんたち。君たちの気持ちはわかったから、そんな幼い未熟な身体を俺にぎゅうぎゅう押しつけるなよ」という展開を天然色の画像で予見していた私は、相も変らぬ灰色の日常と空のメールボックスに、突然飼い主に頭を叩かれた座敷犬のような愛らしい驚きの表情を浮かべざるを得ない。そして、少女たちで形成された肉壁の内側から、ロック歌手よろしく分厚い冬物スーツを両手で引き裂きながら飛び出し、「みんなッ、アリガトウッ! nWoはこの儀をもって再生するッ!」などと観客席の幼女の群れにダイブしながら絶叫するオブセッションまで脳内に渦巻いていたものだから、次回更新後、本当に閉鎖してやろうと思っています。
(女性のアニメ声でのナレーション)簡易更新式の雑記帳が隆盛する昨今では見られなくなりましたが、「閉鎖する、しない」の駆け引きも、ホームページ文化の生み出した素晴らしい伝統芸のひとつです。皆様は、引き続き小鳥満太郎の至芸をお楽しみ下さい。