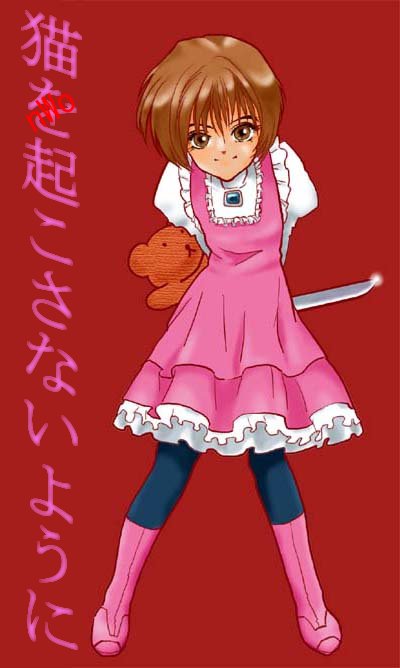見よう見ようと思っていたのに、劇場へ足を運ぶまでの熱量はなかった教皇選挙を、アマプラでようやく見る。ほんとうにこれ、最近は使いたくないんですけど、他に用語がないのでしょうがなく口にしておくと、全編にわたって「ローマ・カソリック的ポリコレ」に満ちあふれた作品でした。たとえるなら、「ああ播磨灘」で主人公がおばあさんを抱きかかえて、女人禁制の土俵へあがるんだけど、絶妙に彼女の足を土へつけさせないパフォーマンスによって、伝統への配慮を同時におこなっている感じと表現すれば、伝わる人には伝わるかもしれません。気になった場面を順にあげてゆきますと、アフリカ教区の黒人司祭が下馬評1位で1回目の投票において最多得票となるのに、人種ではなくスキャンダルを理由にその支持を失わせることで、「黒人を教皇とする」暗黙のタブーに対して、きめこまやかな配慮を行っています。また、この黒人司祭の醜聞の内容はといえば、30歳のときに19歳の女性とのセクシャル・インターコースによって私生児をもうけたにすぎず、お相手を10歳や12歳の少女に設定しないことによって、「カソリック司祭による児童への性略取」という真のスキャンダルへの追求は、巧妙に回避されます。また、アジア人の存在は厳重に秘匿され、クリント・イーストウッド監督が「グラン・トリノ」で見せたような差別意識は、作品の表層へ姿すら見せないまま、無言のうちに抑圧されます(「西洋社会に衝撃を与えるが、かろうじて許容できる」人種はラテン系ヒスパニックまでであることは、最終的に教皇選挙の勝者となるアフガニスタン教区の司祭を見れば、おわかりいただけるでしょう)。
さらに、「ロビー活動なし」「決選投票なし」で参加者の3分の2の票を得るなんて達成できるわけもないのに、階段の踊り場に集まった3人のひとりに「我々は、まるでアメリカ人みたいじゃないか!」と言わせて、「ご覧になっているのは映画的な演出にすぎず、じっさいのコンクラーベはもっと公明正大で、作為はありませんよ」と観客に目くばせーーこっち見んな!ーーしてくるのです。そして、イエス・キリストが男性をしか使徒に選ばなかった事実に由来する、「女性は枢機卿になれない」伝統への挑戦には、なんと候補者が両性具有であったという反則級のウルトラCが使われます。しかも、「体内に子宮があるのに、30代まで気づかなかった」として、排泄と性交を男性として行うことができる程度にしかアンドロギュノっていないとの言い訳まで、周到に用意されております。かてて加えて、戴冠式(着座式?)の場面を映さずに、路地をかけてゆく若い尼僧たちの姿で物語の幕を降ろすことによって、「あれからどうなったって? もちろん、ノーコンテストの再選挙となったに決まってるじゃないか!」という逃げ道まで、神経質にしのばせてくるのです。ついでに、難癖レベルの不満(いつもの)までぶちまけてしまいますと、「システィーナ礼拝堂のフレスコ画が完全に無傷な、上部の窓ガラスが内向きに割れる程度の自爆テロで、主人公が気絶するほどふきとばされる」って、もうこれ、完全なプロレスじゃないですか! ジョーカー2の裁判所シーンぐらい盛大に爆破して、コナゴナになった最後の審判を見せて、アジア人たちの溜飲を下げてくださいよ! それに、最終投票の直前、鳥の羽音とともに礼拝堂へ光が差し、列席者全員がなんとなく空を見あげる演出も、「政治や信条の話じゃありませんよ、これは宗教と信仰の話ですからね」という、キリスト教徒へのビクビクした目くばせーーこっち見んな!ーーとしか思えません。
ここまで読んでおわかりいただけたでしょう、本作は現代のローマ・カソリックがかかえる問題にふみこもうとしてふみこみきれず、制作者がふみとどまった地点をそれぞれ線でつなぐと問題の輪郭がボンヤリとうかびあがり、「意図せぬ痛烈な批判」になってしまっているという、じつにヘンな映画なのです。最後に、個人的な体験をお伝えすれば、持ち前の億劫病から、「28年後…」と視聴の順番が逆になってしまったせいで、キリスト教の腐敗に絶望したレイフ・ファインズが、いつ自室でヨードチンキを顔に塗りだし、礼拝堂に居ならぶ枢機卿をみな殺しにしはじめるのか、終始ドキドキが止まりませんでした。